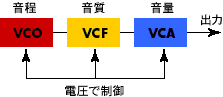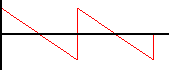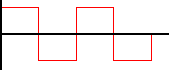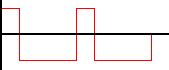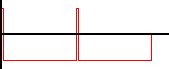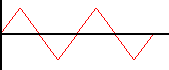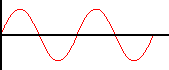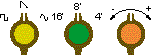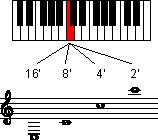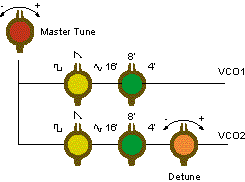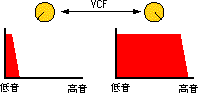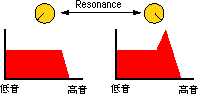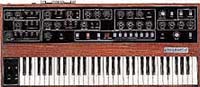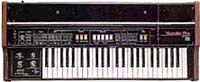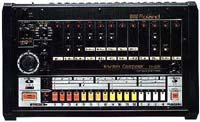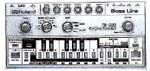11-7 シンセサイザ
11-7-1 シンセサイザについて
最近は一般的に「キーボード」と世慣れることの多い電子鍵盤楽器だが、ちょっと前までは「シンセ」つまり「シンセサイザ」と呼ばれていた。シンセサイザ(Synthesizer)というのは合成器、つまり、あらゆる音を合成できる機械という意味で名付けられたわけなんだけだ。最初は学者系の人たちからのアプローチだったので、波形を正確に発振させる道具という位置づけだった。よって当初はいかにもという電子音を出す機械で、決して楽器として考えられていたものではなかったのだな。
その後シンセサイザは音楽に徐々に取り入れられて行くんだけど、シンセサイザは大きく分けて、現在ではビンテージとかアナログシンセという呼ばれ方をする第一世代と、いまどきさんの第二世代に分けられる。
 |
写真11-7-1
The RCA Synthesizer |
最初のシンセサイザとされているのは、1952年にヘンリー・F・オルソン(Harry
F Olson)が、中心となって設置したThe RCA Synthesizerという名のシンセサイザで、当初から音楽を演奏することを考えて作ってあったが、その入力はパンチを空けた紙ロールによる前近代的なものだった。その後ドナルド・ブックラ(Donald
Buchla)、ジョン・イートン(John Eaton)などの研究者による改良が続き、1994年にロバート・ムーグ(Robert
Moog)がムーグシンセサイザーを発表した。
このシンセサイザは、後のアナログシンセサイザの基本となるもので、(パチンコの正村ゲージみたいなもん)すべてのパラメータを電圧制御するシステムになっていた。(後述)1968年にウォルター・カルロス(Walter
Carlos)という人が、このムーグシンセサイザをだけを用いて、バッハの楽曲を多重録音した「スイッチド・オン・バッハ」(Switched
on Bach)というレコードが出し、大ヒットさせている。ちなみにこのレコードは今無理して聴く価値はない(笑)その当時は驚異的だった曲も今聴くと、ホームページに張り付けてあるベタ打ちMIDIファイルよりタチの悪い音にしか聞こえない。(笑)
11-7-2 第一世代のシンセサイザ
第一世代のシンセサイザの原理は、倍音を多く含む波形を電子回路によって発生させ、その音をフィルタに通してやることによって、明るい音(フィルタをあまりかけない)から暗い音(フィルタを多めにかける)までを表現するというものだ。
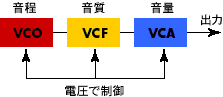 |
図11-7-1
アナログシンセサイザの概念図 |
楽音(あまり使われない言葉だけど、雑音の反対語)の三要素とはなにかといえば、「音程」「音質」「音量」になるわけなんだけど、この当時のシンセサイザはこの三要素をすべて電圧でコントロールしている。「音程」は発振器によって作り出されるので、これを電圧でコントロールするのが、VCO(Volage
Controlled Oscillator)、音質はフィルタによって決まるので、VCF(Voltage
Controlled Filter)、音量を決めるのはアンプなので、VCA(Voltage Controlled
Amplifier)という名称がそれぞれついている。さらにこの制御電圧はCV(Control
Volage)と呼ばれ、0〜5Vの直流と決められている。
CVには1オクターブ上がる毎に1Vづつ電圧が上がっていくOCT/V方式と、1オクターブ音が上がる毎に電圧が倍になるHz/V方式2種類の方式があり、ローランド・アープ・オーバーハイム・ムーグ・シーケンシャルサーキットなどのメーカは前者を、ヤマハやコルグは後者を採用している。
- VCO
発振器(Oscillator)とはなにかというと、この場合は電子的に周期的な波形を生成するもので、これを音に変えれば「ぴー」とか「ぎー」とか連続した音になる。
- 鋸歯状波(Sawteeth wave)
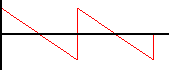 |
| 図11-7-2 鋸歯状波 |
鋸歯状波(きょしじょうは)はそのまま素直にノコギリ波とも呼ばる。奇数次倍音と偶数次倍音を均等に含んでいるので、派手な音がし、シンセサイザで音を作る素材としては一番使いやすい波形だ。
- 矩形波(Square wave)
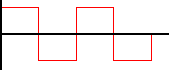 |
| 図11-7-3 矩形波 |
次によく使われるのが矩形波だ。方形波という呼び名もあるけど、「ほうけいは」と言うのはちょっと照れてしまうので、普通は「くけいは」と呼ぶ。(笑)これは偶数次倍音のみを含む波形で、木管系のやさしめの音がする。
- パルス波(Pulse wave)
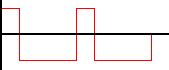 |
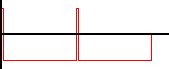 |
| 図11-7-4 パルス波 |
パルス波は矩形波を図11-7-4の左のように変化させたもので、本来の意味から言えば図11-7-4の右ようにほとんど一瞬だけ電圧が入れ替わるような状態をパルス波というんだけど、通常は左のような波形も含めてパルス波と呼んでいる。音的には矩形波を派手にした感じ。またこのパルス幅を周期的に変化させるPWM(Pulse
Width Moduraion)という機能もよく使用される。パルス波は図11-7-4の右の用になるに従って、音が痩せていく感じになるので、音質変化やコーラス効果に近い感じが得られる。
ちなみに日本人はWidthを「わいず」と読む人が多い。Wideが「わいど」と発音するからという理屈だろうな。(実際はまんまの発音で「ういどぅす」)
- 三角波(Triangle wave)
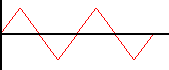 |
| 図11-7-5 三角波 |
三角波は次の正弦波に近く、あまり倍音を含まない音なので、フルート系の音作りや、鋸歯状波などの倍音の多い音と混ぜて芯を出したり厚みを出したりするのに使われる。
- 正弦波(Sine wave)
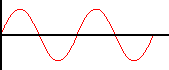 |
| 図11-7-6 正弦波 |
理論上、倍音を全く含まない音なので、VCFの効果が全くない音源。よってこの正弦波を音源として利用するようになっているシンセサイザは少ないが、三角波と同じように補助音源的な使われ方をしたり、LFO(後述)としてよく使われる。
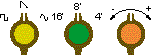 |
| 図11-7-7 VCOのコントロール |
さて、VCOにはメーカや機種によって呼び名は違うが、VCOは通常、図11-7-7のような波形の選択スイッチと、2種類のチューニング用のつまみもしくはスイッチがついている。チューニングに関しては、図11-7-7の緑色のつまみでフィート数を選び、おおざっぱな音の高さを決めて、オレンジ色のつまみで細かいチューニングをする。機種によってはノイズを音源として選べるものもある。
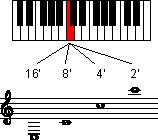 |
| 図11-7-8 フィート数 |
フィート数とは図11-7-8のように、同じ鍵盤を押しても出す音程がオクターブおきに変わるというもので、鍵盤数の少ない当時のシンセサイザには不可欠な機能だった。16とか8などという中途半端な数は、パイプオルガンで、基準とする音の高さで最低音(パイプオルガンの場合、通常ドの音)の音を出すのに、パイプの長さが8フィート必要だったところから来ている。
(ちなみにこれは開管の場合で、閉管の場合は4フィートで済む。)よってパイプオルガンのストップ(音色を切り替えるスイッチ)にも、8'ストップや16'ストップというように、8を中心として倍もしくは半分に音程の違うストップが並んでいる。
オレンジ色のつまみは、ギターやピアノの調律と同じいわゆるチューニング用で、つまみを回しきっても音程は半音も変わらないものや、1オクターブの音程まで変化させられるものがある。
基本的にはこれだけでVCOの機能は終わりなんだけど、多くのシンセサイザはVCOを2つ以上用意して、音に幅を出すように考えてある。その場合VCAまで完全に2系統の回路を用意してあるものと、VCF以降は共用するものがある。共用する場合はVCO部分に簡単なミキサ(それぞれのVCOの音量調整)がついている。
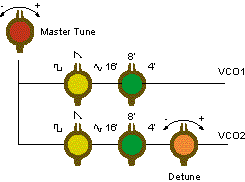 |
| 図11-7-9 デチューン |
さらに複数のVCOがあった場合に、それぞれにチューニング用のつまみがついていると、全体的にチューニングがしづらくなるので、マスターチューニングというつまみをVCO全体のチューニングにして、2つ目以降のVCOにだけチューニングのつまみをつける。この場合、VCO同士のチューニングをわずかにずらして音の厚みを出したり、音楽的に音程をずらして、一つの鍵盤で和音を出す使い方になるので、このつまみはデチューン(Detune)と呼ばれる事が多い。
- VCF

↓
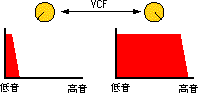 |
| 図11-7-10 VCFの効果 |
VCFは音質をコントロールする部分なんだけど、HPF(High Pass Filter)がその役割のメインとなっている。機種によってはLPF(Low
Pass Filter)を備えているものもあるが、その働きはどちらかといえば補助的だ。元々の発想が倍音をたくさん含んだ音源を、HPFによって高域をカットすれば、その分倍音がコントロール出来るわけだから、堅い音から柔らかい音までを表現できるという事だからだな。当然このVCFによって出てくる音が大きく左右されるわけだから、メーカの個性がもっとも出やすい部分でもあるわけだ。
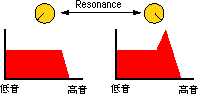 |
| 図11-7-11 レゾナンス |
VCFでHPFについで重要なのがレゾナンス(Resonance)だ。機種によってはピーク(PEAK)と呼ばれたり、エンファシス(EMPHASIS)と呼ばれたりもする。これはHPFのカットオフ周波数の近辺を強調し、音に癖を持たせるためのものだ。いわゆるシンセサイザっぽい音というのは、このレゾナンスを利用した音であることが多い。ローランドのシンセサイザなどは、このレゾナンスのつまみをいっぱいに回しきると、レゾナンス自体が発振を起こし、アクの強い音作りや、もう一つの音源として利用できるのに対して、ヤマハのシンセサイザなどは、いっぱいに回しきっても発振はしないようになっている。このあたりはメーカのポリシーの違いだろう。
- VCA
Amplifierはみんなにとってなじみのある言葉、そう「アンプ」だ。ここでの意味は通常の「増幅器」というよりも音量を決定するところという意味合いが強い。やることは音量の決定だけなので、普通はボリュームだけで、高級機でも複数の系統の音を混ぜ合わすためのミキサ(音量のみの)がある程度だ。
- CV
VCO・VCF・VCAをコントロールする電圧なんだが、これは一定の間の電圧であれば何でもいいのだな。よっていろいろのものがこれらをコントロールするものとして使われる。
- KCV
もっとも一般的なCV。シンセサイザのキーボード(鍵盤)から出力されるコントロール電圧だから、KCVというわけ。通常はこのKCVはVCOにのみ送られて、キーボード一つ一つが違う音程になるわけだ。VFOやVCAにも送って、音程に応じて音質や音量を変化させることもできる。
- LFO
Low Frequency Oscillatorの略で、音として認識できない0.1Hz辺りから100Hz辺りの信号を発生する。これは音源として利用するのではなく、周期的にVCO・VCF・VCAを変化させるために使うものだ。LFOを正弦波にしてVCOにかければ、音程が周期的に変化するビブラート効果が、VCFにかけると周期的に音質が変化するワウ効果が、VCAにかけると周期的に音量が変化するトレモロ効果になるわけだな。
またこのLFOの波形を変えればまた効果が変わってくる。例えば矩形波をVCOにかけると2つの音程を周期的に繰り返すというような効果が得られるわけだな。
- EG
エンベロープ・ジェネレータ(Envelope Generator)という意味。一般にEGはADSRの4つのコントロールからなり、主にVCAに使われる。つまり、音量の時間変化を作るものだ。もちろんVCOにかければ、時間によって音程が変化するし、VCFにかければ、時間によって音質が変化するというわけ。ADSRについて詳しくは第12章を参照のこと。
- Gate
主にキーボードからから出される信号で、いつキーボードというスイッチがオンになって、いつオフになったかを表す信号。トリガ(Trigger)と呼ばれることもある。これはCVとは別系統になっている。ゲートには例えば「ド」の鍵盤を押しながら「レ」の鍵盤を押した時に、先の「ド」の鍵盤が押されたままなので、「レ」の音は出さないシングルゲート(シングルトリガ)と、後から押された「レ」を優先して強制的に「ド」の音を消すマルチゲート(マルチトリガ)の2種類がある。特に同時に二つ以上の音を出せないモノフォニックシンセサイザは重要な設定だ。
| 以下にこの辺りのシンセサイザについて、さらに詳しく解説されているページを紹介しておくので、興味のある人は是非訪ねてほしい。
電子楽器博物館-シンセサイザ講座
http://naoki.hirotaka.co.jp/
TEKNO-BO
http://www.musicmine.co.jp/personal/ryota/tekno-bo.html
|
11-7-3 第一世代の名器
ここで、今でもよく使われたり、話題になる第一世代のシンセサイザを少し紹介しておこう。音の好みは個人差があるので、あくまでも私の主観。それと、この辺りのシンセサイザの音に関していうときは、あくまでも「音素材」としての評価で、今時のキーボードのようにゴージャスな音が出るわけではないのでご注意あれ。
- ムーグ ミニムーグ(Moog MiniMoog)
 |
| 写真11-7-2 Mini Moog |
なんと言っても第一世代で有名なのはムーグ、それもステージ用に作られた「ミニムーグ」が今でも強い人気を誇っている。無骨なデザインの本体から出る音はあくまで太く、リード系の音やシンセベースの音に今でも愛用されている。
- アープ オデッセイ(Arp Odyssey)
 |
| 写真11-7-3 Odyssey |
初期型シンセでミニムーグと人気を二分していたのがこのオデッセイだ。ミニムーグがシンプルな操作系と、太い音をウリにしていたのに対して、オデッセイは多機能と繊細な音で勝負していた。写真は後期モデルだが、ビンテージシンセとしては初期型の白い方が人気がある。
- ローランド システム700(Roland System700)
 |
| 写真11-7-4 System700 |
パッチ型シンセサイザはムーグが有名だが、まだ小さな会社にすぎなかったローランドが遙かに安価に(それでもまだ十分高価だったが)出した本格的パッチ型シンセサイザ。機能を削った廉価版のSystem100は、結構手の届く価格帯だったので、かなり出回った。が、基本的に自宅やスタジオに設置して動かさない性格の機種なので、あまり目にする機会はないかもしれない。
- シーケンシャルサーキット プロフィット5(Sequential Circuits Prophet-5)
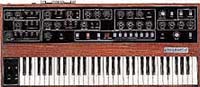 |
| 写真11-7-5 Prophet-5 |
それまでのシンセサイザの常識を大きく塗り替えた名器。5音ポリフォニック(複音)、メモリ機能などの新機能と、独特の音色が受け、多くのミュージシャンに使われた。またこのころテクノポップが流行って、シンセサイザというものが広く受け入れられた時期でもあった。
- ローランド ジュピター8(Roland Jupiter-8)
 |
| 写真11-7-6 Jupiter-8 |
前身のJupiter-4はなんて事のない4音ポリフォニックシンセだったが、その後に出たJupiter-8はかなり「使える」シンセサイザに仕上がった。ローランド特有の「明るい」音の中にも、アナログシンセサイザのもつ音の厚みがあり、今でも愛用している人がいるくらいだ。その後発売されたJupiter-6は、パネルやメモリ部分がソフィスティケートされているにもかかわらず、人気はでなかった。
- ヤマハ CS-80(YAMAHA CS-80)
 |
| 写真11-7-7 CS-80 |
ジュピターやプロフィットと比べて、やはりどこか「エレクトーン」くさい音だが、ホルンなどのブラス系の音質変化は、他の機種にない独特の音があり、その当時大ブレイクしていた「TOTO」などが好んで使っていた。
11-7-4 第二世代のシンセサイザ
特にお決まりがあるわけではないんだけど、「いまどきさん」のシンセサイザは、従来のCV形式ではない回路形式を持つという点や、MIDIの搭載という点で従来のシンセサイザと大きく違う。
 |
| 写真11-7-8 DX-7 |
その先駆けともいえるのが、ヤマハが1983年に発表したDX-7だ。(ちなみに読み方は「ディーエックスセブン」でよい。「デラックスセブン」とか、「ディーばつなな」とかひねくれた読みかたをする必要はない。)
このシンセサイザが画期的だったのは、以下の点だ。
- FM音源
Frequency Moduration(周波数変調)、この言葉自体はFM放送でおなじみのものなんだけど、これを発音方式に取り入れたという点。このことによってそれまでのシンセサイザにない音(その当時は「リアルな音」と表現されていたが・・・・)が出せたわけだな。実をいうと、その原理は比較的簡単にパッチ式のシンセサイザで再現できるんだけど、その音源を全面的に採用し、かつデジタル回路でまとめ上げ、さらにそれが編集可能であるという点が驚きだった。前年にヤマハはGS-1、GS-2、CE-20というFM音源のキーボードを出しているが、いずれも音色の編集は出来なかった。(そのかわりDXシリーズにない「アンサンブル効果」が付加されている)
- MIDIの採用
ちょうど出来たばかりの世界規格、MIDI(Musical Instruments Digital Interface)を採用していた。しかもMIDIにまじめな作りだったので、DX-7はマスターキーボード(他のMIDI音源をならしたり、シーケンサに打ち込むときに使うキーボード)としても長く使われた。
- 大胆なパネルデザイン
それまでのシンセサイザが、とにかくパネル面につまみを並べた前近代的なデザインだったのに対して、DX-7はタッチスイッチと液晶パネルにより操作を行う、今までとは全く違った操作感だった。この操作感は音色の編集をするときにはものすごく使いにくいものだったが、その他の場合はそれまでのシンセサイザに比べ、使い勝手が格段によかった。
- 16音ポリフォニック
これも当時としては驚くほどではなかったにしろ、かなり贅沢なスペックだった。
- メモリ機能
メモリ機能自体はさほど珍しくなかったが、ROMカートリッジ2つによって128音色が付属していたので、その音や自分で作った音を本体に32音色記憶でき、しかも別売のRAMを使えばその32音色をカートリッジの形で保存できたので、音色の保存が楽になっただけでなく、例えばライブの時にカートリッジを入れ替えることによって、今までに出来なかったほどの音色を使うことが出来たりするようになった。また、ROMカートリッジを売ることで、「音色の販売」も可能になった。実際ヤマハからも、他のメーカからも様々な音色カートリッジが発売されていた。
ちなみにDX-7のRAMカートリッジは構造的にはROMの特殊なもので、電池は必要なかった。
- 従来のシンセサイザ並の価格
当時定価で248,000円という価格は決して安くなかったが、プロでなくても手が届く価格帯にあり、爆発的に売れた。(現在までこの販売台数を超えるシンセサイザは出現していない。)
このDX-7あたりから、シンセサイザの音色は「作る」ものから「選ぶ」方式に変わってきたことも大きな変化で、さらにその後MIDIの普及により、「混ぜる」時代へと変わって行くわけだ。
 |
| 写真11-7-9 D-50 |
さて、このFM音源形式はヤマハが技術方面の特許をもっていたせいか、他のメーカには採用されなかったんだけど、遅れること5年、今度はローランドがまたまた画期的なシンセサイザを発表する。D-50という名のそのシンセサイザの特徴は、
- LA(Linear Arithmetic)方式音源の採用
アコースティック楽器の音は、音の出始めの一瞬がものすごく複雑で、その後の余韻の部分は比較的単純であるという部分に着目し、当時一般的になりつつあったサンプリング音源と従来のアナログシンセサイザの音源を組み合わせて、リアルな音を少ないメモリ容量で再現する方式。この方式はサンプリング方式の代用ではなく、独自の音として成功している点や、全く新しい音の組み合わせも可能な点は特筆に値するだろう。
- 内蔵エフェクタの採用
今や当たり前の機能だが、これも当時「コロンブスの卵」的発想だった。LA方式の音源と、リバーブやコーラスエフェクトとの組み合わせは、今までになかったゴージャスな音を出すことを可能にし、プロ・アマ問わずFM音源の音にぼちぼち飽きていた人々に大歓迎された。
と、列挙すると大きく2つしかないんだけど、この2つの特徴は大きな変化で、その他の部分ももちろん進化していたので、一時期シンセサイザのスタンダードとなった。
 |
| 写真11-7-10 M1 |
コルグも少しそれに遅れて、ヒット商品を出す。M1という名のそのシンセサイザは、形こそ違え基本的な発想はD-50と同じものだったんだけど、コルグらしい分厚い音と、シーケンサまで内蔵して、すべての音楽作業が一台のシンセサイザで出来るという「ミュージック・ワークステーション」というポリシーが受けた。この「ミュージック・ワークステーション」という考え方は、その後のTシリーズ、Wavestationシリーズ、そしてTRINITYまで、受け継がれていて、一定のファンを獲得している。
他にもカシオ、カワイのような国産メーカ、海外ではEnsoniq、Overheim、Emuなどが特徴のあるシンセサイザを発表するが、進化はしているものの大きな変化ではなかった。またこれ以降、シンセサイザは分化を始め、
- 「ミュージック・ワークステーション」のようにすべてが一台に凝縮された「オールインワン・シンセサイザ」
- アコースティックピアノ風の鍵盤タッチを持ち、それだけでは音源を持たないマスターキーボード。
- 鍵盤を持たない音源モジュール。
- 音源モジュールの中でもコンピュータミュージック(DTM)に特化したもの。
- 一回り小さい鍵盤を持ち、簡単な操作性のキーボード。
- 家具調の外観と仕上げを持ち、一般家庭でも違和感のないようなキーボード。
- ギターのように演奏できる「ショルダ・キーボード」。
- ヤマハのVLやコルグのProphecyのように、物理音を解析し、シミュレートするもの。
というように様々な製品が発表されているが、爆発的に人気のある機種はなく、選択肢は広いもののシンセサイザ自体は出尽くした感じがある。
11-7-5 ボコーダ
シンセサイザというジャンルからも少し離れるし、後述のサンプラとも違うし、結局今はほとんど使わないし、ということで、紹介しないでおこうかとも思ったんだが、「ぼこだ?何それ?」といわないように、ざっと紹介だけはしておこう。
原理は、マイクなどのから素材となる声を入れて鍵盤を弾くと、素材の声が鍵盤の音程で鳴るというものだ。といっても元々高さを持っている声をどうやって、自由に音程を付けて出すかというと、入力された声をそのまま加工するのではなく、フォルマント(Formant)を検出し、フォルマントだけを素材にして音程を付けて出すわけだ。よって、「あ〜」と声さえ出していれば(理論的には)鍵盤で正確な音程で歌うことが出来る。
フォルマントとは、人間の声の特徴の一つで、人間の声を分析すると、必ず中域に出現する周波数特性の山のことだ。で、このフォルマントは面白いことに、声の調子を変えたり、歌う音程を変えたりしても位置が変わらないのだ。電話のような周波数特性の悪いシステムで誰の声か判別できるのも、「声紋」で脅迫電話の犯人を割り出すのも、みんなこのフォルマントがあればこそなのだな。
ただ、このフォルマントを利用するということは、低音高音を思い切ってカットするバンドパスフィルタをかけるということなので、サンプリングほど素材の音の雰囲気が残っておらず、最終的には「ロボットの声」という貧弱なイメージの音だけに使われるようになってしまった。有名なのはYMO(Yello
Magic Orchestra)の「テクノポリス」という曲で使われた「トキオ」という声。(ちなみにあの声は、ボコーダのベンダを利用して、最初から最後にかけて音程を1オクターブ下げて、イントネーションを付けている)
 |
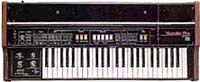 |
| 写真11-7-11 VC10とVP330 |
鍵盤を持った形のボコーダは写真11-7-11の2種しかないといってよい。上がコルグのVC-10で、当時これしかなかったこともあって、みんながこれを使っていた。専用マイクと入力レベル監視用のVUメータが、学校の放送室のような雰囲気を出している逸品である。(笑)
下がその後に発売されたローランドのVP-330で、正式名称がVP-330 Vocoder
Plusとなっていることからもわかるように、ボコーダ専用機というより、ストリングスや、シンセサイザの女性・男性コーラスの音とボコーダの音を混ぜて、リアルで厚みのある合奏音を出そうというポリシーだった。VP-330には専用マイクはなく、別にマイクを用意する必要がある。
11-7-6 サンプラ
サンプラとデジタルレコーダ(ハードディスクレコーダやMDレコーダなど)は、音(というアナログ量)をデジタル化して、記録・保存し、再生するという点で全く一緒のものだということが出来る。違いは「楽器」というアプローチか、「レコーダ」というアプローチかだ。基本的にはサンプラは楽器なので、鍵盤かMIDI端子がついているが、最近ではDJミキサなどにも内蔵されているので、楽器という分類も曖昧になってきている。
楽器としてサンプラを一気に有名にしたのは「オーケストラヒット」の音。(たまにオーケストラピットと混同している人がいるけど、オーケストラピットはホールでステージのすぐ前にあるオーケストラ用のスペースのこと)なんせフルオーケストラの何十もの楽器を一斉に鳴らした音を指一本で出すなぞ、シンセサイザなどではとても表現できず、一時期猫も杓子も「新しい音」として使っていた。オーケストラヒットを含めて、サンプラを有名にしたのはイエス(YES)というグループのロンリーハート(Owner
Of A Lonely Heart)という曲で、その後のサンプラの使い方のお手本となった。
 |
| 写真11-7-12 Mellotron #400 |
さて歴史的に最初のサンプラといえばメロトロン(Mellotron)だろう。もっともポピュラーなモデルは#400。鍵盤の数(35鍵)だけテープレコーダ(再生のみなので正確にはテーププレーヤ)を内蔵した力技のキーボードだ。
メーカから提供されたテープには、コーラスの声とバイオリン3本の音とフルートの音が、35の音程ごとに録音した音が入っていたわけだ。構造上エンドレステープをつかっているわけではなかったので、同じ音を数秒間しか出していることが出来ず、鍵盤から手を離した後も、テープ巻き戻しのため1秒程度音を出せない。
またテープレコーダ自体の性能も高くなかったため、音程が不安定で、周波数特性も悪かった。ところがさすがは何でもありのミュージシャン、「この音がいいんだがね。」ということで、プログレッシブロック愛好者を中心に、未だに人気の高いキーボードである。
その後、デジタル技術の進歩により、電子的に音を記録できるようになった。初期で有名なのがフェアライト(FAIRLIGHT)のCMIというサンプラ。量子化ビット数8ビット、同時発音数8音というスペックで、当時日本で一千万以上。これは一つの大型コンピュータといってもよいようなものだったので(実際ワープロにもなったらしい)、ボッタクリの部分や円相場の部分もあるが、当時デジタルサンプリングにはそれだけお金がかかったということだ。
その他イーミューシステムズ(E-mu Systems)もイミュレータ(Emulator)という名前でサンプラ(というかシステム)を出していた。(今でも同じブランドで出している)ちなみにサンプラはほとんどコンピュータと同じ中身を持つので、イミュレータを動かすのには、EOS(Emulator
Operating System)という名前のOSが使われている。
まあこのようにめったとみれないようなシステムだったので、とにかくサンプラが出た当初は、なんか「どんな楽器でも全く同じ音を出せる魔法の楽器」というような噂ばかりが先行していた。
 |
| 写真11-7-13 MIRAGE |
その後1985年にアメリカのエンソニック(Ensoniq)からミラージュ(MIRAGE)というサンプラが、量子化ビット数8ビット、同時発音数8音というフェアライトCMIと同じスペックでありながら、$2000-以下という安さで出現した。(といっても日本では40万円以上したが・・・)
また「システム」ではなく、「キーボード」としての形をしていた点も大きなポイントだ。とにかく今までは雲の上の話だったサンプリングというのが手軽に出来て、しかも持ち運べるようになったわけだ。またこの当時のサンプラは、サンプラとしてだけにコンピュータと同等の回路を使うのがもったいないと思ったらしく、このミラージュは後述のS-50と同様、シーケンサとしても使えるようになっている。
キーボード型のサンプラとしてアカイS-900やローランドS-50が出るまでは人気の高かったマシン。量子化ビット数8ビットというスペックは、今となってはかなり見劣りがするけど、「サンプラはスペックではなく、音の持ち味」というような評価がはじまったのもこの機種辺りから。よって、楽器的・音楽的なアプローチから、現在でもあえてサンプリング周波数や量子化ビット数を落としたサンプリング音を使うこともある。
 |
| 写真11-7-13 S-612 |
さて、国産初のサンプラ専用機として記念すべき機種は、意外なメーカからやってきた。それまでテープレコーダのメーカというイメージしかなかった(実際1984年にマルチトラックレコーダを出すまで、楽器業界とは何の関わりもなかった)アカイ(AKAI=赤井電機)が1985年に発売したS-612だ。鍵盤を除いたラックマウント式で、2.5インチのフロッピユニットを外付けすれば、データの管理も出来た。量子化ビット数12ビット、サンプリング周波数最高32KHz、同時発音数6音というスペックは、当時十分な音質を備えていたといえる。
ミラージュがある音を出す方に重点を置いてあるのに対し、S-612はあくまで自分でサンプリングすることに重点が置かれていた。そのためかサンプリング操作も、比較的簡単に出来た。これ以降アカイはS-900、950、1000と立て続けにヒット商品を送りだし、サンプラのスタンダードメーカというべき地位を築いている。
 |
| 写真11-7-14 S-50 |
ローランドが1988年に発表したキーボード付きサンプラ。テレビ(パソコンのモニタじゃなくて)を接続しパラメータを管理できるのがかっこよかった。音質的にも明るめのローランドらしい音色で、決してS/Nが良いとは言い難かったが、音色ソフトもかなり用意されていたこともあって、良く使われた。このS-50もDirector-Sという別売のフロッピによって、シーケンサとして使うことも出来るようになっていた。
ヤマハはTX-16Wというラックマウント型のサンプラを出していた。アップグレードが容易なようにと、処理をDOSでおこなっていた。国産初のステレオサンプリングが可能な機種で、音職的にも機能的にも「優等生」っぽい作りだったのだが、起動にやたらに時間がかかるのであまりヒットしなかった。これ以降ヤマハは何故かサンプラを作らなくなってしまった。
 |
| 写真11-7-15 CD3000XL |
1990年代に入ってからは、サンプラはアカイのものが目立つようになり、1992年にラインナップしたS3200・S3000・S2800が広く使われるようになった。特にS-2800はサンプラのスタンダードといってよいほどで、現在でもよく使われている。その後3000シリーズは3000XLにリプレースされているが、(写真はCDを内蔵したCD3000XL)1992年以降目立った変更はなく、サンプラも出尽くした感がある。
11-7-7 リズムマシン