11-5 ピアノ
11-5-1 ピアノについて
 |
| 写真11-5-1 グランドピアノ |
ピアノの起源は11世紀に中近東からヨーロッパに伝えられたダルシマーや14世紀に生まれたクラビコードと言われているんだけど、構造上もっとも近いのはチェンバロ(ハープシコード)だろう。チェンバロは鍵盤楽器としてある程度完成された構造を持っていたんだけど、もっとも大きい弱点は、ダイナミクス(音の強弱)を出しにくいと言う点と、サスティン(余韻)が短いという点だろう。(チェンバロ曲がやたらターンやトリルなどの装飾音符が多いのは、この余韻の短さをカバーするためだといえる)
その後イタリアのクリストフォリという人が1698年に打弦式という現在のピアノ・メカニズムを発明し、「クラビチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」(弱い音も強い音も出せるチェンバロ)という名前を付けた。これを大幅に省略したのが現在の「ピアノ」という名称だ。だから、音楽記号で弱音を表す「ピアノ」のほうが先にあった名前なのだよ。その後数々の改良を受けて現在に至る訳なんだけど、鍵盤数が現在の標準の88鍵になったのは第一次世界大戦後と比較的最近だ。
この伝統的な流れにのっとって作られているピアノの事を「グランドピアノ」といい、その中でも大きくしっかり作られた物(簡単に言えば高い物)を「コンサートグランド」という。また主に家庭用として親しまれている縦型の箱形ピアノは「アップライトピアノ」とか「トラックピアノ」と呼ばれている。
メーカで有名なのは国産では「ヤマハ」と「カワイ」。その他だいぶ廃業してしまったけど、浜松にはピアノメーカが点在していて、中でも「ディアパーソン」(現在はカワイの傘下)は有名。
外国産ではやはり「スタンウェイ」が有名。(ドイツハンブルグ製とアメリカニューヨーク製がある)だいたい中規模の公共ホールには、「ヤマハ」と「スタンウェイ」のグランドピアノが1台づつおいてあることが多い。(使用料はスタンウェイの方が倍くらいする)近年は朗々と鳴るタイプのピアノが好まれることもあって、高級ピアノの代名詞になっている。
以前は「ベヒシュタイン」(ドイツ製)のレスポンスのよい音が主流だった。今ではビンテージ扱いのピアノと言っていいだろう。その他では「ベーゼンドルファー」(オーストリア製・現在はアメリカのキンボール社の傘下。97鍵のお化けピアノ「インペリアル」を作っている。)や「ブルーツナー」(ドイツ製・中高音でさらにもう1弦共鳴用に弦が張ってあるアリコットシステムで有名。共産圏系(笑))などがブランド品だろう。
11-5-2 ピアノのペダル
11-5-3 調律
鍵盤楽器とか打鍵楽器とは言われても、ピアノには弦が張ってある以上、弦楽器と同じくチューニングをする必要がある。ピアノの場合はこの作業を調律という言い方をする。調律にはピッチと呼ばれる周波数があって、「A」の音の周波数をとって「ピッチは442Hz(よんよんに)」という言い方をする。「ピッチは?」と聞かれて「え?DDIですけど・・」とかいうボケはかまさないように。一般に弦楽器はこのピッチが高いほど弦のテンション(張力)が高くなり、張りと音量のある音になるので、ピアノソロの場合やオーケストラのピッチは最近高めが好まれる傾向にある。(といってもA=444Hzより上には余りしない)逆に電子楽器やバンドものの楽器は、キリの良さからかA=440Hzが一般的。
今は性能のよいチューナがでているので、それにあわせれば誰でも調律が出来るのかというとそうでなく、やはりそこは職人芸の域の事柄もたくさんあるわけだ。一番機械で割り切れないところは、「聴感」で合わせていくと、高域や低域になるに従って、音程がだんだん広がって行く傾向になるんだな。その他うなりをとったり、ほかの弦との「鳴り」を調節したりと、よく聞くと私のような素人でも調律師の腕の違いはわかる。
その他、一般に「調律」と呼ばれている作業のほかにも、タッチのばらつきを直す「整調」や、音質のばらつきを直す「整音」や、ピアノ全体の鳴り方をコントロールする「発音」などの作業もある。あ、直接関係ないけど、グランドピアノの3本の足に付いているキャスターは、通常ピアノが置かれているところの木目に沿うような方向に向ける。こうする事によって床をも反響版の一部として使用してしまおうという発想だな。まあでもこれはクラシックの様にピアノの生音を非常に重視する場合での話なので、普通はあまり気にする事はない。(仕事をするときなんかに、相手になめられないように、「俺は経験豊富なんだぞ」というはったりをかます時には使える)
11-5-4 電気ピアノ
通常エレクトリックピアノ、略して「エレピ」と呼ばれることが多いんだけど、分類的にここではあえて「電気ピアノ」と「電子ピアノ」に分けよう。
 |
| 写真11-5-2 Fender Rhodes |
電気ピアノとは、音源が物理的な機構によって音を出すもので、鉄片をたたくものや、アコースティックピアノを模倣したものなどがある。なんと言っても代表的なのはフェンダーローズ(Fender
Rodes)だろう。1948年にアメリカのハロルド・ローズという人が考えて、ストラトキャスターなどのギターで知られるフェンダー社が販売していたのでこの名前があるわけだな。(「ローデス」とか、単純に「フェンダー」という人もいる)現在ではローランドが「Rhodes」ブランドを受け継いでいる。昔の人は「ローズ」=「エレピ」という意味で使うので、おやぢに「エレピ用意して」といわれたら「88鍵のスーツケースでいいですか?」と聞き直すと機嫌がよくなる。(かもしれない)
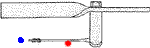 |
| 図11-5-1 トーンバー |
構造的には、トーンバーといわれる鉄の棒をハンマで叩くという、比較的アコースティックピアノに近い方式。(図11-5-1の赤色の部分をハンマで叩き、青色の部分にピックアップを置き、その振動を音に変える)よって、ピアニストたちにも受け入られやすかった。当初はアコースティックピアノの代用的な使われ方だったんだが、その独特の暖かみのある音が次第に認知され、「エレクトリックピアノ」という楽器として扱われるようになっていったわけだ。
ローズには大きく分けて、「ステージピアノ」と「スーツケースピアノ」があり、違いを簡単に言えば、ステージピアノにスタンド兼アンプを付け加えたものがスーツケースだ。(写真11-5-2はスーツケースピアノ)で、いわゆる「ローズの音」というのはスーツケースピアノでないと出しにくい。その理由は専用アンプとスピーカによる音質変化(単に周波数特性が悪くて歪んでいるだけなんだけどね)と、トレモロ回路によるところが多い。
トレモロとは周期的な音量変化のエフェクトなんだけど、これが見事にローズの音に「はまった」わけだ。スーツケースのアンプはステレオ仕様になっていて、このトレモロで音が左右に揺れるので、弾いていてすごく気持ちがよい。ただし、内蔵されているトレモロのモジュレータが矩形波なので、「右」「左」を繰り返すだけで、右からなめらかに左に音像が移動するわけではない。よってライン録音をするときにはバカ正直に右左にパンを振ると、気持ちの悪い録音になってしまう。かといってパンを余り狭めずに使うと今度はトレモロの効果が無くなるので、ローズのトレモロを活かしたい時には、マイク録音をすることをおすすめする。ローズのトレモロの気持ちよさは、(2つのスピーカから)交互にでた音が空間上で混ざった音を聞いているからに他ならない。
 |
| 写真11-5-3 ウイリッツァー |
ローズと同じようなタイプの電気ピアノではウイリッツァー(Wurlitzer)社のものも有名。1955年にベンジャミン・フランクリン・マイスナーという人が、子供向けに安価な電気ピアノを提供する目的で開発したもの。金属製のリードを叩いて音を出す構造で、ローズより少しかわいい目の「ころころ」という音。ダンパワイヤがよく切れたなあ・・(笑)
その他の電気ピアノは、ヤマハのCP-70シリーズがある。これはピアノとほぼ同じ構造もちながら、2つに分割して持ち運びが出来るようにしたもので、ピックアップから音を拾うのはローズと同じだけど、ちゃんと弦をハンマで叩くのでかなりアコースティックピアノらしいタッチと音が出せ、一気に人気がでた。当時とても画期的だったのは、PAなどでアコースティックピアノもどきの音が、大音量で出せる事だった。それまではアコースティックピアノにマイクをたてて、無理矢理音を拾っていたんだけど、どうしてもほかの音がかぶったりハウリングが起きやすいわけだ。(それでも鬼畜ミュージシャンは、「ステージ中央で、ふたを開けた状態で、大きい音でPAしてくれ」とか平気で言うのだな。)ところが、CP-70は限りなく弦に近いところでピックアップで音を拾っているので、アコースティックピアノ+マイクの組み合わせに比べれば、遙かにハウリングマージンが高いわけだ。(といっても、やはり限界を超えればハウリングはする)鬼畜ミュージシャン側も、モニタにしっかり返ることから、ステージを中心に使用し始め、一時期かなりポピュラーな存在となった。
ステージではアコースティックピアノの代用品として使われていたCP-70だが、レコーディングではその歯切れのいい音で、新しい楽器として認識されて使われていた。でもまあ、アコースティックピアノが問題なく使えるレコーディングの世界では、中途半端な存在ではあったので、ステージのように大ヒットはしなかった。
 |
| 写真11-5-4 CP-60M |
CP-70はその後CP-70Bにマイナーチェンジした。ピックアップが直列から並列式になったのと、電源アダプタを外付けするようになったくらいで、それほど大きな変更ではなかったが、こだわる人は初期型の方がいいらしい。ちなみに出力端子はキャノンコネクタのバランス型と、フォーンジャックのアンバランス型の2つがあるけど、バランス出力は本体のボリュームが効かないようになっているので、もし使うようなことがある場合はご注意を。その後発表されたCP-80はCP-70Bの88鍵バージョンで、その後MIDI対応でアップライト型のCP-60Mとかがでたけど、いつの間にか消えてしまった。
11-5-5 電子ピアノ
 |
| 写真11-5-5 RD-1000 |
電気ピアノが機械的な構造により音を発生させ、それをピックアップで拾って電気的に増幅するものだったのに対して、電子ピアノは音源も電気的に作るものを言う。用はシンセサイザやサンプラの一種なんだけど、ピアノのような重めな鍵盤と、ピアノの音にこだわった作りから、それなりにRolandのRD-1000やKORGのSG-1などのヒット商品はでている。
 |
| 写真11-5-5 クラビノーバ |
家庭用に従来のアップライトピアノの代わりというようなねらいで結構がんばっているのが、ヤマハのクラビノーバ。後述のエレクトーンとアコースティックピアノの中間のような位置づけだ。





