何回も言っているように、エレクトリックギターはギターアンプがあってはじめてギターらしい音になるので、ある意味ではエレクトリックギターの音を出すのにギター本体よりも重要なものだ。ギターアンプ以外のアンプ、例えばオーディオ用とかPA用のアンプやスピーカーなんかは、原音に忠実に音を大きくする事を目標にして技術の粋を集めた回路設計をしているのに対して、ギターアンプはギターの音が音楽的によい音で出ればいいわけだから、基本的に何でもアリだ。だからギターアンプの市場というのは、どっかの片田舎で趣味で作ったようなギターアンプが全世界で爆発的に売れたり、まじめにハイクオリティーを追求したアンプが全然売れなかったりする特殊な市場だ。(なんせ相手は思いこみの強い鬼畜
ミュージシャンだからなあ・・・)まあその辺はおいといて、ギターアンプにはコントロール部分とスピーカーボックスが1つになっている「ビルトインタイプ」のものと、アンプ部とスピーカーボックス部が別々になっている「セパレートタイプ(スタッカブルタイプ)」と呼ばれる2種類のものがある。ビルトインタイプの代表選手はフェンダーの「ツインリバーブ」とローランドの「JCシリーズ」だろう。セパレートタイプの代表はマーシャルかな。
- ツインリバーブ
真空管式のアンプで出力管は6L6。通称「ツイン」だが、「ツリバ」と妙な省略の仕方で呼ばれることもある。フェンダーの作っているギターアンプだけあってやはりテレキャスターやストラトキャスターとの相性は抜群にいい。ツインリバーブといってもリバーブが2つある訳じゃなくて、ギターアンプ「リバーブ」シリーズの中で入力回路が2系統あるものという意味だ。まあギターアンプのスタンダードということで、あとのギターアンプの設計に多大なる影響を与えたことは確かなんだけど、逆に言うと特に特徴のないギターアンプという言い方もできる。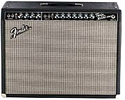
写真11-2-1 ツインリバーブ 変わっているのはトーンコントロール回路で、トレブル(高域)ミドル(中域)ベース(低域)とあるんだけど、回路設計上この3つのつまみを左に回しきると音がいっさい出なくなってしまうのだ。(音質を変える回路が音量に影響するなんて普通じゃ考えられないことだ)あとどうしてもミドルコントロールの効きが悪いという特徴がある。(これも抵抗1本を変えれば改善できる)あとビブラートというつまみがあるけど、これは周期的に音量を変化させる「トレモロ」のこと。ビブラートアームのことをトレモロアームといったり、トレモロコントロールのことをビブラートといったり、この頃のフェンダーは言葉を知らなかったのか(?)
- JC
ローランドが20年前に発表したトランジスタアンプシリーズ。当初のラインナップはJC-60. JC-120. JC-160の3種。その後色々なタイプが追加されたり、廃番になったりしたけど、JC-120とJC-160の人気は衰えず、外観も少しマイナーチェンジがあっただけで変わっていないという、考えてみればとんでもない大ヒット商品だ。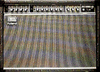
写真11-2-2 JC-120 その人気の秘密は搭載しているコーラスとヌケのいい音色。コーラスについては第2章のギターアンプのマイキングを参照してもらうとして、ヌケのいい音という事はエフェクターの「ノリ」もよくピッキングなどのニュアンスも出しやすいアンプという事だ。よって下手クソが使うと最悪の音になるアンプでもあるわけだ。また逆に太い音を作りにくいアンプという言い方も出来るわけで、このアンプを好むギタリストはエフェクトを多用し、生音と歪ませた音を同じくらいの比率で使い分ける、どちらかというと器用な人が多い。また裏側にラインイン端子があるので、キーボードアンプとして愛用する人もいる。
- マーシャル
大型真空管ギターアンプの代名詞とも言えるものだ。70年代初頭のハードロック全盛期のギターサウンドはマーシャルなしにはあり得なかったことは確かだ。アンプ自体で真空管独特の歪みが作れるのでエフェクターを多用するギタリストよりも「ケーブル1本あればいい」というタイプのギタリストに好まれる。初期型の(いわゆるオールドタイプの)ものにはマスターボリュームが付いていないので、歪みを得るのには音量を上げなければならない。PAが未発達の時代では丁度良かったんだけど、今となってはそんなことやられてはいい迷惑だ。まあギタリスト側もその辺は判っているみたいで、マーシャルを使う場合もエフェクターで歪ませたりする事が多くなったし、最近のJCM800以降のシリーズではマスターボリューム付きの方が売れ筋みたいだ。ちなみにどうでもいいことだけどJCM800ってのはジムマーシャル所有のフェアレディーZのナンバーだ。日本でいえばギターアンプにでかでかと「名古屋77ほ38-17」って書いてあるようなもんだぞ。それにマーシャルには基本的にリバーブが付いていない。「そんなもんホールで馬鹿でかい音出せば、ホールが鳴るでいらんがや。」という発想だな。また更にスピーカーボックスのトップボックスには、スピーカーをとりつけてある面に傾斜が付いていて、音がなるべく遠くへ飛ぶように考えてある。とにかく今となってはPA屋泣かせの機能満載のアンプだ。
写真11-2-3 マーシャル
- メサブギー
人気のあるギターアンプで忘れてはいけないのがこのメサブギーだ。アンプメーカーとしては後発で、少し前まではカルロスサンタナ等にカスタムメードのギターアンプを作っているところみたいな認識のメーカーだったんだけど、ここ10年くらいで(特に日本で)そのシェアを広げた。「青いランプがきれいだ」とかいうミーハーな奴は置いといて、(実際私の知人にそれだけで買った大馬鹿者がいる)何故ここまで(高価なアンプであるにも関わらず)評価を受けたかというと、「サイマルクラス」という独特の回路設計による「ブギーの音」がするからだ。
写真11-2-4 メサブギー サイマルクラスとは違う種類(同じ種類の場合もある)の出力真空管2組を片方は三極管結合で、片方は普通に接続してA級動作させるもので、簡単にいえば「パワーを犠牲にして音質を優先する」モードという事が出来る。まあ三極管結合にしろ、A級動作にしろオーディオ用の真空管アンプの設計の世界では珍しくもなんともない回路なんだけど、ギターアンプにこの技術を取り入れて、しかもギターアンプとして最適なように昇華した面は評価できるだろう。しかし残念ながらこのサイマルクラスはオプション扱いで、これを付けると一気に値段が跳ね上がる。それに回路設計上パワーを出せないので、ハイパワーのアンプには装備できない。