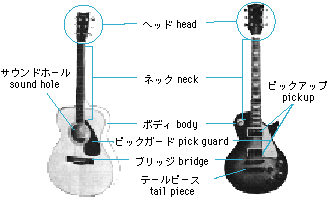ソリッドギターてのは、アコースティックギターのように共鳴部(胴)を持たないもので、大ざっぱにいってしまうと板に弦を張っただけのもんだ。
フルアコーステイックギターは逆に普通のアコーステイックギターにピックアップを取り付けたような構造をしている。ただしエレアコと違ってあくまでエレクトリックギターなので、ボディはピックアップで拾う音を豊かにするくらいの意味しかない。
セミアコーステイックギターはソリッドギターとフルアコーステイックギターとの中間的な構造で、フルアコーステイックギターの胴を薄くしたようなものだと思えばよろし。
まあ今エレクトリックギターといったらほとんどソリッドギターのことだ。ギターの音をでかくしたいという要求から自然発生的に生まれてきたエレクトリックギターは、最初は単純にアコースティクギターにピックアップを取り付けただけのものだったんだけど、そのうちエレクトリックギター専用に設計されたものが出てきた。
最初に成功したのはフェンダー(Fender)が1948年に発表したブロードキャスターで、オリジナルなものはブリッジが3点止めでチューニングが合わせにくいなどの欠点があるものの、現在もテレキャスターという名前で依然根強い人気を保っているな。(個人的にはカントリーミュージックやブルースギタリスト、特に「職人気質」の人が持つギターというイメージがある。)その後エクスワイアー(1S)、テレキャスターカスタム、(1H1S)テレキャスターデラックス(2H)、テレキャスターシンライン(2H)などのシリーズが発表されたが、(括弧内は搭載されているピックアップの種類と数、H=ハムバッキング、S=シングル)現在ではこれらはさほど使用されていない。
フェンダー社は続いて1953年にストラトキャスターを発表、これは実に完成されたエレクトリックギターで、特筆すべきは、女性のボディーラインを模写したと言われるそのシェイプの美しさで、現在のソリッドギターのボディーデザインは(エレクトリックギターはアコースティックギターに比べ比較的ボディーデザインが自由にできるにもかかわらず)ストラトキャスターの模倣といっていい。ちなみに一風変わったヘッドデザインはフェンダー社のFをデザインしたものだ。フェンダー社は以降ソリッドギターにこだわり、いろいろなタイプのギターを発表していくけど、結局このテレキャスターとストラトキャスターが生きのこっとる。
 |
 |
| ストラトキャスター |
テレキャスター |
 |
 |
 |
| ジャズマスター |
ジャガー |
ムスタング |
| 写真11-1-6 フェンダー社の主なギター |
他にもアコースティックギターのノウハウを持ったギブソン(Gibson)社も早くからエレクトリックギター業界にちょっかいをかけるが、ハムバッキングピックアップ(後述)を搭載したSG(元プリプリのかなちゃんが愛用してたやつだ。このSGってのはソリッドギターの略らしい。)シリーズががんばっていたものの、最初はあまりぱっとしなかった。ところがレスポールシリーズを発表したところ、これが大当たりしてギブソン社は一躍ソリッドギターの市場でかなりのシェアを誇るようになったわけだ。
元々レスポールというのはジャズギタリストの名前で、この人とギブソンが共同開発したギターがレスポールという訳なんだけど、このギターをどこぞの奴が歪ましたら「どえなげにゃ〜ゑ〜音するぎゃ〜」(ヘヴィな名古屋弁・標準語では「ものすごくいい音がしますね」)ということで、その当時(70年代初期)台頭してきたハードロックバンドのギタリストが、好んで使うようになってから馬鹿売れし出したわけだ。(レッドツェッペリンのジミーペイジなんかが有名)まあ瓢箪から駒というか、そんな感じだな。しばらく人気は下降線だったんだけど、少し前にガンズ(=ガンズアンローゼズ
Guns' n' Roses)のスラッシュなんかが使ってたりしたため、またぼちぼち人気が出てきている。
ギブソン社は他にも変な格好のソリッドギターをたくさん発表していて、フライングV(マイケルシェンカー御用達。むかしコマーシャルでパチパチくんが持ってたやつだ。)エクスプローラー(ヘビメタにいちゃんが愛用する「さわると刺さってちょっと痛いよ」みたいなかっこうの変形ギターの元祖。)ファイアーバードなど、それぞれ地味に人気がある。あとギブソン社のギターで忘れちゃいけないのは、セミアコースティックギターのESシリーズ。セミアコーステイックギターの代名詞とも言えるもので、特にES335はフュージョン系やジャズ系のギタリストを中心に人気がある。
 |
 |
 |
| レスポール |
SG |
ES335 |
 |
 |
 |
| エクスプローラー |
フライングV |
ファイアーバード |
| 写真11-1-7 ギブソン社の主なギター |
フェンダー社とギブソン社のほかに、モズライトシリーズのモズライト社、(初期のベンチャーズなどが愛用)リッケンバッカー社(ビートルズなどが愛用)やカントリージェントルマンやカジノが有名なエピフォン社(現在はギブソン社から発売)など昔からあるメーカーもあるけど、まあ少数派には違いない。現在はオーダーメイドギター(ボーディーやネック、ピックアップなどを自分の好みで組み合わせて製作してもらうギター)の流行で、メーカーも数多くあって単純に分類は難しい。
|
 |
 |
 |
| モズライト |
リッケンバッカー |
エピフォン |
| 写真11-1-7 その他のメーカのギター |
11-1-4 ピックアップについて
エレクトリックギターがアコースティックギターと大きく違う点は、アコースティックギターが本体だけで音を発音し、共鳴させて音を放出するように考えられているのに対して、エレクトリックギターは弦の振動をピックアップで拾って、電気的に増幅してスピーカら出すことを前提としている点だ。よってピックアップはボディと同じくらい大事な部品ということが出来るわけだな。それでこのピックアップには大きく分けて2つのタイプがあって、一つがシングルタイプ、もう一つはハムバッキングタイプと呼ばれるものだ
元々ピックアップというのは、シングルタイプのものだったのだな。このシングルピックアップは簡単にいうと、磁石の周りにエナメル線を巻いただけのものなので、外部の雑音を拾いやすいという欠点があったのだ。それでシングルピックアップを2つ並べて逆相で結線したピックアップが考案された。これがハムバッキングピックアップで、この名前はハム(ぶーんというノイズ音のこと)をバッキング.(裏に隠す)、つまり外部からのノイズをキャンセルするという意味だ。で、元々の生い立ちはそんな風だったんだけど、現在ではピックアップも高性能化してシングルピックアップでもノイズに強くなってきたので、音のキャラクターの好みでギタリストが使い分けているという感じが強い。それぞれの特徴を列記すると、
シングルピックアップ
- 細く繊細な音が得られる。
- ハーフトーンといわれるサウンドが得られる。
- 比較的ピッキング(弦のはじき方)によるニュアンスが出しやすい。
- 物理的な大きさを小さくできる。
- 外来ノイズに弱い。
- 電気的に出力が小さく、歪ませにくい。
- 迫力のある音が出しにくい。
ハムバッキングピックアップ
- 丸くて太い音色が得られる。
- 外来ノイズに強い。
- 電気的な出力が大きく、歪ませやすい。
- 迫力のある音色が得られる。
- 細く繊細な音が出しにくい。
- 比較的ピッキングのニュアンスが出しにくい。
- 物理的な大きさが大きくなりがち。
といったところだ。
現在では少し下火になっているけど、一時期はピックアップを交換が流行っていて、ディマジオ(Dimarzio)やEMGのピックアップは非常に人気があった。
11-1-5 トレモロアーム
エレクトリックギターの弦はテールピースというところで固定されて、ブリッジで弦をネックから浮かせているわけなんだけど、トレモロアームってのは、このテールピースとブリッジを一緒に動かすことによって弦の張力をゆるめて、音程を変化させるものだ。音程を変化させるんだから「ビブラートアーム」というのが本来正しいんだろうけど、最初にフェンダーが「トレモロアーム」といってしまったので、トレモロアームと一般的には呼んでいる。それでこのトレモロアームは全弦の音程を変化させることができるので、コード(しかも何の変哲もないマイナーコード)を押さえて「じょわぁ〜ん」とやるのが最初の「正しい」使い方。日本でいうグループサウンズのエンディングにいやというほど使われたテクニックだ。
それ以降はあまり使う人はいなかったんだけど、15年程前にフロイトローズというトレモロアームが発売され再びアーミングが流行した。このフロイトローズというのはナット側で弦を6角レンチで固定することによって、従来はせいぜい1音程度の音程変化しか得られなかったものを、弦がだらだらになってしまうまでの音程変化が得られるようにし、しかもチューニングの狂いを最小限に押さえたものだ。また従来のトレモロアームではほとんどできなかったアームアップといわれる音程を上げることも比較的簡単にできる。まあでもこのフロイトローズはヘビメタにいちゃんの大道芸用という認識が一般には強い。もちろん従来のトレモロアームもまだ使われているが、全般的にアーミング奏法は下火だ。
11-1-6 ギターの弦について
弦が太くなればなるほど、その弦をはじいたときの音程は低くなるのは、ギターとベースの弦の太さの違いを見れば何となくわかるよね。逆に言うと太い弦は細い弦に比べて強く張らないと、細い弦のような音程にはならないわけだ。だから太い弦を張ると芯のある太い音が出せるけど、弦の張力が大きくなるので(簡単に言うと弦が固くなる)演奏はしにくくなる。
ギターの弦は普通6弦で細い方から1弦〜6弦というんだけど、通常エレクトリックギターにはライトゲージと呼ばれる弦(の6本セット)が張られるんだな。ライトゲージにもいろいろ種類(太さ)があるけど普通は1弦(一番細い弦)の太さでその種類を表わすのだ。一番よく使われるのが「ゼロキュウ」とよばれる1弦の直径が0.09ミリのもの。次によく使われるのが1弦が0.10ミリのもの。これは「イチゼロ」と呼ばれている。「高音は弾きやすく、低音は太い音を」という人のために123弦はゼロキュウのゲージで、456弦をイチゼロのゲージにした「ボトムヘビー」というゲージもある。まあこの辺のゲージはメーカーによって「スーパーライトゲージ」といってみたり「エクストラライトゲージ」といってみたりと、呼び方が違うので注意した方がいい。ピックアップに音を拾わせるわけだから、当然全弦スチール弦で、ライトケージでは123弦がプレーン(単芯)で456弦がラウンド(巻弦)だ。

|