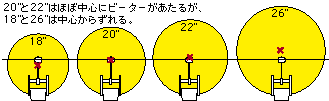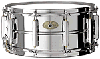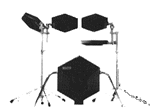- バスドラム
ベースドラム、ベードラとも呼ばれるんだけど要は低音(ベース)を受け持つドラムだということだ。ベースという単語がつく楽器はほかにもあるので、混同を避けるため音響屋は「キック」ということが多い。キック(Kick)というのは蹴るという意味で、ベースドラムはフットペダルを使って、足で蹴って演奏することからこの名があるわけだ。
フットペダルというのは、バスドラムを足で演奏するための物で、フットボードと呼ばれる板を足で踏むことによって、ビータと呼ばれる部分がバスドラムのヘッド(皮)にあたって音を出すようになっている。
バスドラムの大きさは直径が18〜26インチのものがあって、一般に標準サイズといわれているのが22インチのもの。だけどもこれも音楽によって異なり、小編成のジャズグループなどでは18インチが多く使われるし、ハードロックやヘビメタなんかではよく26インチが使われる。基本的には口径が大きくなればなるほど低い音を出すことができるんだけど、チューニングが難しく、なかなか「使える」音になりにくい点と、演奏に「リキ」がいるデメリットがある。また物理的に大きいとセッティングがしにくいということもいえるわな。またビーターがヘッドにあたる位置も18インチと26インチは中心からかなりずれるので、音的に不利になる。
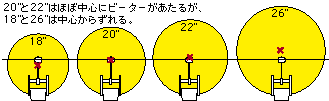 |
| 図11-4-2 ビータの当たる位置の違い |
- スネアドラム
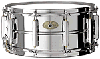 |
| 写真11-4-1 スネアドラム |
小中学校の音楽の時間風にいうと「小太鼓」だな。ほかの太鼓との一番大きな違いは、スナッピ(響線)があること。このスナッピによって「ぽん」という音が「たん」という音に変化するわけだ。スナッピをはずすとスネアドラムは「大相撲ダイジェスト」の音になるぞ。
大きさは9割9分9厘9毛が14インチ。この大きさはスネアドラムが手作りの時代、シェル(胴)にランプのシェードを流用したときの大きさで、別段音響的に深い意味があるわけぢゃないのだよ。胴の深さは最近は6インチか61/2インチが標準で、それ以下のものを浅胴、それ以上のものを深胴と呼んでいる。また3インチ程度の深さのものを特に「ピッコロスネア」と呼んで区別している。
- タム
タムは正式にいうと「タムタム(Tom-Tom)」。
「とむとむ」と言う方も多い。
これはアメリカ発音とヨーロッパ発音の違いのようだ。
「こめこめくらぶ」の手本となった「トムトムクラブ」っていうバンドが昔、いらっしゃいました。
タムの役割はほとんど「おかず」つまり「飾りの音」。だからあまりおかずを必要としない人のドラムセットはタムが少ないし、おかずの多い人のドラムセットはタムが多くなる。またタムが多くなると見た目にもゴージャスになるので、ドラムセットではったりをかましたい人には必需品であるな。だけど音響屋の立場からいうと「盆と正月にしか使わんようなタムにマイクをたてさせるんじゃねぇよ!」なんだけどねぇ。あ、そうそうタムのなかにフロアタムってのがあるけど、フロアタムとタムとの違いはフロアタム自身で足をもっていて自立するだけのこと。普通は一番大きいタムがフロアタムになるけど「大きいタム=フロアタム」ではないよ。セッティングによってはフロアタムのないドラムセットもあるし、フロアタムが3つあるセットもあるわけだな。
タムにはほかに裏の皮のないシングルヘッドタムちゅーもんがあって、シングルタムのなかでもまたいろいろあるんだけど、比較的よく使われるのがロートタムとメロディックタム。ロートタムはまったく胴の部分が無いタムで、リム(ヘッドを張るための金属の輪になった部分)を回すことによって簡単にチューニングを上下できるようになっている。70年代のプログレッシブロックなんかのグループが結構使っていたけど、そのうちだれも使わなくなってきて生産中止になったところで、まさかの大ブームで現在に至る・・・っと。(ビジュアル系の兄ちゃんが好きなのよ)胴がないので余韻のない乾いた音が特徴。・・・のはずなんだけどオンマイクで録ったりすると妙な倍音に悩まされることがしばしば。(そのほとんどがドラマーのいいかげんなチューニングのせいだったりもする。)
メロディックタムというのは略してメロタムといったり、フルセットで8つあることからエイトタムとかいわれるもので、普通のタムの裏側をはずした様な作りをしている。これも余韻の無い乾いた音が特徴だけど、胴がある分ロートタムよりは落ち着いた音で音量もある。いずれにせよシングルヘッドタムはヌケのよい乾いた音が得意なので、ずしりとした低音を出したい大口径のタムには向かない。よく使うのは6インチ8インチ10インチ12インチの4口径。
- ハイハット
スタンデイング(立って)演奏する一部のプレイヤーを除いて、ドラムセットにハイハットは無くてはならないもので、バスドラムとスネアドラムとハイハットだけでドラムの役割がほとんど果たせてしまう。ハイハットは2枚のシンバルを組み合わせ、足でその2枚のシンバルの間隔を操作できるようになっている。ハイハット(High
Hat)は直訳すると「高い帽子」。帽子はハイハットの形からきた愛称のようなものだけど、高いってのはなにかというと、もともとハットは足でシンバル2枚を鳴らすだけのものだったんだな。(おもちゃのお猿さん状態)だから位置的に下のほうにセットされていたんだよ。それを上のほうに延ばしたからハイがついたんだな。それで上にセットすることによって直接スティックなんかでたたけるようになったので、リズムのバリエーションが飛躍的に増えたんだよ。
ハイハットの大きさはほとんどが14インチだけど、フュージョン系のプレイヤーは13インチを使うこともあるし、ハードロック系のプレイヤーは15インチを愛用している人もいる。あと、まったく同じに見えるハイハットの2枚のシンバルも、実は下側のほうが普通厚く作られているのだ。その理由はそのほうが音のヌケがよくなるからで、そのほかにも下側のシンバルの端を波型にゆがめたり、(パイステ社サウンドエッジ)下側のシンバルに小さな穴を4つ開けたり(ジルジャン社ライトハット)しているものもある。これらは2枚のシンバルが合さったときの空気の逃げ道を作ることによって、音のヌケを良くしているんだな。
- ライドシンバル
ライドシンバルはトップシンバルとも言われるけど、現在のドラムセットにおけるライドシンバルの役目はハイハットの代り。つまり主にリズムを刻むためにあるシンバルだ。リズムを刻むためには1つ1つの音がはっきりと聞こえてくる必要があるので、ライドシンバルは大きく厚いシンバルが使われる。叩く度に「ばしゃばしゃ」いっていては使いものにならないからだな。大きさは18〜24インチで20インチがよく使われる。
- クラッシュシンバル
クラッシュシンバルはサイドシンバルともいわれるけど、このクラッシュシンバルはライドシンバルと違ってアクセントをつけるためのシンバルだ。そのためクラッシュシンバルは小さめに薄く作ってある。大きさは大体14〜20インチで16〜18インチのものがよく使われる。
- チャイナシンバル
スイッシュともいわれる(Zildjan社の呼び名)。このシンバルは、普通のシンバルの端を折り返したような形をしている。その名の通り中国的なイメージの音がする。(でもこれって日本=フジヤマ、ゲイシャ、ハラキリと同じようなイメージなんだろうな)大きさは16〜20インチで18インチのものがよく使われる。またそのままだと叩きにくいので裏返しにしてセッテイングされることがほとんど。音の余韻を長くするためにシンバルの外周にリベットをつけてある物もある。
- スプラッシュシンバル
シンバルの中でも特に小さく薄く作られているもので、叩くと「くしゃっ」という音がする。大きさは6〜12インチ。音量も余韻もないので「音のすき間にちょっといれるとかっこいいかな」というだけのものだ。値段が結構安いので中級者のプレイヤーが使いたがるが、大体1ステージだけで飽きてしまう。きちっとこのスプラッシュシンバルを聞かせるためには、PAでも録音でも専用のマイクが必要だ。