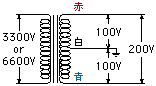10-3 電源ケーブル
10-3-1 日本の電源事情
日本での電源(一般家庭などに電力会社から供給される電気)は交流100Vのアンバランス伝送で、片方がアースされている。コンセントの受口をよく見てみると左側のほうが少し大きくなっていて、こちら側がアース側になっている。(でも前住んでいたアパートの壁のコンセントは、口の小さい方がアース側になっていたので、あんまり信用は出来ないかもしれない。)もし2つの口の大きさが同じ場合は、テスターを交流電圧モードにして、片方のリード線を乾いた手でもって、もう片方のリード線をコンセントに差し込んでみて、電圧が低い方がアースされている方だ。
でまあ、コンセント側にはちゃんと極性がある訳なんだけど、プラグ(オス)側や電源タップなどのメス側は2つの端子が同じ大きさになっているので、挿し方によっては極性が反対になってしまう。日本の電源の悲劇(ちょっと大袈裟)はここにあって、電源事情の悪いところではノイズが発生したり、最悪の場合は感電事故も起きる。アメリカのコンセント(ちなみにコンセントは日本語、むこうではA.C.
Outletという。)は3ピンのものが使われ、電源のラインとアースラインが分離されていて、極性も固定されている。世界各国でコンセントの形状と電圧はまちまちで、アメリカの電源電圧は117Vか120Vだ。ヨーロッパなどでは220Vが一般的だし、中には直流で送電しているとんでもない国もある。どの国がどのようなコンセントを使って、どんな電圧で送っているかを調べたいときは、旅行センターみたいな所にいくと、各国の規格が判る。またHIBINOのホームページの中に世界の電源電圧及び周波数という資料もある。(しかし120Vは判るとしても、117Vちゅー中途半端な電圧はなんなんだ?)
ちなみに電源の周波数は日本では富士川をはさんで東が50Hz、西が60Hzだ。これは1895年に東京電灯(現・東京電力)が浅草発電所を開設した際、ドイツAGE社製の発電機を、関西では1897年に大阪電灯(現・関西電力)がアメリカGE社製の発電機を導入したため。さらに言えば1968年までは周波数の単位としてc/s(サイクル/秒)が使われていた。
日本での電源の供給は発電所で数十万Vの電圧を超高圧変電所・第一次変電所・第二次変電所で次々と降圧(電圧を落とすこと)し、大体6600Vから3300Vで近くの電信柱や地下ケーブルに到達する。何で最初から100Vなり200Vで送らないかというと、電圧を下げると同じ電力を送るのにより多くの電流を流さなければいけなくなるからだ。ケーブルでの色々な損失は電圧より電流に影響されるので、電圧を高くすればするほど有利なわけだな。(実際は余り電圧をバカ高くするわけにもいかず、順番に降圧しながら送っているわけだ。)で、トランスによってみんなが使いやすいように更に降圧するんだけど、この時には図10-3-1のように通常単相三線の形にする。
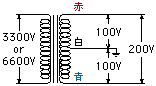 |
| 図10-3-1 単相三線 |
真ん中のくるくる巻いてあるのがトランスの記号で、左側が一次側で電信柱などから送ってきた高い電圧の電源をつなぐ、そうすると右側の二次側に200Vが現れるわけだ。それで二次側のトランスの丁度真ん中の所から端子が取り出してあって、そこを基準に考えると(ここをグランドとする)100Vの電源が2つ取れることになるわけだな。この場合の配線するケーブルの色も図のように決まっている。ホールなどの建物はこの形で仮設用の電源が出ている事が多いので、一応は知っておこうね。ただし勝手に電源を取り出す作業はしちゃいかんぞ。
10-3-2 電源ケーブル
「電源(ケーブル)」「A.C(ケーブル)」と呼ばれるもの。比較的小型で2〜4の口数を持つものは「(電源、A.C)タップ」と呼ばれる。また小さいアダプター状になったものは「タコ足」「ピラミッド」もしくは口数で「フタマタ」とか「ミツマタ」と呼ばれている。
電源ケーブル本体は大電流を扱うということで、スピーカーケーブルと同じようなものが使われるんだけど、「音」を扱う所ではないので電気抵抗が小さくて頑丈であることが最優先されるのだ。2本のケーブルが平行にひっついたものを「平打ちケーブル」、野外などの使用に耐えられるように、ビニール線をさらに太めのビニール樹脂で覆ったものを「キャプタイアケーブル」という。また他のケーブルと違い、電源ケーブルはふつう機器本体からプラグ(オス)の形で出ているので、「電源ケーブル」と言った場合は電源用のオス−メスの(延長)ケーブルのことを指すわけだ。
10-3-3 電源コネクタ
電源ケーブル用のコネクタは、平行・T型・A(C)型が多く使われる。
- 平行
平行はいわゆる「コンセント」で(正確にいうとコンセントは壁などについている受口のことで、オス側はプラグという)で、物にもよるけど大体7〜15Aまでの容量を持つ。音響機器の一台あたりの消費電力は、よっぽど特殊なものを除いて1kW(100V×10A=1000W=1kW)を越えることはないので、(日本用の)音響機器にはこのプラグが付いている。
よく「タコ足配線」はやめようというが、これは電気知識のない人が電化製品を沢山タコ足でつないで、消費電力の合計がかなり大きい状態で使っていてトラブルが起き、「おたくのところの製品はどないなっとりゃーすのかね」といったクレームを防ぐためで(まあ実際これで過熱による火災が発生したりするので大変危険なことには違いない)、きっちり消費電力の計算をしていれば「タコ足」自体は問題はない。(というか、他に方法がない。)
平行コネクタの付いたキャプタイアケーブルをリールに巻き、収納や持ち運びを容易にしたものを「電源ドラム」「電源リール」「電ドラ」などと呼び、割とよく使用されるんだけど、これを使うときは必ずケーブルをリールから全部引き出した状態で使用すること。これはリールに巻いたケーブルがコイルとなって、交流に対して電気抵抗を持ち電圧降下を起こし、その分発熱を起こすためで、使用電力が少ない時にはさほど問題にならないけど、使用電力が大きい場合は馬鹿にできない問題だ。
- T型
T型のコネクタは20Aまでの容量をもつコネクタで、主に照明の世界で用いられ、音響の世界では(中途半端な容量なので)あまり使われることはない。家庭用では昔のエアコン用のコンセントなんかには使われることもあったけど、エアコンの性能が上がって消費電力が減ったため、最近では滅多に使われない。
- A型・C型
A型のコネクタは30Aの容量をもつコネクタで、C型はA型の改良版で、極性を一致させれれるようにA型のコネクタの内部に溝をつけたもの。よってA型のメスにC型のオスは接続することができるけど、A型のオスにC型のメスを接続することは出来ない。
ホールなどの電源は主にこのA型もしくはC型のコネクタで供給されるため、音響機器はA(C)−平行の変換(通称「えーへー」「しーへー」)をしてから使用する。ホールによってはさらに大型で60Aの容量をもつ「ラージA、ラージC」というコネクタが使用されることもあるけど、通常これはホール側で普通のA(C)型に変換してもらってから使う。
さらに仮設ステージなどの現場で分電盤や「ジェネ(レーター)」と呼ばれる仮設発電機から電源をとるときには、A(C)型のメスと先バラのケーブル「A(C)−バラ」が使われるが、接続作業は危険なので専門家に任せたほうがいい。
以上3つのコネクタにはロック機構(ケーブルを引っ張っても抜けない)がないので使用にあたっては注意が必要となる。(よく照明屋さんが接続部分でケーブルを結んだり、音響屋さんがコンセントのところにガムテープを貼っていたりするのは「引っ張り」による脱着を防ぐためだ)他に、楽器やエフェクターなどで本体からケーブルを分離するために、本体にキャノンなどのコネクタのオス側をつけて、そのコネクタのメス側と平行プラグを付けたケーブルも「電源ケーブル」といったりするが、これは非常にローカルな(他にはない)ケーブルなので、「〜用の電源(ケーブル)」といったほうが間違いがない。