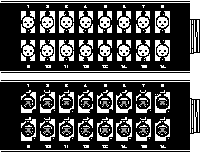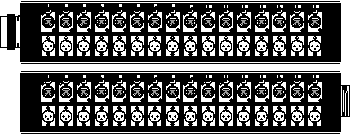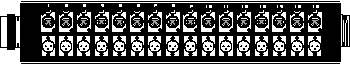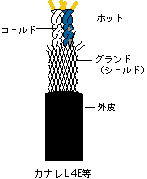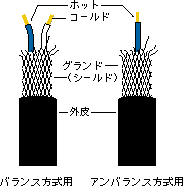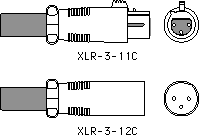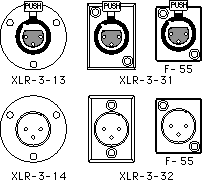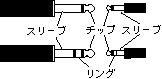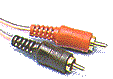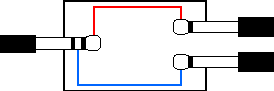10-1 コネクタとケーブル
10-1-1 ケーブルの呼び方
呼び方についての考察
- 呼び名としてはだいたい「ケーブル」か「コード」のどちらかが使われている。
- 細いめの物を「コード」といい、太いめのものを「ケーブル」と使い分けている人もいる。「マルチケーブル」とはいっても、「マルチコード」とはいわないのはその辺に理由があるのかもしれない。
- 「ワイアー」なんていう奴ぁーいねーけど、不思議とコードのないマイクは「ワイアレスマイク」という。なんで電話機みたいに「コードレス」とはいわないのかねぇ。
- 「線」なんて言い方も使わないけど、ケーブルをつなぐ作業は「結線」といってしまうのは日本人の「血」か?
- ワイアレスマイクに対して普通のマイクのことを「ワイアード」とか「有線」という。
- 普通ケーブルやコード(以下ケーブルと言ふ)と呼んでいるものは、大体その前に「何用の」がわかる単語がつくようになっている。(マイクケーブルとかスピーカーケーブルとかというようにね。)
10-1-2 シールドケーブル
特殊なケーブルや電源ケーブルに関しては後述するとして、音声信号のやりとりをするのには普通、シールドケーブル(Shielded
Cable)というものが使われる。ちなみに「シールド」の訳は「遮蔽」なので、正しく言うなら「シールデッドケーブル」。エレクトリックギターとアンプをつなぐようなケーブルをよく「シールド」といってるけど、あれはシールドケーブルの略なのだ。たまに「おーいシールドとって!」なんてのを耳にするが、シールドケーブルからシールドを取ったら、芯線がむき出しになってしまうぞ。
| 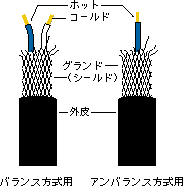
|
| 図10-1-1 シールドケーブルの構造 |
シールドケーブルは図のようにホット(とコールド)を金属の網状のものでおおった構造をしている。図10-1-1ではケーブルのみを書いてあるけど、本当はケーブルをしなやかにしたり、ねじれを防ぐための糸などが巻き込んである。なぜこのような構造のケーブルを使うかというと、音声信号は微弱な電気信号なので、外来ノイズの影響を受けやすいからだ。よって金属の網で「バリア」を作ってやって信号を受け渡しするときにノイズがのってしまわないようにするわけだな。大体全てのケーブルにおいていえることなんだけど、白色と他の色があった場合には、白をコールド側にするという「有色ホットの法則」みたいなものと、黒と他の色があった場合は、黒をコールドにするという「黒色コールドの法則」があって、図の場合は青色をホット側としている。別にケーブルの両端で同じところにつながってれば問題はないんだけどね。
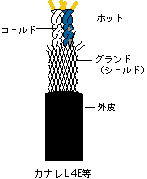 |
| 図10-1-2 ツイストペア構造 |
さらに最も良く業界でマイクケーブルなどに使われているカナレというメーカのL4E-6S等は、図10-1-2のようにホットとコールドがそれぞれ2本づつはいっている。これは耐久性を高めるとともに、静電容量を少なくするためだ。余談だけど、カナレ自身が作って売っているコネクタ付のケーブルは、分解すると白側がホットで、青側がコールドと「有色ホットの法則」を無視した作りになっているので注意。
またシールドケーブルはその構造上、シールドと芯線の間に静電容量を持ってしまうので、ケーブルの長さを長くすればするほど高域が劣化してしまうという弱点があるので、実際の使用に関してはシールドケーブルは必要悪と考えて、なるべく短く使うのが基本だ。もちろん全てのケーブルにある、芯線が持っている微弱な抵抗による電気信号のロスも、長さが長くなると馬鹿にならないので、シールドケーブルに限らず、ケーブルはなるべく短く使うようにしよう。
10-1-3 キャノンコネクタ
プロ用のコネクタとしては最もポピュラーなものだ。一般的に業界では「キャノン」ということが多いんだけど、これはこのコネクタを最初に作ったメーカの名前で、正しくはXLRコネクタというのだ。まあでもここではキャノンコネクタという言い方に統一しよう。
とにかく頑丈で、踏まれたくらいでは変形しない。また目立たないが大きな特徴として1番ピンが必ず他のピンより先に接触する構造になっている。(2ピンタイプのもの以外)1番ピンは通常グランド端子として使用するようになっているので、接続時には必ずグランド端子が最初につながるようになっているわけだ。これによって接続の時に、ほとんど衝撃音が出ないようになっているわけだな。(逆にグランドより信号線が先につながると、衝撃音が出てしまうわけで、後述のコネクタはすべてこの欠点を持っている)またコネクタにロック機構がついていて、(これもこの中で紹介するコネクタの中ではキャノンとスピコンだけの特徴)確実に接続すればケーブルを引っ張っても、接続がはずれないようになっているので、プロ用に信頼性を要求される現場では、必ずと言っていいほどこのキャノンコネクタが使用されている。
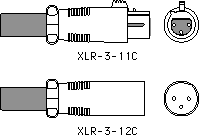 |
| 図10-1-3 キャノンコネクタ |
キャノンコネクタのピン数は2ピンから7ピンまであるけど、一番よく目にするのは3ピンタイプのものだ。またコネクタにはどのようなものかを表す品番がついていて、例えばSM-58などのマイクにさすコネクタは、XLR-3-11Cという。これはXLRの後の3はピン数を表していて、11はコネクタの形状、Cはケーブルにつけるコネクタだというこだ。ケーブルにつける形状のものはメスの11Cとオスの12Cしかない。ちなみに数字の下1桁目が奇数の場合はそのコネクタがメスであるという事を表し、偶数の場合はオスであることを示している。
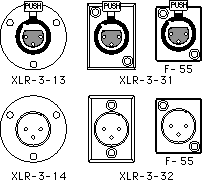 |
| 図10-1-4 キャノンレセプタクル |
音響機器のパネル面につけるようなものは「レセプタクル」と呼ばれる。これには一番よく使われるメスの31とオスの32の他に、昔の機器でよく使われた丸形の13と14がある。13と14は、オスとメスのレセプタクルの外径が同じという点がメリットと言えばメリットだけど、限られたスペースに、なるだけ多くのコネクタを配置したいミキサなどには不向きで、最近はあまり使われない。さらに最近は、オスとメスのフランジの大きさを一緒にした(31と32ではオスとメスのフランジの大きさが違うでしょ?)F-55タイプや、更にフランジを小型化したF-512(オスのみ)というものも出ているけど、普通は区別して呼ばない。
昔からこのキャノンコネクタと互換性のあるコネクタを作っているメーカーは多くて、最近ではキャノン社のキャノンコネクタは余り使われることはなくなってきている。形状もほとんど同じキャノンコネクタを作っているのはアメリカのITT(最近はITT
CANNONとなってるけど合併でもしたのかなあ)や日本のJAEというメーカー。違う形状だけどキャノンと互換性のあるコネクタを作っているのが、アメリカのスイッチクラフト(SWITCH
CRAFT)やスイスのノイトリック(NEUTRIK)というメーカーなどだ。スイッチクラフトのものは流線型の結構かっこいいデザインで、以前(80年代まで)はよく使われたんだけど、コネクタに逆ネジ(右に回すと普通ネジは締まる方向に回るけど、逆ネジはゆるむようになっている)を使っていたりして、ケーブルの製作や補修に時間がかかることもあって現在ではほとんど使われなくなってしまった。逆にノイトリックのコネクタは製作時間の大幅短縮を狙った構造と、コストの安さが受けて、日本ではかなりの割合で普及している。
10-1-4 フォーンコネクタ
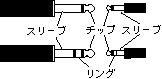 |
| 図10-1-5 フォーンコネクタ |
その名の通り、当初はイヤフォンやヘッドフォン用のコネクタとして開発されたものだ。正確な品番はよく判らないけど、「100」とか「47」とかいう人がいるので多分そうなんだろう。(無責任)フォーンプラグは2端子のものと3端子のものがあって、比較的安価なので、2端子のものは楽器などを中心に、3端子のものはヘッドフォン端子などに広く使われている。(3端子のものは後述の110と一応の互換性がある)で、普通「端子」というのを省略して「P」で表して、「2P」とか「3P」とかと普通は呼んでいる。それぞれの端子にはちゃんと図のような名前が付いているのだ。またフォーンコネクタのひとまわり小さいものを「ミニ」といって、例えばウオークマンなどのヘッドフォン端子に使われているのは「ミニの3P」という。このミニには径が違う2種類のものがあるんだけど、まあ通常は太い方しか音響用には使わない。(というか、ミニ自体ほとんど使用しない)
図10-1-5のような形状のオスを「プラグ」といい、受ける側を「ジャック」という。一時期流行った「アンプラグド」というのは、「プラグを差し込まない」、つまり、「アンプやPAにプラグを差し込まない」という意味が転じて、「アコースティックな」という意味になった。
10-1-5 その他コネクタ
- ピンコネクタ
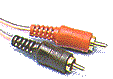 |
| 写真10-1-1 RCAコネクタ |
「ピン」といったり、「RCA」といったりする。民生用のオーディオ機器の入出力はほとんどこの規格だけど、ホット側から先に接触する構造になっている(ということは接続時に大きなノイズが発生する。最近ノイトリック社から、先にグランド側が接触するピンプラグが発売されたけど、余り一般的ではないからね。)ことや、物理的強度の問題からプロ用の機器にはほとんど用いられない。それじゃ何故パンピー向けの音響機器にこのピンが使われるかというと、それはなにをおいてもコストの安さという理由だ。だけど接触面積は結構広いので、抜き差しを考えない用途ならば、結構理想的なコネクタではあるな。
- DINコネクタ
その名の通り、日本のJISにあたるドイツの工業規格DIN(Deutche Industrie
Normen)によって定められたコネクタの一種。日本ではその中でも13.5mm径の丸形のものが一般的なので、DINコネクタといったら普通はこれを指す。他に一般にMINI-DINと呼ばれているひとまわり小さいものもコンピュータなどにはよく使われる。ちなみに「でいん」と発音するのが本当だけど、普通は「でぃん」ということが多い。綴りを見てもらえば判るようにドイツ語の略だ。
DINコネクタにも色々なピン数があるんだけど、現在最も使われているのは、5ピンタイプのもので、MIDIケーブルに使われている奴だ。その他6〜8ピンのものがリモートコントローラーの端子や、コンピューターのキーボード端子に使われることもあるけど、日本で使われる音響機器の入出力端子としては現在は使われることがない。20年ほど前に5ピンタイプのもので、カセットデッキの入出力を1つにまとめたケーブル(入力のLR、出力のLRの4つのホットとグランド端子)があったんだけど、流行ることなくすたれてしもうた。(合掌)
- 110/239A
一般に「ひゃくとお」といわれているもの。元々は電話の交換台用として開発されたコネクタだ。110というのはプラグ(オス側)の名称で、ジャックの方は239Aという名称だ。バランス転送が出来てコネクタの信頼性も高いので、音響の世界では古くからパッチベイなんかに利用されている。(昔からあるホールや放送局ではよく見かける)ところが最近のレコーディングスタジオでは、膨大な数の入出力を扱うために110では場所をとりすぎるようになってきたので、パッチベイのコネクタの主流は次のバンタムに移りつつある。
- バンタム
110を半分ぐらいの大きさにしたような形状。バンタムというのは通称で、ちゃんとした規格統一がされているわけじゃないんだな。だからメーカーが独自に勝手な品番をつけている。形状の小さなコネクタなので、接触不良やなんかはよく起きる。だから信頼性という点では110/239Aの方がよっぽどあるんだけど、同じスペースに110/239Aの2倍くらいのジャックを並べれるという小ささは魅力的で、レコーディングスタジオのパッチベイにはまず間違いなくこのバンタムコネクタが使われている。(しかしこのバンタムという名前はどこから来ているのかなあ?ボクシングの階級からだろうか?だったら「フライコネクタ」でも良さそうなものだし・・・)
10-1-6 マイクケーブル
マイクから何かに接続するケーブルはみんな「マイクケーブル」なんだけど、音響業界で「マイクケーブル」といったら、両端にキャノンコネクタのついたものを指すのだよ。長さに関しての明確な規定はないけど、5m以上のものを「マイクケーブル」と呼ぶことが多いようだ。PA屋さんは5m,
10m, 15m, 20mというように長さ別に数種類用意しておいて必要に応じて使い分けるのだ。注意しなくてはならないのは、PA屋さんの「マイクケーブル」は両端にキャノンの11Cと12Cがついているけど、放送局関係やホール関係では11C-11Cのケーブルを「マイクケーブル」と呼び、11C-12Cのケーブルは「延長ケーブル」などと呼んだりすることだ。これは放送局関係やホール関係のマイクを入力する機器には、32もしくは14のコネクタ(オスのコネクタ)がついているからだ。(逆に出力はメス)そういやあ昔の生徒がマイクケーブルのことを「マイケル」と呼んでいたな。(地味に気に入っている)
| Q |
PAの現場で「マイケル」のことを何といっていますか? |
| A |
マイクケーブル |
■■■■■■6名 |
| マイクコード |
■■■■■■■■8名 |
| 特に区別しては言わない |
■1名 |
| ただ単に○○m物のケーブル |
■1名 |
| 11-12シールド |
■1名 |
| 長めの11C-12Cは、マイクをつなごうが、DIやミキサをつなごうが、マイクケーブル(コード)という人が多いみたいね。 |
| 表10-1-1 マイクケーブルの呼び方 |
10-1-7 立ち上げ
PAの世界では、マルチケーブルのボックスからミキサーに入力するためのケーブルのことをいう。「マイクケーブル」の短いものだと思えばよろし。長さに決まりはないけど、1〜2m程度のものが多い。PA屋さんによっては1.5mと3mというように2種類以上の長さを用意しているところもある。他には「パッチ」「パッチング」「パッチケーブル」などの呼び方がある。ちなみにでかい音で有名な東京の某PA屋さんでは「短マイク」というそうだ。「マイケル」の短いものだから「ミニケル」と呼んでもいいような気がする。(笑)
他に(16chまでの)マルチケーブルに使われるFKコネクタから、直接12Cのコネクタがマルチケーブルの回線数分出ている「立ち上げ」もあって、このようなものは「FK」とか「FK-12」などと呼ばれる。放送局やホールや録音の世界では入出力は、パッチベイにすでに立ち上っているので、「立ち上げ」といういい方はしなくて、「パッチ」「パッチング」「パッチケーブル」ということが多いな。ホール関係では11C-11Cの短いものが、放送関係や比較的小規模のレコーディング関係では110-110が、中規模以上のレコーディング関係ではバンタム−バンタムがこれにあたる。長さはパッチベイの対角線以上の長さがあればいいので、長くて1mくらいで、通常長さの違う数種類のものを用意する。
| Q |
PAの現場で「ミニケル」のことを何と呼んでいますか? |
| A |
立ち上げ |
■■■■■■■■■■■■■■14名 |
| パッチ |
■■■3名 |
| PAの場合は「立ち上げ」と呼ぶ人が多いけど、この人達もパッチベイ用のケーブルは「パッチ」「パッチング」「パッチケーブル」という人が多い。 |
| 表10-1-2 立ち上げケーブルの呼び方 |
10-1-8 2Pケーブル
いわゆる楽器用の「シールド」だ。2P-2P「つーぴーつーぴー」と呼ぶ人が多い。(たまに「りゃんぴーりゃんぴー」などといって、すさんだ日常生活をうかがわせる奴もいるけど。)不思議と3P-3Pは「さんぴーさんぴー」という。これってツービート、フォービート、エイトビートときて、じゅうろくビートというのと一緒だな。これも「血」か?たまに「標準」とか「47」とか「フォーン」とかいう人もいる。またジャックの径から「3.5φ」という人もいるぞ。
でも2つのピンをもつコネクタはみんな「2P」なので、本来2P以外のいい方のほうが正確だけどね。そうそうたまに「ピン」という人もいるけど、これは「RCA」の意味でのピンと混同しやすいので使わない方がいい。主な用途は楽器だけど、民生用の機器では、コネクタの主役なのでスピーカー端子に使ったり、マイク端子に使ったりと用途を特定できないくらいいろいろなものに使用される。よってスピーカー用の2P-2Pをギターに使って
「ノイズだらけやんけ〜!」となったり、
3P-3Pをギターに使って
「エフェクターの電源が入らんやんけ〜!」となったり、
マイク用の2P-2Pをスピーカに使って
「火事になったやんけ〜!」
とか、とにかく楽しい事例はつきない。
10-1-9 変換ケーブル・アダプタ
ケーブルの両端に異なる種類のコネクタが付いている場合、これを変換ケーブルというわけだ。2P、ミニ、ピンの間の変換はアンバランスで両端ともオスになるので、両端のコネクタの名前をとって「2P-ピン」とか言えば問題ないけど、片側がキャノンコネクタの場合は「キャノン-2P」というとキャノン側がオスかメスかわからないので「11-2P」とか「12-2P」とかいういい方をする。さらにバランスをケーブルでアンバランスにしてしまうので、2番ホットなのか3番ホットなのかが重要になってくる。(2番ホットの11-2Pと3番ホットの12-2Pを組み合わせて2P-2Pを作ると、ショートして音が出ない。)とはいうものの、変換ケーブルを使うのはほとんどPAの世界で、この世界ではまず2番ホットなので、普通は変換ケーブルも2番ホットになっている。キャノンはこのほかに11-11や12-12などのメスメス、オスオスの変換や、逆相変換(リバース)もある。
 |
| 図10-1-6 バランス・アンバランス変換 |
3P-2Pの変換も2種類あって、一つは3Pのバランスを2Pのアンバランスに変換するもの。リングとスリーブをショートさせて作る。通常使用することはほとんどない。
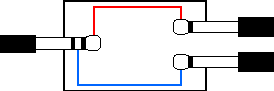 |
| 図10-1-7 インサートケーブル |
もう一つは「インサートケーブル」と呼ばれる3P-2P×2のもの。インサートケーブルは3Pのチップとスリーブ間、リングとスリーブ間でセンドリターンをするんだけど、どちらをセンド側にしてどちらをリターン側にするかについては機材によって違うので注意。
 |
| 写真10-1-2 ダンガン |
変換アダプターと呼ばれる、ケーブルではないコネクタが一体化した10cmくらいの筒形のものもある。俗称「ダンガン」。よく使われるのは11-11、12-12、逆相、パッド、11-2Pなど。11-2Pは小型のトランスが内蔵され、簡単なパッシブタイプのDIのようになっているものも多い。
10-1-10 コネクタのピン接続
10-1-11 スピーカーケーブル
| 3ピンの場合の接続例 |
| 1番 |
2番 |
3番 |
| 無接続 |
ホット |
コールド |
| コールド |
ホット |
無接続 |
| コールド |
ホット |
ホット |
パワーアンプとスピーカーの間を接続するケーブルのことで、マイクケーブルなどに比べて、大電流に耐えられるように太めの芯線を使う。インピーダンスが極端に低い箇所なので、普通シールデッドケーブルは使用されず、アンバランス伝送だ。ケーブル本体は2芯または4芯の撚線が使われている。よく使われているカナレの6S4などは4芯のうえにビニール皮膜があって、ぱっと見はマイクケーブルによく似ているので混同しないように注意。レコーディングでは一度接続すればそのままなので、ケーブルのビニール表皮を剥いただけの状態(先バラ)で使われることも多い。
またPAの現場ではほぼまちがいなく両端に3ピンのキャノンコネクタが付いている。これは音響屋さんが3ピンのキャノンコネクタ(の部品)を多く持っているからで、本来ならマイク系との混同をさけるためにも3ピンでないものを使用するほうがいい。といっても2ピンのものは電源によく使われるので、混乱を避けるためにはホール設備関係によくあるように4ピンを使うのがいい。しかしながらこれにも欠点があって、4ピンは3ピンのものよりも流せる電流が少ないのだな。しかも4ピンのうちの半分しか使わないのももったいないし・・・
ということで結局、3ピンのキャノンが両端についたスピーカケーブルを使うことが多いんだけど、3ピンのうちどの2つを使用するかが音響屋さんによって異なり、統一はとれていないので、借り物が混ざるシステムは十分に注意しよう。最悪の場合機材を破損するおそれがある。
 |
| 写真10-1-2 スピコン |
キャノン以外のコネクタでは、2P、バナナプラグ、先バラ(これはコネクタではないけど)などがある。2Pは楽器用や比較的安価なものに多く見られるけど、接続の際に一瞬ショートするので大出力のシステムに使用されることはない。バナナは接点面積が比較的広く、極性を簡単に逆に出来るなどのメリットはあるものの、「引っ張り」に弱く、最近使っているところはない。先バラは接点面積が大きいけど、何回もの装脱着にはむかないので、移動する事のないスタジオなどで音質を最優先して使われているくらいかな。また最近のフロントスピーカーシステムなどでは「スピコン」といわれる(ノイトリック社の商品名、アポジ社のスピーカーシステムなどに使用されている。)スピーカー専用のコネクタやスピーカーメーカー独自のコネクタが使われることも多い。これらは太いケーブルが使用出来て、接点面積も大きく、しかも装脱着が容易になっているのが特徴だ。(ただ経年劣化でロックが緩くなって接触が悪くなることもある)
| スピーカコネクタの比較 |
| 接点面積 |
キャノン
2P
バナナ
先バラ
スピコン |
■■■
■
■■■■
■■■■■
■■■■ |
接点の面から見ると、先バラが接点面積も大きく、接点での抵抗値も低いので一番よい。コネクタではバナナやスピコンが優秀。2Pは限りなく点接触に近いので、接点面積の面では不利。 |
| 経年劣化 |
キャノン
2P
バナナ
先バラ
スピコン |
■■■■■
■■■
■■■■■
■
■■■■ |
経年劣化はすべてのコネクタに起き、それに対して特に優秀なコネクタはない。スピコンはロック機構がゆるむことがある。(特に初期型のリングロックを採用しているタイプ)先バラはむき出しになっている銅の部分が酸化して、接点不良を起こす事がある。 |
| 強度 |
キャノン
2P
バナナ
先バラ
スピコン |
■■■■■
■■
■
■■■■
■■■■■ |
強度の面ではキャノンとスピコンが優秀。どちらもロック機構を持ち(引っ張っても外れない)、頑丈なコネクタだからだ。先バラもコネクタでロックするので引っ張りには強いが、それ以外の衝撃には弱い。 |
| 価格 |
キャノン
2P
バナナ
先バラ
スピコン |
■■
■■■■
■■■
■■■■■
■ |
現実問題として、コネクタは数十〜百、場合によっては千の単位で必要となるので、価格の問題は無視できない。単価でいうとスピコンは1000円位・キャノンは500円位・2Pは300円くらい(ボディが金属製のもの)・バナナは50円位・先バラは0円だ。 |
| 汎用性 |
キャノン
2P
バナナ
先バラ
スピコン |
■■■■■
■■■
■
■■
■ |
PAなどで機材の貸し借りをしたときに、他の会社との互換性があるかという面では、キャノンがダントツだ。ただし前述の通り、ピンの使用が同じとは限らない。 |