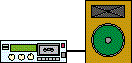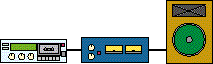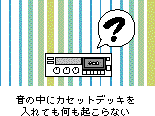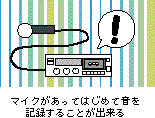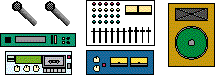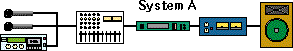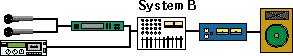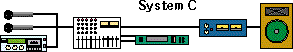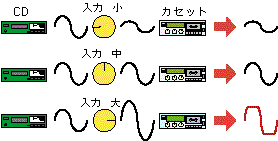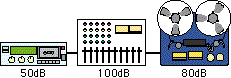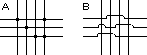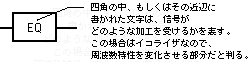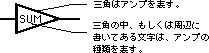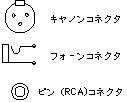9-1 音響システム
この章では音響理論の基本となる部分で、重要な事項であるにも関わらず、結構判ってないままほっておかれることの多い事項について簡単にまとめてある。本来だったら一番最初に来るような内容なんだけど、最初から拒絶反応を起こすといけないので、こんなに後ろに来てしまったのだ。さて、最初はシステムのお話から・・・・
9-1-1 音響システム
たぶんみんな部屋に入れば、いくつかの音響製品があるでしょ?これらの音響製品はほとんどのものが「自己完結型」の機器という事が出来る。例えばラジカセならカセットテープを入れて再生ボタンを押すだけで音が出る。つまり、その1台だけでカセットテープを聴くという作業は出来てしまうわけね。
ところが例外もあって、ビデオデッキなんかの場合はどうだろうか。ビデオデッキにテープを入れて再生しても「ぢーころぢーころ」いっているだけで、面白くもなんともない。つまりビデオデッキはテレビ等と一緒に使って、はじめて「画像を見る」という本来の目的を果たすことが可能となるわけだ。音響機器はほとんどこのビデオデッキタイプのもので、単体では何の役にもたたないものばかりだといえる。
さて、それらの機器をつないで「どうしたら音が出るか」を考えていこう。音響システムには必ず信号の「入力の部分」と「出力の部分」があり、その入力の部分と出力の部分のあいだには必要に応じて「信号を加工する部分」があるというのが基本。信号は電気の形で受け渡しされる。
ためしに、カセットテープをスピーカで鳴らす音響システムを考えてみよう。この音響システムにとっての音の「入力の部分」はカセットテープを再生するカセットデッキで、「出力の部分」はスピーカなわけだ。「音を加工する部分」は必要がないような感じがするので、とりあえずこの音響システムにはいれないでおこう。
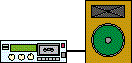 |
| 図9-1-1 システム1 |
ここでいう入力の部分とは音響システムから見た「音が入ってくるところ」という意味で、「音源」といういいかたをすることもある。だから、逆に言うと何がしかの信号が音響システムに「出力」される。(この場合はカセットテープに記録された信号)出力の部分というのは音響システムから見た「音が出ていくところ」でこの部分には何がしかの信号が音響システムから「入力」される。(この場合はカセットデッキから出力された信号)
で、実際にこのようなシステムを組んでみても音はなってくれないんだな。その理由はカセットデッキの出力からの信号とスピーカの必要とする信号は、信号の「質」と「大きさ」が違うからだ。たとえて言うなら、乾電池で電子レンジを動かそうとしているようなものだ。それではこのカセットデッキとスピーカのあいだに、「通訳役」のパワーアンプを組み込んでみよう。このパワーアンプが「音を加工する部分」にあたるわけだな。
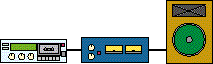 |
| 図9-1-2 システム2 |
こうすると、晴れてカセットテープの音をスピーカから聴くことが出来るわけで、この音響システムの目的を果たしたことになる。よかったよかった。実際の音響システムでは「入口の部分」、「出口の部分」、「音を加工する部分」がそれぞれ複数になり、複雑なシステムになるんだけど、基本的にこの3つが必ず存在するという原則は変わらない。
- 入力部
音響システムでは電気の形で信号がやりとりされる。ところが音響システムが扱うのは音で、その実態は空気の振動なわけだ。空気振動と電気信号のあいだには何の関係もない。
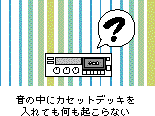
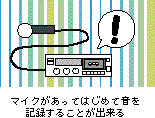 |
| 図9-1-3 入力部分の必要性 |
音を録音しようとして音が鳴っているところへカセットテープを入れたカセットデッキを置き、録音ボタンを押したところでカセットテープには何も録音されない。ゆえにここで空気振動を電気信号に変換する器材が必要になってくる。その変換器の名前はマイクロフォン。いわゆるマイクだ。(以降マイクと表記)「なあんだ」というなかれ、マイクがあってはじめて音響機器は音を扱えるようになるのだ。マイクがなければ音響機器などほとんど粗大ゴミと同じだ。
またマイクによって取り込まれた音をさまざまな方法によって記録、伝送した「入力」もある。たとえばCDやテープ、ラジオやテレビの音声などなど。これらの音響機器の出力は信号レベルがマイクに比べて比較的大きい。この出力の信号レベルが大きいことを「ラインレベル」、小さいものはその名の通り「マイクレベル」というわけだ。
- 出力部
音響システムが音を出すことを目的としている場合、出力部に用いられるのはスピーカである。(ヘッドフォンもスピーカの一種)
マイクが空気振動を電気信号に変換する働きをもっているのに対し、スピーカはその逆の働き、すなわち電気信号を空気振動に変換する働きをもっている。マイクと同じくこのスピーカがないと音響機器は意味のないものになってしまうわけだな。そのほかに音響システムの出力としては記録媒体、伝送媒体などがあるぞと。記録媒体とは簡単いいうと「録音するもの」で、CD、テープレコーダーなどがこれにあたる。また伝送媒体とは放送や電話などであり、これら両者ともに電気信号のまま出力とするが、最終的にどこかでスピーカによって空気振動に変換されることには変わりがない。
- 加工部
加工部というと少し堅苦しいが、音量、音質、音程や信号の形を変化させたり、混合分岐する役目で、ここの代表格はミキサとアンプ。実際の音響システムではこの加工部が複雑になることが多い。ミキサの役割はいろいろあるが、基本的には音量操作と混合と分岐。アンプの役割は信号レベルを大きくしてやることである。そのほかにこの加工部には、さまざまな効果を得るエフェクタなどがある。
9-1-2 音響システムの設計
音響システムの設計(というと少し大げさだが)は次の2点に要約される。
- 必要な器材を選ぶ。
- それらを最良の方法で接続する。
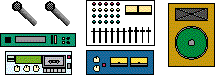 |
| 図9-1-4 必要な機材 |
たとえばカラオケの音響システムを考えてみよう。まず入力部で必要な器材は、カラオケのテープなりレーザーディスクなりを再生する装置。ここではカセットデッキとしよう。(イラストを描き直すのが面倒なのでな)歌用のマイクは「銀座の恋の物語」のことも考えて2本とする。(おやぢ)出力部は、放送するわけでもなく録音するわけでもないので、スピーカだけでいい。スピーカを鳴らすためにはパワーアンプが必要で、そのほかにも2本のマイクとテープの音を混ぜて音量や音質の調整をするミキサと、歌用のマイクにいわゆるエコーをかけるためにエフェクタが必要である。ということで、図9-1-4のような機材が必要となるわけだな。
さてこれらの機材をつないでゆくわけだが、スピーカを鳴らすためにはパワーアンプが必要なので、スピーカの前には必ずパワーアンプを置くとすると、大体次のようなつなぎかたが考えられる。ところがこれらはそれぞれ音響システムとして成り立っているが、機能的には大きく異なっているのだな。
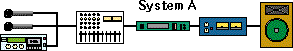 |
| 図9-1-5 システムA |
図9-1-5のシステムは、入力はミキサでまとめて、エフェクタをかけて出力するという点では理屈にあってるんだけど、歌(マイク)とカラオケ(カセットデッキ)の両方にエコー(エフェクタ)がかかってしまうので不都合だ。こういったシステムをはじめは組んでしまいがちなので気をつけよう。
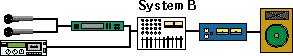 |
| 図9-1-6 システムB |
図9-1-6のシステムは歌にだけエコーがかけられて、カセットにはかからないと言う点では図9-1-5よりは使い勝手がいいが、マイクの出力レベルがエフェクタにとって十分とはいえない点と、マイク2本の音量や音質が操作できないのが難点だ。
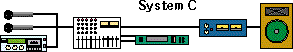 |
| 図9-1-7 システムC |
図9-1-7のシステムがこの場合の正解といえるだろう。図9-1-5と図9-1-6のシステムにある不都合がない。すなわちこのシステムはマイク2本とカセットデッキの音量と音質を、別々に調整でき、エフェクタのかかり具合もそれぞれに調整できるわけだ。
図9-1-7では上の2つと違った概念が登場しているの気づいたかな?それはエフェクタのつなぎ方だ。上の2つの例が入力から出力まで、通り道は一つしか存在しないのに対して、図9-1-7ではエフェクタがミキサからの出力を入力し、出力をエフェクタに返している。つまり、入力や出力に直接関係しない信号の流れが出来ているわけだな。このようなつなぎ方をするのはほとんどの場合、ミキサとエフェクタ(さらにエフェクタの中でもリバーブ・ディレイなどの原音に効果を付加するタイプのエフェクタ)だけだ。
このように同じ機材を使用しても、使い勝手がつなぎ方によって大きく左右される。よって音響システムの設計の基本は、使用する機材を選出し、それらを最良の方法でつなぐことだ。
9-1-3 ダイナミックレンジ
ダイナミックレンジというのは、基本的に音響機器の性能を表わすものの一つにしか過ぎないのだけれど、ダイナミックレンジを上手く使うということが音響システム全般の大前提なので、しっかり理解しておこう。ダイナミックレンジとは簡単にいうと、「ある音響機器が扱える最大の信号レベルから、その音響機器自体が持つ雑音のレベルを引いたもの」。語弊を恐れずにもっと簡単に言うと、「その音響機器にはどれだけ大きい信号まで大丈夫か」ってことだ。
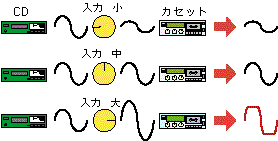 |
| 図9-1-8 扱える信号の限界 |
たとえば録音レベルの調整ができるカセットデッキ(要は普通のラジカセなんかと違って、録音する前に録音レベルをつまみで調整しなくてはいけないもの)でCDから音楽をダビングするとしよう。入力レベルが小さいうちは、カセットテープにそのまま記録できるけど、ある程度以上大きい入力をすると、音が割れてしまう。ということはカセットデッキには正常に録音できるレベルの大きさには限界があるということだ。音響機器には必ずこのように扱える信号レベルの限界がある。
かといって音が割れないように小さく録音すればよいかというとそうでもないんだな。知っての通りカセットテープには雑音があって、(カセットデッキ本体にもある。ただしテープにくらべればかわいいもんだが)これは音を大きく録音しようと小さく録音しようと知ったことじゃなく、常に一定。だから雑音を避けるためには(なるべく雑音をめだたてさせないようにするためには)、録音レベルを大きくとった
ほうがいい。
このように雑音と扱える信号レベルの限界という相反する2つの面をかかえているため、「なるべく大きく、かつ音が割れないようなレベルで信号を入力してやる」ってことが大事となるわけだ。これは何もカセットデッキにかぎったことじゃなく、すべての音響機器に関していえることなのだ。
それではなぜ音響機器には扱える信号レベルの限界があるのかを説明しよう。(マイクやスピーカについては構造上の問題なので、ここでは省略)
音響機器にはごくわずかの例外を除いて、コンセントや乾電池などのいわゆる電源が必要だというのは、何となく身近なものを見てればわかるよね。つまり音響機器は「電気信号」を電源という「電気の力」で加工しているというわけだ。だから音響機器はその電気の力よりも大きい電気信号は扱いきれないわけだな。「電気の力」というお金を千円しかもってない「音響機器」という人が、「電気信号」という人に『5百円銀行にいれて4百円出せ』と命令されれば、「音響機器」という人はそれを実行することができるが、『一万円銀行にいれてから9千円出せ。』と命令されても「音響機器」という人ができるのは千円いれて千円出すことだけ。つまり「電気信号」という人に言われたとおりにできるのは千円までで、それ以上の金額の出し入れは言われたとおりにはできないってことだ。このように音響機器に対しての信号レベルが大きすぎて、その音響機器の出力が入力と違ったものになってしまったときの信号の状態を「歪(ひずみ)」という。読んで字のごとく(音が)正しくないってことね。
「雑音」ってのはまあ日常会話でも使われる言葉なんで特に説明はいらないよな。まあ「いらん音」ってなイメージだ。
それじゃ「雑音」の反対語はわかるだろうか?答えは「楽音」という耳慣れない言葉だ。この雑音と楽音の区別はどこでするかというと、規則性のある信号を楽音、そうでないものを雑音と呼んでいる。くだけていえば音楽的な信号や言語的な信号を楽音、そうでないものを雑音というってこと。それで雑音は「雑音」という言葉より「ノイズ」といった言葉のほうがよく使われるので、今後はノイズということにしよう。(雑音を英訳するとNoise(ノイズ)だが、日本での使われ方は微妙に異なる。雑音がとにかく「不必要なもの」といったニュアンスなのに対して、ノイズは不必要なものといった意味に加えて「不規則な信号音」といった必ずしもマイナスのイメージとはいいきれないニュアンスを含んで使われている。ただしこれは少しハイレベルな話になるので、しばらくは「ノイズ=不必要な音」としておこう。)
さきほどにもいったように、何百万とする音響機器でも、おもちゃに毛の生えた程度のものでも、音響機器ってのは必ずノイズを発生する。ただなるべくその音響機器のノイズを減らすのが音響機器を設計する人の役目であり、その音響機器のノイズをなるべく気にならないように使うのが私たちの役目なのだ。じゃあいったいどうすればいいかというのはもうわかるよね。「音響機器を使用するときは適正な信号レベルで使用する。」ってことだ。適正な信号レベルってのは信号が歪まない最大の信号レベルのことだ。さきほどカセットデッキの録音レベルを例にとって説明したけど、ミキサであろうがアンプであろうが同じこと。
ダイナミックレンジというのは、その音響機器が扱える最大信号レベルからノイズレベルを引いたもので、「実質扱える信号レベルの大きさ」ということになる。当然これは大きければ大きいほど優秀な機器だといっていい。(ダイナミックレンジが「広い」といういいかたをすることも多い。ちなみに「広い」の逆は「狭い」。)
また「音響システムのダイナミックレンジは、その音響システムの中の最もダイナミックレンジが小さい音響機器のダイナミックレンジに等しくなる。」というのも理解しておこう。たとえば図9-1-9のようにカセットテープに記録された音楽をミキサを通してオープンテープにダビングする音響システムを考えてみよう。
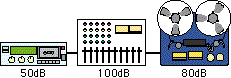 |
| 図9-1-9 トータルのダイナミックレンジは50dB |
カセットデッキの再生時のダイナミックレンジが50dB、ミキサのダイナミックレンジが100dB、オープンデッキの録音時のダイナミックレンジが80dBだとしよう。(dBについては後述。ここではダイナミックレンジをあらわすときの単位で、数値が大きければ大きいほどダイナミックレンジが広く、性能がよいとおもってくれ。)この音響システムのダイナミックレンジはダイナミックレンジが最小のカセットデッキと同じ50dBになる。これはカセットデッキのダイナミックレンジよりダイナミックレンジが広いミキサやオープンデッキのダイナミックレンジを1000dBにしようが10000000dBにしようが、かわらず50dBのままだ。よって、システムを考えるときにあまり極端にダイナミックレンジの違う機器を入れると、システム全体がその機器と同じダイナミックレンジになってしまうので注意しよう。
9-1-4 ブロックダイアグラム
音響機器一つ一つについても、音響システムと同じように単体では何の働きもしない部品を組み合わせて、なにがしかの機能を持たせたものだ。たとえばカセットデッキを例にとると、カセットデッキはケース、モーター、コネクター、電子基板などのさまざまな部品から構成されている。わたしたちはカセットデッキ屋さんではないので、ケースの横幅が437.5ミリだとかモーターの型番がどうだとかについてのヲタッキーな知識を持つ必要はとりあえずない。けれども音を扱う以上、信号経路については知っておく必要がある。
 |
| 図9-1-10 理解しやすさ |
信号経路はおびただしい数の電子部品によって構成されていて、この電子部品のつなぎ方を表わしたのが回路図といわれるものだ。これは修理の時や、細かい情報を読み取ったりするのに使われる。だが、回路図は読み取るのにはかなりの知識やなれが必要なことと、細かすぎて全体の流れがわかりにくいという理由から、通常ブロックダイアグラムによって信号経路の情報を読み取る。ブロックダイアグラムは電子回路をその役割ごとにいくつかに分けて、それらがどのようにつなぎ合わされているかを示すもので、まあ回路図を簡略化してよりわかりやすくなったものだと思えばよろし。
このブロックダイアグラムが読めるようになることによって、初めて使う音響機器でもこのブロックダイアグラムさえあれば使いこなすことが出来るので、少しこむずかしい部分ではあるけれども、なんとか読めるようにしておこう。
- 信号経路
基本的に信号は左から右の方へ流れる。つまり、入力が左で出力が右側にかかれるわけだ。ちなみにほとんどの音響機器は実際のパネル配置もそうなっていることが多い。唯一の例外は、ギター用のコンパクトエフェクタで、右が入力で左が出力だ。これは左が入力だと、(多数派の)右利きのギタリストが、エフェクタをつないだときに、ギターからエフェクタへのケーブルが足下を横切ってしまうためだ。
 |
| 図9-1-11 接触・非接触 |
信号経路は、ブロックダイアグラムを見るといろいろな記号が直線で結ばれているので判かると思う。2本もしくはそれ以上の直線が交差する場合、それらがつながっているかつながっていないかを示すのには2通りの方法があるけど、最近はAの方法が主流になっている。
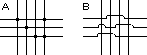 |
| 図9-1-12 信号経路の交差 |
Bの方法だと、図9-1-12のように複数の信号経路が交差した場合、非常にみにくくなるためだ。
- 加工部
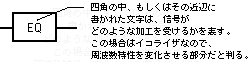 |
| 図9-1-13 加工部 |
図9-1-13のように長方形は信号が何がしかの加工を受けることを示している。長方形の中もしくは近くにどのような加工がされるかが表記されている。
- アンプ
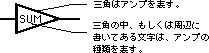 |
| 図9-1-14 アンプ |
図9-1-14のように三角の記号はアンプを表わすもので、三角の中もしくは近くにどのような種類のアンプかが表記される。
アンプというと前に出てきたパワーアンプやギターアンプを想像してしまう人も多いかもしれないが、ここではとりあえず「信号の大きさや形を変えるもの」と理解しておいてほしい。
- HA(Pre) ヘッドアンプ
HAとはHead Ampの略で、Head→頭→最初ということから、信号が一番最初にはいるアンプというのがもともとの意味だけど、実際には、「小さい入力信号をその機器の動作に必要な分だけ信号を増幅してやるもの」という意味に使われている。またHAには増幅率を変化させられるものも多く、その場合は「GAIN」などという表記のボリュームやスイッチの記号がある。
- LINE ラインアンプ
HAと違ってラインレベル、つまり比較的信号レベルの大きい信号を増幅するためのアンプだ。
- DA ドライブアンプ
何かの機械部分、つまりメーターなどの電子部品ではないものを動かすためのアンプ。
- PA パワーアンプ
スピーカやヘッドフォンを鳴らすためのアンプ。
- BA(BUF) バッファアンプ
バッファーアンプとは信号の増幅をおこなわないへんてこなアンプだ。じゃあなんの役に立つのかというと、「インピーダンス」というものの変換をするのだが、この「インピーダンス」については後述するとして、ここでは「増幅率が1倍のアンプ」とでも理解しておけばよろし。まあ実際信号の流れを確認する分には無いものとみなしてもらってもいい。ちなみにバッファー(Buffer)とは「緩和するもの」という意味だ。
- SUN(Σ) サミングアンプ
サミング(Summing)っていうとなんか洗剤の名前みたいだけど、「合計」という意味。だからサミングアンプというのは信号をまぜあわせるためのアンプ。これも信号の増幅はおこなわないので、まあバッファーアンプの一種という考え方もできる。
- ボリューム
 |
| 図9-1-15 ボリューム |
ボリュームてのは可変抵抗器(抵抗値を連続的にかえれる部品)のこと。正確には「バリオーム」なんだけど、今更こだわってもうっとうしがられるので(笑)ボリュームで統一しておこう。これによって音響機器のさまざまなコントロールをおこなうわけだ。記号は図のように抵抗器の記号に矢印がささった記号になっている。これはアンプなんかに較べて視覚的にわかりやすい記号だよね。この記号がブロックダイアグラムの中にあったら、その音響機器のパネルには「つまみ」がついていると思っていい。(たまに基盤の中にあるボリュームもあるけどね)音量(その名の通りボリュームのことだね)やイコライザーやパンポットのつまみなんかがその代表だ。
- スイッチ
 |
| 図9-1-16 スイッチ |
スイッチというのは「テレビのスイッチをいれる。」とか割と聞き慣れた言葉だね。スイッチには2種類あって、1つは回路を入れたり切ったりする働き。「テレビのスイッチをいれる。」というときのスイッチは、いちいちコンセントと抜き差しする代りに電源を入れたり切ったりする働きだ。もう1つは回路の切り替えをする働きで、これは鉄道のポイントみたいなものと思えばいい。たとえば名鉄電車だと名古屋駅から知立に来た列車を、豊橋方面に送ったり、豊田方面に送ったり、蒲郡方面に送ったりするのと一緒で、(ああ、三河ローカル)やってきた信号の送り先を選ぶ働きだ。もちろんその逆の複数の入力信号の中から1つを選ぶ働きもする。スイッチの記号は図9-1-16のように書く。これも視覚的にわかりやすい記号だね。
ちなみにブロックダイアグラムに書かれている入切型のスイッチは、スイッチを「切」の状態でで書いてあり、切り替え型の場合は基本ポジションが書いてある。
- コネクタ
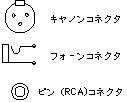 |
| 図9-1-17 コネクタ |
コネクタは日本語でいうと「端子」。どちらの言い方も使われる。音響機器に入出力やら電源やらいろいろなものをコードでつなぐところだ。コネクタにはいろいろな種類があって、それぞれ目的に応じて使い分けられているけど、詳しくは次章でふれるね。
- その他
 |
| 図9-1-18 その他 |
>