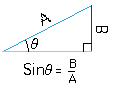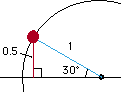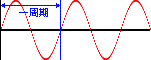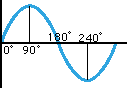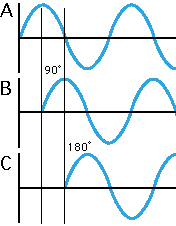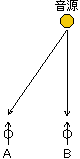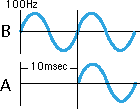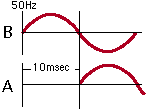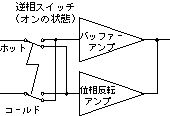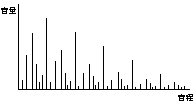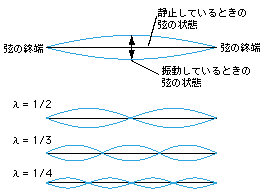倍音(Over Tone / Harmonics)とは簡単にいってしまえば、「音色」を決める要素だ。例えばギターとバイオリンで、同じ音程の音を同じ時間だけ弾いても、みんなはギターの音とバイオリンの音を聴き分けることができる。これはギターとバイオリンの持つ音色が違うためという理由が一番大きな要因だ。それでは音色の違いというのはなにかというと、これが「倍音」というものの含み方の違いなんだな。倍音とは例えば"ド"の音を出したときに同時に出る"ミ"や"ソ"や"1オクターブ上のド"やそれ以外の様々な音のことだ。ちなみにこの倍音を全く含まない音が正弦波なのだったね。
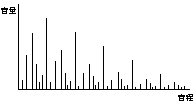 |
| 図9-4-10 倍音 |
もう少し詳しく説明すると、楽器なんかの倍音のようすを見てみると大体図のようになっているのだ。
このようにたとえ"ド"の音を出していても実はいろんな音が出ている訳なんだな。何故このようにいろんな音が出ているのに"ド"の音だと感じられるかというと、いちばん"ド"の音が大きく出ているからなんだ。(図で定期的に音量の大きい部分)シンバルなど、倍音を多く含みかつ、この周期的に大きくでる倍音がない場合は、その音からは、音程感が感じられなくなるわけだな。
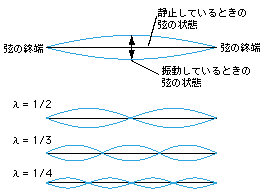 |
| 図9-4-10 倍音の発生 |
それでは1つの音程を弾いているはずなのに何故こんなにいろいろな音が出るのだろう。ここでギターのような弦楽器について例を取ってみよう。ある太さの弦がある張力で引っ張られていたとすると、それをはじくと図9-4-10の一番上のような振動をはじめるのは判るよね。これが「基音」と呼ばれるもので、基本的には一番低い音になる。(共鳴などで他のものと反応して、さらに低い音がでることもある)実際、弦のちょうど中心で弦をはじくとほとんどこのような振動のしかたしかしない訳なんだけど、考えてみると弦楽器って弦の中心で弦をはじくものってないでしょ?みんな真ん中からずれたところで弦をはじいてるよね。(逆の言い方をすると色々な振動を発生させるためにわざとそうしている面もある訳なんだけど)そうすると弦はいろんな振動の仕方をはじめるわけだ。
このいろんな振動というのが倍音の正体で、音程のある楽器に使われる振動は倍音の発生のが比較的規則正しいのだな。というのは色々な振動といっても全く不規則な振動をはじめるわけではなくて、図9-4-10の下の部分のように振動する山と谷の部分が2つになったり3つになったり4つになったりと、本来の振動の正数倍の振動が起こりやすくて、21/3とかいう振動は起こりにくいのだ。で、正数倍の振動も山と谷の数が多くなってくると発生しにくくなってくるわけだな。
また中途半端な振動は折り返し地点の弦がとめられているところ近辺では比較的発生し易いんだけど、弦の中心にいけばいくほど他の振動成分と打ち消し合うことが多くなるので発生しにくいのだ。だからギターなんかブリッジ(ギターの弦がとめられているところ)近くで弾くと堅い(比較的倍音の多い)音がするし、弦の中心で弾くと柔らかい(比較的倍音が少ない)音がするわけだ。またエレクトリックギターなんかはブリッジに近づけてピックアップをつけると倍音を拾いやすいので堅めの音がするし、弦の中心に近づけると柔らかめの音がするわけで、リアーピックアップ(ブリッジに近いピックアップ)とフロントピックアップ(ブリッジから遠いピックアップ)が同じ種類のピックアップを使っても音質が違うのはこのためだ。
ちなみにギターでハーモニクス奏法(弦をはじいてから弦に軽く指をふれて「ぽーん」という丸い音を出す奏法)というのがあるけど、これは弦に指をふれることによって振動モード(振動のしかた)を強制的に変化させているわけだ。例えば開放弦を弾いて12フレット上で弦にふれると、ちょうど弦の中心をふれていることになるので、弦を2分割したような状態となって弦の中心が揺れるような振動が発生できなくなるわけだ。だから元の音程の振動は中心が押さえられているので発生することができないし、1/3の振動なども発生できなくなるわけで、結果として1オクターブ高い(開放弦の半分の長さの振れ)音が出て、倍音も少ないので正弦波に近い柔らかい音になるというわけだ。だから5フレットか24フレット上で弦にふれると弦の1/4の部分にふれているわけだから2オクターブ高い音が出るし、7フレットか19フレット上で弦にふれると弦の約1/3の部分にふれているわけだから1オクターブ上の5度上の音が出るわけだ。このようにハーモニクス奏法は弦の信号と密接な関係があるので、ハーモニクスが出やすいフレットというのは必ず弦の整数分の1の場所にある。