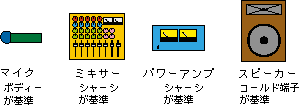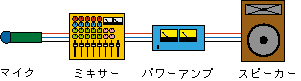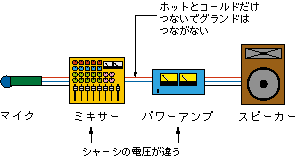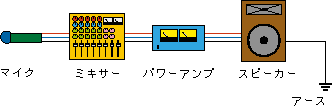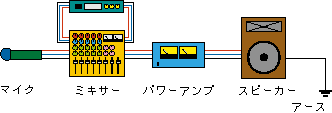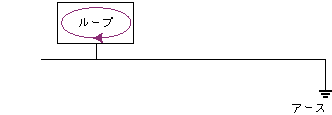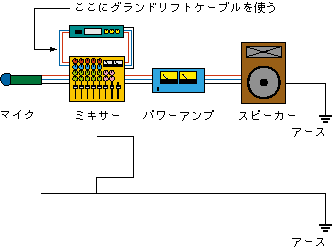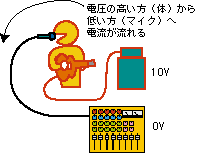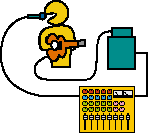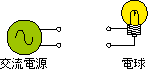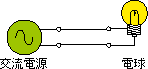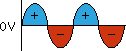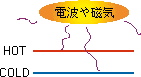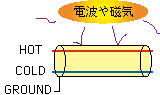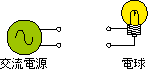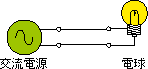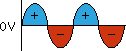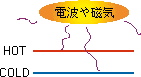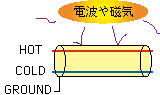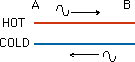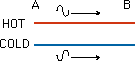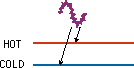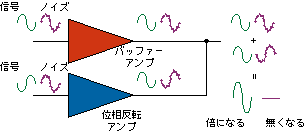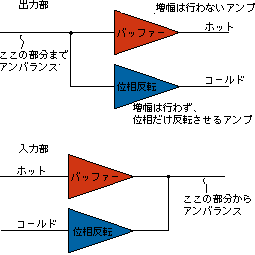9-6 バランスとアンバランス
ある音響機器から別の音響機器に信号を送る場合には、普通ケーブルを使って信号を受け渡す訳なんだけど、この信号の受け渡しの方法にはバランス方式とアンバランス方式があるわけなんだな。結論から先にいうと、バランス方式の方が外部からのノイズに強く、信号の受け渡しには優れている。
9-6-1 ホット・コールド・グランド
9-6-2 バランス方式
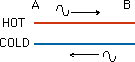 |
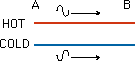 |
| 図9-6-7 信号の流れ |
バランス方式がなぜ外来の雑音に強いかを説明する前に、図9-6-7の左のようにAからBに信号を送っているとき、ホット側から信号を送っているとすると、コールド側には同じ波形のものが返ってきてるわけなんだけど、考え方を変えて右のように、コールド側からは全く逆相の信号を出しているという見方が出来る。こういう考え方をした方が、音響機器のダイアグラムなどは理解しやすい。
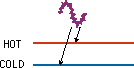 |
| 図9-6-8 ノイズの混入 |
バランス方式がなぜ外来の雑音に強いかというと、例えば図9-6-8のように外部ノイズがバランス方式のケーブルに飛び込んできたとしよう。この時外来ノイズはホットコールドともに同じ位相で混入するわけだ。
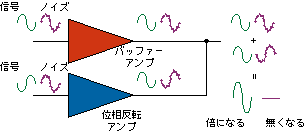 |
| 図9-6-9 ノイズキャンセリング効果 |
ホットコールドともに同じ位相で混入したノイズが、バランス入力の部分に到達してバッファーアンプと位相反転アンプから出てくると図9-6-9のようになるわけで、それぞれをたすと、信号は倍になるけど、外来ノイズは逆相同士になるので打ち消しあってしまうというわけだ。これがバランス方式が外来ノイズに強い理由だ。
さて実際の音響機器では、このバランス方式で信号をやりとりするために、昔は入力と出力にトランス(正式には結合トランスフォーマー)という電子部品を使っていたんだけど、最近はトランスによる音質劣化や重量増加を嫌って、トランスを使わないトランスレス方式のものが多い。(D.Iなどアンバランス方式とバランス方式が機器の中で混在する場合などは、まだトランスを使う方が多いけど)
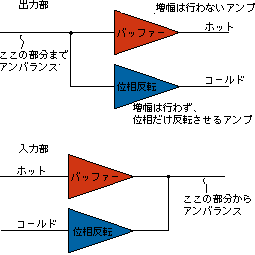 |
| 図9-6-10 トランスレス方式の出力と入力 |
それでトランスレス方式の出力と入力はそれぞれ図のようになっているわけだ。どんな音響機器でも内部ではアンバランス方式で信号をやりとりしている。これは音響機器は基本的に金属ケースでシールドされていて、やりとりする距離も数mmから長くて20cm位なので、外部ノイズの影響を受けにくいことと、バランス方式にすると回路が複雑になりすぎてかえって性能を落としてしまうからだ。それで、出力部分はそのアンバランス方式出来た信号を2つに分けて、バッファーアンプという増幅率0の前後の干渉を防ぐためだけにあるアンプを通してホット側を出力し、コールド側は、同じく増幅率0で入力された信号を逆相にするだけの位相反転アンプを通して出力する。(グランドは省略してある)
入力側はこの逆で、ホット側はバッファーアンプを通して、コールド側は位相反転回路を通してその2つを混ぜ合わせる。(実際の回路の多くはこの2つのアンプを、オペアンプ1つにやらせている)ちなみにここでは余り関係ないけど、2つの信号を足すんだから入力されてアンバランス方式になった信号のレベルはこの時点で2倍の大きさ(6dB増加)になっていることになる。
9-6-3 アンバランス方式
で、確かに信号をやりとりするのにはバランス方式がいいんだけど、コネクターやケーブルが割高になるし、音響機器も回路が複雑になるというデメリットがあるわけで、比較的安価な音響機器の入出力にはアンバランス方式が使われるのだ。
アンバランス方式というのは、バランス方式のグランドをコールドと兼用にして、ホットとグランドの2本で信号をやりとりする方法だ。バランス方式の時は信号の流れなかったグランドにも音声信号が流れるわけだ。このアンバランス方式は、みんなの周りにある機器にはよく使われている。オーディオ用のピンケーブルや、楽器用の2Pケーブルなどだな。またパワーアンプとスピーカーをつなぐケーブルのように信号レベルが十分に大きく、インピーダンスが十分い低いときにはバランス方式にしてもアンバランス方式にしてもさほど変わりがないので、安価に出来るアンバランス方式にすることが多い。大体スピーカーケーブルなんかはシールドもしていないでしょ?(スピーカーケーブルはシールドケーブルにすると逆に、静電容量の問題が出てくる)