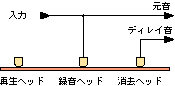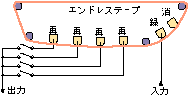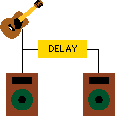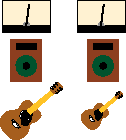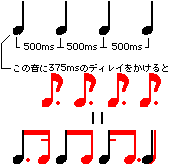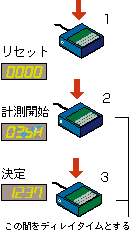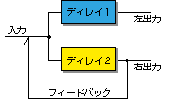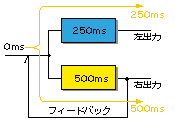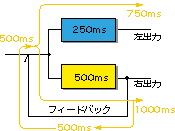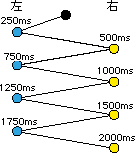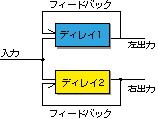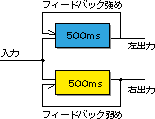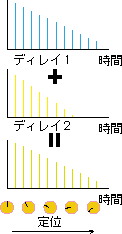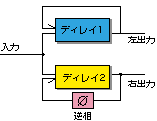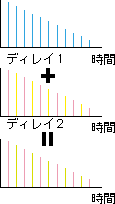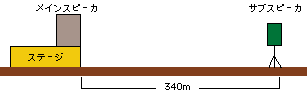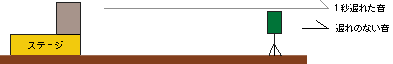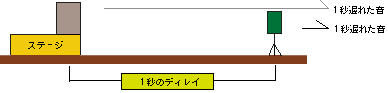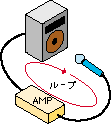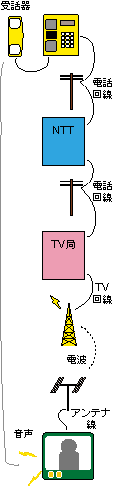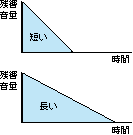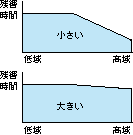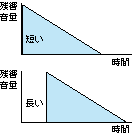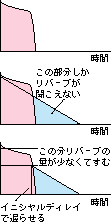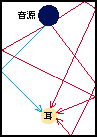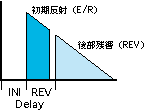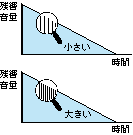8-1 リバーブ
8-1-1 リバーブの歴史
リバーブとは直訳すると、「残響」。現在最もポピュラーかつ重要なエフェクトだ。自然界の音にはその物自体が発生する音に加えて、なにがしか残響成分がかかっている訳で、この残響成分をシミュレートするエフェクターがリバーブだ。昔は電気的にこのリバーブを発生することが難しかったので、エコールームと呼ばれる残響の多い部屋を作り、そのなかでスピーカとマイクを立て、残響を得るという力技で残響を手に入れていたんだよ。
まあでもこの方法はかなりの大きさ(最低でも10畳以上)の部屋を必要するし、残響時間などをほとんど変えられないという欠点があったんだな。(当然運搬することは不可能だし、コストもかかった。逆に言うと良いエコールームを持ったスタジオは人気があった訳だ。)
その後、パイプの片端にスピーカをひっつけて、もう片端から出た音をマイクで拾う方式のCOOPER
TIME CUBEというものが考案されたんだけど、音質的には実用レベルに達しているとはいいがたかった。
初めて人類が残響を簡単に得られるようになったのは、スプリングを利用したリバーブが考案されてから。もちろん急速にスプリングリバーブはスタジオに設置され、リバーブの付加はエンジニアの腕の見せ所となった。またスプリングリバーブによって、リバーブの残響時間が自由に設定出来るようになったことや、可搬型のリバーブも製作可能になった点も見逃せない。
けれどもスプリングリバーブはその構造上、外部からの振動に弱くて、アタックの強い音を入力すると独特の「バネ鳴り」をおこすので使用には注意が必要だったんだ。(おぢさんたちは、入力の前にコンプレッサを入れてみたり、ハイパスフィルターを入れてみたり、ディレイをかけてみたりして苦労して使ってたんだぞ・・・)
スプリングリバーブの中でも、最初にレコーディングスタジオでの使用に耐えうる性能を持って発売されたのが、AKG社のBX-20だ。これは長さや張力や重さの違う(つまり振動モードが違う)スプリングを複数組み合わせて、それまでのスプリングリバーブの持っていた「バネ鳴り」や「バネ臭さ」を排除した物だ。この機種の独特の深みのある音は今でもファンが多い。(わしもその一人)その他にもBX-20を小型にして可搬型にしたBX-25や、日本製のリバック社のスプリングリバーブは今でもよく使用される。
まあでもギターアンプなんかではバネ鳴りの「ピチピチ音」が市民権を得てしまったことも手伝って、現在では(かえってコストが高くついてしまうにもかかわらず)かたくなにほとんどのギターアンプで、スプリングリバーブが使われているけどね。
スプリング式のあとに考案されたのが鉄板式リバーブだ。これは振動系に鉄板を使うことによって、高域特性が格段に良くなった。またアタックの強い入力にも比較的強く、独特の音色とも相まって、ボーカルやパーカッション系に現在でも好んで使用されてるよ。(デジタルリバーブの中のプリセットによくある「PLATE」とはこの鉄板リバーブのシミュレーションだ)
このプレートリバーブの代表選手はEMT社の#140で、古くからあるスタジオには必ずといっていいほど設置してある。また鉄板の代わりに金箔を振動板に使って小型化を図った#240も良く見かける。
その後半導体技術の進歩によりデジタルリバーブが考案された。これは時間の不規則なデジタルディレイの無数の集合によってリバーブ効果を得るもので、自然界に存在する残響のシミュレーションはもちろん、自然界には存在しない残響も作り出せるという、考えてみればとんでもないものだ。機械的な振動系を持たないので、当然外部からの振動やアタックの強い入力にも強く、現在はこのデジタルリバーブが主流になってるんだな。(価格も10年前に比べ10〜30分の1になった。)以後はこのデジタルリバーブについて説明していこう。
8-1-2 デジタルリバーブの原理
デジタルリバーブは、デジタルディレイ(ディレイについては後述)の集合体なんだな。といってデジタルディレイにフィードバックをかけて、何度も繰り返せばデジタルリバーブになるかというと、人生そんなに甘くなくて、繰り返す時間が一定なために不自然な響きになる。これはコムフィルター(詳しくはフランジャの所で触れる)が発生して音に癖が付いてしまうからだ。それでデジタルリバーブは、ディレイタイムのランダムなディレイを多数発生させて、更にディレイタイムが長くなるほど音量を小さくする事によって、リバーブを得ている。2つのチャンネルに違ったディレイタイムを持たせると、リバーブをステレオ化でき、リバーブに広がり感を持たせることが出来る。
8-1-3 デジタルリバーブのパラメータ
ここではヤマハのSPX-1000を例に取って基本的なパラメータをみていこう。メーカーや機種の違いによって表記の仕方が異なっていることもあるけど、大体同じ様な表記がしてあるはずだ。また安価なモデルの場合はパラメータが少なかったり、固定になっていたりする場合もある。
- REV.TIME (Reverberation Time)
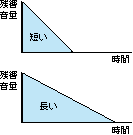 |
| 図8-1-1 リバーブタイム |
ぶっちゃけていっちゃえばリバーブの響く時間。ただしこれは周波数帯によって時間が違うので、通常は500Hzもしくは1kHzの残響音が60dB減衰するまでの時間のことをいっている。通常に使用するリバーブはこの値を2〜3秒に取る。1秒以下にすると、響き感が無くなって金属的な響きが付加される感じになるし、5秒以上ではトンネルの中のような感じ、10秒以上で、リバーブをかけた音源自体のサスティンが伸びたような感じになる。
- HIGH (High frequency reverberation time ratio)
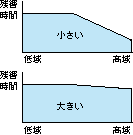 |
| 図8-1-2 ハイ |
残響時間は周波数帯によって違うというのは上述の通り。だいたい自然界に存在する残響は皆そうなんだな。例えば大きなホールで起こる残響は、低域に比べて高域の残響時間が短い。これは音が壁や床などにあたってはね返る際に、その壁や床が柔らかい材質であればあるほど、高域が吸収ために起こるわけだ。よって音がはね返る回数が増えるほど、低域より高域が小さくなっていって、その結果低域の残響時間に比べて高域の残響時間が短くなるというわけ。だから自然な残響をシミュレーションする時には、低域に対して、高域の残響時間を短く設定してやる必要があるわけで、(あまりキラキラした残響なんて聞いたことがないでしょ)逆に言えばこのハイパラメータによって、シミュレーションしている音場の、壁や床の材質を表現することが出来るわけだ。小さくすれば柔らかい布やカーペットを壁や床に張った音場になるし、大きくすれば全面鏡張りの部屋になる。(以前総鏡張りのいかがわしいホテルがあったけど、現在では安全基準に合格しないのでこの手の部屋は出来ないそうだ。)
で、このパラメータの名前の最後にRATIO(比率、割合)と付いてることから判るように、高域の残響時間を、前述のリバーブタイムで設定した値に対して、どれぐらいにするかという表示だ。つまり高域残響時間=中域の残響時間×HIGH。(よって単位はつかない。)このパラメータが1.0の時は中域の残響時間と高域の残響時間が等しくなる。通常のプログラムでは、自然な残響にするためにこのハイを、0.6位に設定してあるけど、あえてこれを1.0にしてデジタルリバーブならではの音作りをすることもできる。またハイの他にLOWというパラメータを持つものもあって、これは中域に対して低域の残響時間を設定するものだ。通常のプログラムでは1.0〜1.5位になっている。
- DIFFUSION (Diffusion)
リバーブの左右の広がり感をコントロールするパラメータ。大きくすれば左右の広がり感は強くなるけど、リバーブの密度は(後述のDENCITYの設定が一定なら)薄くなるので、むやみに上げない方がいい。0〜10までの間で設定できるけど、ポリシーのない時は5にしておこう。
- INI DLY (Initial Delay time)
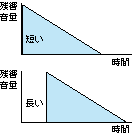 |
| 図8-1-3 イニシャルディレイ |
イニシャルディレイといういい方になっているけど、一般的には「プリディレイ」というほうが多い。後述のアーリーリフレクションとリバーブが発生する時間を遅らせるパラメータ。音源までの距離なんかをシミュレーション出来る。リバーブのかけ方にもよるけど、80msecを越えた辺りからリバーブが遅れて出ているのが音を聞いて判るので、長めに取る場合は慎重に設定しよう。アタックの余りない音源だけにかける時は、このパラメータを上手く設定することによって、少ないエフェクトで最大限の効果を得ることが出来る。
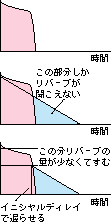 |
図8-1-4 イニシャル
ディレイの使い方 |
たとえば図8-1-4のようにアタックが余りなく、サスティンの長い音源があったとしよう。
これにイニシャルディレイが0のリバーブをかけると、リバーブをリバーブとして感じられる(聞こえる)のは、後半の部分だけだ。だったら前半の部分をイニシャルディレイで遅らせてやれば、リバーブの量も少なくてすむし、リバーブの量が少なくなった分だけ音もクリアになるというわけだ。またもっと積極的に、曲のテンポに合わせた長めのディレイにするという様な用途もある。よくあるのが、バラード系の曲でプリディレイを8分音符の長さに合わせてスネアにかける使い方だ。
- HPF FRQ (High Pass Filter Frequency)
リバーブ音の低域をカットするフィルター。THRUにするとキャンセルされる。リバーブに不必要な低域があると全体の音を濁らせるので、リバーブを使う際には必需品だけど、ミキサでイコライジングが可能なら、そちらを使った方が操作しやすい。
- LPF FRQ (Low Pass Filter Frequency)
リバーブ音の高域をカットするフィルター。THRUにするとキャンセルされる。HPFほど重要ではないけど、ホールの音をシミュレートしたプログラムなどでは、少しこのLPFをいれて高域をカットしてやった方が、音に暖かみが出る。これもミキサでイコライジングが可能なら、そちらを使った方が操作しやすい。特にポリシーのない場合はプリセットのままか、THRUにしておく。
- ER/REV BAL (Early Reflection / Reverberation Balance)
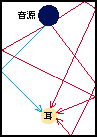 |
図8-1-5 アーリー
リフレクション |
ここからのパラメータはSPX1000ではINT PARAMキーで操作する。
E/R(アーリーリフレクション=初期反射音)と後部残響音(これまでリバーブといってきた部分)のバランス調整。特に意図のない限り50%でいい。アーリーリフレクションというのは、リバーブの本体(後部残響音)が始まる前に、壁や床などに1回だけ反射して届いた音の集合体だ。(反射のしかたによって届く時間が変わるので、1回だけの反射音も時間がいろいろのディレイの集合体になる。)図8-1-5では説明を簡単にするために、単純な長方形の部屋になっているけど、左側に青線で描いてあるのがアーリーリフレクションだ。で、1回反射した音ぐらいは何となく人間の耳にも認知できるけど、2回以上反射した音は、反射のパターンも増えて、届く時間もまちまちになるので(3回反射した音が2回しか反射していない音より先に届くこともあるわけだな)人間の耳にはいわゆるリバーブの音として聞こえてしまうわけだ。図では3本しか描いていないけど、これが赤線の部分だな。
- REV DELAY (Reverberation Delay time)
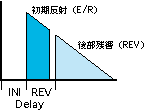 |
| 図8-1-6 リバーブディレイ |
アーリーリフレクションが始まってから、リバーブが発生するまでの時間の遅れをコントロールするパラメータ。従ってリバーブが始まるのはイニシャルディレイ+リバーブディレイの時間が経ってからってことになる。このパラメータは効果的な設定が難しく、極端に変えない限り違いが判りづらいので、プリセットのままにしといた方が無難だ。
- DENCITY (reverberation Dencity)
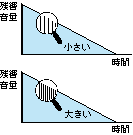 |
| 図8-1-7 デンシティ |
リバーブの密度の設定。デジタルリバーブはこれまで、いかに密度の高いリバーブ音を作るかに心血を注いできたようなものなので、このパラメータを小さく設定する必要はなく、最大値の4にしておけばいい。ただし、あえてこのパラメータを小さくして、安っぽいリバーブ音を作って効果音的に使うという方法はある。
このほかにもパラメータがあるけど、ゲートに対するパラメータなので、詳しくは次のゲートの所を参照のこと。(SPX-90まではリバーブプログラムとゲートリバーブのプログラムは別のものだったんだけど、SPX-900やSPX-1000では全てのリバーブプログラムの中にゲート設定が付いた)
8-1-4 ゲートリバーブの作り方
ここではYAMAHAのSPX-900及び1000を例に取ろう。
SPXに音を入力し、SPXへの入力レベルを調整する。(LEDメーターの上から2つめがたまに点灯するくらい)そしてプリセットの中から、適当なリバーブプログラムをリコールする。(呼び出す)とりあえずなんでもいいなら、1番のホールをリコールする。
パラメータキーで、REV TIMEの画面にしてリバーブタイムを2.5秒程度にセットする。派手なゲートリバーブにしたい時はもう少し長めに取る。
イニシャルパラメータキーを押して、TRIG LVLの画面を出し、60から70位の値にする。さらに何度かイニシャルパラメータキーを押して、ATTACKを最小値・HOLDを20ms程度・RELEASEを300ms程度に各々設定する。TRIG
MSKは初期値でいい。これでゲートリバーブの出来上がりだが、この設定ではそんなに派手なゲートリバーブではないので、もっと露骨にしたい場合はRELEASEを0に近くし、HOLDの値を上げる。ちなみにATTACKを上げていくとリバースゲートのような効果(リバーブ音が段々大きくなってくるようなリバーブ)を得ることが出来る。
SPXがリターンしてあるミキサのチャンネルに、ハイパスフィルタやイコライザーがあるなら、150Hz辺りまでハイパスフィルターを入れる。さらに3kHz辺りをブーストすると、ゲートリバーブの音量を上げることなく効果を強調できる。うるさいこと言わなければSPXの内蔵のデジタルイコライザを使ってもいい。
ちなみに後述のアーリーリフレクションのTYPEをRANDOMして派手なアーリーリフレクションしたものが、「GATE
REVERB」というプログラム。これは「ゲートリバーブみたいな音のするプログラム」という事で、厳密には本物のゲートリバーブではない。本物か偽物かを判断するには、パラメータを見てみればいい。TYPEやROOM
SIZEというパラメータがあったら偽物(アーリーリフレクション)で、REV TIMEというパラメータがあったら本物だ。SPX-90では16番、SPX-1000では9番の「GATE
REVERB」がアーリーリフレクションを使用したプログラムだ。ちなみにSPX-90では17番、SPX-1000では10番の「REVERSE
GATE」というのも最初の反射音より後の反射音の方が大きい特殊なアーリーリフレクションを使ったプログラムだ。このように非常に紛らわしい表記になっているのでプログラムの名前に惑わされないように。
しかし偽物とはいっても、PAなどでは非常に使いやすいプログラムだ。なぜなら本物のゲートリバーブは、入力に対してのゲート設定を慎重にしないと上手くエフェクトがかかってくれないので、設定にある程度の時間がかかるけど、偽物の方はどんなレベルの入力にもゲートリバーブのような効果を付加するので、すぐにエフェクトをかけれるといったメリットがあるからだ。
8-1-5 アーリーリフレクション
アーリーリフレクションというエフェクトは、リバーブの中のアーリーリフレクションだけを取り出したものだ。独特の部屋鳴りのような感じを出せるエフェクターで、派手なエフェクトではないものの、一度使うと結構病みつきになるエフェクトだ。
アーリーリフレクションを個別のエフェクトとして扱っているのは今の所ヤマハだけなので、ここでもSPX-1000を例にとって説明しよう。ちなみにSPX-1000のメーカープリセットの6番のEARLY
REF1は低密度タイプ、7番のEARLY REF2は高密度タイプなので、音を聞きながら良い方を選ぼう。ポリシーがなかったら7番の高密度タイプのEARLY
REF2にしておこう。さらにSPX-1000ではアーリーリフレクション1本1本を自由にエディットできるプログラムもあるけど、細かくなりすぎるのでここでは触れない。
TYPE(Early Refrection Type)
一番変化の現れる部分で、アーリーリフレクションの基本的な音色を選ぶものだ。S-HALL,
L-HALL, RANDOM, REVERSE, PLATE, SPRINGという名前がそれぞれ付いてるけど、これはそれぞれの名前が示すリバーブをシミュレートした時に発生する、アーリーリフレクションを取り出してあるという意味なんだけど、部屋鳴りのシミュレートならばL-HALLが使いやすい。
ROOM SIZE(Room Size)
その名の通り、部屋の大きさのシミュレートだ。この値を大きく取るとディレイ同士の間隔が長きなって、大きい部屋のシュミレーションになるけど、あまり大きく取るとアーリーリフレクションが1本1本のディレイとして聞こえてしまうので、通常は2.0程度にしておこう。
LIVENESS(Room Liveness)
多少のばらつきはあるものの、アーリーリフレクションは時間が遅い反射音ほど音量が小さくなる傾向がある。(特にホール系のアーリーリフレクションでは)この遅くはね返ってきた音が、どれぐらい最初にはね返ってきた音に対して小さくなるかを設定するのがこのパラメータだ。もし時間の早い反射音も長い反射音も音量が同じだとしたら、シミュレーションしている音場は、非常に響きやすい部屋(音が反射する時に吸収されにくい材質の壁を持った部屋)だということが出来るわけで、LIVENESS(響き具合)という名前はここから来ている。1〜10までの値を設定できるけど、(10で最初の反射音と最後の反射音の音量がほぼ等しくなる)これもポリシーのない時は5にしておこう。
DIFFUSION(Diffusion)
アーリーリフレクションの左右の広がり感を設定するパラメータ。リバーブの時と同じくこのパラメータを大きく設定すればするほど左右の広がり感は増すけど、アーリーリフレクションの密度が薄くなってしまうので、ポリシーのない時は5にしておこう。さっきから「ポリシーのない時は・・・」という表現が多いけど、すでにお気づきのように、これは私のいつも無視するパラメータの時にこのいい回しになっているのだ。(笑)
INI DLY(Inital Delay)
入力があってからアーリーリフレクションが始まるまでの遅れを設定するパラメータ。通常は10msec程度でいいけど、アーリーリフレクションを強くかけてその効果を全面に出したい時は少し多め(50msec位)に取った方が、アーリーリフレクションの効果が判りやすくなる。
HPF FREQ(High Pass Filter Frequency)
ハイパスフィルター。低音楽器にかける場合は特にこれをかけておかないと音の濁りにつながりやすいので、100Hz位まで入れておこう。ミキサ側でハイパスフィルターがかけれる場合は、ここであえて設定する必要はないよ。
LPF FREQ(Low Pass Filter Frequency)
基本的にはTHRUでいいんだけど、メーカープリセットを見ると10kHzになっている。確かにTHRUにすると音にざらつきが出てくるので、ここはおとなしくメーカープリセットのまま10kHzにしておこう。
ER NUMBER(Early Refrection Number)
ここからのパラメータはINT PARAMキーで操作する。で、このパラメータはアーリーリフレクションの反射してくるディレイの本数。少なくしてもいいことはないので素直に最大値の19にしておこう。
FB DLY(Feed Back Delay)
アーリーリフレクションがかかって出力された信号を、もう一度入力に戻す時に、どれだけ遅らせてから戻すかを設定するパラメータ。
FB GAIN(Feed Back Gain)
アーリーリフレクションがかかって出力された信号を、もう一度入力に戻す時に、どのくらい戻すのかを設定するパラメータ。見かけ上アーリーリフレクションのディレイの本数を増やすことが出来るけど、あまりいいことはないので使わない方がいいーだろーな。(このパラメータをマイナスにすると逆相でフィードバックがかかるので、音に変な癖を付けるために使うのには面白いかもしれないけどね)よってこのパラメータは0にしておこう。(ここが0ならば、上のFB
GAINと下のFB HIGHはどんな設定になっていてもかまわない。
FB HIGH(Feed Back High Ratio)
入力された信号をもう一度入力に戻す時、高音の減衰具合を設定するパラメータ。もしフィードバックを使う時は1.0でいい。
DENSITY
アーリーリフレクションの密度を設定するパラメータ。元々低密度のEARLY
REF1にはこの設定はない。これももっとも多い3にしとけばよしだ。