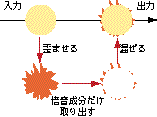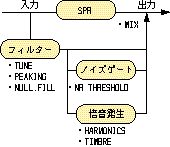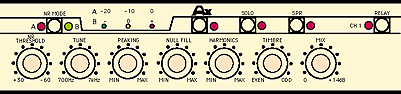まあ原理的には上記の通りなんだけど、これはあくまで初期型のものの動作原理だ。現在あるエキサイタは、歪ませずに波形を分析して倍音を合成するものをはじめ、色々な回路を組み合わせてあるので、説明を読んでも多分さっぱりなんだか判らないと思う。だから使う時には「適当につまみを回して聴きながら各つまみを設定する。」というような使い方になってしまうのだな。といってもめったやたらにつまみを回しても仕方がないので、一応参考までに、APHEX
TYPE-Cを例にとって各コントロールについて説明しておこう。
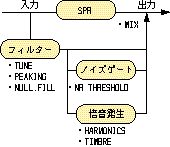 |
図8-6-2 APHEX TYPE-C
ブロックダイアグラム |
APHEX TYPE-Cは大きく分けてエキサイタ部分と、後述のSPR機能の2つの部分があって、エキサイタ部分はさらにノイズゲート部とフィルター部と倍音発生部との3つの部分に分けられる。これはどのように関係しているかというと、まず入力された音を分岐して、フィルター部分に入れる。ここでエキサイタの効果を高めるために、高域をブーストしたような周波数特性にするんだけど、フィルターの特性によって位相のずれも同時に発生する。で、このフィルターからの出力そのままのものと、ノイズゲートを通ったもの、さらに倍音発生器を通ったものの3つを合成して1つにまとめて、元音とミックスするのだ。
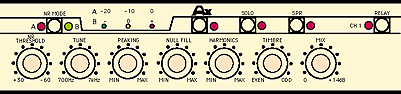 |
| 図8-6-3 APHEX TYPE-C パネル |
- TUNE
まず分岐された入力を高域を強調するフィルターに通す訳なんだけど、どの辺りの周波数から上を強調するのかという設定だ。つまみを右に回せば回すほど(周波数を下げれば下げるほど)エキサイタの効果は増えるけど、元音のイメージが変わってしまう恐れがあるし、左に回すと上品なエキサイタ効果にはなるものの、エキサイタ効果自体は弱くなる。実際の使い方としてはつまみの12時の位置(大体3kHz)から始めて音を聞きながら設定しよう。
- PEAKING
基本的にはTUNEで設定した周波数の下に谷を作り、上に山を作って音に「クセ」をつけるもの。取り立ててこうなるというのは難しいので、実際さわってみて好きな所にしてちょ。(名古屋弁)めんどくさい時は12時の位置にしとけばいい。
- NULL.FILL
NULLはナルと発音するんだけど、この場合は、フィルターをかけるとどうしてもTUNEで設定した周波数近辺で元音の特性に谷が出来てしまうんだけど、この谷のことをいっているんだな。でFILLというのは「満たす」とか「埋める」とかいう意味なので、この谷を平らにする機能だ。右に回しきった状態で谷は完全に埋まるんだけど、埋め立てた分だけTUNEが下がってしまうのだな。まあでもNULLの谷は、音としてそんなに聞いてはっきり判るもんでもないので、難しいことは考えずにこのつまみは12時の位置にしときゃいいと思う。
- NR
これはフィルターをかけることによって発生してしまうノイズを低減させる為の付属回路。コントロールはA/Bタイプの切り替えスイッチとTHRESHOLDつまみ。Aは一般的なノイズゲートのような効き方をして、Bは前述のHUSH
IIのような効き方をする。まあ複数の音源にエキサイタをかけるならA、1つの音源だけにかけるのならBというような使い分けでいいと思う。THRESHOLDはノイズゲート効きを調整するものなので、+30(左に回しきった状態)で事実上ノイズゲートはかからなくなる。他のコントロールの設定によって効き方が変わってしまうので、このノイズゲートの設定は他のコントロールの設定が終わってから決めた方がいい。
- HARMONICS
倍音を人工的に作り出す部分で、従来の歪みを利用したエキサイタではDRIVEと呼ばれてた部分。このエキサイタでは内部素子による演算で倍音を作り出しているので、歪みは発生しないそうだ。(???よーわからんけど)右に回すほど倍音の発生量が多くなる。
- TIMBRE
HARMONICSで発生させた倍音成分の「音色」ともいうべきコントロール。EVENというのは偶数という意味で、ODDというのは奇数の意味だ。だから左に回しきると偶数次倍音だけが出力され、右に回しきると偶数次倍音だけが出力される。こんなものが何で付いているかというと、音響心理学的に偶数次倍音は耳障りの良い音、奇数次倍音は耳障りの悪い音とされているのだな。ギターアンプで真空管アンプがもてはやされる大きな理由の一つは、真空管という素子が歪みを発生する時に偶数次の倍音を多くだす事にあるのだ。(もちろんその他にトランスによる音の「なまり」や、高電圧動作によるダイナミックレンジの広さも大きな要因だけど)だからといってこのつまみはEVENの方に回し切っとけばいいかというとそういう訳でもなくて、音を目立たせたい場合は耳障りが悪いだけにODDの成分が多い方が効果がある。
- Ax
エキサイタ部分と、後述のSPR機能うちエキサイタ効果だけのオンオフスイッチ。
- SOLO
元の音を混ぜるか混ぜないかを選択するスイッチ。オンで元の音は出力されなくなる。コンプレッサなどのエフェクターと同じように、単体の楽器にかけるためにはさみ込む時はオフ、リバーブなどのエフェクターと同じようにミキサから送り出してリターンする場合は、オンにしておく。
- MIX
エキサイタの効果を元音にどのくらい付加するかの設定。左に回しきった状態ではエキサイタの音は一切出力されない。SOLOがオフの時はこのつまみでバランスを決めるわけだけど、SOLOがオンの時は右に回しきっとけばいい。
- SPR
SPRとはSpectral Phase Refractorの略で、低域(この場合は150Hz)の位相を進めるもの。この機能は直接エキサイタとは関係ないんだけど、音声信号は色々な音響機器を通ってくると、低域の位相が遅れがちになるというのがあってそれを補正してやろうという回路だ。これも必ず結果の出るエフェクトでもないので、使ってみて音に迫力が出たなと思ったら使えばいいというようなものだ。BBEというエフェクターのベースコントロールも同じ理屈のエフェクターだ。
- RELAY
電子部品のリレーのことなんだけど、ここでは他の機器でいうバイパスのことだ。リレーを使って入力から出力に何の回路も通さずに出力するようになっているので、この名前がある。