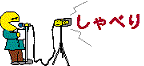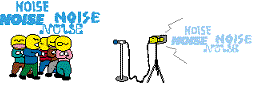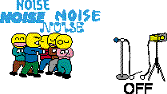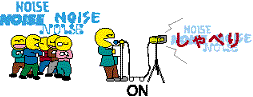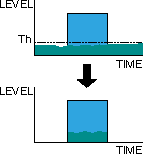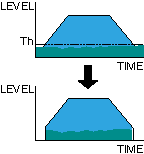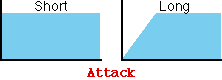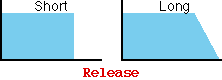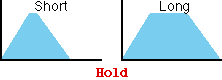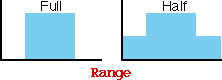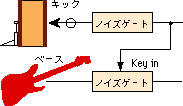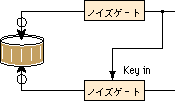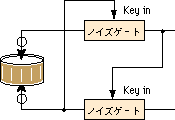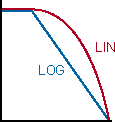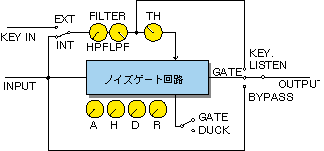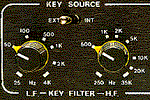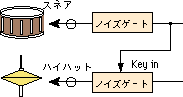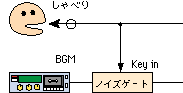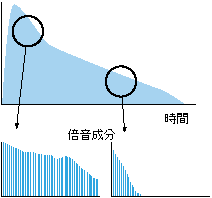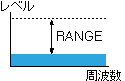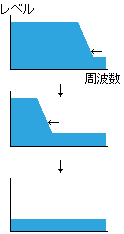8-5 エキスパンダ/ノイズゲート
8-5-1 エキスパンダについて
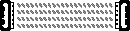
エキスパンダ
昔は必ずどこの家庭にもあって、しかも絶対使われることのなかったもの。バネを伸ばすことによって筋肉が鍛えられるという「大リーグボール養成ギプス」のようなもので、取扱説明書には四十八手の体位が書いてあった。ちなみにバネの部分で皮膚や髪の毛をはさむと死ぬほど痛い。 |
コンプレッサのまったく逆の働きをするのが「エキスパンダ」で、直訳すると意味は「伸張器」。要は変化の度合を強めるもんだ。みんなのうちの物置にもあるかもしれない。バネが何本か付いてて「筋肉が鍛えられまっせ」という元祖ブルーワーカーみたいなやつが・・・。あれもバネを「伸張」するからエキスパンダという名前が付いているんだな。
エキスパンダの働きは、音量を伸張するものなんだけど、音量を伸張するわけでもなんでもなく、スレッショルド以下を圧縮すると、相対的にスレッショルド以上の音量が伸張されたように見えるだけの話だ。つまり、コンプレッサではスレッショルド以上の入力信号を圧縮していたのに対して、エキスパンダではスレッショルド以下の信号に対して圧縮をかけるのだ。
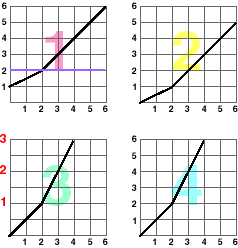 |
| 図8-5-1 エキスパンダの原理 |
- スレッショルドを2にして、レシオは1:2でレンジは∞にしよう。(レシオとレンジについては後述)するとエキスパンダは1のようにエンベローブを変化させるわけだな。
- 次に縦軸の基準を1つ落とす。
- 縦軸を2倍の目盛りにする。
- 出力を増幅して2倍にする。
できあがった4を見てみると、確かにスレッショルド以上の部分は、元々が1:1の変化だったのに、1:2の変化になったように見えるでしょ?これで音が伸張されたというサギみたいな原理だ。まあこの辺は無理矢理納得してもらうしかなかろう。人生そんなものだ。
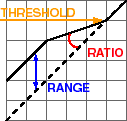 |
| 図8-5-2 レシオとレンジ |
エキスパンダにもコンプレッサと同じようなコントロール類があるわけなんだけど、スレッショルドはまあ判るとして、RATIO(レシオ)とRANGE(レンジ)はどういうものかというと、スレッショルド以下の音量になったらさらに圧縮をかけるわけでしょ?で、どのくらいの割合で小さくしていくのかを決めるのがレシオで、どの程度までそれを続けるかを決めるのがレンジだ。
レシオとレンジの兼ね合いは判りにくいと思うけど、ご安心あれ。エキスパンダの使い道の9割以上のノイズゲートとして使用では、ノイズゲートはレシオを1:∞にして使う事が多いので、みんなはレンジだけ判ってればよろし。逆にValley
PeopleのKeypex llのようにレシオのつまみがあるノイズゲートに出会っても、レシオは1:∞にしときゃいいのだ。(ただしレシオをうまく使えるに越したことはないんだぞ。とりあえず知らなくてもノイズゲートは使えるという意味だからね。)
 本当にどうでもいいことだけど、うちのATOK君さっきから「えきすぱんだ」を「エキス」と「パンダ」に分けて、まるで「絶倫白黒熊」みたいな変換をするぞ。まあ結果的にはあってるからいいけどさ。
本当にどうでもいいことだけど、うちのATOK君さっきから「えきすぱんだ」を「エキス」と「パンダ」に分けて、まるで「絶倫白黒熊」みたいな変換をするぞ。まあ結果的にはあってるからいいけどさ。
8-5-2 ノイズゲート
ノイズゲートってのはその名のとおり、不必要なノイズを除去してしまおうというものだ。理屈はある音量以上の音が入ってくると回路が通じて、それ以下の音量になると回路が閉じる(もしくは増幅率を少なくする)ってこと。だから「ノイズをなくす魔法のエフェクター」ではないわけで、人間の耳の特性を利用して、ノイズを目立たせないように音量操作をするだけのものなのだよ。トランシーバーなんかに付いている「スケルチ」という機能も同じような機能だ。
簡単にその動作原理を説明すると、たとえば図8-5-3の上ように、アナウンス用のマイクを1本PAしているとしよう。「なんでマイクから直接つないだスピーカが鳴るんだ」とか、「なんだこの下手な絵は」とかいわんように。
さてこの近くに人は数人いて、おしゃべりをしていたとしよう。この時にマイクをオンにしたままだと、このおしゃべりの声など不要な音が、小さいながらもマイクに入ってきてPAされるのでうっとおしい。
そこで、周りのざわめき声は、アナウンスの時のマイクに入力される音量に比べて十分小さいので、マイクに入ってくる音量が小さい時には回路を遮断するようにする。そうするとPAからはアナウンスをしていない時は一切音がしなくなる。
この状態でアナウンスの声が入ると、マイクがオンになりPAシステムはその声を出す。この時に本当は周りのざわめき声も一緒に出てるんだけど、都合のいいことに人間の耳には「マスキング効果」とか「カクテルパーティー効果」というのがあって、周りのざわめきはほとんど気にならないのだよ。
このように不必要な音と必要な音が、明確に音量差がある場合は話が早いんだけど、楽器の音なんかは、どの音量以上が必要な音で、どの音量以下が不必要な音かってのは一概に決めにくいことが多いのだな。「余韻も音楽のうち」というやつだ。
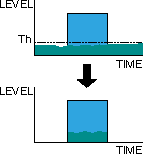 |
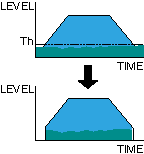 |
| 図8-5-4 ノイズゲートによる音質変化 |
例えばスレッショルド以下の音は一切出力に出さないノイズゲートがあったとしよう。図8-5-4の左の音源のようにぱっと出てぱっと消えるようなものなら、このノイズゲートは十分使いものになるけど、音の立ち上がりも消え際も緩やかな右のような音源では、立ち上がりの最初の部分と、消え際の最後の部分が一切聞こえなくなってしまう。これではあまりにも使いものにならないので、登場するのが次に説明するATTACKやHOLDやRELEASEやRATIOというコントロール部分だ。
8-5-3 ノイズゲートの各コントロール
8-5-4 各種ノイズゲート
ノイズゲートもコンプレッサと一緒で、各メーカーから色々な機種が出ているんだけど、Vlley
PeopleのKEYPEX llとDRAWMERのDS-201の2種類が、PAレコーディング問わずよく使われる。
- Valley People KEYPEX ll
 |
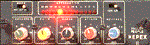 |
| 写真8-5-1 Valley People KEYPEX ll |
ノイズゲートというものを一躍有名にした名器。今でも主にレコーディングスタジオで活躍している。縦型のものと、横型のものがある。縦型のものは昔からあるやつで、4Uの横半分のサイズで4台のKEYPEX
IIと電源を内蔵している。横型のものは比較的最近のもので、1Uラックに2台のKEYPEX
IIと電源を内蔵して、縦型のものには無いステレオリンクスイッチを装備している。どちらも中身は一緒だ。
コントロールつまみは上から、リリース・アタック・レンジ・レシオ・スレッショルドと特に変わったものは付いていない。前述の通りレシオは判んなければ右に回し切っとけばいい。MODEは「IN」がノイズゲートのオン、「OUT」でOFF、「KEY」でキーインから入力された信号でゲートの閉開を行うということだ。
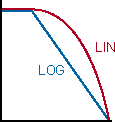 |
| 図8-5-13 LIN/LOG |
ちょっと変わっているのは、パネル左上の所にリリースのカーブ切り替えが付いている事だ。これはホールドの代わりのようなもので、リリースの下がり具合をコントロールするためのものだ。図8-5-13のように、聴感上LOGは均等に、LINは最初は緩やかに後は急にといった下がり方をするのだな。なぜLIN(=Liner=直線)が曲線になるかというと、このグラフの縦軸は対数になっているからだ。
で、実際に使う時は、最初に極端な設定(レシオを右に回し切り、レンジ、アタック、リリースを左に回し切った状態)でスレッショルドをまず決める。この時はブツ切れで、まともな音になってない状態でいい。それで次にリリースを少しずつ上げていくんだけど、スネアなんかの場合はスネアらしい音がする一番短い状態で止める。(これは比較的簡単)タムなんかは実際の余韻を半分くらいにする感じで設定するといい。リリースにLOGとLINの切り替えがあるけど、スネアやキックなんかの場合はLINのほうが、タムなんかの場合はLOGのほうが切りやすい。要はゲートを「ぱしっ」と閉めるか緩やかに閉めるかの違いなので、音を聞きながら切り替えてみていい方を選べばいい。あとは全体を聴きながら順次レンジ等を自然に聞こえるまで弱めていく。当然ながらレシオを余り弱めすぎるとノイズゲートの効果が無くなるので、適当なところで妥協しないと何のためにノイズゲートをかけてるのか判らなくなってしまうぞ。またタムなんかはタムの音だけ聴いていると不自然な感じがしても、オーバートップの音などを混ぜた状態で聴くとあんまり気にならなくなることが多い。
- DRAWMER DS-201
レコーディングPA問わず、プロ用のノイズゲートのスタンダードとなっているのがこのDS-201だ。KEYPEX
IIより後発のもので、KEYPEX IIに比べて、よりノイズゲートとしての使用を考えた設計になっている。
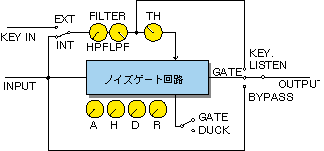 |
| 図8-5-14 DS-201のブロックダイアグラム |
図8-5-14はDS-201のブロックダイアグラムなんだけど、コントロールつまみはスレッショルド,
アタック, ホールド, DECAY,(ディケイ=リリースのこと) レンジまあこの辺はオーソドックスなものだ。
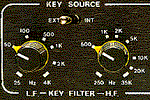 |
| 写真8-5-2 キーフィルタ |
特徴的なのはKEY FILTER(キーフィルタ)の設定だ。普通のノイズゲートではノイズゲート回路のコントロールをする信号は、通常入力を分岐したもの(KEY.INからの場合はそこに入力された信号)がスレッショルドを通ってゲート回路に入力されるんだけど、そこに4kHzまでカットできるハイパスフィルターと250Hzまでカットできるローパスフィルターをはさんであるんだな。
これをどう使うかというと、例えばキックを収音したんだけどスネアの音が全く同じ音量で入ってしまった場合なんか、(普通は録音し直すけどね)キックの音だけを取り出すのは、普通のゲートでは不可能だけど、このフィルターをスネアからは出せないような低音しか通さない設定にする事によって、ゲートはキックの音が入ってきた時にしか開かないように出来るわけだな。このフィルターを決める時には、モードスイッチをKEY
LISTENにしておけば音を聞きながらキーフィルタの設定が出来るので便利だ。当然ながらこの二つのつまみの位置によっては、ゲートが利かなくなってしまうので注意。
もう一つ特徴的なのはGATEとDUCK(ダック)の切替が付いていることだな。ダックってのはノイズゲートの逆の動作、つまりスレッショルド以上の音が入ってきた時に音量を小さくする機能だ。このままでは何の役にも立ちそうにないけど、これが先ほどのキーインを使うと、結構いろいろな用途に使うことが出来る。ちなみにこのような使い方の時にはダッカーと呼ばれることもある。
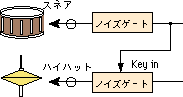 |
| 図8-5-14 ダックの使用例 |
まず図8-5-14のようにBGMにノイズゲートをかけておき、そのノイズゲートのキーインにしゃべりのマイクの音声を入れておく。そうすると、マイクでなにかしゃべる時には自動的にBGMの音量が下がるという寸法だ。このときにはアタックを最速に(声が入ったらすぐBGMを下げるため)、ホールドを長めに(声の「間」でBGMが元の音量に戻らないように)、リリースも少し長めに、(声が終わったらBGMがフェードインしてくる感じ)するわけだな。店内放送なんかによくある使い方だ。DJ用のミキサのマイク入力なんかこのダック機能を内蔵するものも多い。(そんなもんより先にハイパスフィルタつけろと言いたくなるが・・・)
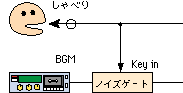 |
| 図8-5-15 ダックの使用例 |
その他スネアのマイクにかなりハイハットがかぶってしまった場合に(これも普通は録り直すけど)スネアにゲートをかけてスネアの音が鳴った時だけゲートを開けることが出来たとしても、スネアをたたいた時にはハイハットの音も一緒に出るので、スネアをたたいた時だけハイハットの音量が上がってしまう。このような時に図8-5-15のようにつないで、スネアの音でハイハットのノイズゲートをDUCKすればハイハットのマイクはスネアをたたいた時には小さくなるので、結果としてスネアをたたいた時もそうでない時にもハイハットの音量を一定にすることが出来るというわけだ。ただしこれは位相関係や他の音とのかぶり具合を全く考えていないので、実際に使えるものでもないけど、使い方のヒントということでな・・・
- ROCKTORN HUSH ll
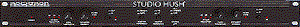 |
| 写真8-5-3 STUDIO HUSH |
HUSHシリーズはどちらかというと、楽器用のノイズゲートとして開発されて、HUSH
llで人気が出たノイズゲートだ。現在ではスタジオ仕様のSTUDIO HUSHがレコーディングで使われている。他のノイズゲートとはちょっと違った働きをするので紹介しておこう。
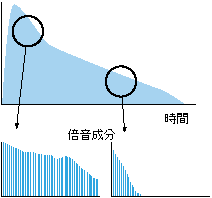 |
図8-5-16
時間による倍音構成の変化 |
まずこのノイズゲートは余韻をコントロールするという用途より、その名の通り、(特に特定の楽器の)ノイズを除去するという用途に限定して考えてあるんだな。で、例えばピアノやギターの音を思い浮かべてほしい。弾いた瞬間のいわゆる音のアタックの部分は、非常に複雑な音で(それがその楽器らしい音にもつながってる)、余韻の部分は意外に単純な正弦波に近い(つまり倍音を余り含まない)音になっているのだな。
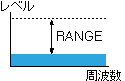 |
| 図8-5-17 普通のノイズゲート |
で、普通のノイズゲートは、図8-5-17のように、スレッショルド以下の入力に関しては、全周波数帯域で均一に音量を下げるわけだ。
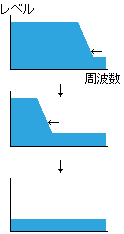 |
| 図8-5-18 HUSH |
それに対してHUSHは、スレッショルド以下のレベルになったらまず高域を減少させ、以下レベルが下がるに連れ中域→低域と減少させて、最終的には全周波数帯にわたってゲインを下げるというようにするわけだ。つまり、ローパスフィルタのつまみを低い方へ回していったような効果だな。こうすると、楽器の余韻部分は倍音、つまり高域成分を余り含んでいないから、高域だけ減少させても楽器の音自体にはほとんど影響を与えずに、耳に付きやすい高域のノイズだけを減少させることが出来るし、ノイズゲートが効き始めてもしばらくは中低音の音はそのままなので、その分スレッショルドも低く取ってもノイズゲートの効果は失われないし、設定も比較的楽になる。
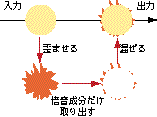
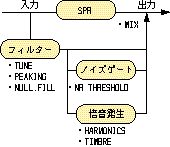
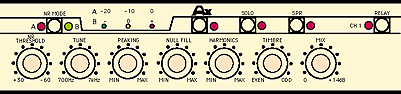
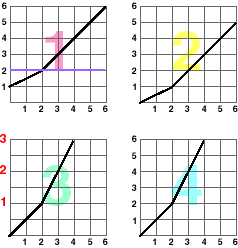
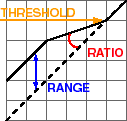
 本当にどうでもいいことだけど、うちのATOK君さっきから「えきすぱんだ」を「エキス」と「パンダ」に分けて、まるで「絶倫白黒熊」みたいな変換をするぞ。まあ結果的にはあってるからいいけどさ。
本当にどうでもいいことだけど、うちのATOK君さっきから「えきすぱんだ」を「エキス」と「パンダ」に分けて、まるで「絶倫白黒熊」みたいな変換をするぞ。まあ結果的にはあってるからいいけどさ。