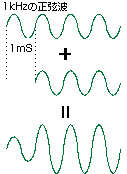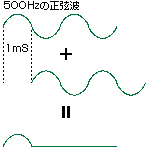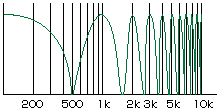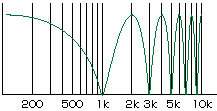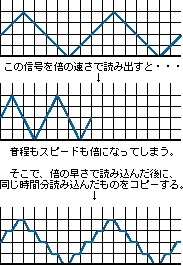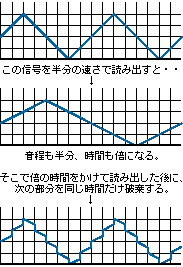フランジャは「しゅわ〜ん」という変調音で、独特の金属感を出すエフェクターだ。このフランジャ単体、もしくはディストーションとの組み合わせで「ジェットマシン」という呼び方をすることもある。(ほぼ死語)
フランジャの原理は、ディレイによるコムフィルターを利用したものなので、まずディレイによるコムフィルターについて説明しよう。
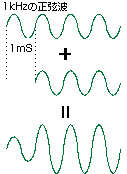 |
図8-3-1
コムフィルタの原理1 |
ここで1kHzの正弦波(サイン波)があったとしよう。別に正弦波でなくてもいいんだけど、波形が単純な方がわかりやすいからね。1kHzということは、1秒間に1000回振動する(図8-3-1の山の部分と谷の部分1回づつで1振動したことになる)ということだから、1回の振動にかかる時間は1/1000秒、つまり1msecになる。で、この正弦波に、1msec遅らせた同じ正弦波を足してやるとどうなるか?ちょうど1msecだけ遅れた同じものを加えるのだから、山の部分と山の部分、谷の部分と谷の部分がぴったり重なって、(1msec以降は)単純に信号の大きさが2倍になる。同じようなことが1kHz以降、2kHz・3kHz・4kHzというように起きる訳だ。
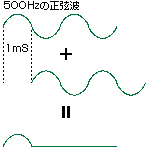 |
図8-3-2
コムフィルタの原理2 |
今度は500Hzの正弦波に、1msec遅らせた同じ信号を加えるとどうなるだろうか?500Hzは1秒間に500回振動する周波数だから、1回の振動にかかる時間は1/500=2msecだ。ということは1msec遅らせた信号を足すと、山の部分と谷の部分、谷の部分と山の部分が重なるので、図8-3-2のように(1msec以降は)音が打ち消し合ってしまう。これも500Hz以上の周波数で同じようなことが1.5kHz・2.5kHz・3.5kHzというように起きるわけだ。
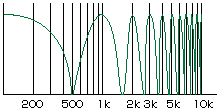 |
図8-3-3 ディレイタイムが
1msecの時のコムフィルタ |
これをグラフにすると図8-3-3のようになる。これがコムフィルタと呼ばれるものの特性だ。見ての通りかなりすごい周波数特性になるんだけど、ある一定の部分だけが強調されているのではなく、強調と減少を繰り返しているので、聞いた感じは図からうけるイメージのように、無茶苦茶な周波数特性には聞こえないが、音にかなり「癖」が付いて聞こえることには変わりない。
横軸の区切りが等間隔になっていないのは、対数表記のため。人間の耳の周波数の違いの感じ方は対数(に近い)変化をするので、周波数特性などのグラフを書く時にはこのように書く事が多いのだ。ちなみに縦軸の音量も対数表記だけど、ここで使う単位はdBで、これは既に対数になっているのでグラフの方は対数にする必要はない。ということで、横軸だけを対数にしたグラフを特に片対数グラフと呼んでいる。ちなみに横軸を等間隔にすると、鋸の歯のようなグラフになる。で、このグラフの見た目が櫛(コムComb)の様に見えるので、コムフィルターという名前があるわけだな。
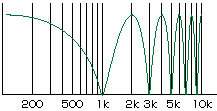 |
図8-3-4 ディレイタイムが
0.5msecの時のコムフィルタ |
さて今度はディレイタイムを変えるとどうなるだろうか?ディレイタイムを半分の0.5msecにしてみると、図8-3-4のように、最初の谷は1kHzの所に、その次の山は2kHzの所になる。つまりディレイによるコムフィルターは、ディレイタイムが小さくなるほどフィルターの目が粗くなり、低域には影響を与えなくなるのだな。
で、ここで連続的に1msecから0.5msecまでディレイタイムを変化させたとすると、フィルタの櫛が左右に動いたような特性が得られるわけだ。これは打ち消される周波数が変化するということだから、当然音質変化が起こる。これがフランジャのしゅわ〜んという音の元なのだ。ちなみにフランジャという名前は、電子式のディレイがなかった頃に、同じ内容の録音されたテープをテープレコーダ2台にかけて、それを同時に回してリールのふち(フランジ)を手で触って片方のデッキを遅らせることによってフランジャの効果を得ていたことから来ている。
ということで、フランジャの原理はこのくらいにしといて、実際のフランジャはどうなってるかというと、機種によって違いがあるものの大体次のようなパラメータがある。
- ディレイタイム(Delay Time)
さっきいったように、ディレイタイムを小さくすると高域のみフランジヤーの効果が選られるし、大きくすると低域から効果が得られるようになる。一般的には大体2msec位を使うことが多い。昔の製品にはディレイタイムをウィドゥス(width)と表示してあるものもある。
- デプス(Depth)
生音にディレイ音をどのくらい混ぜるか、つまりフランジャの効果をどのくらい得るかという設定。
- フィードバック(Feed Back)
フランジャの効果を強調するために、ディレイにフィードバックをかける割合。フィードバックをかけないとおとなしい音になってしまうので、通常は結構強力にかかるように多めに設定する。(フランジャというエフェクトは、あまり控えめにかけても意味がないからね。)
- スピード(Speed)
モジュレーションのスピード、つまりディレイタイムを変化させるスピードで、『しゅぅわ〜〜ん』という感じにするのか『しゅわわわわわ』という感じにするのかの設定だな。機種によってはフリクエンシー(Frequency)という名前になっているものもある。
電気的にコーラス効果(同じ音程の音が複数の音源から出ているような効果)を得ようというもの。ローランドが初めてギターアンプのJC-120に搭載という形で製品化し、その後コーラス機能を持ったエフェクターをCE-1という名前で単体で発売した。ちなみにこの頃はディレイにアナログディレイを採用している。(というかアナログディレイしかなかった)
コーラスの原理は実はフランジャと全く一緒で、フランジャと違う点は、ディレイタイムが比較的長いことと、フィードバックはほとんどかけないことだ。つまりディレイタイムを長め(20msecくらい)に取ることによって、低域からコムフィルタを効かせるようにして、うねり感を出す代わりに、あまりどぎつくエフェクトをかけないことによって、ふんわかとした効果を狙っているわけだな。
- ディレイタイム(Delay Time)
フランジャに比べてディレイタイムが大きいので、コーラスには独特のうねり感が伴う。最近の製品の中にはこのうねり感を強調するためAM
DEPTH(音量の変化)をコントロールしてうねり感を強調できるようにしたものもある。また昔の製品にはこのディレイタイムをウィドゥス(width)と表示してあるものもある。つまり、ディレイタイムを長く取ると、低域から変化が現れるために、効果を深くしたように感じるからだな。
- デプス(Depth)
生音にディレイ音をどのくらい混ぜるか、つまりコーラスの効果をどのくらい得るかという設定。コンパクトエフェクターなんかでは省略されていることが多い。その場合は最大値(生音:ディレイ音=1:1)になっているのが普通。生音よりディレイ音を少し抑え気味にした方が、上品なコーラスエフェクトになる。ちなみに生音を0にしたときの状態をビブラート(Vibrato)というエフェクト名で呼ぶこともある。
- スピード(Speed)
モジュレーションのスピード、つまりディレイタイムを変化させるスピード。通常の使用では1Hz以下のゆっくりしたスピードで使用することが多い。機種によってはフリクエンシー(Frequency)という名前になっているものもある。
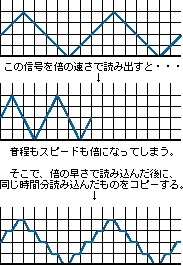 |
図8-3-5
ピッチチェンジャの原理1 |
オープンテープに7.5ipsのスピードで録音したものを、倍の15ipsの速さで再生すると、速さと一緒に音程も倍になるし、半分の3.25ipsで再生すると、音程も半分になるよね。理屈はこのことと一緒で、デジタルディレイで、入力された信号をデジタル変換してメモリーに蓄え、それをすぐ取り出して、(実際にはここでわずかな遅れが生じる)倍の早さで読み出したり半分の早さで読み出したりしてやれば、デジタルディレイでも同じ事が出来るわけだ。
ただしこのままでは図8-3-5のように音程と同時に、速さも倍になってしまう。例えば1秒かかって鳴っていたドの音が、0.5秒で終わる1オクターブ上のドの音にかわるわけだな。ちなみに図8-3-5では、横軸が時間で縦軸が信号の変化、線の角度が音程だと思ってほしい。上と下を比べると信号の変化のしかたは一緒で、角度が倍になって時間が半分になってるでしょ?
そこでピッチチェンジャでは少しズルをしている。それは図8-3-5の一番下のように、一定時間(サンプリング周波数によって変わる)倍の早さで読み込んだ後に、同じ時間分読み込んだものをコピーしてしまうのだ。図では線が平行になっている部分だな。上に比べて下は時間は倍になってるけど、信号の変化がある時の線の角度は一緒でしょ?
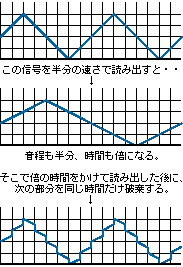 |
図8-3-6
ピッチチェンジャの原理2 |
今度は読み出し時間を倍にした時を見てみると、図8-3-6のように信号の変化のしかたは一緒で、角度が半分になって時間が倍になってるよね。で、またズルをして一定時間、倍の時間をかけて読み出した後に、次の部分を同じ時間だけ読み込まないようにする(破棄する)訳だ。そうするとめでたく音程が半分になって時間が同じとなるわけだな。
まあしかしながらこーゆー力技で音程を変化させているので、音程を変化させればさせるほど原音から離れているわけだ。例えば音程を10%下げる時には、10回に1回の割合で元の成分を捨てればいいんだけど、音程を半分(50%)にする時には、元の音の半分を捨てなくてはならなくなるわけだ。逆に音程を倍にした場合は、音の半分はピッチチェンジャが勝手に作った音なわけだ。だから音程を極端に変えると、かなり音質が原音に比べて劣化するのはしかたがない話だ。各メーカともなるべく原音を損なわないように色々な工夫をしてるけど、原音を重視する場合の音程変化は±15%程度が限界だろうと思う。ちなみにピッチチェンジャは「ハーモナイザ」という呼び方をすることもあるけど、ハーモナイザはMXR社の商品名だ。
ピッチチェンジャのパラメータについては、SPX-1000を例を取って説明しよう。
20 PITCH CHANGE 1
入力モノ出力モノで2系統
21 PITCH CHANGE 2
入力モノ出力ステレオで1系統づつ
22 PITCH CHANGE 3
入力モノ出力モノで3系統、FBなし
23 STEREO PITCH
入力ステレオ出力ステレオで1系統づつ
- PITCH(Pitch Coarse)
音程を変化させる度合いの大まかな調整で、+で高くなり−で低くなる。単位は音楽でいう半音で、例えば+2の設定で「ド」の音を入力すると「レ」の音が出力される。
- FINE(Pitch Fine)
音程変化の細かい調整±100で単位はセント。セントは100を表す言葉で、ここでは半音の1/100の意味だ。ちなみに日頃使ってるパーセントってのもパー(/)セント(100)というわけで『100に対していくつ』ってことだ。
- DELAY(Delay Time)
音程を変化させた音を出力するまでの時間。単純な音程変換器として使うなら最小値の0.1msecにしておけばいいんだけど、このパラメータをうまく使うと色々な効果を得ることが出来る。
- F.B(Delay Feedback)
DELAYパラメータのフィードバック量を決めるもの。通常は0%でいいんだけど、このパラメータで特殊な効果を得ることが出来る。
で、最初は声が変わったりして面白いエフェクトだと思っても、意外とそのままでは使い道がない。そこでここでは、単なる音程変換器としてではないピッチチェンジャの使用方法の例を、2つ挙げておこう。
1つめは1つの音源なのに2つ以上の音源が鳴っているように聞かせる方法だ。同じような効果を、ディレイによるダブリングや、コーラスで得ることが出来るけど、ピッチチェンジャで作ると、それらとはまたちょっと違った趣の感じになる。理屈は音程をわずかにずらして複数の音源が鳴っているように聞かせようというもので、(全く同じフレーズを、同時に複数の人が弾くと、ほんの少しずつ音程がずれるでしょ)PITCHは0でFINEを上下5から15程度違う値にずらす。(例えば+8と−13)この時ずらす値を余り大きく取ると、単に調子っぱずれになるのに注意しよう。また大きく取りたい時はなるべく下方向にずらすのがコツ。さらにDELAYを30msec程度の違う値(例えば25msecと32msec)に設定すると、ディレイによるダブリング効果も加わって、エフェクトの効きが強くなる。
2つめは特殊なエフェクトとして、ピッチチェンジャに付いているDELAYとF.Bを使う方法だ。これはむしろディレイに音程を変化させるオプションが付いたものと考えた方が判りやすい。単なるディレイの場合と違うのは、ディレイがかかると同時に、音程も変わっていることで、例えばPITCHを+2、FINEを0、DELAYを200msec、FBを適当に上げておいて、「ド」の音を入力すると200msec毎に「レ・ミ・ファ#・・」というような音階が上がっていくディレイが作れるわけだ。
ここで注意しなくてはいけないのは、音程の変化量は一定なので、「ドレミファソラシド」のような音階を再現することは出来ない。(音階をプリセットしておいて、入力に応じて音程の変化量を変える賢いピッチチェンジャもあるけど、とりあえずSPXでは出来ない)小難しいいい方するとPITCHが1でクロマティックスケール、2でホールトーンスケール、3でディミニッシュスケール、4でオーギュメントスケール、5でフォースブロックになるわけだな。曲の中で使うなら、ドミナントセブンスの部分で+2のホールトーンスケールなんかいいと思う。(鉄腕アトムの最初のビブラフォンの音程・・・といっても判らないか・・・)まあだけど元々音程を出せる楽器なら、わざわざピッチチェンジャを使わなくても弾いた方が早いので、このエフェクトは音程を持たないパーカッション向きだといえる。もちろんマイナスにして音程を下げても面白い。