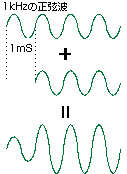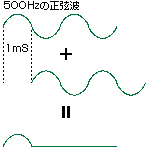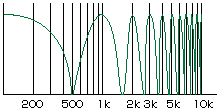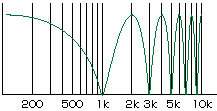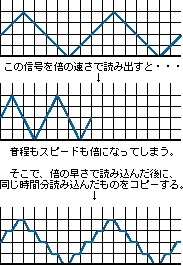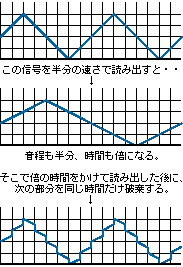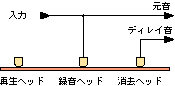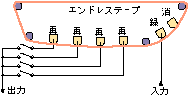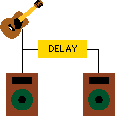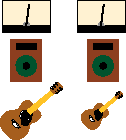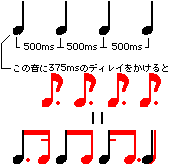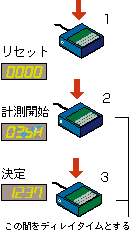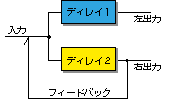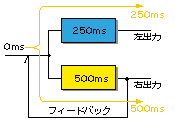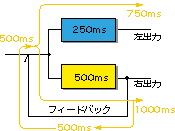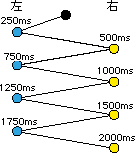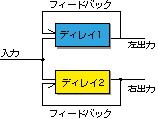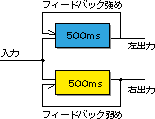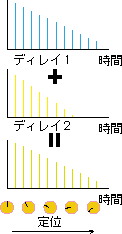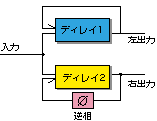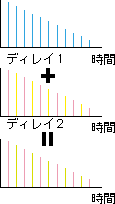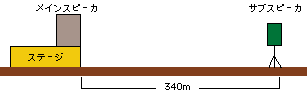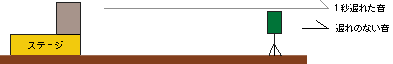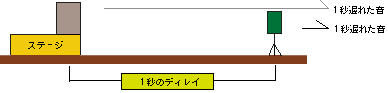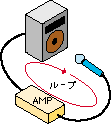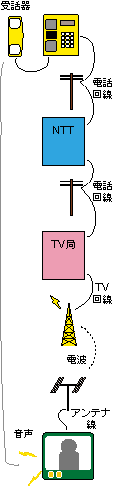現在ディレイマシンといえば、現在はデジタルディレイマシンの事を指すことが多いので、デジタルディレイについて触れていこう。エフェクターとしてディレイを使う場合には、元の音にディレイを加えることが多いけど、ディレイタイムの取り方によって得られる効果はかなり異なったものになる。
10msec〜50msec
一般に元音に10msec以下のディレイを加えても、人間はこれを2つの音として認知できないとされているんだな。だから10msecから50msec程度のディレイは、人間の耳に2つの音として分離して聞こえる最小値くらいのディレイタイムといえる。ということで、このくらいの遅れは、音楽的には同じタイミングといって差し支えなく、(テンポ120の128分音符で約30msec)このくらいのディレイタイムのディレイは別々に聞こえる(ずれて聞こえる)んだけど音楽的にはずれていない。ということが出来る。
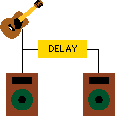 |
図8-2-3
ディレイによるダブリング |
そこで図8-2-3のように、例えばギターの音を、左のチャンネルからは元の音、右のチャンネルからは30msec位ディレイで遅らせた音を出すと、あたかも左右で2本のギターが同じように弾いている感じを出せる。これがダブリング効果だ。この時ディレイタイムは長ければ長いほど、ダブリング効果は強調されて判りやすくなるけど、当然ながらあまりディレイタイムを長くすると演奏がずれて聞こえるので、早いフレーズには30msec程度、ゆったりとしたフレーズなら50msec程度、ストリングスなどで白玉中心の音源で100msec程度が限界だろう。
このテクニックは、トラック数の少ないMTRで録音したものをミックスダウンする時に結構使える。例えばバンドものを8トラックで録音した場合、バッキングのギターなどはどうしても1トラックしか使えないけど、定位を考えた場合、ギターまで中央に定位させると殆どモノラルのミックスダウンになってしまうでしょ?かといって右とか左に定位させると左右のバランスが悪くなるし、ステレオコーラスなどでステレオにしても基本的には定位は中央だし、音色まで変わってしまう。そこでこのディレイによるダブリングを使えばもう1トラック使ってギターを重ねたような効果が得られるわけだ。
この場合注意しなければいけないのは、ハース効果によって左右同じ音量にしてしまうと、ディレイのかかった方の音が小さく聞こえてしまうのだ。ハース効果とは、人間の心理で、左右から同じ音が聞こえた場合、先に耳に届いた方に音源の位置を感じるというもので、この場合は右にディレイをかけて遅らせているわけだから、当然左の方に音源の位置を感じるわけだ。音源の位置を感じるということは、左チャンネルの音の方が大きいということと同意な訳だな。
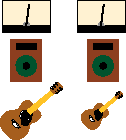 |
 |
| 左右の音量を等しくすると、左側の方が大きく聞こえる。 |
右側の音量を少し大きめにして、聴感上でバランスを取る。 |
| 図8-2-4 ハース効果の補正 |
だから左右の音量を揃えたい時には、メーターを無視して聴感上でレベル設定をしよう。またステレオで再生している時は良くても、モノラルミックスした時に、位相ずれによって起こる干渉から、音が引っ込んでしまったり音質が変わってしまうことがあるので注意が必要だ。まあ最近の再生システムはほとんどステレオなので、あまり気にすることはないと思うけど、モノラル放送のテレビやAM放送なんかでオンエアされる可能性のある場合は、しっかりとチェックしとかなかん。
300msec〜500msec
普通ディレイをかけるといったら、この辺りのディレイタイムのものを指すことが多い。実際に一番よく使われるのもこの辺りのディレイタイムだ。音楽ものに限らずドラマなんかの回想シーンでもよく使われてるよね。
お前がやったんだろう!
人殺し!
みたいなやつね。(^_^;
で、今や陳腐になってはしまった使い方とはいえ、非常に効果としては強力なエフェクトだということが出来る。強力なエフェクトであるが故に、音楽もので使用する時には注意が必要なのだよ。一般に音楽ものでこの辺りのディレイタイムのディレイを使う時には、曲のテンポに合うようにディレイタイムを設定する。なぜかちゅーとテンポにあっていないディレイは音楽を台無しにする恐れがあるからなのだ。
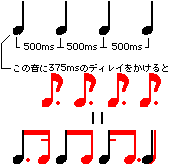 |
図8-2-5
ディレイによるリズムのずれ |
ここで極端な例を挙げてみよう。あるテンポが120の曲があったとして、これにディレイをかける。このテンポでの4分音符1つ分の長さは、500msだ。(テンポが120というのは、1分間に4分音符が120個入る速さのことだから、60秒/120=0.5秒という計算ね)
で、この曲の1拍目に、何も考えずにディレイタイム375msのリピートディレイをかけたとしよう。(図8-2-5の赤い音符ね。)375msecというのは500msecの3/4なので、長さは付点八分音符の長さになるでしょ?そうすると最初のディレイは1拍目の裏裏、2つめは2拍目の裏、3つめは3拍目の表裏というようにディレイが現れるので、元の音符にディレイによって発生した音を加えると図8-2-5のようにとんでもない音符になってしまう。
まあ逆にこれは、ディレイによって出来る音符の長さが「音楽的」なのでまだいいけど、実際にはこのくらいのディレイタイムのディレイをかける時に、他の音と喧嘩したり、音が濁ってしまうことは良くある話だ。で、そうならないようにするには、ディレイの音量を下げるか、ディレイタイムをテンポに合わせてやるという結論になるわけだな。テンポに合わせるといっても、4分音符に合わせるだけじゃなくて、8分音符や三連符に合わせたりしてもいい。図8-2-5の付点八分の例なんかも、判っててやるなら面白いかもしれない。要はセンスの問題よ。
テンポに合ったディレイタイムを求めるのは、曲のテンポがわかっていれば比較的簡単だ。先述の通りテンポ=Xということは1分間に4分音符がX回演奏できる速さだから、1/Xが4分音符1つ分の長さになる。このままでは単位が「分」なので、判りやすいようにミリ秒に単位を換えると6000/Xになる。これを半分にすると8分音符の長さだし、3/4をかけると付点8分音符の長さ、1/3をかけると1拍3連の長さだ。
まあでも、シーケンサーやドンカマを使っていない限り、テンポは大体しか判らないので、こういう場合は
- カンであわせる。
- メトロノームでテンポをはかる。
- タップ機能の付いたディレイを使う。
などの方法でディレイタイムを決める。
カンであわせるといったって、闇雲に探してもしかたないので、日頃から「大体このくらいだとテンポはいくつぐらいだな」という感覚を身につけておくようにする。大体ミドルテンポのものは130〜140位なので、この辺りのテンポの1拍のディレイタイムは400〜500msec位になる。どバラードは60〜70位で、新装開店で地獄の席取り合戦が始まる合図の軍艦マーチは120位だ。ディレイタイムはぴったり合わせるよりよりも少し長めに取っておくのがコツ。 何でかというと、ずれた時にディレイタイムがテンポより早くなると、うざったく聞こえてしまうのだ。逆に少し位テンポに対してディレイが遅れる分にはそんなに気にならないのだよ。(人間の演奏しているものなんか、そんなに正確にテンポをキープできるわけでないので、どこかでずれてくるのは仕方のない)
メトロノームでテンポをはかる時も、大体いくつ位かを測れればいいので、大体のテンポを取った後でディレイタイムを決めて、微調整はディレイのディレイタイムで調整しよう。最近は電子式のメトロノームも安くなっているので1つくらいはもっておいた方がいいぞ。買うとしたらBOSSのDB-11のようにタップ機能が付いたものがいい。タップ機能とはメトロノームにボタンが付いていて、そのボタンを何回か押すと押す間隔の時間がテンポで表示される機能で、大体のテンポを取りたい時にはとても便利だ。ちなみにDB-11は体感器としてもポピュラな存在だ。
| 体感器について
パチンコ機の第1種と第4種(平たくいえばデジパチと権利モノのことだ)やパチスロの中には、大当たりを判定するカウンターの周期が比較的遅く、大当たりのポイントさえわかればカウンター周期に合わせて球を打ったりレバーをたたいたりすることによって少ない投資で大当たりをねらえる機種が存在する。(この方法では大当たりとは関係のないタイミングでは球の打ち出しを止める必要があるので、これを防止するためによくパチンコ店で『単発打ち、変則打ちお断り』という張り紙がしてあるわけだ)
このカウンター周期をはかるためにメトロノームを使う訳なんだけど、パチンコ店の中ででかい音でメトロノームをならしたりイヤフォンで効いていたりすると非常に目立ってしまう。メトロノームをパチンコ店で使っても別に法律違反でもなんでもないんだけど、(パチンコ機などを故意に破壊・変形させたり、誤動作を起こさせるような行為をしない限り法律違反にはならない。トランシーバーや携帯電話などは電波によってパチンコ機などが誤動作を起こすことがあるのでこれらの使用は法律違反になる)パチンコ店には独自の法律があってメトロノームを使っているのが見つかると、事務所に連れていかれて、口頭による穏やかな注意を受けて重傷を負う恐れがあるので、普通は見つからないように、メトロノームのクリック音をリレーなどで振動に変えて体の見つかりにくい部分(腹など)に張り付けて使うのだよ。(体感器の名前はここから来ている)
まあ最近では体感器で美味しい思いの出来る機種はほとんどなくなってきているので、一昔前のようにどう見ても音楽とは縁のなさそうなパンチパーマ軍団が楽器店に来て、メトロノームを50個注文するというようなことはなくなったけどね。まあ確かにチャレンジマン(尚球社のパチスロ2-1号機)なんかは1日10万コースも夢ではなかったんだけど・・・ま、10年前の話だな。 |
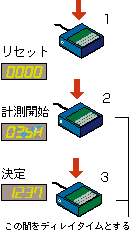 |
| 図8-2-6 プレイメイト |
さらにデジタルディレイの中には、ローランドのSDEシリーズ(SDE-2000を除く)のように「PLAY
MATE」というちょっとえっちな名前で、このタップ機能を備えているものがある。これは超便利だ。PAなんかでメインミキサの近くにフットスイッチが置いてあったら、そのフットスイッチは、ディレイのタップ機能用のものだと思って間違いがない。レコーディングスタジオ志望の人は、「パシリ」が終わった後によくさせられるのが、テープレコーダの調整とともにこのディレイタイムの計算なので、電卓を用意して慣れておくように。
8-2-3 パンニングディレイ
ディレイを複数台用意して、ディレイ音の定位を動かした効果をパンニングディレイというんだけど、この中でも代表的なのがピンポンディレイだ。これはフィードバックの定位が一回毎に右左入れ替わるもので、最近はあんまり流行っとらんけど一時期ボーカルによくかかっていたエフェクトだ。ディレイ音が左右を飛び回ることから、ピンポンディレイというわけだな。
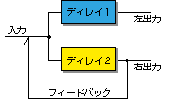 |
| 図8-2-7 ピンポンディレイ1 |
ピンポンディレイの作り方は図8-2-7のように2台のディレイを並列につなぎ、それぞれの出力を左右に分ける。それで基本となるディレイタイムを決めてディレイ1のディレイタイムをそれにあわせる。もうディレイ2のディレイタイムはその倍に設定して、さらにフィードバックをかける。
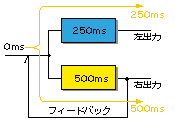 |
| 図8-2-8 ピンポンディレイ2 |
さて説明のためにここでは基本となるディレイタイムを250msに設定しよう。そうすると上側のディレイタイムは250ms、もう一つはその倍の500msになるよね。ここでなにか信号を入力すると、最初はまずディレイタイム分だけ遅れた信号が、左右に出力されるわけだ。
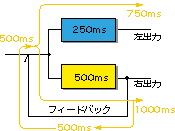 |
| 図8-2-9 ピンポンディレイ3 |
肝心なのはここからで、500ms遅れた信号が入力にフィードバックされているので、入力に500ms遅れた信号が再入力されるわけだ。この500ms遅れた信号がさらにディレイを通るので、それぞれ750msと1000msのディレイが左右に出力される。
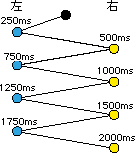 |
| 図8-2-10 ピンポンディレイ4 |
それで今度はさらに1000msec遅れた信号が再入力され・・・と続いていって、左側からは250、750、1250、1750ms・・・と遅れた信号が出力され、右側からは500、1000、1500、2000ms・・・というように出力される。どーだ、図8-2-10のようにちゃんと基本ディレイタイム(ここでは250msec)づつ、左右交互のディレイが発生してるじゃろ。偉いもんだ。
同じ方法でディレイタイムを変えるとディレイ音が2回ずつ返ってくるようなディレイもできる。上側のディレイを50ms下側のディレイを250msにしてみよう。入力された信号はまず50msと250msずつ遅れて出力される。さらに250ms遅れた信号が再入力されるので、次は300msと500msの信号が出力される。これを繰り返していくと、50msecずれたディレイが250msec毎に出力され、「たたん・・たたん・・」といったディレイになるというわけだな。
ヤマハのSPXシリーズでは、このようにフィードバックがお互いのディレイに影響する2台のディレイを1つのプログラムに収めたものが、「DELAY
LR」という名称で入っている。(SPX-900や1000は中央にもディレイを加えて「DELAY
LCR」という名称だ)
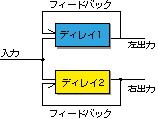 |
| 図8-2-11 パンニングディレイ1 |
さて今度は、フィードバックがお互いに影響しないようにした2台のディレイを用意してみよう。この場合はどんな遊び方が出来るだろうか?まず思いつくのが、左右のディレイタイムをわずかにずらす使い方だ。これはそれなりに隠し味としては使える。例えばディレイ1を200msに、ディレイ2を205msにして、フィードバックを少しかけるというような使い方だな。この時、あまりフィードバックを強くかけると、ディレイタイムの違いが強調されてださくなってしまうので、控えめにしておこう。また10〜50ms辺りのディレイタイムで、フィードバックを0にすると、コーラスやピッチチェンジャなどとはまた違った趣の、疑似ステレオ化が出来る。
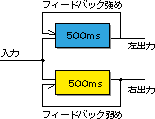 |
| 図8-2-12 パンニングディレイ2 |
さて、ここで二つのディレイのディレイタイムを全く同じにして、片方はフィードバックを強めに、もう片方は弱めにするというセッティングにしてみよう。
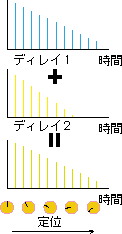 |
| 図8-2-13 パンニングディレイ3 |
そうすると、まず一発目のディレイは、左右同じレベルで出力されていて、ディレイタイムも全く同じだから、中央に定位する。ところが、フィードバックによる2発目以降のディレイは、ディレイ2の方がフィードバックが弱めになっているので、こちら側の方が信号レベルが先に小さくなる。で、定位もそれにつれて左の方へずれていくのだよ。つまりこういうセッティングをするとディレイ音が中央から左に逃げていくようなディレイが作れるわけだ。
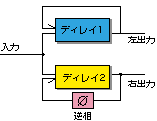 |
| 図8-2-14 パンニングディレイ4 |
次は2台のディレイタイムもフィードバックも全く同じにしてみよう。で、そのままでは単なるモノラルのディレイにしかならないので、ちょっとイタズラをして、図8-2-14のように、片方のディレイのフィードバックを逆相にしてやるのだ。
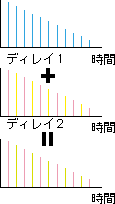 |
| 図8-2-15 パンニングディレイ5 |
このようにすると、ディレイ2の出力は最初は正相で、次が逆相、その次は逆相をさらに逆相にするから正相というように、正相と逆相が交互に出力されることになる訳だ。このディレイ2の出力と、ディレイ1の出力を組み合わせると、左右で正相と逆相が交互に変わるディレイになるわけだ。左右の特性が全く同じものならば、理論上逆相の場合は、互いに打ち消しあって全く音がなくなるはずなんだけど、実際にはお互いが打ち消しあわない部分もあって、それが「逆相の音」として独特の感じを出すわけだ。まあ左右が逆相の音というのは基本的には不快な音なので、このディレイは「えぐい」効果を狙う時なんかにいいと思う。ヘッドフォンなんかで聴くと気分が悪くなっていいぞ。
このようなディレイお互いにフィードバックが影響しあわないようなディレイはヤマハのSPXシリーズでは「STEREO
ECHO」という名前で入っている。
8-2-4 ハイパラメータ
ディレイマシンのパラメータの中には、「HIGH」とかその手の名前の付いたパラメータが付いてることが多いんだけど、これはなにかというと、フィードバックの高域を減衰させるパラメータだ。要はフィードバックの音質を劣化させるものなのだよ。何でわざわざこんなものが付いているかというと、原音がほぼ忠実に反射してくるディレイなぞ不自然だからだ。
ディレイは山彦のような形で自然界に存在しているけど、「やっほー」といった声が、そっくりそのまま返ってきたら不気味でしょ?もしそんなことが起きたなら織田無道を呼んで除霊してもらわなきゃいかん。自然に存在するディレイは必ず音がこもって(=劣化して)返ってくるものなのだ。
テープディレイやアナログディレイの場合は、特に意識しなくても、機械の性能上いやでも音質が劣化してくれたので、あまり気にすることはなかったんだけど、(テープディレイやアナログディレイの音が暖かくて好きだという人は、このことをいっているんだと思う。)デジタルディレイではほぼ忠実に原音を再生するので、人為的にあえて高域特性を劣化させてやることによって、自然な感じに聴かせようとするのだ。まあ最近では、原音そのままのディレイに聞き手の耳が慣れてきたせいもあって、そんなに厳密に設定することも少なくなってきたけどね。
8-2-5 音像定位補正
これから紹介するディレイの使い方は、PAの分野などではとても重要なテクニックなので紹介しとこう。
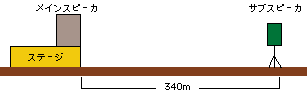 |
| 図8-2-16 音像定位補正1 |
例えば野外コンサートをやっていたとしよう。ステージ横に設置されたスピーカから出る音では、遠く離れた人が音が聞き難いだろうと思ったエンジニアが、スピーカから340m離れたところにサブスピーカを設置した。内心「俺ってなんて親切で仕事熱心なんだろう。」と自己満足に浸っていたエンジニアに届いたのは、「音がおかしいぞ!」という主催者からのクレームだった。(まい・が〜)
なぜこんなことになったかというと、音が伝わる速さ(=音速)は大体毎秒340m位だ。(正確にはt=温度として、331.5+0.6t)ということは、音源から340m離れているところで聞いている人は、1秒前の音を聞いていることになるわけだな。
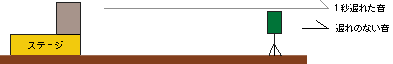 |
| 図8-2-17 音像定位補正2 |
ここにサブスピーカを単純に設置すると、その場所で聞いている人は、サブスピーカからの遅れのない音(電気の伝わるスピードは音に比べてけた違いに速いので、ケーブルの長さなどは無視できる)と、メインスピーカからの1秒遅れの音を同時に聞かされているわけだ。これでは音がおかしいというクレームが来るのも仕方がない。
それでは、このエンジニアの努力を無駄にしないために、どうすればよいかというと、サブスピーカへのラインに1秒のディレイをかけてやればいいのだよ。そうすることによってメインスピーカからの音とサブスピーカからの音は、同じタイミングで音が出ているように聞こえるので、サブスピーカによって明瞭にメインスピーカの音を聞いているような感じにすることができるわけだ。
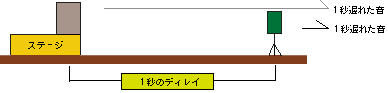 |
| 図8-2-18 音像定位補正3 |
まあ実際には野外コンサートでは、こんなことはしないのが普通。何でかっていうと340mもケーブルを引き回して音を鳴らすのにとてつもない労力が必要だからだ。この音場補正のテクニックが使われるのは、屋内の比較的大きな会場が多いんだけど、単純に計算できる音場は少なく、コンピューターなどで音場のシミュレートをして、複数台のディレイを使ってこのような効果を得ている。このような用途に使われるディレイは音質を重視したもので(すべての音がディレイを通ってから鳴るので当然だ)比較的高価だ。またディレイによっては、ディレイタイムを距離に換算して表示してくれるものもある。
8-2-6 ハウリング対策
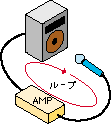 |
| 図8-2-19 ハウリング |
ハウリングというものが何故起きるかというと、図8-2-19のように、マイクから入った音がアンプなどを通ってスピーカから出力されて、それが再びマイクにはいることによって、ループが出きてしまうからなのだな。別にマイクとスピーカの組み合わせでなくても、音響的にループが出来ればこのハウリングは発生する。
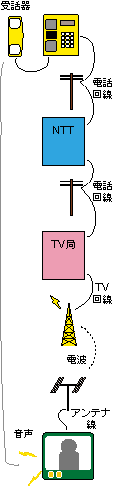 |
図8-2-20
みのもんたハウリング |
もっと遠大なループはワイドショーで暇を持て余した主婦が、『それはあなたが悪い』とか『そんなの別れなさい』とかいう短絡的な答えを聞くために、みのもんたに電話相談するシーンなんかでも起きる。これは暇なオバさんの家にある電話の受話器から始まって、電話回線やNTTの交換所を通ってテレビ局の音声卓にたどり着き、さらにそれが電波に変わって大気中を伝わり、電話をしている暇なオバさんの家のアンテナにたどり着いて、テレビのスピーカから出て、それがまた電話の受話器にはいる。ここまでいろんな所を通ったり、いろいろな信号に変換されたとしても、ループさえ出来ればハウリングは起こるのだ。
で、ハウリングが起きてしまった時に、みのもんたはどう言うかというと、「奥さんテレビから離れて」とか「テレビのボリュームを小さくして」というわけだ。さすがみのもんた、よく音響を心得ていらっしゃる。そう、ハウリングはスピーカから出た音が、マイクなどに入るまでに十分小さい音になっていれば起きないのだ。
十分小さい音にするための手段は、みのもんたのいうとおり2つあって、スピーカとマイクなどを十分に離すか、スピーカから出ている音を小さくすることだ。だけどPAのモニターなどの場合、スピーカの音量を下げるわけにはいかないことが多い。そこでまずは、グラフィックイコライザーなどでハウリングしやすい周波数帯だけ音量を下げるわけだ。但しこれにも限界がある。だってハウリングするということは、十分大きな音がスピーカから出ているということで、それをグラフィックイコライザーなどでカットするということは、どんどんスピーカから出ている音を小さくするということなんだもんな。そうすると肝心の音量が小さくなってしまって元の木阿弥だ。かといってスピーカからマイクを離すと、モニタを聞く人とスピーカの距離が離れるということなので、これも無意味だ。
ということで前フリが長くなったけどここでディレイの登場〜。
前にも少しふれたけど、人間の耳には10msec以下のディレイは、遅れとして認知できないという人間のとろさを利用するのだ。例えばマイクとスピーカの間にディレイをはさんで、10msec遅らせたとしよう。人間の耳にはこの10msec遅れた音は遅れとは認知できないけど、音は1秒間で約340m伝わるので、10msecで3.4m離して聞いているのと同じということになる。とどのつまり、マイクからみれば実際の距離よりも3.4m多くスピーカが離れているのと同じことになるというわけだ。
PAのモニターなどを実際に経験してハウリングと一戦を交え苦労したことのある人なら、すごくいい方法を聞いたぞという気になったと思うけど、ここでディレイを買いにいく人は、多宝搭とかをだまされて買ってしまう人たちだ。世の中そんなうまい話はないぞと。(^_^;
つまりこーゆー訳だ。ディレイをかけることによってコムフィルター(フランジャの所でふれる)が出来てしまい、音に癖が付いてしまって、かえって音が聞きづらくなることが多いという理由と、PAの音場は複雑な音場なので、ただでさえ乱れがちな位相とかがさらに乱れて、実際にはあまり期待したような効果が得られないという理由により、実際あまり使われることはない。まあでも非常手段として知っておいても損はないと思うよ。最近はやたら声の小さい自称ボーカリストが多いからなぁ・・・・っけっ。