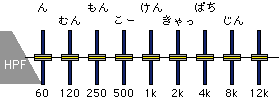7-3 ベースの音作り
7-3-1 アコースティックベース
アコースティックベースは、奏法によって出てくる音がかなり変わるし、マイキングによってもかなり音質に差が出る。ジャズなどの指弾きしたベースは、弦の鳴り・胴の音・指板に弦が当たる音などが合わさった音なので、これらを上手く補正してやる。私の場合は、嫌味にならない程度にシェルビングイコライザで低域をブーストするのが基本。それにプラスして、1kHz辺りを少しブーストするときもある。(指板に弦が当たる音の増強)弓弾きの場合は、低域はほとんどそのままにしておいて、4kHz辺りをほんの少し上げると、音が前に出てくる。
ロカビリー系の音楽のアコースティックベースの場合、ほとんどがベース本体に取り付けたピックアップからの収音になると思うので、後述のエレクトリックベースの音作りを参照にしてくれ。スラップ専用のピックアップがある場合は、大胆にハイパスを入れてやる。(200Hzくらい)メインのピックアップの音と混ぜれば、この処理だけでよいことも多いが、好みでピーキングイコライザで1kHz〜8kHzまでの間のどこかにピークを作ってやる。(Qは狭め)個人的には1kHz近辺にピークを作って、「こんこん」と言う音を付加するのが好きなんだが、プレーヤによってはもっと「ぴちぴち」とした音や、「ぱちぱち」とした音を好む場合もある。
7-3-2 エレクトリックベース
DIで録音してある場合は、低音をイコライザーなどでブーストしてやらないとベースらしい音にならない。これは普通ベースを鳴らすベースアンプが、低音が良く出て高域がさっぱり出ないからそう感じるだけで、ベース本体から出力されている音は本来そういった音なのら。ベースアンプから出た音をマイクで録音してある場合は、比較的ベースらしい音になっているので、イコライジングは補正程度でいい。
DIとマイクの両方を録音してある場合は、どちらか音作りのしやすい方を選んでそれをメインにした方が判りやすい。2つの音をうまく混ぜ合わせてもいいんだけど、経験上思ったほどいい結果にならないことが多いんだな。もし混ぜるなら「高音はマイクで、低音はDIで」と役割分担をはっきり決めた方がいーぞと。またどちらか片方を逆相にして混ぜると音のニュアンスが変わるので、試してみるのも面白いかなと思う今日この頃・・・。
エフェクターは、コンプレッサが必需品だ。最近ではプレーヤ側でコンプレッサをかけることも多いから、そういった場合は特にミックスダウンの時にコンプレッサをかける必要はないけど、「DIから録音しただけ」といった状態ならば必ずかけなさい。
DIで録音した音を使ってどーも上手いこと音作りが出来ない時は、テープに入っているDIの音(≒ベース本体の音)を、ミックスダウンの時にベースアンプに入れて、その音をマイクで録りなおすという、録音ならではの方法もあるぞ。ただしテープからの出力は+4dBなので、-20dB程度のパッドをかましてから、ベースアンプに入れんと歪みまくってしまうでぇ。
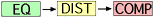 |
| 図7-3-1 ヴイヴイ |
また70年代前半のハードロックで聴かれるような「ヴイヴイ」とした歪んだベースサウンドを出すのには、録音の時点でそういう音をプレーヤに出してもらって、その音をマイク録りするのが一番早いんだけど、DIの音からそう言った感じを出すためには、単純にディストーションをつないだだけでは「じりじり」した軽い音になってしまうので、図7-3-1のようにエフェクターをつなぐ。それでまずイコライザー(グラフィックイコライザが使いやすい)で100Hz近辺を極端にブーストして、1kHz以下を極端にカットする。その後にディストーションを通して歪ませるんだけど、このディストーションは楽器用のコンパクトエフェクターが一番いい。(SPXやGPなどのデジタル系ディストーションは音が痩せるのでだめ。)でその後にコンプレッサをつないで音をまとめてやる。これをやると結構(かなり)ノイズが多くなってしまうはずなので、ミキサのイコライザーで、少し高域を削って仕上げてやれば終わりだ。なかなかティムボガードしてていいぞ。(若い人は知らないだろうけど、BBAというバンドのLIVE盤を聴いてみると判る)
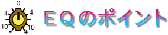 |
- 低音楽器なのでハイパスフィルターは20Hz位にとどめておく。
- DIで録音してある場合のイコライジングは、まず200Hz以下の部分をブーストする。シェルビングでざっくりブーストしても、ピーキングでポイントを探しながら(大体100Hz近辺)ブーストしてもいい。馴れないうちはグラフィックイコライザーで、1ポイントづつブーストしてみて、どのように変わるかを確認しながらイコライジングするといい。このような用途の時のグラフィックイコライザーは、あまりポイントの多いものより10素子程度の物が使いやすい。
- アタック音のポイントは以外に低くて1kHz〜2kHzくらい。
- チョッパーの時は8kHz辺りをブーストしてやると切れがよくなる。
- 丸くて太い音にしたい時は3kHz〜5kHzより高域をシェルビングでざっくりカットしてやる。
- しまりを出したい時は300Hz〜800Hz辺りをカットしてやるといいけど、音量感に影響する部分なのであまりカットしすぎないこと。
|
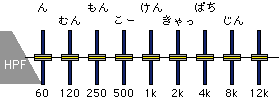 |
| 表7-3-1 ベースのイコライジング |
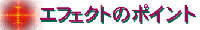 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表7-3-2 ベースのエフェクト |