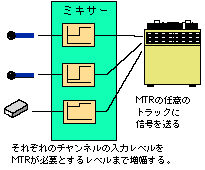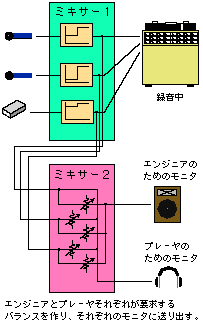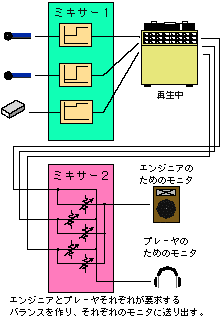5-2 レコーディングミキサ
5-2-1 レコーディングミキサの役割
ミキサの働きはざっと考えて、多くの入力をバランスを取りながらまとめて出力するという事の様に思える。実際PA用のミキサの働きはこれに近く、マイクやD.Iからの入力をまとめて、スピーカをならすように出力する。もちろん実際のPAミキサには、色々な機能が付加されていてもっと複雑なんだけど、入力から出力に送るという点では一緒だ。
レコーディングミキサの場合はどうか?ミックスダウンの時は、MTRからの出力を入力して、バランスを取ってテープレコーダなどに送る。ここはPAミキサと大差ない。だけどそれではミックスダウンしかできないレコーディングミキサになってしまう。レコーディングミキサと名乗るためには、この音をまとめる機能の他に、入力をMTRに送るという機能が必要だ。MTRに信号を送るのだから、この時点でのミキサの働きは、信号レベルを揃えて個別に音を出力することになる。これはPAミキサにはない機能だ。だから簡単にいえばレコーディングミキサは、MTRに送るためのミキサと、MTRからの音をまとめるためのミキサを2つくっつけたようなものなのだよ。
実際に昔は、MTRに送るためのミキサ部分と、MTRからの音をまとめるためのミキサ部分が分かれてたんだ。このタイプのもの(セパレートタイプ)は信号の流れが直感的に理解しやすく、25年ほど前まではレコーディングミキサの主流だったんだけど、MTRのトラック数が増えるに従って不都合が出てきたんだな。一番大きな不都合は、最低限MTRのトラック数の倍のチャンネル数がミキサに要求されるって事。これによってミキサの設置に必要なスペースが増大してしまうんだな。現在プロのレコーディングスタジオでは、48トラック程度の録音も珍しくないけど、このセパレートタイプのレコーディングミキサで、この要求に応えようとすると、最低限96チャンネルのミキサが必要という事になってくる。1チャンネルあたり3cmの幅を取るとして、マスター部やその他の部分を考えると4m近いミキサになってしまうわけだ。これではあまりに操作しにくい。
で現在では、MTRに信号を送る機能とMTRからの信号をまとめる機能を1本のモジュール(1チャンネルごとのまとまり)にまとめたインライン型のミキサがレコーディングミキサの主流になってきている。(インラ・インじゃなくてイン・ラインだからね。念のため。)
このインライン型、省スペースのミキサが出来る様になったのはいいんだけど、1つのモジュールで2つの働きをさせているので、操作が複雑になってしまったのだ。逆にこの2つの部分の働きをしっかり理解していれば、複雑に見えるレコーディングミキサも恐れる事はないという事になる。
5-2-2 レコーディングミキサの信号の流れ
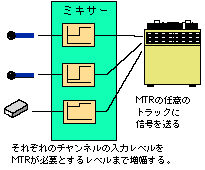 |
| 図5-2-1 MTRに音を送る働き |
レコーディングの一般的な行程としてはベーシック録音、オーバーダブ、ミックスダウンの3行程になるわけだけど、信号の流れを理解するために、まずベーシック録音の時の信号の流れを例にとってみてゆこう。
ベーシック録音では、ミキサに入力されるのはマイクやD.Iからの出力だ。で、このままでは信号レベルが低くMTRに録音できないので、MTRに録音できるレベルまでに信号を増幅してやる。またこの時点では、マイクやD.Iから入力された信号のレベルがバラバラなので、MTRに送る信号レベルをある程度一緒にしてやる事も大きな役割だ。詳しくは後述するけど、最終的に意図しているバランスに関係なく、MTRにはトラック毎に(歪まない程度に)なるべく大きく信号を送るというのが基本だからだ。つまり普通は、ミキサと言う名前のくせに、この時点では音を混ぜ足りしないのだ。
まあでも例外はあるので、この時点で音を混ぜてからMTRのどのトラックにでも送れるようにもなっている。
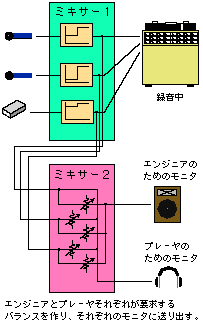 |
| 5-2-2 録音時に音を聞くための働き |
さてこれで確かにマイクやD.Iからの音をMTRに録音する事は出来る。でもこのままではエンジニアはおろかプレーヤまでもが自分の出している音を聴けないでしょ?これでは演奏にならないので、MTRへ送る部分から分岐して、もう一つのミキサ部に入力する。ここでエンジニアにとって聴きやすいバランス、プレーヤにとって聴きやすいバランスをそれぞれ取って、コントロールルームのスピーカやスタジオ内のヘッドフォンに送るわけだ。当然ここのバランスをいくらいじっても、MTRの録音レベルには一切関係ない。
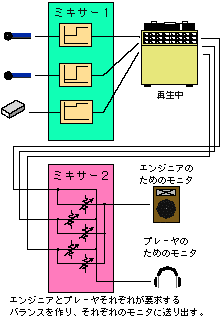 |
| 5-2-3 再生時に音を聞くための働き |
さて一通り録音が終わって、「とりあえず聴いてみようか」という事になったとする。でもこのままじゃMTRの出力には何もつながっていないので、MTRを再生しても音は聞こえない。さらに「とりあえず」って事は、またMTRに録音する可能性があるわけで、ミキサ1の部分もミキサ2の部分も設定を変えたくないわけだ。で、どうするかというと、さっき録音していたときにミキサ1のMTRへの送りから分岐していたものを取って、MTRの出力に付けてやればいいのだ。(実際のミキサはボタン1つで切り替わる)
MTRは入力された音量=出力される音量に調整されているので、(ほんとは録音の前に自分で調整するんだよ)録音していた時と全く同じ音の大きさでミキサ2に入力される。という事はミキサ2の部分は何も設定を変えていないわけだから、録音していた時と全く同じバランスと音量で、コントロールルームのスピーカや、スタジオのヘッドフォンが鳴るわけだ。(素晴らしい)
この部分が理解できれば後は楽勝だ。ミックスダウンの時は図5-2-3からマイクやD.Iとミキサ1の部分を取ってしまえばいいんだし、オーバーダブの時は重ねる(新規に録音する)チャンネルだけ図5-2-2のように、録音済みのものは図5-2-3のようにセットすればいいだけの話だ。