同期運転は、1台のマスターレコーダに、その他のスレーブレコーダを同期させる方式なので、理論上は何台でもスレーブレコーダを増やす事が出来る。基本的な動作原理は次の通りだ。
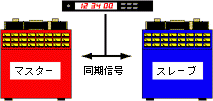 |
| 図4-4-1 録音時の関係 |
ここで同期信号を発生するのがタイムコードジェネレーターと呼ばれる物で、このタイムコードジェネレーターはこの同期信号を入れる作業が終わったら後は必要ない。同時に同じタイムコードジェネレーターから同期信号を録音しても、別々に入れてもかまわないし、フレーム数さえあっていれば別のタイムコードジェネレーターから入れてもかまわない。さらにマスターレコーダから同期信号をダビングしてもかまわないんだけど、ダビングによる音質劣化のために、スレーブ側が同期信号の読み込みエラーを起こす可能性があるので、あまりお奨めできない。どうしてもダビングしなければならない時は、シンクロナイザのリフレッシュタイムコード機能を使って一旦新しい同期信号に書き換えてから録音しよう。
また、音楽の録音の時にタイムコードを一緒に録音するという手もあるけど、何かの間違いで同期信号が上手く録音できなかったりすると、音楽の録音自体のやり直しになるので(スレーブレコーダにも音を入れていた場合)、タイムコードが音漏れする可能性もあるので、おすすめできない。
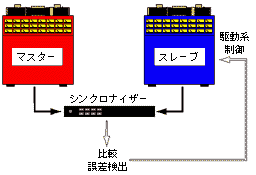 |
| 図4-4-2 同期時の関係 |
シンクイネーブルは、スレーブ機をマスター機に同期させるかどうかを選択するスイッチ。これをオフにすると同期運転はされない。チェイスイネーブルとは、スレーブ機に巻き戻しや早送りを許可させるかどうかを選択するスイッチ。これがオフになっていると、スレーブ機は同期するために巻き戻しや早送りを行わないので、これをオフにしてマスター機を早送りさせた場合などは、スレーブ機はプレイモードのまま必死に追いつこうとするが、同期するまでかなりの時間がかかってしまう。まあ通常はオンにしといた方が間違いはない。