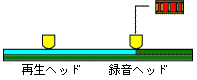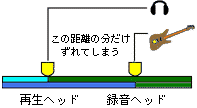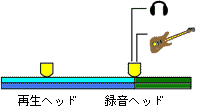MTRのトラック数は、最低でも4トラック、多いもので(単体で)32トラックというところだ。名前の通りたくさんのトラックを持つテープレコーダなんだけど、全てのトラックを同時に録音したり再生したり出来るだけでなく、各トラック毎に録音再生が出来るというのが大きな特徴だ。例えば普通のカセットは4トラックなんだけど、同時に4トラック録音したり、LチャンネルとRチャンネルを別々に録音したりすることは出来ないでしょ?だから普通のカセットはMTRではないといえるわけだ。
- カセットMTR
アマチュア用としてもっとも安価に普及しているのが、カセットを利用した4〜8トラックのMTR。今から20年近く前にTEACが「サウンドクッキー」という名前で出したのが最初だ。(確か品番は#144)
当時20万円ぐらいの値段で、誰でも気楽に買えるものではないにしろ、それまでの主流だったオープンMTRが「1トラック当たり10万円」というのが相場だったことを考えると、割安感があり、さらにテープも普通のカセットテープ(クロムテープ)でいいことから、ミュージシャンを中心に人気があった。その後トラック数も8トラックまで増えてきたんだけど、割高感と、デジタル機器の登場によってあまり人気はない。デジタルMTR全盛の今でもお気軽感(本体の値段が安く、本体だけで録音からミックスダウンまで出来る)という魅力から、多くの人が使用している。またアマチュアの人の作品で優れた作品は、何故かこのカセットMTRで制約の中で作られたものが多い。(所詮機材じゃないって事だな)
技術的には、元々高品位の音質を求めるのが無理なカセットテープを使用することから、色々なアイデアがなされている。そのひとつがテープの倍速化。通常1.875ipsのカセットテープを倍の3.75psで回し、ダイナミックレンジを広く取ろうとしている。(機種によっては、普通のカセットと同じスピードのものや、倍速よりさらに速く回しているものもある)
次がクロムテープの使用。ノーマルテープより性能の優れたクロムテープ専用にすることにより、性能向上とコストダウンを図っている。(ノーマルとクロムの切替スイッチがないだけでも、かなりのコストダウンになるわけだな。)本当は性能面から言えば、メタルテープの方が性能はいいんだけど、何回も何回も同じ所を再生することの多いMTRでは、ヘッドがメタルテープに負けて磨耗してしまうので、メタルテープは使用しないのだな。
その他機種によっては隣り合うヘッドを逆相にして録音し、隣接トラックからの音漏れを少なくしたり、ドルビーやdbxなどのノイズリダクションシステムを最大限に利用して、音質の向上を図っている。
- アマチュア用オープンMTR
最近ではデジタル機器の台頭で、あまり存在価値のなくなってきたアマチュア用のオープンMTRだけど、逆回しやテープ編集による切り張りなど、アマチュア用のデジタル機器では出来ないこともたくさんある。
このアマチュア用オープンMTRもTEACが火付け役。20年前の最高機種80-8は、皆あこがれたもんじゃ。(じみじみ)とにかく普通のオープンテープより大きいテープをぶん回す都合上、なかなか安価なものが作れなくて、小型化(家庭用としては大切な要因)もままならなかった。そこに後発として参入してきたのが、元々スピーカやヘッドフォンなどを専門としていたFOSTEX。テープスピードを15ipsに固定して、トラック当たりの幅をTEACの半分にし、さらに小さめの7号リール専用にするということで、低価格化と小型化を実現し、8トラックオープンを身近なものにした。ボディーもプラスティックが多用してあり、TEACのMTRと見比べると、どうしてもおもちゃのように見えてしまうが、音質には対等とまでは行かないまでも、かなりのクオリティを確保している。またお互いに相手との違いを意識したのか、ノイズリダクションはTEACがdbx、FOSTEXがDolby-Cを使用している。まあ、とにかく比較的安くて軽くて小さいという、日本人の好みにぴったりと合った製品だったために、あっという間にFOSTEXはTEACとオープンMTRのシェアを2分するメーカになった。あとOTARIもこの辺りと競合する製品を出してきているけど、どちらかというと、プロ用MTRの小型版といったイメージで、値段も少し高めの設定だ。
- アマチュア用デジタルMTR
アマチュア用と言ってしまってよいのかどうかわからないくらいに、プロの間でもよく使われているのが最近登場したデジタルMTRだ。前章でもふれたように、各社いろんなものを出しているが、中小規模のスタジオではやはりALESISのA-DATが人気だ。後から容易に8トラック単位で容易に増設できる所などは、これまでのオープンMTRでは不可能だったことだ。もちろん後述の同期信号を使えば、アナログMTRもトラック数を増やせるが、シンクロナイザやタイムコードジェネレータの購入という追加投資が必要で、さらに同期信号のためのトラックが必要になったり、前もって同期信号を録音しておかなければならなかったりと、とても手軽にというわけにはいかない。またヘッドクリーニング以外は、基本的にはメンテナンスフリー(というか、手のだしようがない)なのもありがたいところだ。
- プロ用デジタルMTR
アマチュア用との大きな違いは、手切り編集を可能にしている点。つまり、従来のアナログの操作性を活かしながらデジタルの良さも出すという設計にある。もちろんプロ用と言うことで、細かなところにも気が配られているし、お値段もそれに比べてアマチュア用のものと比べて10〜100倍の差がある。中小規模のスタジオでは少し手が出ないお値段なので、大手のレコーディングスタジオにしか設置されていないのが現状。