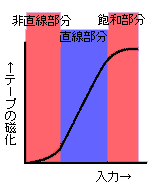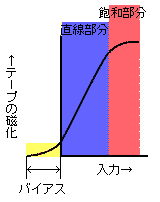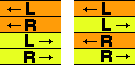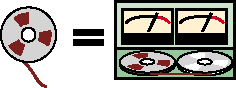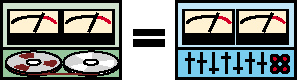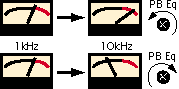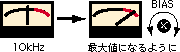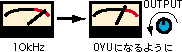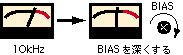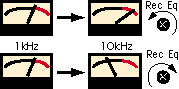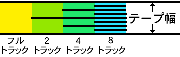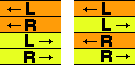3-2 アナログテープについて
3-2-1 テープ幅
オープンとカセットは録音媒体として磁気テープを使うので、当然テープの幅にも規定がある。オープンでよく使われるのは1/4インチ、1/2インチ、1インチ、2インチの4種類(1インチは約2.5センチ)だ。一般にレコーディングの世界では長さの単位はフィートやインチが使われることが多く、放送の世界ではセンチやミリが使われることが多い。例えば1/4インチのテープのことをレコーディングの世界では「シブイチ(1/4)」と呼んでいるし、放送の世界では「ロクミリ(6mm)」と呼んでいる。テープスピードにしたってレコーディングの世界で7.5ips(7.5インチパーセカンド)というのは、放送の世界では19cm/sの事だ。この章では、インチ表示で統一しておこう。ちなみにカセットのテープ幅は0.15インチと規格で決まっている。
3-2-2 フォーマット
テープを進行方向と平行に、いくつに分けるかというのがトラック数だ。「トラック(Track)」というのは陸上競技でいうあの「トラック」と一緒で『軌道』という意味だ。ちなみに車の「トラック(truck)」とは違うので念のため。
よくカセットなんかで表と裏とかいったりするけど、あれは本当にテープの裏表を使っているわけじゃなくて、テープの違うトラックを再生しているだけの話だ。理論的にはトラック数はいくらでも増やせることになるんだけど、テープ幅が同じならば当然トラック数が増えれば、トラックあたりの面積は少なくなる。その結果音質が悪くなるわけだな。またテープ幅が太くなると、同じトラック数でも幅が変わるのは当然で、1/4インチ幅のテープの2トラックのトラック幅と、1/2インチ幅のテープの4トラックのトラック幅は基本的に一緒。
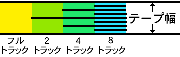 |
| 図3-3-1 トラック数 |
図3-3-1ではテープ面積の100%を使ってるけど、実際にはテープの端とトラック同士はある程度の距離を持っている。つまり音を録音しない部分がテープにはあるのだな。ややこしいことにこの幅がメーカーによって違うことあるので、あるデッキで録音した物を、違うデッキでそのまま消しながら録音すると、前の音が残ってしまうこともある。(具体的にいうとOTARIの1/4インチ2トラックデッキで録音した物をAMPEXの1/4インチ2トラックデッキで消去したときなどにこの現象が起こる。)
また2トラックの中にはトラックとトラックの間にもう一つタイムコードなどに使うキュートラックを持つ3トラック仕様のものがあるので、使用済みのテープを再利用する場合は必ずバルクイレーサで消去してから使用するようにしよう。まあレコーディングではあまりしないテープの再利用だけど、放送関係では当然の作業だ。普通、放送局にはテープを箱ごと放りこめば、一瞬で消去してくれる強力なバルクイレーサがある。
次にチャンネル数というのは、同時に再生できるトラックの数という意味。ステレオの再生は、左右別々に2つのトラックが必要だから、2チャンネルということになる。これをカセットのようにA面B面を使うとすると、A面で2トラック、B面で2トラックの計4トラック必要だけど、同時に再生するのは2トラックなので、4トラック2チャンネルというのが、ステレオ録音のカセットのフォーマットになるわけだ。このようにチャンネル数は、通常トラック数と同じか、もしくは1/2になる。
で、このトラック数とチャンネル数の組合せが、オープンテープのフォーマットという訳なのだな。一番簡単なのはテープ全面を1つのトラックとして使ってしまう方法だ。これはトラックが一つしかないので、当然モノラルの信号しか記録できない。言い方としては1トラック1チャンネルでいいんだけど、通常このフォーマットを図3-3-1のようにフルトラックといっている。現在ではこれは1/4インチテープを使ってAM放送のモノラル用として使われている。
次に2つに分ける2トラック、普通は2トラックを左右用にして片面走行で使うので、2トラック2チャンネル、もしくは2トラックステレオというわけだ。現在オープンを使うのはプロ用としての用途がほとんどなので、MTR(マルチトラックテープレコーダ)以外では、このフォーマットがオープンの主流。いわゆるマスタリング用というやつだな。ちなみにもうほとんど使われないけど、1トラックを表面と裏面として使う方法もあって、これは2トラック1チャンネル、または2トラックモノといわれる。
4つに分けた場合は4トラック4チャンネルと4トラック2チャンネルにわけられる。4トラック4チャンネルは、四半世紀以上前だが、4チャンネルステレオというのがあった時代があって、その時にはその再生用に使われたことがあるフォーマットだけど、今ではMTRなどで使われる方式だ。
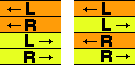 |
| カセット |
オープン |
図3-3-2
4トラック2チャンネルの違い |
4トラック2チャンネルのは、さっきも触れたように、ステレオ再生のカセットのフォーマットだ。あとは今でも細々と販売されている、家庭用オープンテープレコーダもこの4トラック2チャンネル方式だ。但し、オープンとカセットではトラックの使い方が違い、カセットでは図3-3-2の左のように、隣同士のトラックで2チャンネル使用しているのに対して、オープンでは右のように、飛び飛びにトラックを2チャンネル使用している。これはカセットは開発当初2トラック1チャンネルだったので、それ用のデッキでもとりあえずステレオ録音の物が再生できるように互換性を考えたためで、オープンの場合は互換性よりもクロストーク(左右のチャンネルで音が混ざり合うこと)などを避けることを重視したためだ。よって2トラック2チャンネルオープンデッキでは、4トラック2チャンネルで録音されたテープはまともに再生できない。(それで2トラック2チャンネルオープンデッキには、再生専用の4トラック2チャンネル用ヘッドがついているものもある。)
8トラック以上に分けた場合はMTRとして使用することがほとんどなので、トラック数=チャンネル数。ただし昔あった通称「8トラ」というカセットテープの親玉みたいな奴は8トラック2チャンネルだ。
以上テープ幅とフォーマットについて下にまとめておこう。灰色の字のものはあまり使われないフォーマットだ。
| テープ幅 |
トラック数 |
チャンネル数 |
用途 |
| 1/8インチ |
2 |
1 |
モノラルカセット |
| 4 |
2 |
ステレオカセット |
| 4 |
4 |
一般用カセットMTR |
| 8 |
8 |
一般用カセットMTR |
| 1/4インチ |
1 |
1 |
モノラル放送用 |
| 2 |
1 |
モノラル家庭用オープン |
| 2 |
2 |
プロ用マスタリング |
| 4 |
2 |
家庭用オープン |
| 4 |
4 |
TEAC一般用オープンMTR |
| 8 |
2 |
昔の8トラック |
| 8 |
8 |
一般用FOSTEXオープンMTR |
| 1/2インチ |
2 |
2 |
プロ用マスタリング |
| 4 |
4 |
昔のプロ用MTR |
| 8 |
8 |
TEACやOTARIの一般用MTR |
| 1インチ |
8 |
8 |
昔のプロ用MTR |
| 16 |
16 |
TEACの一般用MTR |
| 24 |
24 |
TEACやFOSTEXの一般用MTR |
| 2インチ |
16 |
16 |
昔のプロ用MTR |
| 24 |
24 |
プロ用MTR |
| 32 |
32 |
プロ用MTR |
| 表3-2-1 オープンテープのフォーマット |
3-2-3 テープスピード
テープスピードは、カセットは1.875ips(4.75cm/s)と決まっているので(カセットMTRの中には倍速タイプの3.75ipsの物もあるけど)問題はないけど、オープンには様々なテープスピードがある。
一番よく使われるのは放送関係では7.5ips(19cm/s)、レコーディング関係では15ips(38cm/s)のもので、基本的にはテープスピードが速ければ速いほど性能がいい。ところが形状効果(ヘッドがテープと接触するときにうねりが発生して、ヘッドの接触面の正数倍の波長を持った音声信号に影響を与える。)というものがあって、テープスピードが遅い場合は、このうねりは可聴周波数より低い周波数なので、さほど問題にならないけど、テープスピードが上がってくると、可聴周波数帯域に影響が及び、低域の特性に悪影響を与える。だからちょっと意外な感じがするけど、テープスピードが速いほど低域の特性は悪くなる。ただし、テープスピードが速いことによって得られるダイナミックレンジの広さは、それ以上のメリットがあるし、最近のデッキではこの形状効果を補正する回路を持っている物も多いので、やはりテープスピードは速いに越したことはないというのが結論。ちなみにテープスピードはすべて暗記する必要はないよ。なにか一つ覚えておけばそれから倍にしていくかか半分にしていけばいいからね。これも下にまとめておこう。
| テープスピード |
用途 |
| 0.938ips(2.38cm/s) |
マイクロカセット |
| 1.875ips(4.75cm/s) |
カセット・昔の一般用オープン |
| 3.75ps(9.5cm/s) |
倍速カセット・昔の一般用オープン・放送関係のロースピード |
| 7.5ips(19cm/s) |
放送関係の標準スピード・レコーディング関係のロースピード |
| 15ips(38cm/s) |
放送関係のハイスピード・レコーディング関係の標準スピード |
| 30ips(76cm/s) |
レコーディング関係のハイスピード |
| 表3-2-2 オープンテープのスピード |
3-2-4 リールとテープの厚さ
リールとはテープの巻いてあるもののことで、リールの芯をハブ、ふちの部分をフランジといっている。オープンテープには様々なリールの大きさがあり、一般的に使われているものは小さい順から5インチ・7インチ・101/2インチ・14インチのものだ。日本では慣用的にインチの代わりに号を付けて、5号・7号・10号・14号と呼んでいる。当然リールの大きさによって巻取れるテープの長さが変わってくる。通常5インチで600フィート(約183m)、7インチで1200フィート(約366m)、101/2インチで2400フィート(約732m)もしくは2500フィート(約762m)、14インチで5000フィート(約1524m)となる。で、これで録音できる時間はそれぞれ、15ipsで7分半、15分、30分(2500フィートのものは33分)、66分となる。当然テープスピードを7.5ipsにすれば録音できる時間は倍になり、30ipsにすれば半分になる。
これはプロ用のテープの標準的な厚さのものの場合で、マスタリングテープとしてよく使われるAMPEX#456やSCOTCH
JMT-3100やMaxcell PM-50がこの厚さだ。AMPEX#457は#456の2/3の厚さなので、同じリールにまかれているテープの長さは1.5倍になり録音できる時間も1.5倍になる。
カセットテープは60分のものが標準の厚さで、90分では2/3、120分では半分、最近登場した160分のものでは約1/3の厚さになっているわけだ。60分より短い46分や30分や10分のものは単純にテープを短くしているだけだ。(ものによってはハブを太くしているものもあるけど)
で、このテープの厚さなんだけど、実は薄ければ薄いほどテープがしなやかになって、テープレコーダのヘッドとの密着度が高くなるので、他の状況が一緒ならば音質的には薄い方が有利なのだ。しかしながら、テープは薄くすればするほど、テープが伸びたりして変形する恐れがあるし、テープが薄いと転写(Print
Through 録音済みのテープを保存しておくときに、テープが重なった部分が影響しあって、音が他の部分に移ってしまう現象)がおきやすいわけだ。で、長期にわたって保存することが多いプロ用としては、ちょっと頂けないし、トルク(テープを引っ張る力)が強いテープレコーダを使うこともあって、プロ用のテープはちょっと厚めなテープを使っているわけだ。