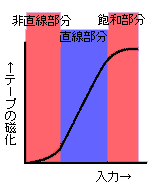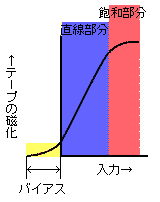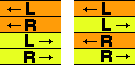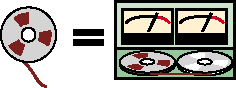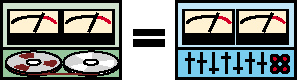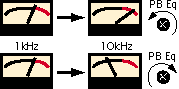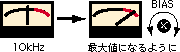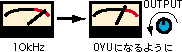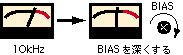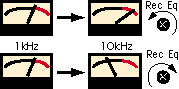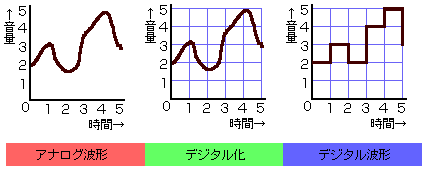3-4 デジタルについて
3-4-1 アナログとデジタルの違い
もうさんざんいろんな所で聞く言葉なので、何となく意味は分かっているとは思うけど、音響屋としてもう一度「アナログ」と「デジタル」の意味のおさらいをしておこう。
一般的には、連続量をアナログ、断続量をデジタルといってる訳なんだけど、数以外で量や時間や長さなど、自然に存在するものはすべてアナログ量なんだな。ところがこのアナログ量を正確に表すことは事実上不可能なわけだ。例えば今の時間は、「何時何分何秒」というふうにはいえるけど、正確には秒以下の細かい時間があって、それを表すのが不可能ということだ。(ちなみに長さとか重さは原子レベルまで突き詰めていけば、正確に表すことが出来ないこともないけど、これも非現実的な話だ)
ということは今更デジタルだデジタルだと騒がなくても、日常生活でほとんどのものはアナログをデジタルに変換して(適当なところで四捨五入とかして)表示しているわけだな。デジタルというと高度なことをやっているイメージがあるけど、同じものを表す場合は、デジタルよりアナログの方がはるかに情報量は多いのだ。勘違いしてはいけないのは「デジタル=2進法=1と0の世界」ではないということ。デジタルというのは「基礎となる量のいくつ分」で表すことであって、電子機器を使って計算などをする場合には、電気的に都合のいい2進法で処理しているだけの話だ。
3-4-2 サンプリング周波数とビット数
さて「音」というアナログ量を扱う音響の世界で、デジタルを利用するときには、アナログ量をデジタル量に変えてやる必要があって、この働きをする機械をDAコンバーターまたはDACといっている。要はアナログ量を適当なところで四捨五入するものなんだけど、この適当なところを表すのが、サンプリング周波数とビット数だ。
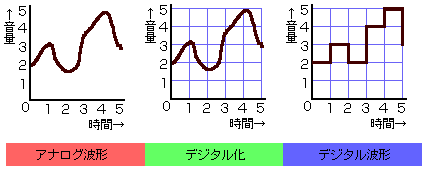 |
| 図3-4-1 DAコンバーターの働き |
DAコンバーターの働きは大雑把に言うと、図3-4-1のようにアナログ信号の上に方眼紙をかぶせて、アナログ信号の細かい部分を切り捨ててキリのいい数(=方眼紙のマス目)に置き換えてやるというものだ。この方眼紙の縦に区切る線の数をサンプリング周波数と言い、サンプリング周波数が高くなるほど(高域の)周波数特性が良くなる。また横に区切る線を量子化ビット数(通常ビット数と呼ぶ)と言い、ビット数が大きくなるほどダイナミックレンジが広くなる、(小さい音から大きい音まで表現できるようになる)という訳なんだな。図ではマス目が荒いので、波形は大きく変わってしまっているけど、このマス目が細かくなれば、元の波形とほぼ同じデジタル波形が出来ると言うわけだ。
サンプリングいうのは標本、つまりある集合の中から見本を取り出すということで、音響の世界では「ある時間の信号の大きさを調べて、それを取り出す」ということだ。これを一定時間間隔でどんどん取り出していけば時間軸に関してはデジタル化できることになる。でこの一定時間間隔を表すのに「一秒間に何回」という言い方をする代わりに、周波数で表現しているわけだ。だから1秒間に1000回の間隔でサンプリングしたとすると、これをサンプリング周波数1kHzというわけだな。サンプリング周波数を上げれば上げるほど原音に忠実なデジタル化ができることはわかってんだけど、サンプリング周波数を上げれば上げるほど扱うデータ量が増えてくるので、(つまり技術的にも難しくなって、デジタル機器の値段も高くなる)実際にはDATなどで48kHz、CDや衛星放送のBモードで44.1kHz、衛星放送のAモードやDATのLPモードで38kHzを採用している。
理論上、ある周波数を再現するためには最低その倍のサンプリング周波数が必要なので、DATの高域周波数特性は48/2=28KHZ、CDは22.05kHzが限界ということになる。人間の可聴周波数帯域、つまり人間が音として認識できる周波数帯は、個人差はあるが大体20歳前後で20Hz〜20kHzといわれているので、DATもCDも一応は充分な性能を持っているといえる。
まあ昔から可聴周波数以上の高域も音質に影響を与えるというのが言われているので、将来のプロ用機器にはもっと高いサンプリング周波数のデジタル機器が標準になるだろう。逆の言い方をすると、現状では一流のレコーディングスタジオにあるプロ用機器も、電気街で叩き売りしているCDラジカセも、デジタルの性能的には全く一緒ということだ。(従来のアナログ録音機がプロ用と民生用では天と地ほどの差があったのを考えれば、とんでもない時代になったもんだ)
それでサンプリング周波数の間隔でアナログ信号のレベルを取り出すのはいいけど、取りだした値がアナログ値では困るので、こちらも一定量ずつ区切るわけだ。ビットってのは区切りの細かさを表す単位だと思えばよくて、1ビットで有るか無いかを表すことができる。「電源スイッチはONとOFFの1ビットの機械」という言い方ができるわけだ。2ビットになると2×2で4つの違いを表せる。で、ほとんどのデジタル機器は16ビットを採用している。16ビットっていうとサンプリング周波数に比べてえらく大雑把なように思うかもしれないけど、ご心配無く、16ビットは216で65,536の違いを表現できるんだ。これも十分かというと、そうでもないんだけど、サンプリング周波数と同じく、実用的な部分でこの辺りに落ちついている。
3-4-3 デジタル機器の入力レベル設定方法
デジタル機器の入力レベル設定をする機会があるのは、DATやSPXなどのデジタルエフェクターなどだな。デジタル機器はビット数によってダイナミックレンジが決まるので、入力レベル設定はビット数の限界まで使いきるのが、もっともいい入力レベルの取り方という事になる。アナログ機器もデジタル機器も、出力が歪まない最大入力を最大レベルとして設定してあるのは一緒だけど、アナログ機器の場合レベルオーバーをした入力があっても、ひずみが増えるけどちゃんと出力してくれる。だけどデジタル機器はレベルオーバーした成分は全く出力に現れないので、完全に波形が変化してしまう。よってデジタル機器を使う場合はレベルオーバーは絶対にしてはいけない。
録音時にはピークホールド機能(メーターの最大表示をリセットするまで表示しておく機能)やマージン表示(最大入力レベルまで、あとどのくらいの余裕があるか数値で示すもの)を使ってオーバーレベルを絶対に避けるようにする。とはいうものの余り入力レベルを低く取るとデジタル機器の性能を悪くして使っているようなものなので、(極端な話、16ビットのデジタル機器を最大入力レベルの半分で使ったとすると、8ビットのデジタル機器を使っているのと同じ事になる)生録や一発録りのように、どんな音量が来るか判らないような状況の場合以外は、「歪まない程度になるべく大きく入力レベルを設定する」という大原則を遵守するようにしよう。
ということで、アナログ機器の場合は大原則だった「1kHz0VUですべての機器のレベルを合わせる」というのがデジタル機器では通用しない事が多いんだな。大体デジタル機器にVUメーターが付いていることはないでしょ?これは何故かというと0.3秒間の音量を平均して表示するVUメーターは、人間の感覚に比較的近い表示をしてくれるという良い点はあるのだけど、デジタル機器にとってみれば0.3秒間の平均値なんていうとろいメータで表示していては、ピーク成分の表示が出来ないので、最大音量を監視して、適切な入力レベルを決める事が出来ないからなんだな。
まあそれでもDATの録音レベルの一応の目安としては、ミキサの1kHz0VUでDATのピークメーターが-12dBになるようにしておく。あとはリハーサル録音の時に、デッキのマージン表示機能などを利用して最適レベル(0dBを一度も超えることなく、かつ録音レベルが一番大きい状態)に設定しておく。マージン表示機能は再生時でも有効だけど、メーター表示を確認しないまま録音したテープを再生して、「お、丁度0dBフルにつかっとるがや。ぅらっきぃ(英語)」なんて思わないように。極端な話ずっと0dBを越えるようなレベル設定をした場合でも、録音時には赤いオーバーロードを示すインディケーターが点灯して、マージン表示が0.0で点滅しているので判るけど、それを録音して再生した場合にはメーター表示は0dBまでしかしなくて、オーバーロードを示すインディケーターは点灯しないし、しかもマージン表示も0.0を示すものの点滅はしないのだ。(ちなみにマージン表示はMARGIN
RESETというボタンを押すとクリアできる。)
3-4-4 SCMS
デジタル音響機器の特徴の1つとして、デジタルコピーをした場合にコピー元(親)とコピー先(子)は理論上全く一緒のものが出来るというのがあげられる。アナログメディアではテープ自体や録音系から出る歪みやノイズによって、必ず親側より子側の音質が劣化するのは避けられない事を考えれば、これは大きなメリットだ。だけどCDレンタルの繁盛ぶりを見れば、これはソフト制作側にとって憂慮すべき事態だというのは判るでしょ?
現時点ではCDレンタルを利用するパンピーが、CDR(書き込み可能なCD)やDATを持っている確率はまだ低いけど、誰かがCDを借りてきて、CDRやDATなんかにデジタルコピーすれば、そのCDRやDATからいくらでもCDと全く同じクオリティーのものが出来るわけで、海賊版天国の地域なんかにとっては、格好の標的になってしまうのは目に見えている。で、当初ソフト制作側は、民生用のデジタル音響機器の発売をかたくなに反対していたんだけど、「デジタルコピーは、1回に限り出来ることにしましょう」ということで合意した。これがシリアルコピーマネージメントシステム(Serial Copy
Management System)略してSCMSだ。もしこれがなければMDなんかもここまで派手に登場しなかっただろうな。そのかわり一部のマニアには「コピーしまくり機」として人気が出ていたかもしれないけどね。
で具体的に「デジタルコピーは一度だけね」という、ひと夏のアバンチュール(死語)のようなこのシステムはどういったものかというと、デジタルコピーをするときに、こそっと「これはデジタルコピーしたものですよ」という信号を音声信号などと一緒に、子側のテープやディスクに書き込んでしまうのだ。でその子テープやディスクから、孫テープやディスクにデジタルコピーしようとすると、孫側のデッキはその隠れ信号を関知して「これはデジタルコピーされたテープですから、このテープからのデジタルコピーは出来ません」と生意気にも拒否するようになっているのだ。(この時孫側デッキにはCOPY
PROHIBITEDという表示が出て、録音ボタンを押しても反応しないようになっている。)
もちろん親テープやディスクからは何回でも子テープやディスクを作ることが出来るし、子テープやディスクをアナログで再生させて、それを孫側のデッキにアナログ入力すればコピーすることは出来る。ただしD/AコンバーターとA/Dコンバーターを1回づつ通っているので、そのテープやディスクはデジタルコピーとはいえない。(=多少の音質劣化がある)またそのテープやディスクは親になるので、そこから更にデジタルコピーをすることは出来る。
現在このシリアルコピーマネージメントシステムは、民生用のデジタル音響機器の全てに搭載されている。まあパンピーにとってはそれでも余り不自由はないとは思うけど、その筋(中小零細スタジオ関係)には不便な規格だ。
例えばDATで何本かに分けてバラバラに録音したものを、デジタルコピーしてマザーテープを作ったら、そのマザーテープからデジタルコピーをすることが出来ないので、バックアップやダビングが出来なくなってしまうのだ。だから結構その筋の人たちは、シリアルコピーマネージメントシステムが搭載される前の古いDATデッキを探して、中古品店や質屋などをうろついたり、「SCMS外し」などという怪しい機械を使ったりすることがあるらしい。(笑)ちなみにお金のあるスタジオではこのような問題は発生しない。なぜかちゅーと、お金のあるスタジオではプロ用のDATデッキ(100万円前後)を購入すればいい。このような完全にプロ用のDATにはシリアルコピーマネージメントシステムは搭載されていないので、デジタルコピーなどし放題だからだ。(まあ確かに300円で借りてきたCDをダビングするために100万円も払う物好きは余りいないとは思うけどね。)