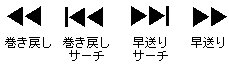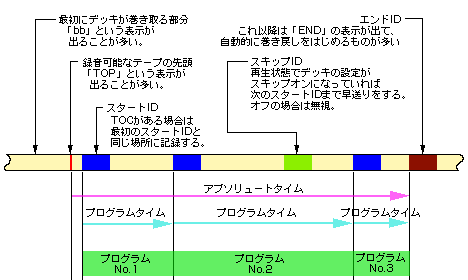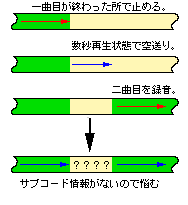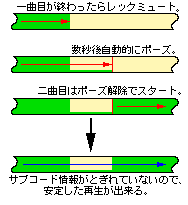あ、それからCDの時は8ビットを14ビットに変換するEFMという変調方式を利用していたけど、DATも同じように変調しなければデータとして認識できない。DATで使われる変調方式はETM(Eight
Ten Modulation = 8-10変調)といわれるもので、これはCDと同じように16ビットを8ビット2つに分けたあとに、今度は10ビットに変換するやり方だ。何故CDと同じじゃないかとわしに聞くな。CDのときは「1と1の間には必ず0が2個以上10個以下含まれること」という取り決めだったんだけど、DATの場合は「1と1の間に0が最大3つまで」という決まりになっているのだな。でこれを満たす組合せは14ビットなくても10ビットで用意できてしまうので、DATでは8ビットから10ビットに変換する方式になっている。
 MDとはミニディスクの略で、現在ソニーが中心となって売り出しているデジタル録音メディアだ。シングルCDを一回り小さくしたようなディスクをメディアとするので、DATなどのテープを利用するものに比べて耐久性が高いというのがもっとも大きなウリだ。
MDとはミニディスクの略で、現在ソニーが中心となって売り出しているデジタル録音メディアだ。シングルCDを一回り小さくしたようなディスクをメディアとするので、DATなどのテープを利用するものに比べて耐久性が高いというのがもっとも大きなウリだ。
原理的にも性能的にもサンプリング周波数が44.1kHzで量子化ビット数が16ビットとCDと同じスペックなんだけど、デジタル化するときにATRAC(Adaptive
Transform Acoustic Coding)というインチキをやって、16ビットのデータを4ビットまで圧縮して記録している。よってCDの約半分の大きさのメディアに70分以上の録音が可能となっているわけだ。
データを圧縮してある関係上、再生にはデータの伸張が必要になり、約3秒間のデータをRAMに読み込んで、順次伸張しながら音声信号を再生する。けがの功名的に、もし読み込みエラーが起きても、3秒以内ならもう一度読み込み直せばよいので、CDより読み込みエラーには強く、振動の多いカーステレオなどの分野やポータブルステレオの分野に向いているといえるわけだな。
DATや後述のDCCなどに比べて、MDのメリットはというとなんといってもCDと同じ、非接触型のメディアだということだろうな。DATやDCCはテープをヘッドがこするという接触型のメディアなので、アナログメディアに比べて長いとはいうものの、確実のテープにもデッキにも寿命がある訳なんだけど、CDやMDは半永久的に使用することが出来る。ATRACによる圧縮は人間の音響心理を利用して、ほとんど必要のないデータの部分を消してしまうというものなので、歪みの発生は避けられないものの、ちょっと聴いただけでは判らないようなごく微量の信号の変化なので、一般用としては十分な性能だ。
だがプロは音のわずかな違いが勝負所という部分もあるので、圧縮をするMDはマスタリングなどの用途に使われることはないといっていい。またプロ用として考えるとサンプリング周波数が44.1kHz固定というのもいただけない。(最近はサンプリング周波数のコンバーターが装備されていることが多いけど)さて、果たしてどこまで家庭用デジタル機器のスタンダードとなるか・・・個人的な意見だが、一般人はそこまで音にこだわっていない気がする(^_^;・・・・カセットでい〜じゃん。
本来なら最初に紹介するべきもんなんだろうけど、お恥ずかしい話しながら私は使ったことがないのだよ。で、ざっとだけふれておくことにしよう。
現在プロ用固定ヘッドデジタルテープレコーダには大きく2通りの規格があって、1つはソニー・松下・TEAC・STUDERが共同提案したDASHフォーマットと、もう1つは三菱・AKAI・OTARI・AEGが共同提案したPRODIGI(PD)フォーマットだ。この2つの規格には互換性はないので、不便は不便なんだけど、どちらも独自の技術で高性能化をはかっているためこの両者の甲乙は付けにくく、将来どちらかのフォーマットが消えてしまうこともなさそうだ。ただしMTRの部分ではSONYがPCM-3348というヒット機種を出したために、DASHフォーマットの方が優位に立ちつつある。共通点はサンプリング周波数が48kHzと44.1kHzに対応している点と、量子化ビット数が16ビットリニアな事だ。
固定ヘッド式の大きなメリットは、アナログテープのように手切り編集が可能な事だ。DATなどが回転ヘッドをテープに斜めに当てることによって何とか記録できるデータ量を増やしているのに対して、同じくらいのデータ量を従来と同じような方法で(しかも同じテープスピードやテープ幅で)記録しようとしているわけだから、とんでもなく高密度記録テープになるはずで、本来なら手切り編集はおろか、手で直接触ることさえ出来ないようなもののはずなんだけど、手切り編集を可能にするために様々なエラー訂正への努力がこれを可能にしているわけだ。(で、DATやDCCなどはこの技術をちゃっかり利用して大きな顔をしている)
- DASHフォーマットのウリ
1/4インチテープを使用する2トラック機は、ツインDASHといわれる方式によって手切り編集時の信頼性に優れる。またマルチトラック機は、トラック数が48トラックでも1/2インチテープで済む。従来のDASHフォーマットの1/2インチ24トラックのフォーマットで録音されたテープを、48トラック機で正常に再生することもでき、さらにそのテープに音を重ねて48トラックテープに変更することもできる。
- PRODIGIフォーマットのウリ
1/4インチテープを使用する2トラック機は、オプションとしてサンプリング周波数そのまま(44.1kHzもしくは48kHz)で、ビット数を20ビットにするSTDモードと、ビット数はそのままサンプリング周波数を96kHzにするHSモードがある。STDモードを使用した場合のダイナミックレンジは約120dBになり、通常のモードより約30dB改善される。HSモードの場合は40kHz以上の周波数帯域まで周波数特性が改善される。
現在新製品発表がもっとも活発に行われている分野だ。一昔前のキャッチコピー風にいうなら「今、デジタルが熱い!」ってとこかな。(ああ恥ずかしい)
一般的な分類でいうと、テープレスレコーディングというくくり方をすることが多いんだけど、そういった意味ではCDやMDもディスクに記録するので、ここの中に分類されることになる。まあでもCDやMDはもう珍しくもなんともない存在なので、ここではその他のテープレスレコーディングメディアについてふれておこう。
その他のテープレスレコーディングメディアと一口にいっても様々なものがあるけど、いずれも音声信号をデジタル化して、読み込んで処理をしてから出力したり保存したりすることには代わりない。これを楽器側からアプローチしていったものがサンプラで、テープレコーダの代用として進化していったものがハードディスクレコーダだ。よってこの2つの構造はほとんど同じものなんだけど、サンプラはより楽器としての使い勝手を、ハードディスクレコーダは今までのテープレコーダのシミュレートや新しい機能を充実させることに重点を置いている。
現在デジタル機器に使われているメディアは
なんかが代表的だ。これらは皆ランダムアクセスが可能だという点が、テープを使った録音メディアとは異なる点だ。
ランダムアクセス(Random Access)とは簡単にいうと、メディアのどの部分にも瞬時に移動できるという事で、例えばCDもランダムアクセスが可能なメディアなので、いきなり1曲目から12曲目にとばすなどという芸当が可能なわけだ。これはDATなどのテープメディアでは出来ないことだ。
更に上記の5種類のメディアの順番はそのメディアの読み書きの早さも表していて、RAM
/ ROMがもっとも速く、フロッピディスクがもっとも遅い。早さの点だけ考えればRAM
/ ROMを使えばいいということになって、他のメディアの存在意味がないことになるけど、現実にこれだけ存在しているという事は、それぞれにメリットデメリットを抱えているという事になるわけだ。
- RAM / ROM
RAMはRandom Access Memoryの略で、ROMはRead Only Memoryの略だ。この2つは構造も性能もよく似ているけど、RAMは何度でも記録の書き換えができるのに対して、ROMはその名の通り、いったん書き込んでしまった記録は消すことができない。
今までのテープレコーダなどの代わりにしようとすると、読み書きできるRAMの方ということになるんだけど、RAMは現在の記録メディアで最高速の読み書きスピードがあるものの(次に高速なハードディスクの約100〜1000倍)、記録容量当たりの単価が高く、大容量にできないのが難点だ。(値段はハードディスクの約50〜500倍)よってRAMは現時点では、デジタルメディアの作業用の記録素子として使われている。保存はハードディスクなどの記録メディアにまかせて、高速な処理が要求される部分にのみRAMを使用しているわけだ。あ、それとRAMにはもう一つ弱点があって、記録を保持するためには電源が必要ということだ。だからサンプラーやデジタルエフェクターなどのデジタル音響機器は、電源を切ってしまうとその中にあった音声信号は消えてしまう。サンプラーがデータをフロッピディスクやハードディスクに保存しなければならなかったり、SPXシリーズのFREEZEでサンプリングした音が電源を切ると消えてしまうのはこのためだ。
(ちなみにキーボードの音色を保存しておくRAMカードは、中に電池がちゃんと入っている。例外としてヤマハのDXシリーズのカートリッジには電池が入っていないんだけど、これは単純なデータなら読み書きできる特殊なROMを使っているのだ。)
RAMに比べてROMは工場で一度データを書き込んでしまったら(通称「焼き付け」)、そのデータは消したり変更したりできず、その分大量生産すればコスト的に安くすることができるので、需要のある自動販売機やエレベーターの音声案内に使用されている。ちなみにROMは一度焼き付けてしまえば電源がなくても内容を保持してくれる。
良く言われることだが、宅急便のトラックの「バックします」というROM音声は「ガッツ石松」と聞こえる。
- ハードディスク
ハードディスクという名前は、それまであったフロッピディスク(へなへなしたディスクという意味)に対してハード(堅い)といっただけで、別に象が踏んでも壊れない訳じゃない。それどころか振動やごみなどに非常に弱いデリケートなメディアなのだ。
構造は、アナログレコードのプレーヤのようなものだと思えばいい。決定的に違うのは、「針」の部分が円盤からほんのわずかに浮いていることと、円盤が超高速だという事だ。大容量のハードディスクはこの円盤と針の部分を何枚か重ねて1つのハードディスクにしている。最近コンピューターの扱うデータが肥大化の一途をたどり、それを保存するハードディスクも大容量化が進んだため、大容量のハードディスクが比較的安価になってきた。15年前20MBのハードディスクといえば超大容量で何十万円もするものだったんだけど、今や読み書きスピードが倍以上になった4GBのハードディスクが3万円程度で買える時代だ。
よって以前は恐れ多くて考えもしなかった「音声データをハードディスクに読み込んでしまおう」という発想が生まれてきたんだ。なんせ1分間の録音に約10MBの容量が必要というのが相場だから、1曲をマスタリングするためだけでも、昔は何百万の金を払ってハードディスクを数台用意しなければならなかったわけだし、ハードディスクの読み書きスピードも遅いので、データの書き込み読み込みエラーを起こす可能性が高かったわけだな。(でもこの流れでいくと、現在ではまだまだ高価で低容量のRAMに音声信号を読み込んで保存するという時代が、そのうちやってくるかもしれない。まあ1999年の7月以降に地球が存在すればの話だけど。)
で、現在脚光を浴びているのが前述のハードディスクレコーディング・HDR(HardDisk
Recording)だ。現在このハードディスクレコーディングの機器は、大きく2通りに別れていて、1つはハードディスクレコーディング専用機。もう1つはコンピューターを利用したものだ。専用機で現在で回っているものはAKAIのDR4VRやDR-8やDR-16、FOSTEX
D-80、RolandのVS-880などで、最近はSONY MDM X4、YAMAHA MD4、TASCAM 564など、ハードディスクではなくMDを利用したものが、アマチュア用を中心として売られている。コンピューターを使うものには、コンピューター本体を利用するものや、本体にカードを増設してやるもの、本体はコントローラーとして利用するものなど色々なタイプがある。いずれも今までのマスターレコーダやMTRのような使い方をするように考えられているわけだ。(AKAIのS-3200などはサンプラーながら、ハードディスクレコーディングも出来るようになっている)
ハードディスクレコーディングで今までのテープレコーダでは出来なかった機能は、何といっても非破壊的(ノンディストラクティブ)編集な編集が可能なことだ。ハードディスクレコーディングではハードディスクに音声信号を記録して、それをRAMに読み込んで編集するために、RAM上にあるデータが使いものにならなくなったとしても、ハードディスクにデータが残っている限り何度でもやり直すことが可能だからで、失敗したらあ゛ーといってももう遅いアナログテープの切り張りに比べると、格段に便利で安心だ。
これを考えるとプロ用のスタジオなんかは、みんなハードディスクレコーディングに移行してもよさそうなもんだけど、48トラックを1時間録音する容量となると、15GB(ギガバイト)ものハードディスクが必要になるし、作業用のRAM領域も膨大な容量が必要になる上に、録音したもののバックアップや保存にも同じだけの容量を持った記録メディアを用意しなければならない。これではとてつもなく高い設備投資とランニングコストがかかってしまうので、現在の所ハードディスクレコーディングは、2トラックや8トラック程度までの使用に限られている。ただし2トラックの編集で、今までさんざん苦労して切り張りしてきたCM制作のギョーカイや放送局にとっては、ありがたいことこの上のない機械なので、AKAIのDD-1000というハードディスクレコーダ(厳密にいうと記録メディアに後述のMOを使用しているので、ハードディスクレコーダではないんだけどね)などは10年ほど前にあっという間に色々な放送局や小中規模のCMスタジオやMAスタジオに普及した。
- MO
通常「えむおー」と呼んでいるけど、これは光磁気(Magneto Optical)の略で、磁気によって円盤の表面を変化させ、それを光学的に読みとる方式だ。まあ構造的なことは知らなくてもいいとして、性能的にはハードディスクに比べて、読み書きのスピードがほぼ同じくらいで、容量は3.5インチで200MB強、5インチで500MB強といったところ。そのまま音声信号の記録に使うこともあるけど、ハードディスクとの一番の違いはメディアがドライブから取り出して交換できる(リムーバブル)だということで、データーの保管用によく使われるが、最近ではOTARI
PD-80などMOを利用したレコーダも発売されている。その他リムーバブルメディアとしてはとしてはSyQuest社の「リムーバブルハードドライブ」やiomega社の「zip」や「jaz」なんかがある。
- WO
余り一般にWOという言葉は使われないけど、Write Onceつまり、一度だけ書き込みが出来るメディアのことだ。現在このたぐいのものは再生専用のものまで含めると、規格といい製品名といい大混乱を起こすようなものばかりだ。何故かというと、生産ラインが確立していて単価を押さえられるメディアであるCDを利用したものがほとんどだからだ。ざっと挙げると、CD-WO,
CD-MO, CD-R, CD(CD-DA), CD-S, CD-G, CD-V, CD-ROM, CD-ROM-XA, CD-I, 電子ブックなど。ここまで色々あると説明する気にもならんし、コンピューター用のフォーマットや映像用のフォーマットも多いので省略するけど、性能的には読み書きのスピードがハードディスクの1/10程度、容量は600MB位だ。
- フロッピディスク
まあどういったものか説明する必要はないと思うけど、実際にこのフロッピディスクが音声信号の記録に使われることはない。ハードディスクなどの他のメディアに比べて記録容量が極端に小さくて、読み書きのスピードが極端に遅いからで、さらに同じデータ量を記録するのにしても他のメディアより割高になってしまうからだ。例えば2HDのフロッピディスクの容量は約1.4MBなので、CDの音声データをもし移したとしても9秒程度しか記録できないのだよ。まあワープロのデータなら、本1冊分のデータくらい入ってしまう容量を10秒弱で使いきってしまうということで、いかに音声のデータが記録メディアやコンピューターにとって負担の大きいものかが判るでしょ。(それでも画像データの比べればかわいいものなんだけど)