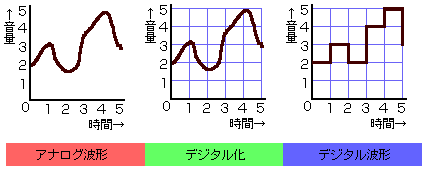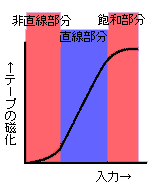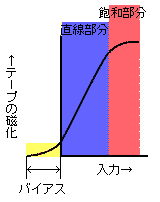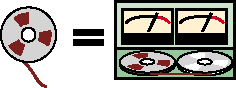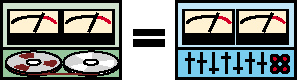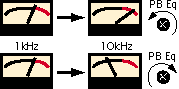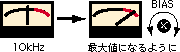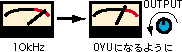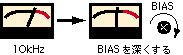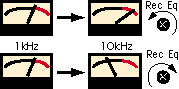3-3 オープンの調整
どんなテープレコーダでも調整は必要だ。これはテープレコーダが動く部分を持っている以上、仕方のないことだ。つまり、動く部分があるという事は、振動によって位置がずれたり、磨耗によって性能が変わったりするということなんだな。みんなが持っているラジカセなんかには、調整用のつまみやネジはどこにも見あたらないと思うんだけど、これは調整が出来ないんじゃなくて、不用意にさわって問題が起きないようにするためで、実際はメカの中に調整用の半固定抵抗やネジなどが隠されている。プロ用の機器では(どこまで調整できるかは別として)必ず調整が出来るようになっている。「あんたらプロなんやから、調整の一つもできるんでっしゃろな」ということだな。(何故大阪弁?)
特にここでオープンテープに限定したのは、アナログテープレコーダの中では調整がしやすい事と、モータなどの振動が大きく調整したものが狂いやすいので、調整の必要性が高いということからだ。DATなんかのデジタル機器は、VTRの技術の応用でちょっと高度になるのでここでは割愛する。(というか専門家以外はいじるべきではないと思う)
それでは調整について説明する前に、何故調整などと言うめんどうなことをしなければいけないかについて理解してもらえるように、簡単にテープレコーダが信号を記録して再生するプロセスで、各調整箇所がどのような役割を果たしているかについて説明しておこう。
3-3-1 ヘッド
3-3-2 バイアス
磁気テープの特性は非直線性を持つので、バイアス電流により直線性を持つ部分を使用する。といっても何のことかわからんでしょ?(^_^;
例えば自動車を例に取ると、ギアチェンジをしないとして、アクセルを踏み込んだ分だけ車のスピードが増えるかというとそういう訳じゃないよね?最初はアクセルを踏み込んだ割にはスピードが出ないけど、そのうちアクセルを踏み込んだ量とスピードが増す割合が同じになってきて、ついにはいくらアクセルを踏み込んでもある一定以上のスピードは出なくなってしまう。扱うものが違うので、全く同じとは言えないまでも、磁気録音も同じような特性を持っているのだ。
| 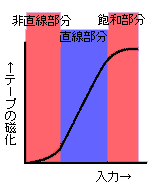
|
| 図3-3-1 テープの磁化曲線 |
つまり最初のアクセルを踏んだ割にはスピードが出ないというのが、磁気録音では、弱い信号(磁気)を受けたときのテープの帯磁の仕方で、変化を与えた量に比例して結果が変化しない。このことを非直線的な関係と言うわけだな。それである程度以上強い信号(磁気)を受けたテープは、変化を与えた量に比例して結果が変化するようになる。このことを直線的な関係といっているわけだ。さらにある一定以上の信号(磁気)を加えると、今度はテープがそれ以上には磁化されない状態になるんだけど、この状況のことは飽和といっている。
それで図3-3-1の赤い部分の、非直線性を持つ部分と飽和してしまう部分は、入力信号の変化の量とテープに記録される磁気の量の変化が一致しないという事なので、録音には使えない。要は磁気録音は、桃の(別に桃じゃなくてもいいけど)タネの部分と皮の部分を取って、実の美味しい部分だけを食べるようなことをしているわけだな。
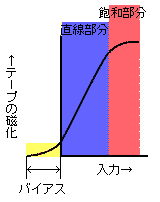 |
| 図3-3-2 バイアス |
で、飽和を防ぐのは、大きなレベルの信号を入力しなければすむけど、入力信号レベルが低いときの非直線性の部分は、小さい音を入力しないわけにはいかないので、バイアス電流(通常バイアスと呼ぶ)というもので下駄を履かせて、この部分を避けているわけだ。
このバイアスを深く(多く)取ると直線部分が少なくなってしまい、結果として影響のうけやすい高域特性が劣化するし、浅く(少なく)取ると、非直線部分を使うことになるので、歪みが増加する。この2つのジレンマの丁度中間点を、トップバイアスとかピークバイアスと呼んでいる。基本的にはこのトップバイアスの所が、テープの性能を一番引き出せる値だ。
で、確かにテープの中にはこのトップバイアスを推奨しているものもあるんだけど、最近のテープは高性能化しているので、高域特性より歪み特性を重視して、トップバイアスより深めにバイアスをかけることが多い。このことをオーバーバイアスといっているんだけど、オーバーバイアスの値はテープやテープスピードによって違うので、調整前に使用するテープの推奨オーバーバイアス値を調べておく必要がある。この部分の調整は後述するね。
| レコーディング用 |
AMPEX #456
AMPEX #457
AGFA PEM469
3M #206
3M #207 |
7.5ips |
-4dB |
| 15ips |
-2.5dB |
| 放送用 |
AMPEX #206
AMPEX #207
3M JMT-3100 |
7.5ips |
-3.5dB |
| 15ips |
-2.2dB |
| 表3-3-2 推奨バイアス値 |
3-3-3 録音基準レベル
ちょっと難しいけど、要はテープレコーダのメータが0VUを指すような信号を録音したときに、テープにどれだけの磁束密度を発生させるかという事。磁束密度の単位はWb(ウエーバー)。通常はウエーバーのままでは大きすぎるので、10-9を表す補助単位のn(ナノ)をつけて、nWb/m(ナノウエーバーパーメータ)で表す。
この磁束密度は日本では放送関係が200nWb/m、レコーディング関係では250nWb/mと思っとけばいい。200nWb/mと250nWb/mのレベル差は2VUなので、レコーディングスタジオで放送用のテープを録音する場合で、放送局の規格のテストテープがない場合は、とりあえず基準録音レベルだけそろえるためにミキサで1kHz0VUを出し、その0VUでテープレコーダのVUメータを-2VUにあわせて、それを基準信号として録音する事もある。(で、放送局側ではそのテープを受け取ったらその基準信号でテープレコーダのVUメータを0VUにして再生する)この磁束密度は高ければ高いほどS/N比が良くなるけど、その分転写も起こりやすくなる。
3-3-4 イコライザ
ここでのイコライザとは、イコライザ本来の意味、つまり変化してしまった周波数特性をもとの特性に近づけてやろうといった意味だ。テープレコーダのイコライザには、再生イコライザと録音イコライザがある。
再生イコライザはその名の通り、テープを再生するときに必要なイコライザだ。何故こんなものが必要かというと、磁化されたテープをヘッドで再生し電気信号に換えると、理論上周波数が倍になるに従って出力も倍になってしまうんだな。で、そのままでは都合が悪いので、周波数が倍になるに従って出力が半分になるようなイコライザを通して特性をフラットにしてやるのが再生イコライザの役目だ。
ただし周波数が倍になるに従って出力も倍になってしまうといっても、実際の高域や低域ではいろんな理由から特性が乱れてしまう。そこでこの乱れを録音の時に補正するためのイコライザが、録音イコライザというわけだ。だから録音イコライザは、再生イコライザに比べると微調整的な意味合いが強い。
で、このイコライザの特性には色々な規格があって、各国各業種別に様々な規格が採用されているんだけど、日本でよく使われているのは、NAB
NAB-J BTS JISの4つ。テープスピードが7.5ipsの場合はこの4つの規格は全く同じイコライザ特性だ。だから7.5ipsの時にはイコライザの規格を意識する必要はほとんどない。15ipsのときにはNAB-JとBTSが同じイコライザ特性になり、NABよりも高域を重視した特性になっている。(JISには15ipsの規定はない。)また今の所この4つの規格は30ipsの規定がないので、30ipsの場合はAESという規格を使うしかない。(ああややこしい)
3-3-5 掃除と消磁
別にダジャレをいっているわけではないのだが、この2つはテープレコーダにとって大変重要なので、調整に入る前に必ずヘッドや走行系の掃除と、ヘッドの消磁を行っておきましょうね。テープレコーダの掃除は、テープの走行するところをアルコールなどで拭き、ヘッドなどに付着したテープのかすなどを取り除くことで、みんなが最も簡単に出来るメンテナンスだ。これは調整前だけでなく通常の作業前と後に必ず行わなければだめだぞ。
商事、障子、賞辞、少時、小事、庄司、東海林、庄子、荘司、消磁とは(どうやら日本語として認められていないようだ)ヘッドにたまった磁気を取り除く作業で、特に3ヘッドのテープレコーダの再生ヘッドに対して重要な作業だ。この作業は毎回行う必要はないけど、大事な録音の前には必ずやっておく。
 |
| 写真3-3-1 消磁器 |
消磁には正直消磁器(ヘッドイレーサ、ディマグネタイザ、ディガウスとも言う)というものを使う。これは2つの金属片の間に強力な磁界を発生させて、ヘッドを磁気的に飽和させるもので、消去ヘッドとほぼ同じ原理だ。(だから消去ヘッドや、録音バイアスという磁気が常にかかる録音ヘッドや録再ヘッドには磁気がたまりにくいのだな。)テープの内容を消去する機械も「消磁器」とか「イレーサ」とかいうけど、紛らわしいので、通常これは「バルクイレーサ」と呼んで区別している。
消磁の方法はまずテープレコーダの電源を切り、消磁器をヘッドに近づけて(金属片をヘッドに直接付けてしまっては駄目。まあ普通消磁器には先端にビニールのカバーが付いているので、金属片が直接ヘッドに付いてしまうことはないけどね。)消磁器の電源をいれ、ヘッドのテープがあたる部分をゆっくり2〜3回なぞって、そしてゆっくりと消磁器をヘッドから離して十分に離してから消磁器の電源を切る。これだけだ。
3-3-6 調整の手順
真剣にテープレコーダの調整をやろうとすると下記のような手順になる。
- ライン入出力レベルの調整
- ピークインディケーターのトリガーレベル調整
- 内蔵発振器のレベル調整
- ヘッド調整
- アジマス調整
- ジニース調整
- 高さ調整
- 仰角調整
- 再生ゲイン調整
- 再生イコライザ調整
- イレース電流調整
- バイアス電流調整
- オーバーバイアス調整
- 録音レベル調整
- 録音イコライザ調整
- 位相補正
- 低域補正
また下記のような機材が必要になる。
- テストテープ
- 交流電圧計 (バルボル)
- 2現象オシロスコープ(シンクロスコープ)
- CR発振器
- バージン(未使用)テープ
- 調整用ドライバーと調整用六角レンチ
- 延長基板やケーブル類
どうだ、いやになってきただろう?
わしも書いとっていやんなってきた。(笑)まあここまでのフル調整は、営業用のスタジオでもそうそう毎回しない。簡単にするためにオシロスコープ以外の測定器は使用しないようにして、(残念ながら、オシロスコープがないと調整はほぼ不可能だ)録音前に30分程度で出来る調整だけ紹介しておこう。機種によってメーカーによって調整方法が少しずつ異なったり名称が異なったりするので、詳しくはその機種の取説なんかを参照してくれ。
手順は次の通りだ。
- ヘッドアジマス調整
- 再生ゲイン調整
- 再生イコライザ調整
- オーバーバイアス調整
- 録音レベル調整
- 録音イコライザ調整
要はテストテープを絶対的に正しいものとして、まずテストテープが正常に再生されるように、再生系の調整をするわけだ。再生系の調整が終わったら、再生系は正常と言うことなので、今度は録音系を再生系を基準にして調整すると言うわけだな。これ以降はトリマ(調整用の半固定式のボリューム)といったら、調整用のもので、ボリュームといったら通常使うレベル調整用のつまみのことにする。またここでいうテープレコーダのINPUTモードとは、出力やVUメータに入力信号が現れる状態で、REPROモードとは出力やVUメータにテープの信号が現れる状態の事をいうことにする。
3-3-7 再生系の調整
 |
| 写真3-3-2 VUメータ調整用ネジ穴 |
掃除と消磁を済ませた後、テストテープが調整しようとしている規格に適応しているかを確認して、さらにテープレコーダのスイッチのイコライザ規格(パネル上、もしくは基盤上に切替スイッチがあることが多い)、テープスピードなどを確認する。同じNABでもNAB-Jとは違うものなので注意しよう。またテープレコーダのVUメータが無信号時に正しく0%の所を指しているかもチェックしておこうね。もしずれていたら、小さいマイナスドライバーで、VUメータの下にある調整ネジであわせておこう。(写真3-3-2)
- 巻き取り時の変形を避けるため、あらかじめテストテープの最初と最後に、リーダーテープを充分に追加しておく。またテストテープは大変高価で痛みやすいので、極力早送りや巻き戻しはしないようにする。
テストテープをかけて再生し、8kHz0VU(MRLの7.5ipsテストテープの場合は8kHzの-10VU)の部分を再生する。この信号でオシロスコープの波形を見ながら、波形がなるべく大きく右上がりに一直線になるように再生ヘッドのアジマスを調整する。さらにテストテープの16kHz0VUの部分で微調整をする。ただしよっぽど運が良くないと16kHz0VUでリサージュ波形が直線になってくれることはないので、なるべく直線に近くなるようなところで妥協するのがコツだ。(7.5ips以下のスピードの場合はストレスがたまるので、やらない方がいいかもしれない。)
これで再生ヘッドが正常な位置に調整されたことになる。もしテープレコーダにSEL
REPRO(SYNC)機能(録音ヘッドを再生ヘッドとして使える機能)があるんだったら、同じ方法で録音ヘッドのアジマスも合わせてしまおう。
 |
これが理想の波形。右上がりにきれいに一直線になっている状態。通常はこの状態を中心にぶれる程度でよしとする。 |
 |
ヘッドアジマスがイマイチ合っていない状態。15ips以上のスピードの時はこれでは問題だが、7.5ips以下のテープスピードでは上の状態とこの状態が交互に現れるぐらいが、調整の実質的限界。 |
 |
ずれている状態。(右と左のトラックで90度位相がずれている) |
 |
上よりも更にずれている状態。(右と左のトラックで180度位相がずれている) |
 |
普通では考えられないが、調整を何年もしていなかったテープレコーダや、誤って調整したものなどは、このように一見合っているような波形になることがある。これは360度位相がずれている状態だ。線が短くなるので、ちょっとずらせばすぐ判別がつく。 |
| 表3-3-3 オシロスコープの変化 |
- ミキサをテープのプレイバックモードにして、テストテープの1kHz0VUの部分を再生する。これでテープレコーダのVUメータをOUTPUTボリュームで0VUに合わせ、その状態でミキサのVUメータが0VUを指すようにテープレコーダのOUTPUT
GAINトリマを調整する。(正式にはテープレコーダで0VUを取った後、テープレコーダの出力に600オームの負荷をかけた状態でバルボルをつなぎ、バルボルが+4dBを指すようにトリマを調整するんだけど、ここではミキサのテープ入力が正確に600オームの+4dBと仮定して手順を省略している。)
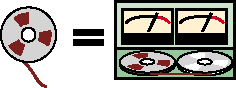 |
| テストテープ(基準)に0VUのレベルで録音されている信号を、再生するときにテープレコーダのVUメータが0VUを指すように調整する。 |
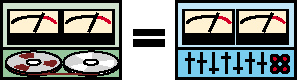 |
| テープレコーダのVUメータが0VUを指しているときに、ミキサのVUメータも0VUを指すように調整する。こうするとテープレコーダとミキサのメータは同じ値を指す。 |
| 図3-3-3 基準レベルの調整 |
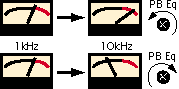 |
| 図3-3-4 再生イコライザの調整 |
上記の状態(テストテープの1kHz0VUでテープレコーダが0VUを指す状態)のまま、テストテープの10kHz0VUの部分を再生して、同じようにテープレコーダが0VUを指すように再生イコライザのトリマを調整する。これで再生の周波数特性が正常に調整された事にするわけだな。
- 調整する部分の狂いがひどかったときには2に戻って再び調整する。
- 低域の調整があるものは、50Hz以下の部分を出して、いちばん周波数特性が平坦になるようにする。単純にスイッチ式のものは低域の周波数特性に乱れが少ない方にすればよい。
- 最後にテストテープの1kHz0VUの部分をもう一度再生してOUTPUTのボリュームをテープレコーダのVUメータが0VUを指すように調整する。もしかなりのずれがあった場合は、に戻って再び調整する。これで再生系の調整は終わりだけど、終了したらOUTPUTのボリュームは録音系の調整が終わるまではそのままにして絶対に動かさないこと。
- テストテープをマスター巻きで(再生状態で)巻き取り、大切に保管する。
3-3-8 録音系の調整
- 録音に使う同じ種類のバージン(未使用)テープを、テープレコーダにかけて少し送っておく。(巻はじめはテープ走行が不安定になり易いため)
-
ミキサのオシレーターか、テープレコーダのオシレーターで10kHzの正弦波を出し、テープレコーダをINPUTモードにして、INPUTボリュームで大体-2VU位の入力レベルにしてから、録音しはじめる。録音状態のままテープレコーダをREPROモードにして、VUメータの振れが最大になるようにBIASを調整する。この時点ではメータの振れを最大にするのが目的なので、VUメータが振り切ったり振れが小さすぎたときは、再生のOUTPUTボリュームを見やすいように適当に動かしていい。
メータの振れが最大の所がトップバイアスの状態なので、ここからバイアス調整のトリマを右に回してオーバーバイアスをかけるんだけど、正式にやると出力用の負荷とバルボルが必要になるので、ここでは怠慢こいてテープレコーダのVUメータで代用してしまおう。トップバイアスの状態で、再生のOUTPUTボリュームを0VUになるように合わせて、そこからオーバーバイアスをかけて(トリマを右に回して)7.5ipsの場合は-3VU、15ipsの場合は-2VUを指すようにする。(AMPEX
#456の場合)調整がすんだら録音を停止する。これはあくまで怠慢こいたやり方なので、「こんな方法が書いてあった」などと他のスタジオでいわないよーに。(^_^;
- ついでにこの状態で録音ヘッドのアジマスを合わせてしまおう。再生ヘッドのアジマスはもう合わせたんだから、録音して再生した音のリサージュ波形(オシロスコープの波形の形)が右上がりの直線になっていないのならば、録音ヘッドが悪いという考え方だな。(もし前述のようにSEL
REPRO機能があるテープレコーダならば、再生ヘッドのアジマス調整をするときに一緒にテストテープで合わせた方が正確だ)
- 一旦テープを止め、ミキサかテープレコーダ内蔵のオシレーターから1kHz0VUの信号を出して、テープレコーダをINPUTモードにして、テープレコーダのVUメータが0VUを指すようにINPUTボリュームを調整する。その状態で再び録音を開始し、テープレコーダをREPROモードにして、(OUTPUTのボリュームを動かしていないことを確認して)テープレコーダのVUメータが0VUになるように録音レベルのトリマを調整する。ここで他のつまみを回すと最初からやり直しなので、注意しよう。これで0VUの信号が入力されたときに、テープレコーダのメータが0VUを指して、今録音している種類のテープでそれを録音し再生すると、再生時に0VUの信号が出力されるということになる。つまり、テープレコーダが正しい状態で動き、かつミキサともレベルが合っている状態になったわけだな。(ちなみにちゃんとバランス方式で600Ωのインピーダンスになっている場合、0VUの信号は+4dBmとなる。)
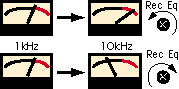 |
| 図3-3-5 録音イコライザの調整 |
ミキサかテープレコーダ内蔵のオシレーターから10kHz0VUの信号を出して、テープレコーダをINPUTモードにして、テープレコーダのVUメータが0VUを指すようにINPUTボリュームを調整する。(多分4の時点で合わせているのでそのままでいいと思うけど)その状態で録音してテープレコーダをREPROモードにして、VUメータが0VUを指すように録音イコライザのトリマを調整する。
- もう一度ミキサかテープレコーダ内蔵のオシレーターから1kHz0VUの信号を出して、テープレコーダをINPUTモードにして、テープレコーダのVUメータが0VUを指すようにINPUTボリュームを調整する。その状態で録音を開始し、テープレコーダをREPROモードにして、(OUTPUTのボリュームを動かしていないことを確認して)テープレコーダのVUメータが0VUになるかどうかを確認する。もしずれのひどい場合は2に戻って再び調整する。狂いのない場合は調整終了となるけど、その他に調整が必要な機種についてはその部分の調整を行う。
とまあこんなところが調整の手順だ。『こんなもん30分で終わる訳無いやんけぇ』と思った人、あなたは正しい。確かに慣れないうちは1時間以上かかると思う。でもこれは定期的に調整を行っているテープレコーダを、調整になれた人がやると15分程度で終わってしまう作業なんだよ。