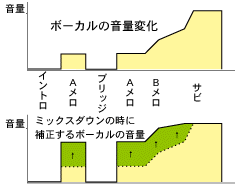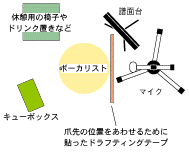2-9 ボーカル
2-9-1 ボーカルの収音について
ボーカルの収音はピアノの収音と同じくレコーディング技術の中でもっとも高度な部分だといっていいと思う。高度だといっても、録音の過程が複雑なわけではなくて、ある程度の所までは誰でも収音出来るけど、それ以上の録音をしようと思うと、音の差が非常に微妙で判りづらい部分であるという意味だ。しかしながらこの微妙な差というのが、最もエンジニアやディレクターやミュージシャンが気を使う部分でもあるわけで、これは現在の作られている音楽の大半がボーカルが入った音楽で、ボーカルはその主役である事を考えれば当然の事であるわけだ。
☆厄介な点とその解決策
- 一人一人声質が全然違う。
ある人の声には最高のマイキングも、他の人にとっては最低のマイキングになる可能性があるという事だ。まあそこまで極端でないにしろ、マイクの選択からマイキングまで、誰にとっても最高の方法はないという事だ。
まあこの辺は経験がものをいう部分なので、一般的な本では「録音を数多くこなして自分なりの方法を築く」と書いてあるんだろうけど、これではみんなの何の参考にもならない。で、ここは割り切ってボーカルにはU-87という様にマイクを決めてしまおう。レコーディングの世界の標準マイクともいえるこのマイクを使っておけば次第点のボーカルは録音できる。マイクを決めてしまえばあとはマイキングの工夫だけなので、後述のマイキング例を基本にして各自のやり方を決めよう。
- 極端にダイナミックレンジが広い
どんなボーカリストでも常に一定の音量で唄うなんて事は、物理的にも音楽的表現上の問題からも無理だ。しかしながら録音機器のダイナミックレンジには自ずと限界があるわけで、いかに上手くボーカルをMTRに録音するかはエンジニアの腕にかかっている。
基本的にこれは、MTRに録音する際にレベル調整をする事によって回避できる。他の音源なんかではそのままの形でMTRに録音するのが基本だったんだけど、ボーカルに関しては録音レベルを曲の途中で制御する必要がある。ここで判りやすい様にありがちなバラードの曲を例にとって説明しよう。
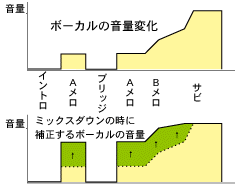 |
| 図2-9-1 ボーカルの音量変化 |
このような曲では普通図の様にAメロの部分では、唄の音程も低く感情表現も落ちついて静かな部分なので、声量(ボーカルの音量)はあまり出ないのが普通だ。それがBメロを経てサビにいくに従って、唄の音程も上がり声量がだんだん大きくなる。(実際の曲ではこのあとに「泣き」のギターソロをはさんでサビを2回以上繰り返して静かな部分で終わる。というのが王道なんだけどここでは省略する。)
で、これをこのまま録音するとAメロが小さすぎてサビが大きすぎる聞きづらい録音になってしまう。それで通常はミックスダウンの時にAメロのボーカルをフェーダー操作で持ち上げて、音量の差を小さくし聞きやすくする。だったらその分ボーカルをMTRに録音する時に音量操作をしてやれば、ミックスダウンの時に最小限の音量操作で済むし、MTRのダイナミックレンジを上手く利用できるというわけだ。ただし操作しすぎると後で取り返しの付かない事になってしまう恐れがあるので、少し控えめにする。(実際発売されたCDなんか聞いててもここをミスったとしか思えないものがある)この音量操作は手でも出来るけど、コンプレッサに任せてしまう方法が一般的。ただしあくまでさりげなく存在感の無い様にかけるのがコツ。コンプレッサも音質変化の少ないものを選び、RATIOは2:1から4:1位がいいだろう。
- ナマモノである
何度でも同じ音を出せる機械と違って、ボーカリストが最も良いコンディションで連続して唄えるのは、個人差はあるもの、数時間がいいところ。トレーニングをしていないボーカリストではもっと短くなる。だからもたもたしてるとエンジニア側の調整をしてるうちに、ボーカリストの声の方が限界に来てしまうという事にもなりかねないわけだ。(30分で声質の変わる情けない自称ボーカリストも多い。とほほ)またボーカルパートのミックスダウンは、その是非は別として切り張り(複数のトラックにボーカルの同じ部分を録音しておき、ミックスダウンの時に最も出来のいい部分だけを抜き出して1つのボーカルの様に聞かせる技法)が当たり前になりつつあるけど、その場合もボーカリストの疲れによって声質が変わってしまっては、切り張りもできない。
これを回避するためにはエンジニア側がてきぱきと準備をして、ミスの無い様に録音をするしかない。その他にはボーカリストが唄いやすい環境を作ってやる事も大切だ。一般的にスタジオ内は暗めにした方がボーカリストが録音に集中できる。また休憩時間やエアコンなどにも気を配るのを忘れない様に。(普通はディレクタの役目なんだが・・・)
2-9-2 ボーカル収音のセッティング
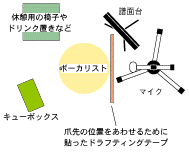 |
図2-9-2
ボーカル録音時のセッティング |
一般的には左の図2-9-2の様にスタジオをセッティングする。ボーカリストがコントロールルームの正面を向く様にセッティングすると、ボーカリストとオペレーターがにらめっこ状態になって唄いにくいので、普通はオペレーターからみてボーカリストが真横を向くような状態にセッティングする。それでまあマイクがあるのは当然として、レコーディング独特の作業としては、足元に一直線にドラフティングテープなどを貼っておき、これにマイクセッティングの時にこのラインに爪先をあわせて立ってもらってマイクセットをする。これは楽器などと違って相手が人間なので、すぐ動いてしまうからだ。それでドラフティングテープを貼っておけばボーカリストが移動してしまっても、すぐ自分で元の位置に戻れるというわけだ。
譜面台は人によっている人とそうでない人がいると思うけど、本格的な録音では発声や音程のチェックを歌詞カードに書き込んでいくボーカリストが多いので、はったりの意味も含めて置いておく様にしよう。キューボックスは、ボーカリストの背中側におく。ヘッドフォンを背中から回してかけるとヘッドフォンのケーブルが前に垂れ下がって邪魔になる事がないからだ。
その他に休憩用の椅子や、のどを潤すためのドリンクなどを置くテーブルなどをおいておく。さらにヒールの靴を履いている場合などはカーペットなどを下にひいて足音が出ない様にしたり、アクセサリーなどをはずしてもらったりといった注意も必要だ。
2-9-3 ボーカルのマイキング
 |
図2-9-3
ボーカル録音時のセッティング |
人間の声ってのは、とりあえず口からまっすぐ出ている。だからマイクも口に向かって立ててやればいいんだけど、もろに口に向かってマイクをオンで狙うと問題がある。
一度自分の口の前に手を持っていって、大きな声で「ぱぴぷぺぽ」と発声してみよう。結構手に息がかかるのが判るはずだ。(本当にやった貴方はいい人)という事はここにマイクを持ってくると、マイクが吹かれてしまうという事だな。これを避ける方法は3つ。
図2-9-3の1のように、マイクを口の正面から少し離して口元を狙う方法だ。ためしに手を鼻の所や顎の所に持っていくと、「ぱぴぷぺぽ」といっても息は手にかからないでしょ?(本当にやった貴方はいい人)ただしこのマイキングは、気を付けないとちょっとしたねらいの違いで、驚くほど音質が変わるので、マイクの位置は十分に吟味して、その位置をキープする様にしようね。
2つめは単純に吹かれない位置までマイクを離す方法だ。口の正面から狙うので迫力と生々しさは一番出るけど、オフマイキングになってしまうために、声量のないボーカリストには不向き。
3つめは2のマイキングほどオフマイクにしないで、ウインドスクリーンを使う方法だ。口の正面から狙うので迫力があり、ウインドスクリーンを使う事によってかなりオンマイクに出来る。ただしウインドスクリーンによっては音質が劣化するので、ウインドスクリーンによって音質が変化するかどうか確認した後で使う様にしよう。マイクの頭にかぶせるタイプのウインドスクリーンは特に音質が変わりやすいので、わしゃオススメはしない。雑誌なんかでリング状のウインドスクリーンを使っているのを見た事があるかもしれないけど、これは輪の金枠さえ探してくれば比較的簡単に自作できる。ウインドスクリーン本体の網の部分は、女性(一部の男性)用のパンティーストッキングを買ってきて張ればいい。(人によっては使用済みの方がいいかもしれない)
さて人によってはハンドマイクでないと唄いづらいという人がいる。こういう人には「わがままゆーなぁ!」と一喝してもいいんだけど、アマチュアのボーカリストの中には(特に毎日のようにライブをやっている人に多い)慣れない録音では実力を発揮しきれない人もいるので、そういった時はSM-58やPL-80などのマイクでハンドマイクで録音する方がいい。音質(特に高音域での微妙なニュアンス)は多少犠牲になるけど、ボーカリストが気持ちよくできるのであればそれがベストだ。またハードコアなどの音楽ではマイクを手でおおって怒鳴るのが音楽(かどうかは別として)の一部なので、それ系の音楽を録音する時もハンドマイクで録音した方がいいだろう。
2-9-4 ボーカルの収音によく使うマイク
| U-87

|
全ての基本はこのマイクに有りだ。とにかくはじめのうちは.このマイクで色々なマイキングを試してみて自分なりの方法論を確立しよう。 |
| C-414

|
U-87に比べて明るい音のキャラクターを持ったマイクなので、どちらかというと男性ボーカル向き。女性ボーカルには音が細く感じる事がある。U-87より吹かれに弱いので注意。 |
| C-451

|
吹かれに弱いマイクなので、ボーカルにはあまり向かないけど、パッドカプセルをはさみ込んでウインドスクリーンを使えば何とかなるかな。ウイスパー(ささやき声)なんかは色っぽく収音してくれる。 |
| C-38

|
「NHKのど自慢」を見ても判る様に、立派にボーカル用としても使える。シバランスが下手に強調されないので、あまりリバーブなどのエフェクターをかけないボーカルなどに向く。またノンエフェクトでも結構「色気」のある音になるのが強みだ。ただし声量のない奴には向かない。 |
| C-48

|
変ないい方だけど「いかにもマイクで収音しました」といった感じに聞こえる。私はこのマイクはボーカルにはあまり向かないと思う。。 |
| PL-20(RE-20)

|
ダイナミックマイク独特の迫力を出したい時にいいと思う。マイキングはコンデンサーマイクよりは少しオン気味にした方がいい。結構ボーカルにも使えるマイクだけど、ハンドマイクに出来ないのと威圧感のある外観がが難点かな。 |
| MD-421

|
明るく通りのいい音なんだけど、ボーカルの場合はこの特性が嫌みになる場合があるのであまり使わない。(元々はボーカル用のマイクだったのにね)ただし、かなり派手にボーカルにフランジャやコーラスなどのエフェクトをかけようと思っている場合にはこのマイクは超おすすめ。エフェクターの効きが良く芯も失われない。 |
| MD-441

|
発声がしっかり出来ていない女性ボーカルなんかにはいいけど、レコーディングであえてこのマイクを使う理由はないかなという気もする。 |
| SM-58

|
ハンドマイクで録音したい時にはとりあえずこれ。またコンデンサーマイクについて十分知らない時に失敗の出来ない録音をしなければいけなくなった時なんかにもいい。他のマイクは100点満点の音が収音出来る場合も0点の音になる場合もあるけど、このマイクは確実に60点の音を収音してくれる。そのかわり90点以上の音を収音するのはすごく難しいけどね。 |