ピアノの音を収音する場合考えなくてはいけないのは、まず音楽アレンジ上で、ピアノがどういう扱いなのかだ。クラシック系のピアノソロから、バンドの中の一部分としてまで、色々な使い方の出来るピアノだからこそ、ピアノのどの音が欲しいのかを常に考えてマイキング(音作りを含めて)しなければいけないわけだ。逆に言うと、どんなときにでも使えるマイキングというのは、残念ながらピアノには存在しないと考えた方がいい。
☆曲中で色々な楽器が鳴っている場合(ロック系)
 |
 |
| 写真2-5-1 アコースティックピアノのマイキング1 | |
この場合のマイキングは比較的簡単だ。なんでかというと、録音するのが難しいピアノの微妙な音の部分が、他の楽器の音に消されてしまうので、ピアノの音の成分全部を忠実に収音する必要はなくて、必要な部分だけを収音出来ればいいからだ。はっきりいってこの場合必要なのは、中高域の音。ためしにピアノが他の楽器と一緒に鳴っている曲を聴いてみるといい。左手で弾くような低域のピアノの音や、ピアノらしい複雑な響きなどは、ほとんど聴き取れないでしょ?
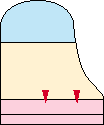 |
|
| 図2-5-1 マイキング1-1 | |
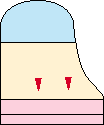 |
|
| 図2-5-2 マイキング1-2 | |
 |
 |
| 写真2-5-2 アコースティックピアノのマイキング2 | |
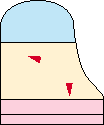 |
|
| 図2-5-3 マイキング1-3 | |
最終的に使う使わないは別として、録音の時はトラック数に余裕のある限り、マイクは立てて置いた方がいい。例えばピアノ1台にマイクを10本立てても構わない。(通常はそんなにトラック数に余裕がないので、せいぜい5本程度)で、ミックスの時にいいものを使えばいいのだ。
☆ピアノ単体の音を収音する時
さて難しいのは、ピアノ単体の自然な感じを収音したい時。これには定番のマイキングはないといってもいいほどオペレーターによっていろいろな手法があるんだけど、基本はピアノの周りを散歩する事だ。プレーヤにピアノを弾いてもらい、自分の両耳を2本のマイクと考えていろんな所に頭を持っていって、(高いところは椅子に乗って)気に入ったポイントを探すのだ。どうしても判らない時は自分なりにポイントを決めて一度録音してみて、その音をプレーヤに聞いてもらう手もある。まあでもよっぽど変な音じゃない限り、「よくわかんな〜い、みたいな。」(バカ女風)という返事が返ってくるような気がせんでもないが・・・(^_^;
小さい頃からピアノに慣れ親しんだ方々が、音響屋を目指すということは考えにくいので、通常、音響屋を目指す人のほとんどが、ピアノの音を知らないところから始まる訳だな。よって最初のうちは、ピアノの自然な音といっても判らないと思うけど、判っているふりをしてマイキングをしよう。(笑)
たぶん、「生のピアノというものは、意外と大した音はしないものだな。」という感じを受けると思う。これはよくCDなどに入っている「ピアノの音」は、加工された音だからだ。その音を基準に考えると、生のピアノはどことなく野暮ったい音がする。まあでもこれは、「美味しんぼ」風にいうと、化学調味料で舌が麻痺した状態。化学調味料の入っていない味になれてくれば、そこにある良さが判ってくると思う。ただ私は「美味しんぼ」のように「化学調味料の味に慣れた奴はダメだ!」というつもりは全くない。音作りの可能性を思いこみでなくさないことだ。(ん゛〜・・自己反省)
ま、でも最初のうちの逃げ方は、プレーヤの後ろにまわって、プレーヤが聞いている音を基準にするのが良い。ピアノの音にこだわる人は、ピアノプレーヤである確率が高いからだ。うはは。
さて、では参考のために比較的よく使われるマイキングを紹介しときましょ。きょうびピアノ単体の音を収音するのに、ステレオ録音は当たり前なので、マイクを2本使う事を前提として、考えてみよう。
 |
| 写真2-5-3 アコースティックピアノのマイキング3 |
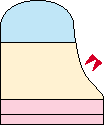 |
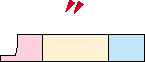 |
| 図2-5-4 マイキング2-1 | |
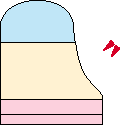 |
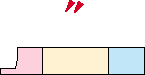 |
| 図2-5-5 マイキング2-2 | |
 |
| 写真2-5-4 アコースティックピアノのマイキング4 |
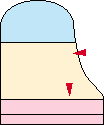 |
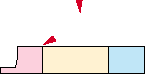 |
| 図2-5-6 マイキング2-3 | |
まあこれから発展してオンマイクとオフマイクを組み合わせてもいいし、マイクを3本使って右中左というような割り振りにしてもいい。要は必要な音が収音出来ればいいんだけど、なるべく違ったポイントから狙ったマイクの音を録音しておいた方が、ミックスダウンの時に音作りの幅が広がって面白いぞ。
☆PAの場合
PAもマイキングの考え方は一緒なんだけど、PAスピーカの音や他の音が鳴っている音場での収音なので、常に「ハウリング」と「カブリ」を意識したマイキングになる。では具体的にどうすればハウリングしにくく、カブリの少ないマイキングが出来るだろうか?答は簡単オンマイクにするこれしか方法はない。さらにピアノも反響板(蓋)をハーフ(半分開けのことなんだが、正式には何というのだろう?)にしたり、閉めたりして、なるべく他の音の混入を防ぐようにすることも多い。反響板って事は、自分の音を外に放出するわけだから、同じ分だけピアノにも他の音が混入してくるわけだな。
マイキングの基本は、写真2-5-1や2-5-2のようなハンマーや弦狙いとなる。レコーディングより更にオンマイクにすることが多いので、マイクの指向性の関係で、収音できる音にばらつきがでることがあるが、この場合はマイクの本数を増やして対応する。とにかく、品の良いマイキングは出来ない事がほとんど。
 |
 |
| 写真2-5-5 アコースティックピアノのマイキング5 | |
さらにレコーディングの世界ではあまり使われないけど、PAの世界ではよく使われるマイキングを紹介しておこう。まず通称「ホール狙い」と呼ばれる方法で、胴の中の金属板にあいている穴を狙う方法だ。耳を近づけて聴いてみると判るけど、この穴から結構いいバランスの音が出ているのだ。ただし「胴鳴り」の音なので、明瞭感はいまいちで、低音が増強された音になってしまうのは仕方がない。使用に当たってはイコライジング(低音のカットと高音の補正)が必要だ。どの穴を狙うかは、音を聞いて決めればいいんだけど、大体一番大きい穴から2番目か3番目の穴が、比較的バランスの良い音がしていることが多い。マイクの先端がフレームの面と同じ高さぐらいにするマイキングがよいだろう。
 |
| 写真2-5-6 マイキング6 |
 |
| 写真2-5-7 マイキング7 |
最近、プレーヤでピアノの蓋はフルオープンにこだわるくせに、モニタスピーカからは、鬼のように自分の音を要求する奴が多いのには困ったもんだけど、そういう人対策なんかにもこのマイキングは有効。まあ、そこまでいかなくても、PAの場合は、ピアノにモニタ専用のマイクを立てることは珍しくない。
その他ピアノのシャーシ部分に棒を渡してその棒の上に小型のコンデンサーマイクを置くマイキングや、PZMマイクを反響板やシャーシに貼り付けるマイキングなどがあるな。
