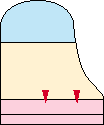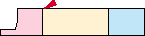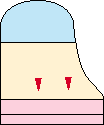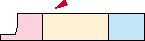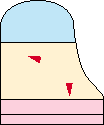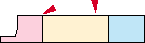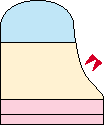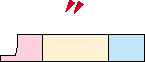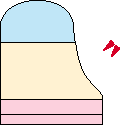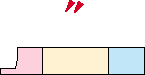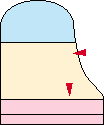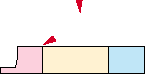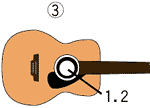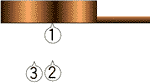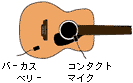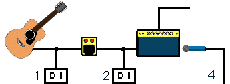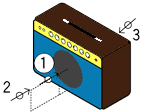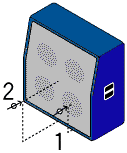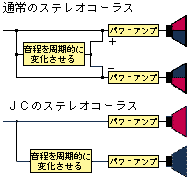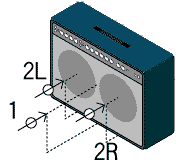2-4 ギター
2-4-1 アコースティックギターのマイキング
ここでいうアコースティックギターとは、エレアコと呼ばれるものではなくて、ラインアウトの付いていない、いわゆるアコースティックギターの事だ。アコースティックギターは、大きく分けてガット弦を張ったガットギター(クラシックギター)と、スティール弦を張ったフォークギター(ウェスタンギター)と呼ばれるものがあって、それぞれ音色が大きく違うので、使用するマイクは好みによって色々使い分けられることが多いんだけど、マイキング自体はさほど大きく変わらないのでここでは一緒にして説明しよう。
アコースティックギターをうまい具合に収音するための基本は、弦そのものの音と、胴で共鳴した音を上手くバランスを取ってやることだ。で、アコースティックギターには、サウンドホールと呼ばれる穴があいているんだけど、基本的にはここをマイクで狙ってやればいい。何故かというと、サウンドホールの上には弦があり、サウンドホールを狙うことによって、弦とサウンドホールから出る共鳴音両方を録る事が出来るんだな。
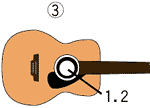 |
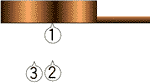 |
図2-4-1
アコースティックギターのマイキング |
PAなんかではなるべくハウリングマージンを稼ぐために、1のようなオンマイクでマイキングするんだけど、他の音源がカブってくる心配のない時は、2の様にややオフめ(30〜50cm位)でマイキングした方がいい。1のマイキングにする時はやや下側からサウンドホールを斜めに狙う様にすると、サウンドホールの音が強調されすぎず、比較的鳴りの弱い高音弦の音を強調してくれるのでごっつ都合がええ。(なぜか大阪弁)また硬い音が好みの時はブリッジ側(図でいう左側だ)にマイクを移動させる。ただしあまり寄せすぎてマイクの指向が、サウンドホールをはずれてしまわない様に注意するよーに。マイクスタンドはギタリストが右利きの場合、通常ネック側(図でいう右側だ)に立てる。これは動きの大きい右手の邪魔にならない様にするためだ。
3のマイキングはギターから斜め上80cm位にマイクを置き、サウンドホールを狙ったセッティング。オフマイクになるので、多少音がぼけてしまうものの、自然な響きがとれるのでギターのソロ演奏を録音する時なんかはいい。ガットギターなんかは弦自体の音量が比較的小さいので、サウンドホールを意識的に狙いからはずした方がバランスよく収音できることもある。あとたまにネック側からもマイクを立てて、他の位置からのマイクと混ぜることをする場合があるけど、これはプレーヤのタッチなど微妙なニュアンスを表現しようというためのもので、プレーヤがよっぽど巧い奴じゃない場合はウラにはまることが多い。
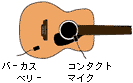 |
図2-4-2 コンタクトマイクや
コンタクトピックアップの使用例 |
その他にコンタクトマイクや、コンタクトピックアップを使って収音する方法があるけど、ライブレコーディングなどで、どうしても他の音とのカブリが気になる場合以外無理して使う事はない。どうしてもマイクでしっかり取った音と比べると、いまいちな音質になってしまう事が多いからだ。
で、どうしても使わざるを得ないときなんだけど、コンタクトマイクはサウンドホールに引っかけて使う事が多い。コンタクトピックアップは後述のエレアコ(エレクトリックアコースティックギター)の台頭で最近はあんまり使われんくなってきたけど、ギターのボディーに貼り付けて使うものが一般的だ。このタイプの代表は「バーカスベリー」といわれる、バーカスベリー社のピックアップ。(まんまやな)使用にあたっては必ず専用のプリアンプを通す事。そのままD.Iに入れてもすかすかの音になってしまう。張り付ける位置は図2-4-2の辺りが一般的だけど、ブリッジに付けることもある。
あと、エレクトリックアコースティックギター、通称「エレアコ」と呼ばれるものがあって、最近アコースティックギターというと、このエレアコのことを指すぐらいに普及している。これはアコースティックギターのボディーのブリッジ部分に、ピエゾマイク(ピックアップの一種)というものを埋め込んで、そのピックアップからの音を内蔵のプリアンプで(そのためほとんどのものが電池を内蔵している)加工してから、アコースティックギター独特の音をライン出力出来る(つまりアンプにつないだり、PAに直接送ったり出来る)ようにしたものだ。
元々はロックバンドなど、他の楽器の音量が大きい中で、なんとかアコースティックギターを使えないかという要求から生まれたものなので、レコーディングでは(他の楽器と別に録ればいいので)あまり使われない。アコースティックギターの音が録音したければ、アコースティックギターを別録音すればいいわけだし、例え貧乏で、エレアコしか持ってなくても、エレアコにマイクを立てて録音すればいいわけだな。
とはいうものの、アコースティックギターとエレクトリックギターとの中間的な音を、あえて活かしたい場合など、ラインの音を使事もある。逆にPAではこのエレアコを使う時は、ラインアウトをD.I.でもらうのが基本。
| 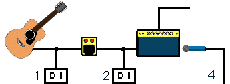
|
| 図2-4-3 エレアコの収音方法 |
エレアコの録音の方法は、図のように4ヶ所からの収音が考えられるわけなんだが、一番一般的なのが、1からD.Iを使って収音する方法だ。この場合エフェクタからアンプまでの部分は音源として使用しない。(エフェクターはオペレータ側でかければいい)つまりエフェクタ以降は、限りなく「ギタリストが自己満足のために作る自分だけが聞く音」に近くなる。この方法でもらうときは、ギター本体のボリュームはフルに、イコライザはコントロールが一つの場合は全開に、2ポイント以上あるイコライザなら、全部真ん中にしといてもらった方が、こちらで加工しやすいぞ。
2はエフェクターと込みで、一つの音として考えた方がいい時。だけどエフェクターにコンパクトタイプのエフェクターを使っている場合は、レコーディングの場合、歪みやノイズなどの問題から、ミックスダウン時にエフェクターをかけた方がいいので、ギタリスト側が音響ヲタクで、レコーディングに耐えうるエフェクター処理をしている場合以外は、奨められない。但しPAの場合は一番よく使う方法だ。(ライブではエフェクタのオンオフなどは、プレーヤ側がやってもらわないと、とても手が足りない。)
3はギターアンプのコントロールで、エレアコの音作りをしている場合にいい。この場合は、ギターアンプにラインアウト(もしくはレックアウト)がある時には素直にそこから収音すればいい。出力インピーダンスは結構低いので、D.Iは使っても使わなくてもいい。スピーカアウトしかない場合は、変換ケーブルなどでダイレクトにつなぐと、アンプや音響機器を傷める危険性があるので、必ずカントリーマンの#85を使って、入力切り替えスイッチをスピーカ側にしておく。(一般的なD.Iの中でスピーカ出力に対応しているのはカントリーマンしかないからぢゃ。)
4はエレクトリックギターと同じ録音の仕方で、ギタリストが「どーしてもこのアンプから出した音じゃないとやだ〜」と、だだこねた場合など。まあギタリストがこだわりを持っているのであればこれも「あり」だ。最近はトレイスエリオットなんかからエレアコ専用のアンプも出ていることだしね。(結構いい音がするんだこれが・・)
2-4-2 アコースティックギターの収音によく使われるマイク
音量がそれほど大きい楽器ではなく、高域の音が決め手となる音なので、やはり高域特性の優れたコンデンサーマイクを使う事が多い。マイクが大きいとマイキングしにくいので、小型のコンデンサーマイクが良く使用される。
| C-451

|
明るい音のキャラクターを活かし、ストローク奏法中心の演奏の時にいい。 |
| C-414

|
奏法を問わずオールラウンドに使える。あまりオフにしない方がこのマイクのキャラクターが出る。乾いた冷たい感じの音。 |
| U-87

|
オンマイクにもオフマイクにも良い。自然な感じの音を収音したい時に向く。 |
| U-67

|
クラシックギターの収音のメインマイクにおすすめ。 |
2-4-3 ギターアンプのマイキング
エレクトリックギターとギターアンプは切っても切れない関係にある。何故かというと、ギターアンプは、一般的な音響機器からすると信じられないような音響特性によって、エレクトリックギターの音を「らしい」音にするからだ。(そーいやぁ以前レコーディングで、「それらしい音にしてください。」といったら、「ソレラシ」と音程を弾いた大馬鹿者のギタリストがいたな。)まあとりあえずエレクトリックギターは、ギターアンプから音を出して、初めてエレクトリックギターの音になる事を知っておこう。
 |
 |
図2-4-4 「冷凍庫」12U(上)と
「冷蔵庫」3U(下)の例。 |
一時期レコーディングで、エフェクターを山の様に使って、エレクトリックギターの音をラインで出すのが少し流行した。その当時ギタリスト(特にフュージョン系)は何かにとりつかれたようにエフェクタを買いあさり、ラックに入れてスタジオに持ってきた。15Uまでは当たり前、(プロ用の音響機器はラックサイズという規格統一がされていて、横が約19インチで、縦の基本となる大きさを「1U」といって、ラック(入れ物)の大きさは、このUの数で表す。)の世界で、私は影で「冷蔵庫」と呼んでいた。それ程違和感のあるものだったわけだな。(笑)で、彼らは大体次に来たときにはエフェクタを買い足して、4Uくらいの小さいラックを追加して持ってくることが多かったからだ。当然私はそれを「冷凍庫」と呼んで区別した。とにかく光ったもん勝ちの世界だった。そう言った意味では、ちょっと前のビジュアル系バンドのギターアンプセットも、東名を走るデコトラもノリはいっしょだ。
まあこれ程までに一部で流行った、ラックエフェクターだが、あまり見ないようになってしまった。理由は重いから。つまり、苦労の割にあまり効果が出なくて、みんな飽きてしまったわけだ。それで、現在ではまた、アンプから出した音を、マイクで収音するという基本に戻った方法をとる事が多くなってきている。よって、ギター本体やエフェクターやアンプのラインアウトから、D.Iで収音する方法はほとんどせず、ギターアンプにマイクを立てるのが王道。
一般的なギターアンプの場合
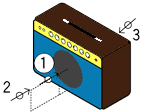 |
図2-4-5 一般的な
ギターアンプの場合のマイキング |
オンマイクで収音する場合、ギターアンプはスピーカから音が出るので、図2-4-5の1のように当然スピーカにマイクを向ける。距離は大体2〜20cmってとこだろう。(ちなみに私は、録音のオンマイクでは10cm位にする事が多い)どこを狙うかっていうと、スピーカの中心でいいんだけど、『スピーカの中心部分にはコーン紙が無く音が出ていないポイントなので、スピーカの中心ではなく、コーン紙の中心を狙うべきだ。』という人もいるんだな。けどスピーカにマイクをひっつけて収音するわけではないので、極端にずらさない限り変化はない。まあそーゆー人たちにウンチクをたれさせないために、マイキングを中心から、ほんの少しずらしておくのが、21世紀の生き方だろう。また、スピーカが複数ある場合はどれか1つを狙えばよし。(例外についてはあとでふれるね。)
オフマイクの場合は、図2-4-5の2の様にオンマイクの場所からそのままマイクを離せばいい。距離は大体40cm〜1m位かな。あまり部屋鳴りがしないスタジオでは、オフマイクは、よっぽどアンプを大音量にして、アンプを箱鳴りさせる時以外は、あんまり効果がないと思う。まあでもオンマイクとオフマイクを混ぜ合わせてみると位相のずれによって面白い音になるので、試してみるのもよろしかろ。
図2-4-5の3のマイキングは、ギターアンプは後面開放型バッフル(簡単にいうと、後ろがあいてる)の場合が多いので、うしろからマイクを狙おうという事だ。でもこれは音がこもり気味になるので、全く奨められない。メリットは他の音のカブリが少ない事と、ギターアンプの正面がすっきりする事だ。スペースの小さいライブハウスのPAなどでは有効だけどね。
大型アンプの場合
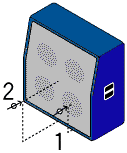 |
図2-4-6 大型アンプの
マイキング |
金髪の兄ちゃんがぼろいワゴン車から、大きいギターアンプをごろごろ転がしてきた場合の対処についてだが、問題はスピーカボックスの外形がでかいとか、音量がでかいとか、兄ちゃんが恐そうだとかじゃなく、(いや、それも問題は問題だが・・・)スピーカが、比較的小さいのが4つついている事が多い事なんだ。
PAでは、4つのスピーカのうち下側のどちらか一つをオンで狙う、図2-4-6の1のようなマイキングが多いけど、これは他の音のカブリを防ぐために、マイキングをオンにする必要があるからだ。下側を狙うのはよく分からないけど、プレーヤ側の根強い信仰、「下側のスピーカの方が背面までの距離が少し長いので、上のスピーカより低域が少し出るような気がする。」という理由によるものだ。(^_^; (実際の所はわからないが、こうすればクレームはない(笑))
上側のスピーカに、傾斜が付いていないタイプのスピーカボックス(ボトムボックスといわれる。それに対して図2-4-6のように上側のスピーカに傾斜が付いているものは、トップボックスといわれる。)では、4つのスピーカのうち、狙うのはどこでもいい。ただしメサブギー社の大型スピーカボックスは、下側が密閉型エンクロージャー(スピーカを入れる箱のこと)上側が後面開放型になっているので、音のキャラクターが上下で違うんだけど、オンマイクにするときは一般に上側の方が『メサブギーらしい音』がするので、上側のスピーカを狙ってマイキングすることが多い。(実際の所はわからないが、こうすればクレームはない(爆))
で、実はこのオンマイキングでは、大型アンプの音を上手く収音出来ないのだ。何故かというと、4つのスピーカからは、基本的に同じ音が同じ音量で出ているのだけど、これがお互いに干渉しあって、一種のコムフィルターを形成してしまうのだな。これが1kHz辺りから上に数箇所のディップ(周波数特性上の谷)を作り、これが独特の音を生んでいるのだ。だからこの雰囲気を収音するためにはマイキングをオフ目にしてやる必要があるのだな。具体的には図2-4-6の2のように、スピーカボックスの中心を狙って、40cmほど離してやるといい。あまり離しすぎると音像がぼけてしまうので注意。また、このオフマイクとオンマイクを混ぜてもいい。こうするとオフマイクはもっと離す事が出来るので、部屋鳴りを含めた音を収音する事が出来る。
JCの場合
JCというのはローランド社のギターアンプのシリーズで、もう20年も現役の脅威的なロングセラーギターアンプだ。そのうちもっとも使われるのがJC-120で、ぱっと見はなんの変哲もない2スピーカのギターアンプだ。だからマイキングは、一般的なギターアンプと同じように、どちらか1つのスピーカを狙えばいいんだけど、このアンプに付いているコーラスを使った時にはマイキングを変える必要がある。ステレオコーラス(エフェクト)を内蔵したアンプは他にもあるけど、このアンプは他のステレオコーラス内蔵のアンプに比べて少し変わっている。
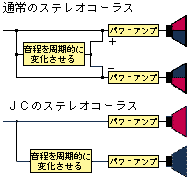 |
| 図2-4-7 ステレオコーラスの違い |
ステレオコーラスの原理について簡単に説明すると、コーラスってのは生音に(この場合エフェクトのかかっていない音という意味で使うね)その生音に周波数変調を加えて、音程を周期的に変化させたものを混ぜて作るものなんだな。で、混ぜる時に片方には正相(加算)で混ぜて、もう片方には逆相(減算)で混ぜる。こうしたものをそれぞれ左右からのスピーカから出すと、音が広がって聞こえるといった仕組みだ。
まあこれが通常のステレオコーラスなんだけど、JCの場合は生音と、音程を変化させた音を、それぞれ別のスピーカから出して、空気中で2つの音を混ぜてコーラス効果を得ようというとんでもない方式なのだよ。効果としては、通常のステレオコーラスが音が左右にゆっくり回って広がっている感じになるのに対し、JCの方はつかみ所無くふわっと音像が広がる。多分JCの人気の理由のうち大きな理由がこの感じにあるんだと思う。実際コーラスをかけてJCの前に立つと、気持ちがいい。でもギタリストが気持ちがいいのはいいけど、PAや録音する方としてはクソ迷惑なエフェクトだ。マイキング一つにしたって、片方のスピーカをオンで狙うと、左からは生音しか出ていないので、コーラス効果がほとんどなくなってしまうし、右からは音程の変化した音、つまり音程の狂った音しか出なくなるのでどっちも使えない。
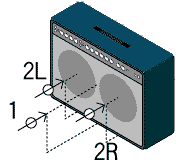 |
| 図2-4-8 JCのマイキング |
よってコーラスをかけたJCのマイキングは、図2-4-8の1のようにマイクを少しオフ目(30m位)に置き、左右二つのスピーカの間を狙うか、マイクを2本立ててそれぞれのスピーカをオンマイクで狙う。図2-4-8の1の方法では当然モノラルになるけど、図2-4-8の2の方法ではステレオで取る事が可能だ。ちなみに録音の場合は、これを馬鹿正直に右左に振ると、音像がどこにあるか判らない非常に気持ちの悪い音になるので、パンニングはあまり広げすぎないようにね。
余談だけど、JCについているコーラスのオンオフスイッチの左横の「SPEED」「DEPTH」は、ビブラートの時だけ効くコントロールで、コーラスの時には全く関係ないつまみだからね。よくコーラスの調整だと思って真剣にセッティングしているビジュアル系兄ちゃんがいるけど、恥かしいのでよゐこは決して真似をしない様にしましょう。
2-4-4 ギターアンプの収音によく使うマイク
ギターアンプから出ている音は思ったより周波数帯が狭く、ギターアンプでかなり強力な音作りをされるので、こういういい方は何なんだけど、マイクをあまり選ばない場所ではある。ダイナミック方を基本に考えて、どうしてもニュアンスの足りないときに、コンデンサーを使うのがよいのでは。
| MD-421

|
輪郭のしっかりした音になるので、歪みで少し音のぼけ気味の音を収音する時にいいだろうな。どちらかというとオンマイク向き。こう言っちゃ何だが、PAの時、素人の歪み系には一番重宝する。 |
| SM-57

|
レコーディングでも、PAでもよく使われる。迫力と繊細さの程良くバランスの取れた使いやすい音だ。どちらかというとオンマイク向き。 |
| PL-20(RE-20)

|
オンマイクでもオフマイクでもいい。あるがままの音をそのまま収音する感じかな。見た目はごついマイクだけど、思ったほど迫力のある音にはならない。 |
| U-87

|
大型アンプのオフマイクに最適。オンマイクで使ってもいいんだけど、それほど「さすが」って音は収音出来ない。 |
| C-38

|
個人的にお気に入りのマイク。とげとげしい部分を上手くまろやかにしてくれるイメージ。だからあまりもわっとした音に使うと訳が判らなくなる恐れもある。 |