太鼓にはヘッドが張ってあって、それを叩く事によってヘッドが振動し、それが音になるわけなんだけど、ここで大事なのは太鼓のヘッドは外周がとめられているという事。だから超簡単かつ大雑把にいうと、ヘッドの中心が一番大きく振動して基音を発生し、外周の部分は固定されているために自由に振動が出来ず、細かい倍音が発生するんだな。(基音・倍音については9-3-2を参照のこと)
 |
| 図2-2-1 スネアのマイキング |
「コーン」という妙な共鳴音が入ってしまう時は、あえてマイクの指向をヘッドと水平にはずしてやるとこれが取れる時もある。(まあ本当はちゃんとチューニングし直してもらうのがベストだけど)あと非常にマイクが叩かれやすい所なので、特にトーシロ相手の時はマイクをリムより中に入れない方がいいよ。
スナッピ(響き線)の音がほしい場合には、裏側にもマイクを立てるんだけど、裏側は演奏の邪魔にならないからといって、裏のヘッドの中心をもろに狙ってはいけない。なぜならこの場合は、裏のヘッドの音を収音するのが目的じゃなくて、スナッピの音を収音するのが目的だからだ。裏のヘッドの中心を狙うと裏のヘッドの音が結構強調されてしまうんだな。よって外側の部分(リムに近い部分)でスナッピを狙うようにしよう。
通常はドラムセットの正面(ドラマーと逆側)からマイキングする事になるんだけど、一度マイキングをしたらドラマー側に回ってドラム椅子に座ってみるといい。多分とんでもない方向にマイクが向いているはずだ。これはタムが角度を持ってセッティングされている上に、マイキングする側も斜め上から狙うためで、どうしても慣れないうちは角度を浅く設定しがちなのだよ。フロアタムは口径も大きいし、ほぼ水平にセットされるからマイキングも楽だけど、小口径のタムのマイキングは非常にシビアなので気をつけようね。
タムにはそのほかに、なくても大勢に影響はないけどあると楽しい、手数の多いドラマー御用達の「シングルヘッドタム」と呼ばれる、裏のヘッドが張っていない類のものがあって、(有名なのはロートタムだな。その他にもメロタムとかキャノンタムとかいろいろある。)これも基本的には同じマイキングでいいのだけれど、マイキングが難しかったり、カブリが多かったり、ドラマーの顔をよくみえる様にしたい時などは裏側からマイキングする。この場合、その他の胴を持つシングルヘッドタムの場合は、特に目的のない限り胴の中にマイクをつっこまない方がいい。音がこもったり、マイクの部分で音が歪んでしまったりするからだ。裏側からオンにする場合でも胴の終端とマイクの頭が同じくらいか、少し離してマイキングする。同じ音源でも胴の中と外ではえらい音量差があるのだ。また裏から収音しているからといって、特に逆相にする必要はないよ。
さて、普通はキックの前のヘッドには穴があいている。私は昔、破れたヘッドをもったいないから使い回ししてるんだなと思い、「やっぱりミュージシャンって貧乏なんだ。」と勝手に思いこんでた。
本当の目的は何かというと、ジャズやクラシックなどの例外をのぞいて、キックの音にはサスティン(余韻)がない方がありがたいからだ。キックを踏む度に「でよよよん〜でよよよん〜」という音がしたら困るじゃろ。で、それでも普通は余韻がまだ残るので、キックの中に毛布やら何やらを詰め込んで、ミュート(消音)するわけだな。
30年くらい前は前のヘッドを取ってしまって、ぎちぎちにミュートするのが一般的だったんだが、いくら何でも、それでは胴鳴りなどの生音の良さが損なわれてしまうので、最近では前のヘッドに比較的小さな穴をあけて、軽めにミュートするのがはやりだ。ミュートが軽ければ軽いほど、前のヘッドの穴が小さければ小さいほど、キック本来の音に近くなるが、それに伴ってチューニングも難しくなり、プレーヤの腕(足?)によっていい音にも悪い音にもなる。最悪なのは下手な奴のノーミュート。(よくいるんだ。これが)
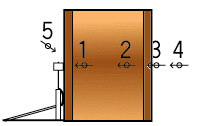 |
| 図2-2-2 キックのマイキング |
一番一般的なのは3のマイキング。比較的しっかりした音が録音でき、前のヘッドの音(生音)も収音出来る。前のヘッドの音がいまいちな時や、比較的「作った」音にしたい時は1か2のマイキングにする。2のマイキングは胴の真ん中にマイクがあるため、胴の中で共鳴した低音がよく収音出来る反面、アタック音が少しぼけ気味になるというきらいがある。1のマイキングはその逆で、アタック音が強力に収音出来る反面、低音が少し不足する。4のマイキングは前にヘッドの張ってある場合や、より自然に近い音を収音したい時にいいけど、他の音のカブリが多くなってしまう。まあ普通は2と3の間で音を聞きながらいいポイントを探すわけだ。
ところでなぜ5の様にスネアやタムと同じ様に「表側」からのマイキングをしないのかというと、収音出来る音が悪いわけでなく、マイクやマイクスタンドの置くところが無く、プレーヤの邪魔になりやすいという事と、フットペダルやスローン(椅子)のきしむ音や、スネアやハイハットの音がかなり大きくカブッてしまうからなのだよ。
シンバルは太鼓と逆で、外周が一番大きく振動する。だから外周の部分が基音を多く含み、中心に近い部分が多く倍音を発生というわけだ。それならマイキングは、外側を狙えばいいかというと、そういう訳でもないんだな。なぜならシンバルの音でほしいのは、「しゃーん」とした倍音の部分。シンバルの基音ってのは意外に低くて、ドラみたいな「ごわ〜ん」とした音なので、シンバルを収音する場合は基音はほとんど必要ないんだな。それでシンバルの収音は、程良いバランスで倍音の出ているシンバルの中心を狙うわけだ。
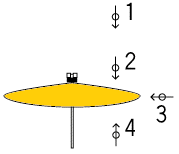 |
| 図2-2-3 シンバルのマイキング |
だからといってシンバルを叩いても、マイクの距離がほとんど変わらない3のマイキングで収音すれば良いかというと、これにも問題があって、シンバルが揺れるとシンバルの表から出ている音と裏から出ている音が周期的に入れ替わり、これも非常に気持ちの悪い音になる。(ヘッドフォンなんかで聴いてた日にゃ、げー吐きそうになる)それにシンバルがうちわのように、マイクに風を送るのも問題だ。
それでは裏から収音すればどうかというと、裏からの収音は気持ち悪い音にはならないものの、重要なシンバルの音の一部分であるピン音(スティックがシンバルに当たった時に出るアタック音)が上手く収音出来ないという欠点があるのだ。(特にライドシンバルでね)
ちなみにライドシンバルはピン音を強調するために重く大きく厚く作ってあり、スティックの先でシンバルの平面の部分を叩くので、クラッシュシンバルに比べて揺れは少ないから、比較的オンマイクで収音しても大丈夫だよ。
結局コンサートでよく見かける様にドラマーの頭の上1メートルくらいの所にマイクを置くわけだ。それでそこまでオフにすると、マイクの指向エリアも広がるし、シンバルはもともと広い範囲に音を放出するので、複数のシンバルを1〜2本のマイクで収音出来るわけだな。で、シンバルの数が多い場合でもシンバル1枚ずつにいちいちマイクを1本ずつ立てる事は余りやらない。
ハイハットはキックスネアに次いでドラムの中で重要なパートなので、比較的オンで収音する。目安としては10cm〜20cmくらい上から打点を狙うってとこかな。ただしあまり打点を狙おうと躍起になると、プレーヤの邪魔になりやすいので注意しよう。またやっきになって打点を狙わなくても、結構アタック音は収音できるから不思議。
レコーディングではよくオフマイクというのが使用されるんだけど、これはドラムの自然な鳴りを収音するためのものだ。考えてみれば、最近のドラムのレコーディングでは、迫力を出したり各音源の分離をよくするために、各音源ごとにマイクをオンマイクで立てているので、生のドラムを少し離れて聞いている時とはかなり違った音になってしまっているわけだ。さらにミックスダウンの時にノイズゲートなどでサスティンをカットする事も多いので、ドラムセットの共鳴もなくなってしまう。(ドラムセットの共鳴とは、たとえばスネアを叩いた時に、その音に反応してシンバルやタムなどが響く事で、基本的には「濁った」音なんだけど、これが音に「ドラム」単体ではなくて「ドラムセット」の雰囲気を加えているわけじゃ。)
さらに加えてもう一つオフマイクには「部屋鳴り」を収音するといった意味合いもある。プロのレコーディングでは、このためにオフマイクを立てているといっても良いかもしれない。このような用途のマイクを「アンビエンスマイク」というだけど、80年代から流行りだしたこのマイキングは、音響機器の発達によって迫力が増したり分離が良くなったりはしたものの、その分自然な響きの良さが無くなっていたドラムサウンドを大きく変えて、「ラウドな音」というような訳の分からない表現まで生むようになった。
スタジオもそれまでデッド(残響があまりない)な方が喜ばれてたんだけど、それ以降はライブ(残響がどちらかというと多め)でいい響きを持ったスタジオが喜ばれる様になったというわけだ。で、当然部屋の響きやドラムセット全体の音を収音しようってんだから、オンマイクにするわけがなく、当然のごとくオフマイクになる。だからこのアンビエンスマイクの事を一般的にオフマイクという様になったんだな。
ドラム全体のサウンドを収音したい場合は、最も簡単な方法がドラマーの頭の上辺りに下を向けてマイクをセットする方法。オーバートップとかオーバーヘッドとかいってキック以外の音が比較的バランスよく収音出来る。(シンバルのマイキングとほとんど一緒だな。通常は同じマイクを2本でステレオにして収音する。) その他にドラマーのすぐ後ろに、ドラマーの大体耳に高さに正面に指向を向けマイクを置く方法もある。これはドラマーが自分で聴いている音と同じ音を収音しようという発想。その他本格的なスタジオでは、ハイスタと呼ばれるクレーンみたいなマイクスタンドに付けて、高さ2メートルくらい、距離3メートルくらいの所に立てる方法もある。この辺のセッティングから「部屋鳴り」を意識したものになる。
もっと「部屋鳴り」を収録しようとする時は、スタジオとコントロールルームの間のガラスにPZMマイクを張り付けて使う事もある。(もちろんスタジオ側に張り付けるのだぞ)ここまで部屋鳴りを意識したオフマイクになると、部屋の大きさや残響の仕方がかなり重要となってくるので、残響も良くなく狭く天井の低いスタジオでは効果がない。