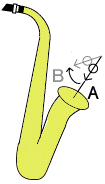☆穴のいっぱいあいているもの
穴のいっぱいあいている管楽器の演奏のしかたは、まず管の一端から息を吹き込み、リードを鳴らしたり、管を共鳴させたりする。それであいている穴を手や弁でふさぐ事によって音程を作り出す様になっている。この穴をみんなふさいでしまうと、息の逃げ場が無くなってプレーヤの血管が切れてしまうので、管のもう一端は必ずあいている。で、音は息を吹き込む部分・穴のあいている部分・管の終端の3ヶ所から出ているわけで、結構いろんな方向に音が放出されているわけだ。
このような管楽器を1本のマイクだけでオンマイクで収音したい場合は、どこか1ヶ所を狙うわけなんだけど、この3ヶ所の中で比較的音量があって、その楽器らしい音がする部分は、管の終端の部分。だからここを狙うのがとりあえず正解。(例外は下記参照)逆に考えると、オンマイクである必要がない時には、オフマイク気味のマイキングの方が、この3ヶ所からの音全てを収音する事が出来て、管楽器の自然な音を収音出来る事になるわけだ。
| サックスの場合 | ||
| サキスフォン、またはサクスフォンが正式名称。楽器自体の歴史は比較的新しいんだけど、(だから一般的なクラシックのオーケストラの中にサックスはない)今や一番ポピュラーな管楽器だ。基本的にはソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4種類があって、それぞれ音域や調性は違うものの、音色も似ていてソプラノ以外は同じようなSの字形をしている。
さて、前述のようにこのタイプの管楽器は、管の終端を狙うのが正解だ。沢山の穴からも色々なニュアンスの音が出ているが、芯の太さや音量の面でやはり「アサガオ」と呼ばれる管の終端分を狙うのが一番「らしい」音がする。ちなみに口で吹く部分は、音は殆ど出ていない。 さてここで基本的にはアサガオの部分を狙うとして、マイクをアサガオの部分から離せば離すほど、(図のAの距離)マイクの角度をアサガオから中心に向ければ向けるほど、(図のBの角度)穴から出ている音も含めて収音出来るので、より生の状態に近い収音が出来る。当然ながらその分芯の太さや音量感は薄くなっていくけどね。(ちなみに図がいい加減なのはサックスの複雑な形を描くのに挫折したため。(^_^;)ソプラノサックスの場合はアサガオが下を向いているので、マイクも下から狙う。このマイキングの考え方は、クラリネットなどのシングルリードの管楽器に応用できる。 | ||
| フルートの場合 | ||
| フルートも穴のいっぱいあいた楽器だけど、例外的に管の終端を狙うマイキングはしない。なぜかちゅーと、フルートの音は管から出ている音と同じくらい、口から出る息の音(ブレス音)がフルートらしい音を構成しているわけだ。 管自体から出ている音はサイン波に近い音色なので、シンセなどでサイン波にホワイトノイズ(息の音のシュミレーション)を加えるだけでフルートっぽい音色になる。 で、この息の音と管の音を収音するために普通オンマイクではプレーヤの口の部分を狙うマイキングになる。ただしフルートを演奏しているプレーヤの息は口から斜め下に出ているので、口の正面や下からマイキングするとマイクが吹かれてしまうので、プレーヤの目の高さぐらいから口を狙って斜め下の向かってマイキングするのが一般的。 このマイキングで、ブレス音がきつい(管自体の音が小さい)と感じる時は、マイクをプレーヤの手の方へ少し角度を付けてマイキングすると改善される。ちなみにPAの世界では見た目の問題で、この様にプレーヤの顔の真ん前にマイクを立てる事が少ないが、レコーディングではプレーヤが演奏しにくくない限り、このマイキングをお奨めする。またこのマイキングの考え方は、オカリナなどのリードを持たない管楽器に応用できる。 | ||
| オーボエの場合 | ||
| 負け犬の・・・オーボエ、ファゴットなどのダブルリード楽器は、リードの出す音色と管の音のバランスが大事。だからこういう楽器は口元と穴の開いた部分の中間をを狙う。 |
☆いっぱい穴のあいていないもの
これの発音原理は簡単。管の一端で音を共鳴させて、それをもう一端で音として放出しているだけ。極端な話、水道管みたいなものでも、この手の管楽器になりうるわけだ。実際の管楽器の管が曲がりくねっているのは、音を比較的簡単に出せるようにしたり、音程をコントロールしやすいようにするためのものなのだな。従ってこの手の管楽器のマイキングは、オンマイクであろうとオフマイクであろうと音の出口を狙うだけでいい。
| トランペットの場合 |
| 通常トランペットというと、コルネットやフリューゲルホーンなども含んでトランペットというけど、音色が違うだけで、音の出方は一緒。要はラッパだ。これはもう文句なしに音が出ているのは管の広がった出口なので、マイクもここを狙う。ここをオンマイクで狙うとマイクがすぐ吹かれそうだけど、意外に「風」は来ない。ただし、むちゃくちゃ音量の出る部分なので、マイクの選択や、ミキサの扱いを間違えるとすぐに歪んでしまうので注意。オンマイクの場合は大体15cm、オフの場合は30cm以上離す。管に対してまっすぐにマイクの指向を向けると攻撃的な鋭い音に、少し斜めから狙うと柔らかい音になる。このマイキングはトロンボーンやチューバなどの楽器に応用できる。演奏者を基準としてチューバは上に、フレンチホルンは後ろに管の終端がくるので注意しようね。またトロンボーンは管の長さを変えて音程を決めるので、プレーヤの邪魔にならないマイキングにしよう。 |