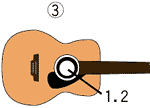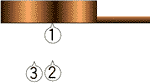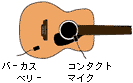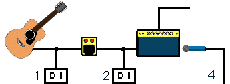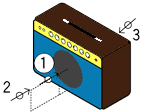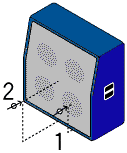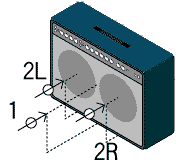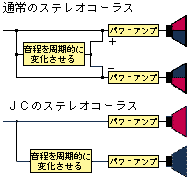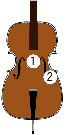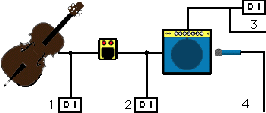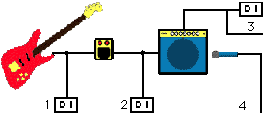2-3 ベース
2-3-1 アコースティックベースのマイキング
ジャズの世界ではウッドベース、略して「ウッベ」と呼ばれる事が多いな。クラシックでいう「ダブルベース」もモノ自体は一緒だ。
最近では、アコースティックベースにもピックアップを付けて、ラインアウトが出る様にしてあるものが多いけど、これはベーシストが後から付けるものが多く、エレアコとは違ってプリアンプを持たないものが多い。だから普通はピックアップが付いてても、エレアコベースといったりはしない。(共鳴用のボディーを持たない、本当の意味でのエレアコベースは存在するけどね。)
アコースティックベースを使う音楽の中で特にロカビリー系の音楽では、弦をつまんではじくスラップ奏法というのがあって、この場合スラップ音がバンド全体のリズムを決定するほど重要な音なので、スラップ音専用のピックアップをもう一つ取り付けてある事が多い。
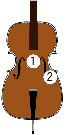 |
図2-3-1 アコースティック
ベースのマイキングポイント |
さてラインアウトを持たないアコースティックベースには、マイクを立てるほかに収音方法がないので、マイキングについて考えると、大まかに1と2のような2通りの収音方法がある。
1は弦を指で弾いている辺りを狙う方法で、大体ブリッジ(アコースティックベースの場合は木製の駒の事)よりやや上のあたりになる。ここを狙った場合はタイトな音がとれる反面ベースの響きが少し足りない感じ。
2のマイキングは、「f穴」と呼ばれる(バイオリン系の楽器には必ずあいているもので、弦の振動を胴で共鳴させた音の出口。)場所を狙う方法。何で下側を狙っているかというと、穴が大きいという理由と、ベーシストの邪魔にならないという理由からだ。で、このマイキングはボディーで増幅された響きが収音出来るので豊かな低音が得られるんだけど、反面弦自体の音は1のマイキングに比べて小さくなってしまう。「じゃあ、1と2両方から収音して、ミキサで合わせればいいじゃん。」と思った人・・・正解です。
ただ通常は、そんな手間をかけなくても、他の楽器のカブリがなければ、1のマイキングでマイクをオフ目にしてやれば、胴鳴りも収音出来るので、普通はそうする。ただし、PAの場合や、ドラムと同時にアコースティックベースを録音する時なんかは、1と2を混ぜるか、1のマイキングでオン目で収音して、ミックスダウンの時にイコライザで低域を補強してやる。何で2のマイキングじゃ駄目かというと、ドラムが入っているような音楽では、ベースの芯のある音がほしいはずで、2のマイキングでは芯がなくなってしまいやすいためだ。
| 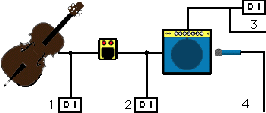
|
| 図2-3-2 アコースティックベースのライン収音ポイント |
ピックアップが付いている場合は、図2-3-2のように4通りの収音方法がある。
1がもっとも一般的なもので、ピックアップから直接収音する。これでいい音がとれれば問題ないけど、ベースらしい音にするにはイコライジングが必要だ。何でかというと、アコースティックベース用のピックアップはベースアンプにつなぐ事を前提とした音になっているからだ。(んなもんでD.Iでそのままダイレクトに収音すると低音のないパキパキの音になってしまう。)
2はエフェクターを使っている場合。よっぽどえぐいエフェクト(ディスとーションとか)をかけてない限りは、1の方法で収音してミックスダウンの時にエフェクト処理をした方がいい。が、But、しかし(三重否定)エフェクターを通して音響特性をあえて劣化させた方が、いい場合もあるから一概には「やめた方がいい」とはいえん。特性が優れている音が、音楽的に優れている音とは限らんのだな。
3はベースアンプのコントロールが使えるのが利点。音作りをある程度ベーシストにやらせてしまおうという発想なんだが、収音出来る音はそれほど1や2の方法と変わらない。出力によってD.I.を使うかどうか決める。
4はピックアップの音がベースアンプを通して音に変わるので、「らしい」音が簡単に収音出来るのがメリット。ただし、ピックアップの電気信号をアンプで空気振動に変えて、その空気振動をマイクで電気信号に変換するという回りくどい事をやっているので、1〜3の方法で収音した時よりも少しぼけた音になる。
2-3-2 アコースティックベースの収音によく使われるマイク
| PL-20

|
オンマイクで狙う時にいい。しっかりと弦自体の音を拾ってくれるが、ふくらみはいまいち。 |
| MD-421

|
これもオンマイク向きで割と派手な音がする。音量感のある音なので、ライブレコーディングなどにも良い。 |
| MD-441

|
F穴を狙う時にお奨め。 |
| U-87/C-38
 
|
ジャズ系の音楽向き。「ぶんぶん」とした音が上手く収音出来る。 |
| C-414/C-48
 
|
上記の2つよりも派手な音。イコライジングで高域を少しコントロールしてやらないと、少しざらついた感じになるきらいがある。 |
| SM-58

|
これは番外編。このマイクでF穴を狙ったら、すごくいい感じで収音出来た事があったのでご参考まで。 |
2-3-3 エレクトリックベースのマイキング(?)
エレクトリックベースについてといったって、「何年のジャズベースはポジションマークがドットタイプで、インレイがどうのこうので・・・」というような話ではなくて、エンジニアとして、(エンジニアってかっこ良すぎるな)音響屋として、(うん、この方がしっくりくる。)・・・・所詮は士・農・工・商・ディレクター・ミュージシャン・ミキサだよ。ふん。えーっと、なんの話だっけ・・・。あ、そうそう音響屋として知っておかなければいけないのは、エレクトリックベースにはピックアップが(出力が)アクティブタイプのものと、パッシブタイプのものがあるという事。
ピックアップってのは構造的には磁石にコイルを巻いただけのものだ。このピックアップからボリュームやトーンコントロール回路を通って出力しているのがパッシブタイプで、ピックアップからの音をベースに内蔵のプリアンプを通してから、ボリュームやトーンコントロール回路を通して出力するのが、アクティブピックアップと呼ばれるものだ。(もっと簡単な見分け方は、ベースに電池がついていなければパッシブで、ついていればアクティブだ。)
パッシブタイプのベースをD.Iで収音する時は、ベース本体のボリュームやトーンコントロールは全開にするのが基本。その名の通りパッシブ(受動)タイプのベースのボリュームやトーンコントロールは、元々あるものを削って音量や音質を変えているので、たとえば「丸い音にしようと思って、ベースのトーンを絞って録音したけど、ミックスダウンの時に他の音と混ぜたらやっぱりもう少し高域がほしい」と思って、いくらイコライザのつまみを回しても、削られた音は復活できないからだ。
アクティブタイプはパッシブタイプと比べて出力がでかいので、パッドの付いていないD.Iで収音すると歪む事がある。もし歪んだ場合はパッドを入れるか、パッド付きのD.Iに替えるか、少しボリュームを落としてもらう。歪まなければボリュームは全開でいい。次にアクティブタイプのトーンコントロールは、いろいろな種類があって特定は難しいけど、ほとんどのものが2ポイント以上のイコライザを内蔵していて、基準はつまみの真ん中だ。だからトーンコントロールのつまみは真ん中にしといてもらおう。下手に低域などをブーストされると出力レベルが大きくなって、歪んでしまう事もあるからね。
| 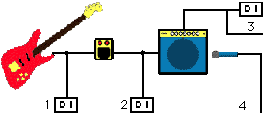
|
| 図2-3-3 エレクトリックベースのライン収音ポイント |
それでは収音方法を見ていくと、これもピックアップ付きのアコースティックベースと同じような4つの方法が考えられるのだ。
1の方法がもっともポピュラー。というかPAでもレコーディングでもまずほとんどこうする。(だもんで、タイトルの「エレクトリックベースのマイキング」の後に?が付いているのだな。マイクを使うことがあまりないのだ。)この方法がもっとも輪郭のあるベースの音が収音出来る。けど、ピックアップ付きアコースティックベースの時と同じく、エレクトリックベースのピックアップはベースアンプから出して初めてベースらしい音になるので、この方法で収音した音は、パキパキの低音のない音になる。よってほとんどの場合音質補正が必要となる。
2はベーススト側でエンジニアが付加するのが困難なエフェクターを使っている時に使うけど、エンジニアが付加できるエフェクターを使用しているのなら、1の方法で収音した方がいい。ただしベーシストの中にはかなりこだわりを持って、エフェクターで音作りをしている人もいるので、(特にチョッパーを多用する人に多い。)そーゆー時はありがたくエフェクターからの出力を頂戴しよう。まあこの辺は事前にベーシストと打ち合わせして決めようね。(リバーブなんかは基本的にプレーヤ側でかけない方がいいが、それもケースバイケース)
3の方法も2と同じで、「アンプのラインアウトから録ってくれ。」というような話になったらそうしよう。どうでもいいようだったら1の方法で収音しといたほうが、後でつぶしが利いていいぞと。
4のベースアンプの音をマイクで収音する方法の一番のメリットは、ベースの音がほぼ「完成品」になっているという事。D.Iのベースらしくない音を何とかベースらしい音にする手間が省けていいぞ。(ただし輪郭のある音ではD.Iにはかなわない)具体的には、割と「もわっ」とした音や「ぶいぶい」と歪んだ音の時にはマイクで収音するのがいい。マイクはベースアンプのスピーカの中心をやや外したところを狙い、10cm程度離した所にマイクを置く。
2-3-4 エレクトリックベースの収音によく使われるマイク