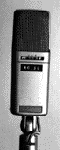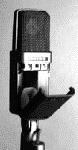|
| 写真1-2-1 SM-58 |
いわゆる「マイク」らしい形をしたマイク。ハンドボーカルマイク用として開発されたもの。マイクを口に近づけて歌う事を前提としているために、近接効果の分だけ低域をカットしてある。また高域ののびを少し犠牲にして、強力なウインドスクリーンを使っている。だもんでハンドマイクで歌う事が少ないレコーディングの世界では、あまり使われる事がない。通称「ごーはち」「ごっぱ」。PAの世界では誰がなんと言おうとボーカル用マイクのスタンダードだ。
シュアーのページのSM-58はこちら。
| |
| 写真1-2-2 Beta58A |
SM-58の改良版としてリリースされた物。最近の嗜好に合わせてかなり高域特性が改良されているが、従来のSM-58に合わせて作ってあるモニタースピーカなどと組み合わせると、高域特性の良さがかえって災いして、「ハウリングしやすいマイク」という評価になりがちなのも確か。
シュアーのページのBETA 58Aはこちら。
 |
| 写真1-2-3 SM-57 |
SM-58と同時期に発表されたマイク。楽器用のマイクとして楽器を選ばずオールラウンドに使えるが、高域が明るい音がするので、収音した音はどちらかといえば「乾いた」音になる。またボーカルにも使えるが、この場合はウインドスクリーンを付けて使うのが普通だ。通称「ごーなな」。(まんまやな)
シュアーのページのSM-57はこちら。
| |
| 写真1-2-4 Beta57 |
SM-57の改良版としてリリースされた物。SM-57よりも更に輪郭のある音が録れ、大音量にも追従してくれるので、同時期にリリースされたBETA 58Aよりは市民権を得ている感じ。
シュアーのページのBETA 57Aはこちら。
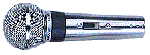 |
| 写真1-2-5 565SD |
SM-58やSM-57が発売されるまでは、シュアーのダイナミックマイクのメイン商品だった。70年代初頭のPAといえば、このマイクでドラムであろうがベースアンプであろうが、収音していたものだ。製造元のシュアーでは現在はカラオケ用のマイクという位置づけみたいだ。昔はスイッチのないものや(565D)、4ピンタイプのコネクタのもの(ケーブルの作り方でインピーダンスが選べる)もあった。
シュアーのページの565SDはこちら。
 |
| 写真1-2-6 55SH |
その外観から「ガイコツ」という愛称のあるマイク。もともとシュアーが50年代から60年代までの間に作っていたボーカル用のマイクだったんだけど、この外観のファンが多く、ふたたび作り出したというわけ。よって現在の品番は55SHの後にII(ツー)が付いている。
シュアーのページの55SHはこちら。
 |
| 写真1-2-7 MD421U |
もう生産はしてなくて、在庫だけ販売しているという状況になっているはずなんだけど、相変わらずどこいってもあるマイクだな。後継機種としてでていたMD-422がこけたので、現在はMD-421-IIというのを出しているようだ。通称「くじら」。
「ドラム用のマイク」というイメージが強いけど、元々はボーカル用として開発されたもの。プラスティックボディーのくせに物理的強度にも優れていて、コストパフォーマンスも高いのでよく使われる。中高域に少しずつピークを持った周波数特性をしていて、それがパーカッションやドラムなどのアタックを上手く強調してくれるため、打楽器に用いられる事が多い。よく使うのは正式には品番のあとに"U"が付くキャノンコネクター使用のものだ。またMD-421の専用ホルダーは非常に抜けやすく割れやすいので、使用にあたってテープで補強するなどしておいた方がいい。(人によっては接着剤で固定している。)それと使用する前にコネクタの近くにあるリング式のハイパススイッチが「M」になっている事を確認する様にね。これが結構動きやすいのだ。(P側になっているとハイパスがかかってしまう。ま、この辺がボーカル用マイクとしての名残だな。)
ゼンハイザーのページのMD-421はこちら。
 |
| 写真1-2-8 MD441 |
このマイクの当初の開発ポリシーは、「ダイナミックマイクで、コンデンサーマイク並のフラットで広い周波数特性を」というものだったんだけど、「ドンシャリ」(低域と高域がやけに強調された音のたとえ)が当たり前の今となっては、収音される音はややこもり気味に聞こえる。愛称は「ようかん」。暖かい音を上手く収音したい場合にいい。これも使用の前にMD-421と同じくリング式のハイパススイッチが「M」になっているかを確認しておこう。声がきつめの女性ボーカルなんかにもいいが、ハンドマイクにするには少し重い。あと普通はマイクホルダーに隠れてしまって見えないけど、裏側にハイブーストスイッチがあるのでこれも線が平行になっている方にしておこうね。マイクをマイクホルダーからはずす時は、マイクホルダーに付いているフックを、スライドさせないはずせない。無理矢理引っ張るとマイクホルダーを壊してしまうぞ。
ゼンハイザーのページのMD-441はこちら。
 |
| 写真1-2-9 PL-20 |
PL-20とRE-20の違いは指向性で、PL-20がスーパーカーディオイドでRE-20がカーディオイド。音質的には似ているのでここでは一緒にしてしまおう。外見に似合わず「さらっ」とした音が持ち味。下品な奴等(私?)は「馬並」と呼んだりする。でもアメリカでも「Elephant's Dick(象のちんちん)」という奴がいるそうな。マイクの横にあるスリットで指向性を作っているので、ここをふさぐような使い方はしてはいけない。またマイクが重いのでマイクスタンドやホルダーのネジがゆるんでいると、すぐマイクが「反省」してしまうので注意。使う時はマイクホルダーの輪っかの部分の上にあるハイパススイッチがオフ(線が平行になっている方)になっている事を確認してから使おうね。
 |
| 写真1-2-10 PL-80 |
これはSM-58と同じくハンドボーカル用のマイクだ。SM-58に比べて「さわやか」な音が特徴。逆にこの特徴のために「腰がない」という評価を受けて、あまりPAの世界で使われなくなってしまったかわいそうなマイク。ま、もうあまり使われることもないだろうな。廉価版とも言えるPL-77も音質的には似ている。どうでも良いけど付属のホルダーはすぐマイクが落ちてしまうので、使わない方がいいぞ。
ハンドボーカル用に開発されたマイク。優しい音がするので女性ボーカルなどに向くことが多い。また比較的小口径のキックなどにも用いられる事もある。いずれにせよ大音量の場所で使用すると振動系がとんでしまうこともあり、注意して使っていても振動系が「へたってくる」のが分かるので、他のダイナミックマイクと比べると少しデリケートだな。
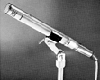 |
| 写真1-2-11 224E |
高域用と低域用に二つのマイクカプセルを持ったマイク。非常に上品な音だが、大音量には向かない。コンデンサマイクのような外観をしているので、思わずファントム電源をかけたくなるが、それをやってしまうとこのマイクは壊れるので注意。
銀色のボディーがかっこいいハンドボーカル用のマイク。このシリーズはD-330の他にD-320とD-310がある。高域にクセがあるために多少使いにくいが、男性ボーカルにぴったりのこともある。個人的には廉価版のD-320方が使いやすいと思う。
 |
| 写真1-2-12 D-112 |
ドラムのキック専用に作られたマイク。比較的完成品に近い(がMD421とはまた違った感じの)キックの音が収音できる。
AKGのページのD-112はこちら。