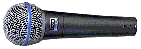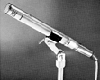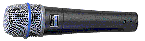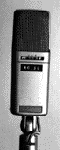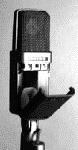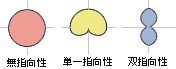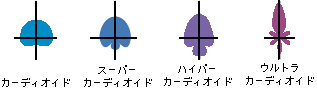1-1 マイクについて
1-1-1 マイクの種類
表1-1- 1
| マイクの種類 |
| ダイナミックマイク |
ムービングコイル |
| リボン |
| その他 |
| コンデンサマイク |
コンデンサ |
| エレクトレットコンデンサ |
マイクはその構造から2つの種類に大きく分けられるんだな。
一つはダイナミックマイク。 その原理は簡単に言えば、音に反応して振動する部分を持ち、その振動を電気信号に換えるということだ。ダイナミック型は更にムービングコイル型とリボン型とその他の物に分類できるんだけど、まあ一般的に音響業界で使うダイナミックマイクといえばまずほとんどがムービングコイル型だ。ムービングコイル型というのは、ちょうどスピーカと同じ構造をしていて、スピーカが電気信号を音(空気振動)に換えるのに対して、ムービングコイル型のマイクは全くその逆、つまり音を電気信号に換えるというわけだな。実際、音響特性を無視すればムービングコイル型のマイクはスピーカに成りうるし、スピーカはムービングコイル型のマイクに成りうる。(特に後者はトランシーバなどで、スピーカをマイクにするということが実際に使われている)
もう一つはコンデンサマイク。これは電極の間に電圧をかけ、その静電容量を変化を電気信号に換える。(だからコンデンサマイクはマイクを動かす為の電源が必要)コンデンサマイクも、いわゆるコンデンサー型とエレクトレットコンデンサ型に分けられるんだけど、エレクトレットコンデンサ型は音響の世界ではあまり使われない。
ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いは、あえて言い切ってしまえば音質の違い。コンデンサーマイクは構造上、ダイナミックマイクでは再現が難しい高域特性に優れているというわけだ。但しこの高域特性のためだけに「高価」「振動や湿気に弱く取扱に注意が必要」「電源が必要」などのデメリットをクリアしなければならない。従ってコンデンサマイクにとって厳しい条件の多いPAの世界(移動
による振動や野外での使用、盗難や破損の危険などが大きい)では、どうしても必要な部分のみにコンデンサマイクを使い、その他の部分はダイナミックマイクを使うのが普通。
1-1-2 指向性
「カクテルパーティー効果」というのを知っているだろうか?別にカクテルパーティーじゃなくてもいいんだけど、パーティーの会場のように騒がしい所にみんながいるとしよう。で、ぼ〜っとしているときは周りのざわめきを
みんなは何となく聞いているわけだな。で、ここで友人が来てしゃべり始めた。こいつは声のあまり大きくない奴なのだが、みんなはこの友人の声を(ざわめきの中にもかかわらず)さほど苦もなく聞き取ることができるわけだ。
このように人間には、ある程度の音の大きさの差などものともせず、目的の音だけを大きく聞くことができるようになっていて、このことをカクテルパーティー効果という訳だ。
ところが残念ながらマイクにはこのような知能はないわけで、周りのざわめきであろうと、友人の声だろうと、単に音として電気信号に変換するのだ。これでは特定の音を録りたい時に不都合が生じるわけだな。そこで考え出されたのが、音がマイクに入ってくる方向によって感度の違うマイク、つまり「指
向性」をもったマイクだ。
 |
図1-1 赤い部分は
手で被ってはいけない。 |
指向性を作っているのは、ほとんどの場合マイクのスリット(穴とかの 部分)なので、ここを塞いでしまったりするとせっかくの指向性マイクが、無指向性になってしまうわけだ。よくマイクの頭を手でくるんで使うボーカリストがいるけど、音響的にみるとあれは 大ばか!音の「抜け」が悪くなる上に、マイクの指向性がなくなってハウリングしやすくなる。マイクを覆うと他の音が入ってこない感じがするか
らなんだろうか、プロのミュージシャン(といえる人も少なくなってきたけど)でもこういう使い方をする人が多いのには困ったもんだ。まあ演出上こういう持ち方をしたいと言われれば、それはそれで仕方ないけど。ちなみにハードコアなんかは、もうそーゆーレベルの話ぢゃなくて、あの抜けの悪い音が音楽(か
どうかは別として)の一部だと思っといたほうがいい。
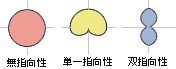 |
| 図1-1-2 マイクの 指向性 |
で、マイクの指向性なんだけど、図1-2のように大きく分けて3種類あって、それぞれ「無指向性」「単一指向性」「双指向性」とよばれている。ちなみに指向性はダイナミックマイクにもコンデンサマイクにもある。
- 無指向性
全指向性ともいわれるもので、指向性のないマイク。ラジカセなんかに ついている内蔵マイクがこのタイプだね。「小川のせせらぎ」とかみたいな
「雰囲気モノ」を録る時なんかに便利だ。PAやレコーディングではよっぽど安易なことをやるか、よっぽどレベルの高いことをやるとき以外にはあまり使われることはない。
- 単一指向性
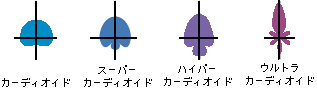 |
| 図1-1-3 単一指向 性の種類 |
ほとんどのマイクがこのタイプ。マイクの正面から来る音に対して最も感度がよいマイクで、ある特定の音だけを録りたい時に便利だ。単一指向性の
マイクは指向性の「鋭さ」によってさらに「カーディオイド」「スーパーカー
ディオイド」「ハイパーカーディオイド」「ウルトラカーディオイド」4つに分けられる。カーディオイドが比較的指向性が広く、ウルトラカーディオイド(超指向性とも呼ばれる)がもっとも指向性が鋭い。ちなみにカーディオイド
(Cardioid)というのは「心臓の形」という意味。図1-3のようにカーディオイドはハートマークをひっくり返したような形をしてるでしょ?
また4種類の単一指向性をみると指向性が鋭くなればなるほど背面への指向性も出てくることがわかる。普通は指向性が鋭ければ鋭い程、目的とする音を録れるんだけど、マイクの背面に不必要な音がある場合なんかは、かえって指向性の広いカーディオイドのほうが目的とする音だけを録れるのだよ。
- 双指向性
「両指向性」とか「8の字指向性」とも呼ばれるもので、マイクの正面 と背面から来る音に対して最も感度がよい。ラジオのトーク番組などで2人が
向かい合ってしゃべるときに、2人の間にマイクをおいて録る時や、MS方式と
呼ばれる録音技術で使われる以外には、あまり使用することはない。
1-1-3 オンマイク・オフマイク
「オンマイク」「オフマイク」ってのは「マイクのスイッチを入れたり切ったりすること」ではありませぬ。「音源にマイクを近づけて録るか、離して録るか」という意味だ。音源からの距
離がどのくらいで、オンマイクというかオフマイクというかは厳密にはいえな
いけれど、だいたい30cm位を境にオンマイクとオフマイクということが多いみたいだな。まあ30cmといってもオンマイクが基本のPAの世界では、どちら
かといえばオフマイクになるし、レコーディングの世界ではまだオンマイクのうちになったりする。オンマイクやオフマイクといういいかのほかに「オンにする」とか「オフにする」という言い方をすることもあり、これはそれぞれマイクを音源に「近づける」「離す」という意味になる。
1-1-4 近接効果
比較的小さな音源に、指向性を持ったマイクを近づけると、収音される音は、オフマイクの時と比べて低域が強調されるという特性がある。これを近接効果というんだな。ドラムなんかをマイクで録ってスピーカから音を出すだけで、音が「太く」なるのはこのためだ。逆にハンドボーカル用に設計されたSM-58のようなマイクでは、オンマイクでの使用を基本と考えて、あらかじめ近接効果分の低域をカットしてある。よってこのようなボーカル用に作られたマイクを、オフマイクで使ったりすると、低音のない「かすかす」の音になってしまう。
1-1-5 ハンドリングノイズ
ハンドリングノイズとはマイクを手で持ったときに、手と本体との摩擦で起きる「ごそごそ」といったノイズだ。はなっからハンドボーカル用として設計してあるマイクはその辺を考慮してあるので、PAでの使用ではまず問題にならないが、ノイズにシビアなレコーディングでは目立つこともある。
解決方法マイクスタンドに取り付けて使うか、ボーカリストに「マイクを持つ手を少しでも動かすな!」という無理な注文をつけるしかない。まあハンドマイクは演出上のものと考え、それ以外のときはなるべくマイクスタンドにマイクを取り付けて使おう。(もちろんボーカリストがハンドマイクでないと非常に歌いにくいといった場合はこの限りではない。)
1-1-6 位相
一応JISの規定では『マイクの振動板を押し込む力が加わったときに、プラスの電圧が出る端子をホット端子とする。』という規定があるんだけど、これだけじゃマイクに付いてるコネクターの、どの端子がホットなのかわからない。通常PAではキャノンコネクタの2番ピンをホット、3番ピンをコールドにしてあるマイクを使うことが多いが、会館設備やレコーディングでは、その逆が多い。
ということで、いろんなところからマイクをかき集めてきた時などは、 同じ種類のマイクであっても位相が違っている可能性が高いので、簡単に位相チェックをしたほうがいい。位相チェックは、簡単にやるなら誰かにマイク2
本をくっつけて持って、『あ〜』とかなんとか連続した声を少しの間出してもらい、それで1本目だけで音を聞いて、同じくらいのバランスで2本目の音を足す。そうしたときに音量が増えれば正相、逆に音量が少なくなれば逆相だ。でもラフにいっちゃえば位相は、あんまりマイクが近接しているとき以外は、でてくる音が良ければそんなに気にしなくてもいいと思うんだけどね。
1-1-7 吹かれ
いわゆる「風」をマイクが「音」と勘違いして、「ぼぼぼ」とか「ぼそ ぼそ」っといったノイズが出てしまうことだ。野外コンサートなどではよくこの現象が起きる。根本的な解決方法は風を止めるしかないんだが、まあそんな大それた話は、一般庶民には縁もゆかりもない話なので、普通はまずマイクの位置とか方向で回避できないかやってみる。それでも駄目な場合はウインドスクリーンといわれるカバーを、マイクにつける。風のほかにも人間の「ぱぴぷぺぽ」などの声はマイクに強い息がかかるので、この現象が起きる。これを特に『ポップノイズ』といっている。
1-1-8 特殊なマイク
- ワイアレスマイク
文字どおり線(ワイア)の無い(レス)マイク。まあ最近はカラオケで も、ワイアレスマイクが当たり前の時代だ。ワイアレスマイクだけではマイクとして機能しないので、当然受信器(レシーバ)と一緒に使う。ワイアレスマイク本体には、いわゆるマイクとしての部分に加えて電波を送信するための回
路と、それ用の電池が内蔵されている。
| ワイアレスマイクのメリット |
- マイクを持って自由に動き回れる。
この特長はいろいろな用途においてかなり魅力的で、極端な場合は音質を犠牲にしてまでもワイアレスマイクを使う場合もあ
る。
- マイクケーブルが絡むことが無い。
マイクを持って猛烈にダッシュしようが、複数の人間がマイクを持って輪になって踊ろうが、(ジャニーズ系のコンサートを想像してもらえれば分かりやすいかな?)ワイアレスマイクはマイクケーブル
が絡むことが無い。
|
メリットはこの2つだけだ。それに対してデメリットはたくさんあるぞ。
| ワイアレスマイクのデメリッ ト |
- 電源が電池。
これは宿命だ。(ワイアレスマイク本体に電源アダプターなど付けたらそれこそ本末転倒だ。)だからあまり長時間の使用に耐えられない。
- あまり強力な電波を出せない。
これも電源が電池であることから考えて当然だ。 もし仮に強力な電波が出せたとしても、電波法によって届け出や免許を持たずに使える電波は微弱なものに限られている。
- 場所によって電波の受信状態が違う。
これは電波を扱っている以上当然出てくる問題だとはいうものの、ちゃんと動作するかどうかが使う場所で実際に使ってみるまで分からないという厄介な問題。ダイバシティー型の(2本以上のアンテナを使い、一番受信状況のいいアンテナを自動的に選択するシステム)受信器を使い、アンテナの位置を工夫してみることによってかなり回避できるけど、それでも運が悪いと(本当にそうとしか言いようがない)マイクの位置によっては、受信できないこともある。ちなみにこの受信できないところのことを「デ
ッドポイント」という。
- ダイナミックレンジが狭い。
ダイナミックレンジとは簡単に言うと、どのく らい大きい音まで扱えるかという事。電池を電源とするワイアレスマイクは、
有線式マイクに比べるとそれほどの大音量でなくても歪んでしまう。一応これ
を避けるためにワイアレスマイク本体の中には、パッドスイッチやゲイン調整
のねじがあるものも多いけど、これはS/Nを犠牲にしてとりあえず音が歪まないようにする消極的な対応方法。ノイズリダクションシステムを内蔵して、少
しでもダイナミックレンジを稼ごうとしているものも多い。
- 音質が有線式に比べていくぶん落ちる。
「いくぶん」か「かなり」かは物によって違うんだけど、音質的にワイアレスマイクは、まだまだ有線式にかなわない部分が多い。最近の物は一昔前に比べて格段に進歩しているので、音質面ではかなり
のレベルまで来てるんだけどね。ワイアレスマイクは、出来れば使って欲しく
ないというのが、エンジニアの本音。
- 高価。
当然だけど有線式のマイクと比べると値段が高 い。特に音のいいワイアレスマイクは、ばか高いのだ。またランニングコスト
(購入するためのお金じゃなくて、買ってからそれを使うのに必要なお金。車
でいえばガソリン代や保険代なんか。)の電池代もばかにならない。単純計算で、250円のアルカリ乾電池を毎日2つずつ使うとそれだけで年間18万円の出費になる。
- 重く大きい。
単純に考えても、電池分は重く大きくなる。たかが電池分と思うなかれ、ワイアレスマイクは基本的にはず〜っと手で持って
いるもんなんだぞ。
- 強度的に弱い。
あの小さい中に電波を発信する回路を組み込んであるもんだから、故障もしやすい。しかも『全然音が出んくなった。』とかいうような分かりやすい故障でなく、「さっきぼそぼそとノイズが出てたけど、
ちょっとしたら消えちゃったよ。」「じゃあ一応電池替えてみようか。」「ありゃりゃ、またノイズが出てきたよ。」というようないいや らしい故障の仕方が多い。(経験上ね。で、修理に出すと『症状出ず』
でそのまま直らずに返ってくるんだな、これが。ん゛〜)
- 南極や北極では使えない。
まあそんな所でマイクを使う物好きはいないだろうけど、これは乾電池があまり低温では使えないってこと。その他汗や息などの湿気にも弱い。(まあ、マイクはみんなそうだけど。)
- 同じ周波数の電波を、他で使っている可能 性がある。
法律で、ワイアレスマイクで使用してもよい周波数は決まっているので、混信の恐れが常にある。よくあるのがホテルなどに音響機材を持ち込んだ場合に、下の階とか上の階のように気がつかないところで同じ周波数のマイクを使用している場合。上の階の国際会議に、下の階の結婚式場のおやぢの「マイウエイ」が紛れ込んでしまったりした日にゃぁ 悲惨だ。
|
以上のようなことから、プロの音響業界では、まだまだ有線マイクのように気軽に使えるものではないけど、使う側からしてみれば1度使ったら結構病みつきになるワイアレスマイクなので、ワイアレスマイクのオーダーはますます増えてくるだろうな。あ〜、やな時代だ。
- ステレオマイク
ステレオで録るためには当然ながら2本のマイクが必要なんだが、これが結構めんどくさいんだ。なにがって、マイク以外のスタンドやホルダーなどの付属品も2つずつ必要だし、特性のそろったマイクを2つ用意しなくちゃいけないし、マイクのセッテイングも難しいし・・・。というものぐさ者のためにあるのがこのステレオマイクというやつだ。ステレオマイクは2つの特性のそろった同じマイクを1つにまとめてあるもので、単純に横に並べたものと、MS方式というワザを使ったものがある。単純に2つマイクを並べたものは、いわゆる「生録」なんかに便利。一時期デンスケ(ソニーのポータブルテープレコーダの愛称)をかついで、SLの音やら鳥の鳴き声だとかを録るのが「おっしゃれぇ〜」だった時代があった。まあ今風に言うと『ヲタク』だけ
ど、その頃にゃそんな言葉はなくて、そういう人達は『生録 マニア』と呼ばれていた。
閑話休題、この手のマイクには2本のマイクの角度を、スイッチで切り替えられるものも多くあって、『雰囲気モノ』を録るにはなかなか都
合がよろしい。MS方式のマイクは2本のマイクを1本にしたというよりも、ちゃんとセッティングするのが結構難しいMS方式のセッティングを、楽にするための意味合いが強い。よって使われ方もプロの現場での使用が多く、マイクの値段も高価なのが普通だ。
- PZM
PZMってのはPressure Zone Microphoneの略で、作ったアムクロンという会社の商品名なんだけど、このタイプのものはすべてPZMと言ってしまうことが多いようだ。(「ハイミー」とか、「いの一番」が「味の素」といわれるのと一緒だな)とにかく、売りはオフマイクでもオンマイクのような芯のある音色が得られることかな。とはいうもののちょっと変わりものなので、いまいちメジャーな存在とは言えんなぁ。外見も「エイ」みたいだし、壁とかにはっつけて使うことが多いし・・・
比較的よく使われるのは、レコーディングでドラムなんかのアンビエンス(部屋鳴り)マイクとして使ったり、演劇関係などで、ステージのかまちの前あたりの床に張り付けて、マイクがない様に見せるとかの場合かな。
- コンタクトマイク
コンタクトってのは「接触」という意味。(目に直接付けるからコンタクトレンズと言うわけだな)だからコンタクトマイクってのは「音源に直接取り付けるマイク」ってこと。サックスやバイオリンなどを録る時に、楽器に直接取り付けるものなどがそうだ。テレビ番組なんかの出演者が、ネクタイのところなんかに付けてるマイクもコンタクトマイクの一種なんだけど、
タイピンのようにして使うので、これらは特に「タイピンマイク」と呼ばれている。
音源に取り付ける関係で、コンタクトマイクってのは小さく軽く作られているので、通常のマイクと比べると音質面で少し見劣りしてしまう。
だからこの手のマイクがよくライブなんかで使われているのを見としても、ステージ上での演奏者の動きを、比較的自由にする所に一番のメリットがある訳で、そのマイクが音質的に優れているわけではないことが多い。だから動きまわる必要がないレコーディングでは、コンタクトマイクを使う必然性は、全くない。
- コンタクトピックアップ
厳密にいうとこいつはマイクじゃないんだけど、コンタクトマイクとよく混同されるので説明しとこう。マイクとピックアップの違いは、マイクが、音源が振動する事によって起こった空気振動を電気 信号に変換するものなのに対して、ピックアップはスチール弦などの
音源の振動を直接電気信号に
変換するものだということだ。エレクトリックギターのピッ クアップなんかがそうだね。音源の振動を直接拾う分、マイクよりも音源の音
だけを録ることができるけど、音質的にはイマイチなのはいたしかたない。
1-1-9 マイク本体のアクセサリ
- オンオフスイッチ
マイク本体についているオンオフ用のスイッチ。PAで司会のマイクなどに使うくらいで、プロの現場ではあまり使うことがない。これはマイクがステージ側でオンオフできる便利さよりも、何かの間違いでスイッチがオフになってしまい、音が切れてしまうトラブルのほうがよっぽど怖いからなのだよ。(以前中小企業の社長っぽいおやぢが、「スイッチ付きのマイクはありません」といわれて、「安物しかないのか!ここは!」 と怒っていた。知らぬとは恐ろしきことなりだな。)
会館設備の会場内アナウンス用のマイクや、放送用のスタジオなどでは「カフ(ボックス)」といわれる簡易フェーダーをつけて、マイクを使う側でオンオフをする。カフ(Cough)ってのは「咳」のこと。咳止め薬の「ヴ
ィックスコフドロップ」のコフも日本語表記の違いだけで一緒の事だ。
何でこんな名前が付いてるかというと、アナウンサーなんかが咳をしたいときなどに、手元でマイクをオフにできるようにってことだな。まあ実際は咳をするときというよりも、ミキサ側のフェーダーは上げっぱなしにしておいて、喋るときにはカフを上げ、喋らないときには下げておくというのが実際の使い方。たまにニュースなどでCM明けにアナウンサーの声が聞こえなかったり、VTRの途中で打ち合わせの声が聞こえたりするのはこのカフの操作ミスによるもの。
放送局などのスタジオに設置されているカフは他に、キューランプや、本線に出さないで(放送では電波にのせないって事だな)ミキサやディレクターと対話するためのトークバックスイッチなど、付加機能が付いている物が多い。それに対して会館設備のアナウンス用マイクのカフなどは、単純にアッテネッター(ボリューム)の機能しかない簡易型が用いられる事が多い。
- イコライザスイッチ
マイクの周波数特性をコントロールするためのスイッチ。ほとんどが近接効果による低域をカットする目的で付いている。最近はミキサが安価なものでも高性能になってきたので、この機能を使う人はあんまりいなくなってしまった。「とりあえずマイクに入ってくる音は全部ひろっといて、不必要な部分はミキサのほうでカットすればいいじゃん」という発想だな。とはいうもののベテランエンジニアの中には、このイコライジングスイッチとマイクの置き方で音作り(それもかなり高度な)をしてしまう人もいる。はっきり言ってあれは「職人芸」だな。
- パッドスイッチ
「マイク本体に内蔵されている電 子回路が、過大な音圧によって発生した過大な電圧に対して、歪んでしまうの
を防止するための付加装置の、動作を決定する開閉器」っていったって判んないよなぁ。(笑)要はコンデンサーマイクを使うときに、音源の音量が大きすぎてマイク本体で歪んでしまう事を避けるために、マイクの感度を落としてやるスイッチ。マイク本体で歪むことを避けるといっても、音を電気信号に変える部分でやるのではなくて、その次にあるプリアンプ部(マイクに内蔵されている)に抵抗を挟み込んでいるだけの話。当然構造的にプリアンプ部を持たないダイナミックマイクにはこのスイッチは存在しない。
- 指向性切り替えスイッチ
マイクの指向性を変化させるためのスイッチ。コンデンサーマイク(しかも比較的高価なもの)に付いていることが多い。このスイッチを使い分けるのは、結構高度なことをやるときだろう。
1-1-10 アクセサリ
- ウインドスクリーン
ウインドスクリーンには、マイク本体と一体化しているものと、マイクの付属品としてのものがあるんだけど、通常ウインドスクリーンといった場合は、後者のことを指すことのほうが多い。役目はマイクの「吹かれ」を軽減することなんだけど、マイクに布っ切れをかぶせてる様なものなので、他の方法では吹かれをうまく軽減できないときに使う『必要 悪』と思っといた方がいい。使わないほうがマイク本来の性能を発揮できるに決まってるんだかんね。
シュアーのSM-58のように本体と一体化したウインドスクリーンをもつマイクは、ウインドスクリーンを含めて音作りがしてあるので、これははずすと本来の特性が得られなくなる。(そういう使い方も面白いけど・・・)
- マイクホルダー
マイクホルダーは地味な小物ながら、マイクをマイクスタンドに固定するのになくてはならないものだ。マイクホルダーにはそのマイク専用のものと、いろいろなマイクに使えるものがあるけど、基本的にはそのマイク専用のものを使ったほうがよいよ。ゼンハイザーのMD-421やエレクトロボイスのPL-20などのマイクは専用のものを使うしかないんだけど、シュアーのSM-58やSM-57なんかは、いわゆる「普通のマイクホルダー」(シュアータイプのマイクホルダーと言うことも多い)なら使えるので、実際にはこのタイプのマイクには、専用のマイクホルダーを使わないことも多い。またマイクホルダーのなかにはユニバーサルタイプといわれるものもあり、これはいろいろな太さのマイクを使えるように洗濯ばさみの親玉みたいな格好をしたものなんだけど、マイクホルダーからマイクを取ろうとするときに両手を使わなければいけないことと、マイクケーブルを引っぱってしまった場合に、マイクがマイクホルダーから抜け落ちてしまうという欠点があるので、特にPAでの使用には向かない。
- マイクスタンドのねじ
たかがマイクスタンドとマイクホルダーをジョイントするねじ なんだけど、このねじの規格が5/16インチ、3/8インチ、1/2インチ、5/8インチと4種類もあるからややこしい。さらに1/2インチはねじの規格まで違うんだよ。
でもマイクスタンドの所でも触れるけど、PAではマイクスタンドはAKG(B&Kj社の製品を使うことが多く、それに合わせて3/8インチのねじを使うことが多い。ホールや放送局関係では1/2インチのねじを使うことが多いかな。ねじの違うマイクスタンドとマイクホルダーを組み合わせるときには変換ねじが必要なんだけど、この変換ねじは、マイクホルダー側に常に付けておくようにすると分かりやすい。(で、実際みんなそうしてます。)
1-1-11 マイクスタンド
マイクをハンドマイクで使うとき以外はこのマイクスタンドでマイクを固定する。その目的によっていろいろなものがあるので、ざっと紹介しましょうかね。
- ストレートスタンド
一番シンプルな形のマイクスタンドだ。基本的には次のブーム型からブームの部分をとったものなんだけど、ボーカル専用のストレート型も市販されている。これは軽量化が図ってあり、片手で楽に持ち上げることができる。まあその分強度的には弱いので、アクション専用マイクスタンドと思っといたほうがいい。
また最近のマイクスタンドの足の部分は3本足のタイプが多い けれど、昔は足の部分が円盤型のストレートスタンドが一般的だったので、60's
あたりの雰囲気を出すためにあえてこの円盤型の足のマイクスタンドを愛用している人もいる。このような円盤形のスタンドは「丸皿」とか「ラウンド」とか呼ばれることが多い。
- ブームスタンド
とりあえずほとんどの状況で使える便利なマイクスタンドだ。 ブームスタンドにはいわゆるブームスタンドと、それよりひとまわり小さいミニブームまたはショートブームと呼ばれるものがある。PAの世界ででは9割方このブームスタンドが使われる。そのブームスタンドのなかでもAKG(K&Mjの製品を使っているところが非常に多いので、PAの仕込み図などにはAKGの
ブームスタンドの品番であるところの(関係代名詞)「ST-210」または「210」と書かれることが多い。同じくミニブームは「ST-259」または「259」と書かれる。
- 卓上スタンド
文字通り机の上において使用する。「青年の主張」なんかの弁論大会で演台がある状況では、下手にブームスタンドなんかを使うより、マイクスタンド自体を演台の上に載せた方が見た目がすっきりするでしょ。あとはたまにギターアンプやキックを録る時に使う人があるけど、卓上型はマイクセッティングの自由があまり利かないので、講演会や会議などの用途以外はあまり勧められない。
- グースネック
グースネックってのは「がちょうの首」。ほかに「フレキ」と呼ばれることもあるけど、このフレキってのはフレキシブルの略で、曲げやすいとか融通の利くといった意味だ。えーっと、みんなの家にはたぶんガス湯沸かし器があるでしょ?そのガス湯沸かし器に付いている水道管みたいなやつだ。(実際この水道管もフレキ管という)
もちろんマイクスタンド全体をこのフレキ管で作ったらぐにゃぐんやして使いもんにならんので、他のマイクスタンドの先につけて使う。どんなところにもセッティングできて、非常に便利そうに思えるけど、マイクの重みで自然に曲がってしまったりするし、安定性もよいとはお世辞にも言えないので、すぐすたれてしもうた。ただマイクスタンドの先端の向きから、Uターンさせて180度逆の方向にマイクを向けるのには便利なので、ドラムボーカルやハイハットの収音にはまだよく使われる。
- ハイスタ
たぶんハイスタンドの略なんだろうな。放送局やレコーディングスタジオ関係などでは、ST-210のようなブームスタンドもよく使うんだけど、「かなり離れた所へ、かなりの高さで」(たとえば4メートルはなれたところへ3メートルの高さで)というのは、普通のブームスタンドでは物理的に不可能やんね。こーゆー目的に使われるのがハイスタ。見た目のイメージ的にはクレーンの様な感じ。
- 中2段・小3段
なんか「学生将棋トーナメント」みたいな名前が付いてるけど、これも放送局やレコーディングスタジオ関係などでよく見るタイプ。基本的にはストレートスタンドなんだけど、軽さ(移動するのが大前提であるPAでは音の次に大事な事)を捨てて、安定性に重点を置いてあるマイクスタンドだ。高さとジョイント数で「中2段」とか「小3段」などといっている。中2段は大体2.5m位の高さまで、小3段は1.5m位の高さまで対応できる。マイクの高さや向きはロックできないので、手があたったりすると、セットした位置が変わってしまうこともある。
- エレベーターマイク
ホール関係独特のもので、一種の「設備」。よく漫才なんかで「ど〜も〜」っと出てきたときに、下から出てくるアレだ。舞台袖や音響室にオンオフスイッチと高さを決めるつまみがあって、そこで操作をする。「けっこう結構使いこなすには、慣れが必要だよ。」と自慢げに小屋のオヤヂは言う。
(^_^;
- 吊りマイク
これはマイクスタンドではないんだけど、比較的軽いマイクなんかは吊して使うことがある。クラシックのレコーディングなどでは、よくホールの客席上のシーリング室から、コンデンサーマイクを吊すし、ほとんどのホールでは最初っから「3点吊り」といわれる設備がある。これは3本のワイアーの長さを変えることによって客席の上のいろいろな位置にマイクを持っていくことができるもの。クラシック系のレコーディングでは、この3点吊りマイクだけでレコーディングされることもある。あとPAでギターアンプなどに、どうしてもマイクスタンドが立てられんときは、苦肉の策としてギターアンプにマイクを吊すこともある。
1-1-12 良くあるマイクの扱われ方
いわゆる『トーシロ』の方々のマイクの扱いには、毎回驚かされるので、一応紹介しておきましょうか・・・(苦笑)
- マイクチェックのつもりでマイクを叩いたり、息を拭きかけたりする。
どうしてマイクが最も苦手とする『振動』と『風』をマイクに与えるのだろうか・・・・音の専門家はこういうことをやっている人に忠告すべきだ。相手が弱そうだったら殴ってもいい。
- マイクを持つとスイッチをさがしてしまう。
まあ、これは可愛いほうだな。カラオケの悪しき影響だ。
- マイクの用途を考えない。
たとえばドラムに使っていたマイクを、ヴォーカルに使い回そうとしたりするってこと。これは相手に説明してもわかってもらえるかどうかわからないので、私は「いやーぁこのマイクは歌には使えないんっすよぉ」などと訳のわからんことを、にこにこしながら言うことにしている。
- マイクがあればどんな音でもひろえると思っている。
これも相手に説明してもわかってもらえるかどうかわからないので、私は「いやーぁ、このマイク感 度悪いんっすよぉ」と少し困った顔をして言うようにしてい
る。
- マイクを持つと小指が立ってしまう。
実害はないので、好きにさせてあげましょう。