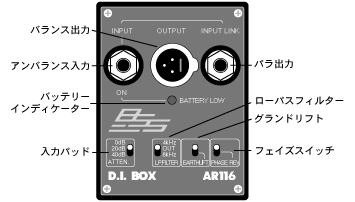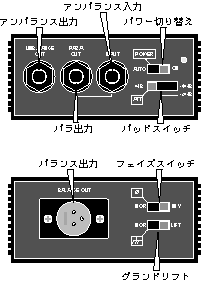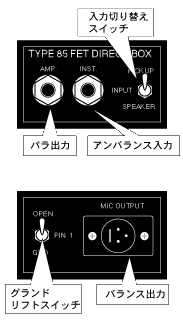 |
| 図1-3-1 カントリーマン#85 |
アクティブタイプのD.I.をメジャーにしたアクティブタイプのD.I.の元祖的存在だ。頑強なボディーによる耐久性と、太めの音質が好まれて現在でも多く使われている。
フロントパネルは左からパラ出力用の端子、入力用のアンバランス入力端子がそれぞれ2Pであって、右側には入力(インピーダンス)切り替えのスイッチがついている。このスイッチはスピーカアウトなどから入力する時以外は、必ずピックアップ側(上側)にしておかないと出力が歪んでしまうので注意。
リアパネルには右側に出力端子があって、MIC OUTPUTとかいてあるけど、これはマイクレベルの信号ですよという意味位にとっておけばいい。左側にはグランドリフトスイッチがついている。これは通常どちら側にしてあってもいい。ノイズが出た時にこのスイッチをその状態と逆側にしてやると、止まる事があるというものだ。これは回線のつなぎ方によって出来てしまった、アースループを遮断したりするもので、複雑なシステムになればなるほどこの問題が起きやすく、しかも前もって予測できないタチの問題だ。
|
|
| 図1-3-2 BSS AR-116 |
カントリーマンと並んで、よく使われているD.I.。カントリーマンと比べて色々な付加機能が付いている。音質的にはさらっとしたやや軽めの音だ。注意しなければいけないのは、このD.I.にはバッテリー専用タイプとファントム電源も使えるタイプの2種類あるんだけど、中を開けてみないと区別が付かないのだ。バッテリー専用のものにファントム電源をかけるとD.I.を壊してしまうぞ。
上から左がアンバランス入力、真ん中がバランス出力で、右側がパラ出力。パラ出力の表記が「INPUT LINK」となっていてINPUTと間違えやすいので注意。その下にあるバッテリーのインディケーターは普通は消えていて、D.I.内蔵のバッテリーが少なくなると点滅して知らせる。正常な時には点灯しないので心配しないように。
下のスイッチは左側から入力のパッド。キーボードなどの電子楽器をつなぐ時などに、 入力が大きすぎて歪んでしまった時に入れるといい。普通は使ったとして20dBで十分。 40dBのパッドを入れる事はまず無い。その次はローパスフィルター。何でついているのかよく判らないんだけど、D.I.以前に「ジー」といったノイズがのっている時に、これを除去するような用途に使うんだろうな。まあ普通は使わないので真ん中にしておこう。その次がグランドリフト。TYPE85で説明した様に、ノイズがでている場合、このスイッチを現状と逆の方にするとノイズが消える事もある。通常はどっちでもいい。一番右のスイッチはフェイズ(正相逆相)の切り替え。一応スイッチが上にある時は3番ホットになっているんだけど、使う時は別にどっちになっていてもかまわない。ただし2台使ってキーボードのLRを収音する時や、同じ楽器の高音部と低音部を収音する時は同じ方になっているのを必ず確認する事。
このD.I.の詳しいスペックはこちら。
|
|
| 図1-3-3 BOSS DI-1 |
国産のD.I.。少し丸めの音色が特徴。性能の割に安価なので、最近よく使われている。
フロントパネル左側から、アンバランス出力。これは単純な入力のパラではなく、内部回路を通ってインピーダンス変換をしてからの出力。だから後述のパッドも当然有効だ。(でもまあ普通は使わない)次が入力のパラ出力で、その次が入力。その横にスイッチが上下2つついていて、上側が電源のモード切り替え。「AUTO」と「ON」があるけどこれは必ず「ON」側にしておく。「ON」側にしておいても「INPUT」に2Pプラグを挿さない限り電源が入る事はない。じゃあ「AUTO」というのは何かというと、入力信号が入ってきた時に電源を入れ、入力信号がとぎれたら電源を切るといういわば「省エネモード」だ。このモードは電源が入ったり切れたりする事によって、ノイズがでてしまうので使いにくい。このスイッチの横にはバッテリーインディケーターがあり、バッテリー駆動の時はINPUTに2Pが挿された時に点灯し、ファントムを使っている時は常に点灯する。パッドスイッチ、バランス出力、フェイズスイッチ、グランドリフトについてはAR-116と同じなのでそちらを参照の事。
ただしファントム電源を使用している時に、グランドリフトをLIFT側にするとファントム電源から電源を供給できなくなってしまうので注意。この点と、入力に比べて出力が正直に6dB大きくなってしまう点は、はっきりいって使いにくい。