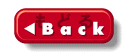|
text by Toshio Mizuno●● ●データ● ●田口ランディ(女性・東京生まれ) ●関連リンク・田口ランディのコラムマガジン |
ドラえもんは まず、このコラムは田口ランディさんのコラムを読んで、僕が思った事であり、決して田口さんの考えを否定するつもりはないのです。しかも、これはドラえもんを否定されたから、それに対して反撃をしよう!というつもりでもないのです。 「できればムカつかずに生きたい」(田口ランディ著/晶文社)の中の一編「私は父性を持ちたい」は、とても面白い内容でした。娘さんとTVアニメを観ていて、ドラえもんに腹が立つというお話。 このあと、日本の社会、学校、国のシステムから父性(秩序、ルール、規律、道徳、思想を無尽蔵に与える力)が消え、母性(何でも許し、愛で包み込んでしまう力)を重んじ、母性だらけの社会になった事が、日本という社会に歪みを生み、数々の少年事件を生んだ…というコラムです。 もちろんドラえもんは頭の掴みであって、本筋は父性と母性のバランスの話なんです。文末を読むと、すでに多くのドラえもんファンから批判のメールをもらったとあり、いまさら僕が何を書いても意味は無いかもしれません。 「ドラえもんが母性である。」という事は、ファンなら誰もが昔から認識している事であり、作者の藤子・F・不二雄先生は確信的にそれを描いています。つまりおっしゃる通り。 初期のドラえもんは、あくまで児童向け漫画としてスタートしており、夏目房之介さん(漫画評論家)が語っていた、児童漫画としてのドラの構造「快・不快原則」(子供がおもしろさの基準とするのは-気持良さ-)を狙って描かれていたのは事実でしょう。ただ重要なのは、この漫画が描かれたのが劇画漫画全盛期の1970年代だという事。この事はこの作品を語る上で重要なのです。 ドラえもんの漫画連載がスタートしたのは、1969年(昭和44年)。東大安田講堂にて機動隊8500人と学生運動家が衝突した年であり、新宿西口広場のフォーク集会に、機動隊2500人が出動し、それを排除した年です。次の1970年には赤軍派学生による日航機よど号ハイジャック事件。自衛隊市ヶ谷駐屯地で、クーデターを呼び掛けた三島由紀夫と盾の会メンバーの一人が割腹自殺しています。 子供達が強いヒーローや劇画に熱中していた70年代頭に、なぜ藤子・F・不二雄氏が「ドラえもん」をスタートさせたのか?まだ、父性が正義だった時代に。 藤子・F・不二雄(藤本弘)さんは終戦の昭和20年の時11才。小学校に転校してきた藤子不二雄A(安孫子素雄)さんと出会ったのもこの頃です。みなさんご存知の様に漫画の神様・手塚治虫氏に憧れて、2人は漫画家を目指した訳ですが、この頃の世代の手塚・藤子氏や多くの漫画家が「戦争を見てきた」世代である事は重要なポイントなのです。戦争を見てきた世代・経験した世代にとって、父性は軍国主義の象徴であり、権力や支配は悪なのです。これは戦争を実際には経験していない、甘っちょろい我々の世代が云々と気軽に意見できる事柄ではなく、この世代の想いを否定する事は出来ません。 手塚氏以降の日本の漫画は権力・支配に対する疑問をいつも投げかけ、父性が全てだった日本社会の歪みを批判してきたのです。これは手塚治虫が意図的に仕掛けた時限爆弾であり、漫画を使って日本を変えようとした彼の目論見は見事に成功・達成されようとしています。もちろんそれを読んで漫画家を目指した藤子・F・不二雄氏が、その想いを受け継がない訳は無く、ドラえもんという児童漫画の中にさえ、父性(権力)に対する反発は多く描かれています。 「社会に出て、出世する事、強くなる事が全て」と教えられて、「子供としての時間」を犠牲にしていた多くの70〜80年代の子供達にとって、「勉強の出来ない子でもいい、強くなくてもいい、優しい子であれ。」という「ドラえもん」のメッセージは、多くの子供達を救ったのです。いまさら教育論をうんたら言うつもりはありませんが、その時救われた少なくとも一人が僕自身であり、世代によっての意見が違う事はあっても、これは事実です。 ただ、時代は移り変わっていく物であり、無尽蔵に愛を与える母性「ドラえもん」がいつまでも時代に合う訳ではありません。ドラえもんは物語の性質を少しづつ変えていき、ドラえもんは無尽蔵に愛を与えなくなります。「大長編ドラえもん・映画ドラえもんシリーズ」以降は、のび太は自分自身の事を考え、人を守る為に強くなろうとし、自分の周りの人々を理解しようと努力し始めます。それをサポートするのがドラえもん。彼は「母性」から「友人」へと変化し、時にのび太を叱り、時に励まし、一緒になって努力します。これは明らかに藤子・F・不二雄先生が子供達に向けたメッセージであり、「ドラえもん=理想の友人・理想の父親」と藤子先生の中で設定は変更されたのです。 僕は社会に出てみて、田口ランディさんの主張される「日本社会=母性の社会」などとは感じた事はありません。それは僕が社会で必死に生きていかなくてはならない環境の人間だった事、決して「どうにかなるさ」「困った時はどっかから助けが来る」などといった甘いバブル時代の就職ではなかった事などの違いがあるのかもしれません。 昨今の急増している少年事件は本当に母性社会の甘やかしが原因なのか?そこに至るまでの少年達のストレスの高まりは、効率・合理性だけを求めた父性社会の責任ではなかったのか? 人は何でも悪いことはまず人のせいにします。子供がグレれば学校教育・漫画のせい。犯罪が増えれば警察・景気のせい。漫画は昔から「子供への害」「悪書」として叩かれてきました。しかし、そうでなかった事は今の中年世代・手塚漫画世代が証明してくれるでしょう。子供が歪んでしまうのは、親と、それを取り巻く人間環境の責任であり、漫画のせいではありませんよね(^_^)。親として、自分の子供をしっかりと見つめる事、成長に責任を持つ事、それが親の責任です。「ドラえもん」のTVアニメが、自分の子供にふさわしく無いと思うなら見せない事です。ドラえもんのおもちゃが高価で贅沢だと思うなら、子供に我慢させ、買わない事です。これは、一方的で理不尽な「父性」ではなく、愛のある筋の通った「父性」が必要であるという事。 過去の戦争の反省をする時、理論や一時的感情で語るのではなく、経験者達の言葉や事実・証拠の記録調査、世界的な広い視野での検証を行った上で語るべきです。少なくとも手塚治虫・藤子・F・不二雄世代はそれを経験した上で支配的「父性」を否定している訳で、戦争を経験していない世代はそれに耳を傾けるべきです。 次世代の子供達の事を考えた時、いったい何を与えるべきか? |