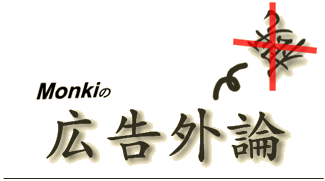
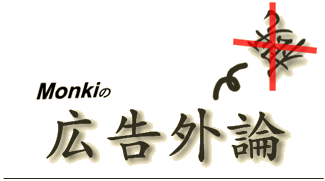
毎年、夏の甲子園が準決勝を迎えるころ、夏の終わりを感じる。夏といえば、海である。ビーチボーイズである。
つい最近、NHKでビーチボーイズ・ヒストリーが放送されて、それがすっごくよくて、だから感じたことを少し書いてみたい。
一番感動したのは「God Only Knows」。いくつかのライブ映像がつなげられていて、月並な手法であるにもかかわらず、ジーンとしてしまう。この曲でリードボーカルをとるカール・ウィルソンのインタビューがまたよくて、この曲に対する彼の思い入れと、作曲者である兄ブライアン・ウィルソンに対する敬意が滲み出ていた。
番組の中で明らかにされているように、ブライアン・ウィルソンは精神を病みやすい体質のミュージシャンである。おそらく、「クソ兄貴!」と思ったこともあっただろうが、みんな年をとり、一番華やかだった時代を思い返してみたとき、「やっぱり兄貴はすごかった」と自然にいえてしまうその家族愛がいい。このアメリカ的家族主義がビーチボーイズの魅力であり、限界であろう。
ブライアン・ウィルソンは、チャック・ベリーの世界(「Surfin' USA」)とフォー・フレッシュマンの世界(「In My Room」)を統合した、当時としては無茶なミュージシャンだが、似たような傾向はジョン・レノンにも見ることができる。それは、「Please Please Me」と「This Boy」がともにジョン・レノンの手による傑作であることからもうかがえる。現代では驚くべきことではないかもしれないが、1963年の時点において、この2つの音楽性がまったく異なる名曲をつくりだしたことは奇跡といっていい。
ちなみに、ブライアン・ウィルソンはビートルズが大っ嫌いである。数年前に見たドキュメンタリー番組の中で、苦々し気に「あんなのどこがよかったんだ」と語っていた。ブライアン・ウィルソンにしてみれば、「音楽的には勝っているはずなのに何故?」ということだったのだろう。おそらく、いまもそう思っているに違いない。
決定的な勝負の分かれ目は1966年にあったと思う。自ら作詞したものではなかったにせよ、ブライアン・ウィルソンが「God Only Knows」と主張したのに対して、ジョン・レノンは「Tomorrow Never Knows」とアジテートした。この時点で勝負はついたのである。個人的には「God Only Knows」のほうが好きなのだが。
アルバム『Pet Sounds』におけるトニー・エイシャー(本職はコピーライター)の歌詞は、じつに女々しい。例えば、「God Only Knows」の最初のフレーズは「I may not always love you」だし、最後の「Caroline No」では「Where did your long hair go」という具合。いいでしょう、女々しくて。でも、時代はそんな女々しさを退屈な独り言としか認めなかった。
時代はブライアン・ウィルソンを足蹴にして、ジョン・レノンを選び、それから十数年後、新たな時代はジョン・レノンを射殺し、ブライアン・ウィルソンを正気の世界に戻したのである。
ともあれ、非常に良質な番組で、おおいに堪能した。この番組をこの時期に放映した担当者のセンスに感心する。制作はイギリスである。ビーチボーイズはイギリスでの人気が高いのだ。ブライアン・ウィルソンとマイク・ラブの漫才コンビのような関係も、とても微笑ましかった。
私事になるが、今年の夏は学校が夏休みに入ると同時に家族と久米島に行った以外は、まるで休みがなかった。土日も仕事をしていたのである。悲惨な40才である。
むか〜し、人生は海水浴であるという哲学を聞いたことがある。まあ、哲学というほどたいしたものではないのだが、単純にいうと、ひと夏の間に海水浴に行くのはせいぜい2回ほどであり、海水浴を楽しめるのはせいぜい40代までであり、そうするとあとウン十回海水浴に行ったら人生はおしまい、という考え方である。
その哲学を聞かされたとき、なんて人生は短いんだと思ったことを、夏が来るたびにビーチボーイズとともに思い出す。その哲学を語ってくれた子の本心はたんに、早く海に連れていけ、であることが分ったのは、ず〜っとあとになってからだった。
18回目へ続く・・