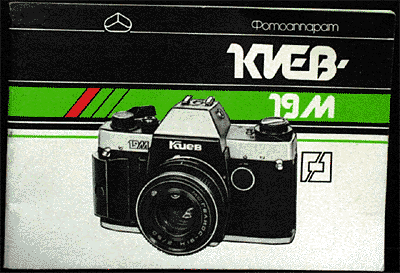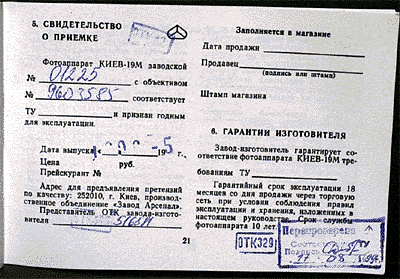|
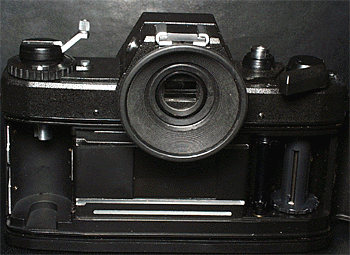 |
有る意味で旧ソ連カメラの象徴といえるカメラかも知れぬ。このカメラを見るとソヴィエトカメラの終焉を見るかの如き想いがこめてくる。 キエフでまず頭に浮かぶのはコンタックスの組み立て(部品もジグも全て同じなので敢えて模倣とは言わぬ)から始まったレンジファインダー・カメラだが、一方では同じブランドで1965年に世界初の自動露出一眼レフをしてデビューさせ、74年にはTTL自動露出へと進化させるほどの技術力を誇っていた。ところが、あまりにも機構がユニークであったためソ連独自の一眼レフの雄は姿を消した。その後77年にキエフ17として露出計を持たないニコンマウント、縦走りのメタルフォーカルプレンシャッターのカメラが現れるが、かつての技術力はどこへいったのか?と驚くほどの後退ぶりである。次いで翌年に露出計内蔵の20と17Mが出された。20は開放測光でシャッターの最高速度が1/1000秒であるが世の中自動露出の時代において既に過去の遺物的な存在でしかなかった。ところが、更に80年代半ばに両者は絞り込み測光で1秒と1/1000秒を省いた19へと更に交代&後退していく。そして、88年頃に外装をプラスチックにし、開放測光にした最終形?の19Mとなりソ連崩壊後の今もウクライナ共和国に於いていまだに生産され続けている。 さて、肝心のカメラだが駄目カメラか?というとそうでもない。まずファインダーが以外にも明るい。そして、音は喧しいのだが以外とシャッターおよびミラーのショックは少ない。プラモデルのような外観だが附属のグリップもこれまた以外にもホールドしやすい。故になかなか実用的なカメラである。ただ、ひとつ大きな欠点は巻き戻しが硬い。巻き上げスプールの抵抗が大きすぎるのである。この点は他の方も指摘されているのでおそらく構造的欠陥なのだろう。 製造年と出荷年の謎: ちょっと見づらいかも知れぬが右の取説のページにある検査証を見ていただきたい。01225とあるのはボディーナンバーでフイルム室にシールが貼ってある。そして、その下の9603585はレンズの番号である。ところが、右下の検査日の印には17/08/1999とある。ボディーはシール以外に刻印がないので製造年は不明だが、レンズはソ連の慣わしにのっとれば96年製である。ところが、検査日は99年とは是如何に? 同じような事はベラルーシはベルオモ製のアガートでも見られたが、どうやらかの國では造り貯めをしておいて徐々に出荷するようである。さて、果たして今も造り続けられているのか、それとも96年の在庫がまだあるのか、不明である。 |
|