
|
| ダイオード検波器 | 2000.07.02 (最終更新2001.12.16) |

|
|
これは単なるダイオード検波器です。 私は秋月電子で売っているTEST PROBE社のM12DMBというRFプローブを使っています。 このRFプローブはスペック上の±3dB帯域は100kHz〜750MHzですが、私が持っているものを実測すると 300kHz以下で減衰が大きく、また、900MHzあたりに共振点があるためか250MHzを超えたあたりから 次第に検波出力が大きくなり、1MHz〜750MHzの範囲でも最低と最大で1.8倍以上の差がありました。 実測は、入力にプローブ付属のBNCアダプタを使ってSSG(ANRITSU MG3631A)と50Ω整合終端、出力に DMM(METEX M3850)を繋いで、入力電力をパラメタに検波出力の周波数特性を測定しました。 DMMの分解能が1mVなので-20dBm以下は測定精度がよくありませんが、1MHz以下と250MHz以上で 検波出力が大きく変化しています。 しかし、それよりも問題なのは温度特性が非常に悪く、手で持っているだけで値が大きく変化するので 測定結果の再現性がよくないことです。 元々ダイオード検波器は温度に非常に敏感なので、パワー計のセンサなどは熱が伝わりにくいように 実装が工夫されていますが、このプローブは細い樹脂製なので仕方のないこととも言えますけども。 私が使っているSSGは30kHz〜1040MHzまで出力できるので、それくらいはフラットな特性の検波器が 欲しくて作ってみました。 市販の検波器は当然のように18GHzとか26GHzまで使えるので1GHzくらいならなんとでもなるだろう、と 安易な考えで作ってみました。 回路はごく普通の整合終端型のシングルダイオードの検波回路です。 周波数特性は部品自体の特性と実装で殆ど決まると考えて、チップ部品(2012サイズ)を使って小さく 作りましたが、検波用のショットキーダイオードだけは手持ちにチップ部品が無かったので、普通の ガラスモールドの物を使いました。 終端抵抗は100Ωを2個並列にしています。入力側のコネクタのピンはできるだけ短くしたいのですが、 チップ抵抗をケースに直接半田付けするには長時間加熱しないといけないので今回はやめました。 ダイオードは1SS108(日立)です。秋月電子で以前に買ってあったもので、端子間容量が3pF(max)と 大きいので、このために買うならもっと容量の小さいものの方が良いです。ダイオードの入力側の リード線はできるだけ短くなるように実装します。 バイパスコンデンサは1000pFを2個並列にしています。これも手持ち部品の都合で、厳密なものでは ないですが、これくらいを上限にした方がいいと思います。これはダイオードの出力側のリード線の 根元に半田付けします。 抵抗の値も適当ですが、コンデンサとで時定数をもつので大き過ぎると反応が遅くなります。 入出力のコネクタはSMAです。 マイクロ波をやる人以外にはあまり一般的とは言えないコネクタかもしれませんが、小さくて邪魔に ならないので私はよく使っています。 もっとも、使った物は秋月電子で1個200円で売られている安物で、実際、見た目もかなり怪しげな 雰囲気があるので、18GHzまで使えると書いてあるのは信じていませんけども。 困ったことに、このコネクタはヒロセ電機製などのマトモなSMAコネクタとうまく嵌合しないものが 結構あるので、注意しないと相手側の高価なコネクタを傷めてしまいます。 店頭には、真鍮製なのでステンレス製のコネクタにはうまく嵌合しないことがあるとかなんとか いい加減な言い訳が書いてありますが、そんなバカな話はなく、加工精度が悪いだけだと思います。 ヒロセ電機製のコネクタに合わなかったものは他のメーカのコネクタにもうまく合いませんから。 とは言うものの、SMAコネクタが1個200円は非常に安いので、どうでもいい用途(^^;にはこの安物を 使っています。 これらを、厚さ0.5mmの銅板で作った18mmx20mmx10mmの箱に組み込んだのが下の写真です。 いびつに歪んでいるのはデジカメのせいであって実物はもっとマシです(^^; 写真には無いですが、フタも同じ銅板で作り、本体にM2.6のナットを半田付けしてネジ止めします。 入力にSSG(ANRITSU MG3631A)、出力にDMM(Tektronix STA55G)を繋いで、入力電力をパラメタに 検波出力の周波数特性を測定した結果では、高域が少し落ちていますが1GHzまで十分良好でした。 あらかじめ入出力特性を測っておけば微小電力計としても使えそうです。 |
| 回路図 |
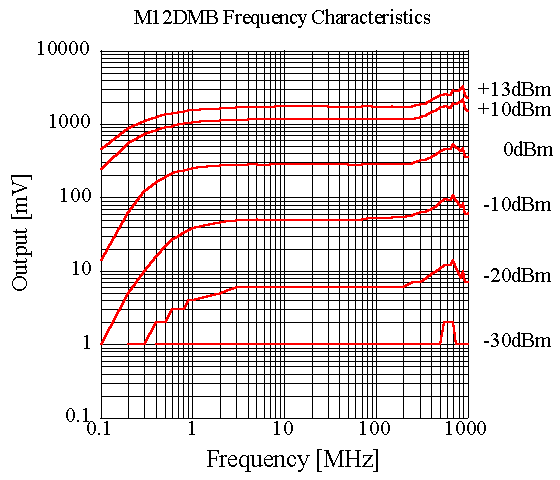 RFプローブM12DMBの周波数特性。入力側に50Ω整合終端とBNCアダプタを使用。 |
 検波器の内部。左側がRF入力、右側がDC出力。 |
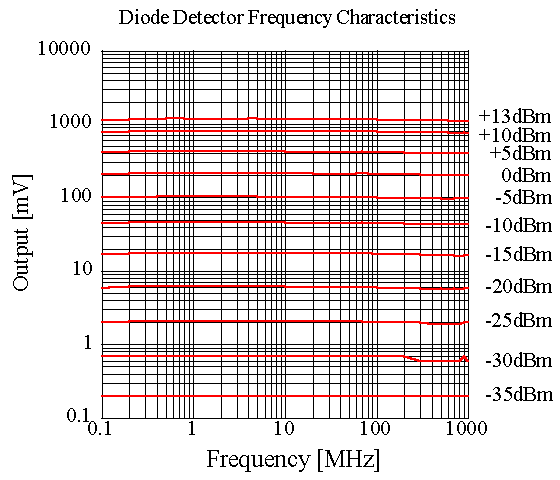 製作した検波器の周波数特性 |
|
2001年12月16日追記。 日本通信機製の検波器 MODEL9632 を入手したので測定してみました。 検波出力は自作のものと似たような電圧でした。 |
 MODEL 9632。左側がRF入力、右側がDC出力。 |
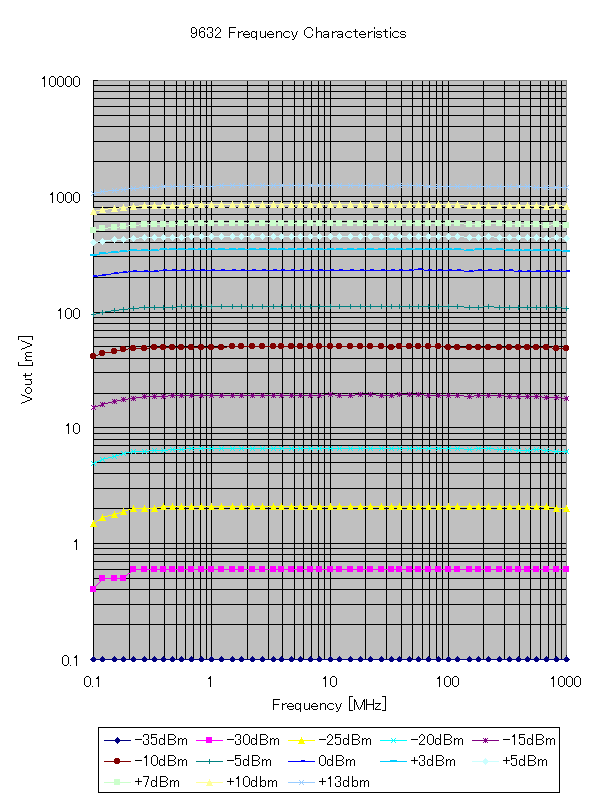 MODEL 9632の周波数特性 |